企業同士のM&Aに関する報道では、頻繁に「シナジー」や「シナジー効果」という言葉を耳にします。
M&Aを活用することで、売上やコスト削減など、さまざまなシナジーに期待できます。しかも、その効果は1+1が2になる以上の、10にも100にもなる可能性を秘めています。
この記事では、M&Aにおけるシナジーの基礎知識やシナジーの種類、およびM&Aによって大きなシナジーを得た事例について解説します。
目次
M&Aにおける「シナジー」とは

シナジー(synergy)とは、もともと薬学や生理学、生物学分野において、「2つ以上の要素が相互に作用することによって、単体で得られる以上の結果を上げること」を表す専門用語です。ビジネス分野においては、「2つ以上の企業ないし事業が統合することにより、単独よりも大きな成果を挙げること」を指します。
M&Aによって2つ以上の企業ないし事業が統合することで、1社だけでは成し得ない売上・収益の増加、大幅なコスト削減、商品開発の技術力の向上といったシナジー効果が期待されます。シナジー効果とは逆で、2つ以上の企業が統合することでマイナスの効果が生じることを「アナジー効果」と言います。
M&Aにおけるシナジーの5分類

M&Aの目的の多くは、企業同士の強みを組み合わせて「シナジー(相乗効果)」を生み出すことにあります。シナジーを最大化できれば、経営効率の向上や市場競争力の強化が期待できます。ここからは、M&Aにおけるシナジーの5つの分類について解説します。
売上シナジー
売上シナジーとは、2つ以上の企業や事業がM&Aによって協力関係を築いたり、経営を多角化したりして、別々に運営していたときよりも大きな売上をもたらすことを指します。簡単に言うと、売上においてM&Aによる効果が1+1=2ではなく、1+1が2以上になることを期待するシナジーです。
例えば、売上高5,000万円の企業と3,000万円の企業が、販売チャネルの増加を見込んでM&Aを実施、一年後の売上高が1億円になった場合、売上シナジーがもたらされたことになります。M&Aにおけるシナジー効果の4分類において、もっともポピュラーで定量化しやすいという特徴もあります。
研究開発シナジー
研究開発シナジーとは、高い技術力を保有する企業同士が、M&Aによってそれぞれの得意な研究分野を融合させ、商品開発の技術力を向上させることです。医療用医薬品のノウハウを持つ企業と、一般用医薬品のノウハウを持つ企業がM&Aを実施して共同開発を行えば、単独ではできなかった医薬品を開発できる可能性が高いです。
製品開発に限らず、管理システムや社員教育プログラム、研修プログラムなど、M&Aの当事者企業が双方の経営資源の強みを活かしたシナジー効果が期待できます。比較的定量化しにくいというデメリットはあるものの、シナジー効果がもたらされれば企業の長期的な競争優位性が得られます。
コストシナジー
コストシナジーとは、2つ以上の企業がM&Aによって1つになることでスケールメリットを得て、生産や物流などのコストを削減することです。同じ原材料で製品を製造している企業同士がM&Aを行い、スケールメリットを活かして原材料を大量購入することで、生産コストの低下が図れます。
M&Aによって企業の規模を拡大すれば、大量仕入や物流の統一、価格交渉力の強化などが可能です。コストを削減した分利益が増えることになるため、コストシナジーは売上シナジーと同様の効果が期待できます。特に、同業種の企業同士がM&Aを実施した場合、大きなコストシナジーが生じる傾向にあります。
財務シナジー
財務シナジーとは、M&Aによって資金調達力を増強したり節税したりすることです。財務状態の良い優良企業同士のM&Aで期待できる効果です。しかし、一方の企業が債務超過を抱えているような場合には、財務シナジーが発生しません。この記事で紹介している5つのシナジーのなかで、もっとも効果が得にくいと考えられます。
組織エナジー
組織シナジーとは、M&Aによって企業文化や人材、経営体制などの組織面で相乗効果を生み出すことを指します。買収先企業の優秀な人材や独自のマネジメントノウハウを活用することで、グループ全体の生産性や意思決定スピードを向上させることが可能です。異なる企業文化が融合することで、新しい発想やイノベーションが生まれるケースもあります。
一方で、価値観や働き方の違いが摩擦を生み、統合後の組織運営に支障をきたすリスクもあるため、PMI(統合作業)による人材・文化面の調整が不可欠です。組織シナジーは、M&Aの成功を左右する最も重要な要素の一つといえます。
M&Aにおけるシナジーを測定するためのフレームワーク
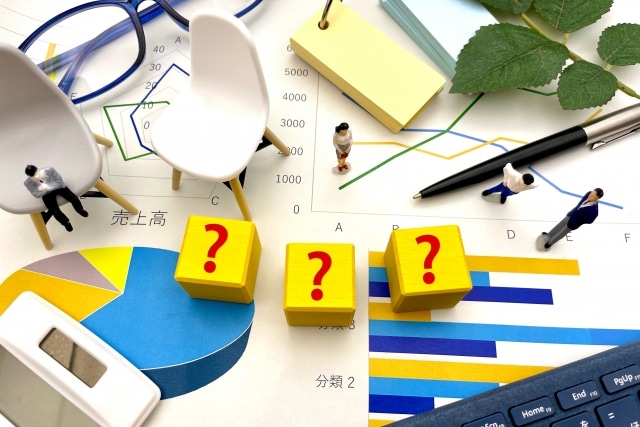
ここまで、M&Aにおけるシナジーの5分類について解説しました。しかし、M&Aにおけるシナジー効果の測定は簡単にできるものではありません。ここからは、M&Aにおけるシナジーを測定するためのフレームワークを紹介します。ぜひシナジー効果を測定する際に実践してみてください。
アンゾフの成長マトリクスとは
アンゾフの成長マトリクスとは、「戦略的経営の父」とも呼ばれるロシア系アメリカ人の経営学者のイゴール・アンゾフ(1918-2002)氏によって提唱された、事業を成長させる際に利用されるマトリックスのことです。
アンゾフの成長マトリクスでは、成長戦略を「製品」と「市場」の2軸におき、それをさらに「既存」と「新規」にわけられており、さまざまな戦略を練ることが可能です。
4つの成長マトリクスに沿った戦略
アンゾフの成長マトリクスでは、4つの成長マトリクスに沿った戦略が展開されています。それぞれに特徴があるので、以下の表で丁寧に解説していきます。自社はどのような戦略を取ればいいのか検討しながらご覧ください。
| 戦略名 | マトリクス(市場×製品) | 代表的な買収・活用例 | 特徴・リスク | 成功のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 市場浸透戦略 | 既存市場 × 既存製品 | 同業他社の買収など |
| 競合との差別化と自社の強みの訴求 |
| 新市場開拓戦略 | 新市場 × 既存製品 | 他市場の同業他社を買収 | 市場浸透よりリスクあり | 既存顧客ニーズに応える商品づくり/他社との差別化 |
| 新製品開発戦略 | 既存市場 × 新製品 | ブランド力獲得・技術取得を目的とした買収 |
| 認知拡大と顧客ニーズに合う新製品の投入 |
| 多角化戦略 | 新市場 × 新製品 | 水平型・垂直型・集中型・集約型に細分化 |
| 慎重かつ迅速な実行計画・資源配分 |
シナジーを目指す過程で起こり得る損失

M&Aでは、企業同士の強みを掛け合わせてシナジーを生み出すことが目的ですが、その過程で一時的な損失が発生することもあります。組織再編や経営方針の変更などによって、従業員や取引先、顧客に不安が生じるケースが少なくありません。
ここでは、シナジーを目指す過程で起こり得る損失について詳しく解説します。
人材流出
人材流出は、M&Aの過程で最も起こりやすい損失の一つです。経営統合や組織再編により従業員の役割や評価基準が変化すると、不安や不満が生まれやすくなります。買収先企業の優秀な人材が離職してしまうと、ノウハウや取引先との関係など貴重な経営資源が失われるリスクがあります。
M&Aによる人材流出を防ぐためには、早期のコミュニケーションと透明性のある情報共有が重要です。M&A後の組織に対する安心感と将来のビジョンを示すことで、従業員のモチベーション維持と定着を図ることが求められます。
顧客離れ
顧客離れは、M&Aの実施によって生じやすい損失の一つです。経営統合に伴いサービス内容や担当者、企業ブランドが変わることで、既存顧客が不安や不満を抱くケースがあります。これまで築いてきた信頼関係が急に変化すると、取引の見直しや契約解除につながるリスクが高まります。
顧客離れを防ぐには、統合後も一貫したサービス品質を保ち、顧客に対して丁寧な説明やフォローを行うことが重要です。安心感と信頼を維持することが、シナジー効果を最大化します。
M&Aにおけるシナジー効果の定量化と取引価値

ここまで、アンゾフの成長マトリクスについて解説しました。ではM&Aにおけるシナジー効果の定量化と取引価値にはどのような関係があるのでしょうか。M&Aをするうえで大切なポイントになるので、必ず把握しておく必要があります。
M&Aにおけるシナジーの価値とは
M&Aにおけるシナジーの価値は、必ずしも取引価格に反映させるわけではありません。発現可能性の低いシナジー効果を反映させてしまうと、シナジー効果を実現できなった際にリスクを背負うことになります。しかし、当然ながら売却側は少しでも高い価格で売却しようと考えます。
発現可能性の高いシナジー効果は、取引価格に反映させるケースがあります。
シナジー効果の定量化や取引価値の決め方
シナジー効果の定量化や取引価値の決め方は、以下のステップを通じて実施されます。
- 考えられるシナジー効果をまとめる
- それぞれのシナジー効果の定量化する
- 定量化したシナジー効果を踏まえて、最終的な企業価値評価を行う
シナジー効果を定量化する際には、この記事で解説しているマトリックスを上手く活用すると効果的な分析が可能です。最終的な企業価値評価にも反映されるので慎重に行いましょう。
シナジー効果を考慮してM&Aを進めよう

「M&Aは時間を買うこと」と言われています。自社がほしい技術やノウハウ、人材、販路などをM&Aによって手に入れることで、売上やコスト削減などさまざまなシナジー効果が期待できるからです。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、M&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。






























