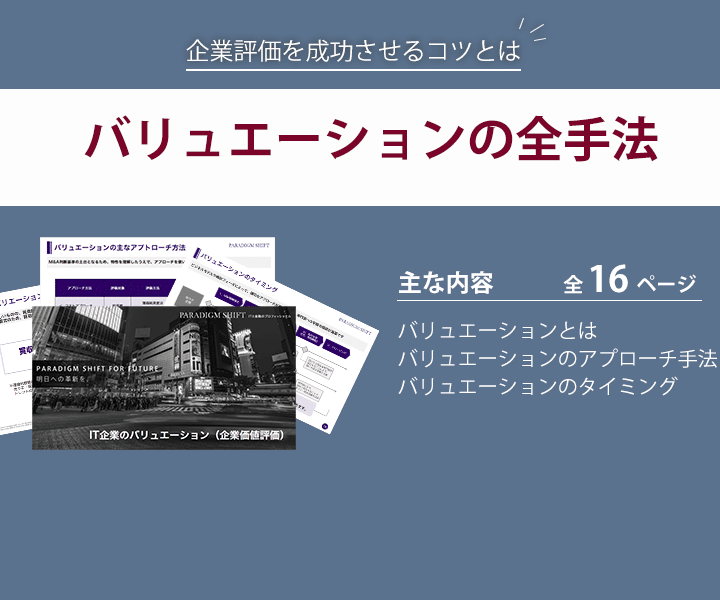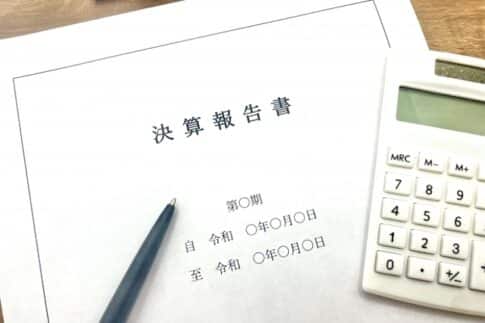M&Aの成約において、重要なデューデリジェンス。
デューデリジェンスは略語でDDと呼ばれることもあり、買い手企業が売り手企業に対して行う調査で買収監査とも呼ばれます。
買い手企業が主体となり行いますが、売り手企業がデューデリジェンスについて理解を深めることでより良い結果に繋がります。
今回の記事では、デューデリジェンスの基本的な知識や売り手企業がデューデリジェンスで良い結果を出すための注意点などを解説します。
目次
- 1 M&Aのデューデリジェンス(DD)とは
- 2 M&Aのデューデリジェンスの目的とは?
- 3 企業価値の確認と判断
- 4 株主やステークホルダーに対する説明責任
- 5 リスク調査と契約内容の検討
- 6 M&A締結後の方針の具体化
- 7 デューデリジェンスを実施しないとどうなるか?
- 8 簿外債務や偶発債務が後から発覚し、追加コストが発生する
- 9 法令違反・訴訟リスクが顕在化し、レピュテーションが失墜する
- 10 PMIが難航してシナジー効果を得られず、投資回収が遅延する
- 11 M&Aでデューデリジェンスを実施するタイミングと期間
- 12 タイミング
- 13 期間
- 14 M&Aのデューデリジェンス、おもな7種類とは?
- 15 事業デューデリジェンス
- 16 財務デューデリジェンス
- 17 税務デューデリジェンス
- 18 法務デューデリジェンス
- 19 人事デューデリジェンス
- 20 ITデューデリジェンス
- 21 知的財産デューデリジェンス
- 22 M&Aのデューデリジェンスの4つの手順とは?
- 23 手順1.資料開示・精査
- 24 手順2.デューデリジェンスの方針検討
- 25 手順3.マネジメントインタビュー・現地調査
- 26 手順4.報告書作成、結果の検討
- 27 デューデリジェンスの費用について
- 28 M&Aのデューデリジェンス、売り手側が注意することとは?
- 29 デューデリジェンスを実施するタイミング
- 30 利害関係のないM&A専門家にデューデリジェンスを依頼
- 31 情報漏えいを防止する
- 32 デューデリジェンスは実績があり信頼できるM&A専門家に依頼しよう
M&Aのデューデリジェンス(DD)とは

デューデリジェンスは広義では投資の際に行う調査のことです。
M&A取引では最終段階で行うもので、買い手企業が売り手企業に対して行う調査を指します。
調査は、第三者となる外部の専門家に依頼するのが一般的です。
理由は、第三者に依頼することで、対象の企業を客観的な視点で調査できるためです。
調査により、売り手企業と買い手企業の間に潜在するシナジー効果やリスクを洗い出します。
買い手企業は譲渡後にリスクを背負うため、デューデリジェンスで念入りに売り手企業を調査する必要があります。
そうすることで、M&Aにおけるリスクを回避できます。
対象となる売り手企業を、財務・税務・法務など様々な方面から調査。
問題点があった場合には、譲渡価格を見直すなどの解決方法を図ります。
M&Aのデューデリジェンスの目的とは?

デューデリジェンスではたくさんの人が時間をかけて、対象企業の調査にあたります。
そこにはどのような目的があるのでしょうか?
企業価値の確認と判断
M&A取引で譲渡価格を決定する際は、資産だけでなく従業員やその企業の技術・将来性も加味する必要があります。
そのため様々な角度から売り手企業を調査し、問題がないと判断した上で取引を成立させるべきと考えられています。
正確な企業価値を確認・M&A取引をしても問題がないかどうかを判断するために、デューデリジェンスは欠かすことができない工程です。
株主やステークホルダーに対する説明責任
買い手企業がM&Aで企業を買収する際には、株主やステークホルダーに対して、どのようなメリットがあるのか説明する責任があります。
ステークホルダーは、従業員・取引先・顧客など、企業の利害関係者を指します。
M&Aを決めた経営者は、正確なデューデリジェンスを行い、株主やステークホルダーにM&Aを行うことになった経緯・メリットを、丁寧に説明する責任があります。
リスク調査と契約内容の検討
デューデリジェンスを行うことは、対象となる企業の負債などのリスクを調査する役割もあります。
M&Aの手法には株式譲渡や事業譲渡など、いくつかの種類があります。
デューデリジェンスを行うことで、売り手企業・買い手企業双方にとって最善の契約内容を検討します。
M&A締結後の方針の具体化
M&Aの締結後、双方が行う統合後の作業をPMIと呼びます。
PMIは、具体的な経営方針や営業のルールを決める統合作業です。
デューデリジェンスを行いPMIを具体化していくことで、問題点を事前に発見して統合後のシナジー効果が最大限に発揮されます。
デューデリジェンスを実施しないとどうなるか?

デューデリジェンスを省略したり、不十分な状態でM&Aを進めたりすると、後になって予期せぬ重大な問題が発覚し、買い手側に甚大な損害をもたらす可能性があります。
最悪の場合、M&Aの失敗だけでなく、企業の存続自体が危ぶまれる事態に発展するケースも少なくありません。
デューデリジェンスを実施しないと起こり得るリスクを紹介します。
簿外債務や偶発債務が後から発覚し、追加コストが発生する
デューデリジェンスを怠ると、簿外債務や偶発債務がM&A後に発覚するリスクが高いです。
簿外債務は財務諸表に記載されていない負債のことで、偶発債務は将来において特定の条件が発生したときに発生する潜在的な債務を指します。
例えば、退職給付引当金の不足や未払いの残業代、製品保証に関する潜在的な債務などが簿外債務として挙げられます。
また、係争中の訴訟や環境汚染に関する賠償責任などが偶発債務として隠れていることも。
これらを事前に見落としたまま買収手続きを進めると、買収完了後に突然負債が明らかになり、数千万円や数億円単位の予期せぬ支払いに迫られる恐れがあります。
M&Aの投資採算性が悪化するだけでなく、資金繰りに影響を及ぼし、最悪の場合は企業の経営を圧迫する事態に陥りかねません。
買収の意思決定前に、必ず簿外債務や偶発債務の有無を確認することが重要です。
法令違反・訴訟リスクが顕在化し、レピュテーションが失墜する
デューデリジェンスを適切に実施しない場合、買収対象企業が抱える法令違反や潜在的な訴訟リスクを見落としてしまう危険性があります。
例えば、労働法規違反による従業員からの集団訴訟、環境規制違反による行政処分、個人情報保護法違反による損害賠償請求などが挙げられます。
SNSやメディアで拡散されやすい現代では、顧客や取引先の不信感を招き、ブランド価値や評判の急落にもつながりかねません。
M&A後に問題が表面化すると、買い手企業は訴訟の当事者となったり、多額の賠償金を支払う義務を負ったりする可能性があります。
デューデリジェンスは、法的問題やリスクを事前に洗い出し、適切な対応策を講じるために不可欠です。
PMIが難航してシナジー効果を得られず、投資回収が遅延する
デューデリジェンスが不十分だと、買収対象企業の組織文化や従業員の士気、ITシステム、内部統制などの実態が把握できずPMIが難航する可能性が高いです。
例えば、買収先の従業員のモチベーション低下や主要な人材の流出、異なるシステム間の非効率な連携などが生じます。
PMIが長期化すれば、当初、見込んでいた業務効率化やコスト削減といったシナジー効果を十分に得られなくなる可能性も否定できません。
M&Aによって期待された企業価値向上が実現できず、投資した資金の回収が大幅に遅延したり、最悪の場合は投資自体が失敗に終わったりする可能性も出てきます。
効果的なPMIには、買収前の人事やITデューデリジェンスなどが不可欠であり、M&Aの成功を左右すると言えるでしょう。
M&Aでデューデリジェンスを実施するタイミングと期間

M&Aでデューデリジェンスを実施する際は、適切なタイミングとある程度の調査期間を要します。
下記では、デューデリジェンスを実施する適切なタイミングと要する期間を解説します。
タイミング
M&Aでデューデリジェンスを実施するタイミングは、以下の通りです。
- M&Aの検討を開始する
- 買収・売却先を検討する
- 基本合意で契約する
- デューデリジェンスを行う
- 最終契約を締結する
- クロージング
デューデリジェンスは、M&Aが取りやめになるリスクが低い時点で行われるため、M&Aについての合意がおおむね固まる基本合意契約後に行われることが多いです。
期間
デューデリジェンスの期間は通常1〜2ヵ月で、対象企業や事業の規模、業種、調査範囲によって変動します。
デューデリジェンスは、対象企業の協力なしには実施できず、必要な文書の準備や回答が迅速に進まない場合は急いでも実現しません。
デューデリジェンスの期間の内訳は以下の通りです。
(※個別のケースによって異なる可能性があります)
| 資料・デューデリジェンスの準備 | 2週間 |
| 相手先の調査・聞き取り | 数日〜2週間 |
| 調査結果の分析 | 1〜2週間 |
| クライアント最終報告・追加分析 | 1〜2週間 |
M&Aのデューデリジェンス、おもな7種類とは?

M&Aのデューデリジェンスは、多岐に渡る分野があるため種類分けされています。
主な種類は、事業・財務・税務・法務・人事・IT・知的財産の7種類です。
その中でも、事業・財務・税務・法務の4項目は、多くのM&A取引で採用されます。
専門知識を必要とするため、それぞれの専門家に依頼して調査を行います。
事業デューデリジェンス
事業デューデリジェンスは、対象となる企業の市場全体の環境を調査する項目です。
売り手企業に対して、競合の企業の調査や分析をします。
また、経営者へのインタビューを通じて、対象企業が市場の中でどのような立ち位置にあるかを調査します。
それにより、統合後に起こりうるシナジー効果を予測します。
今後の事業の安定性や将来性を考え、M&Aの目的と適合するかを見極めるために、必要不可欠な項目です。
財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンスは、キャッシュフロー・貸借対照表・損益計算書などをもとに、財務の観点から、売り手企業の財務状況を調査します。
M&Aの買収価格を決めるのに基盤となる調査で、税理士や公認会計士が担当します。
将来の収益性やキャッシュフローを予測すると共に、不正な経理処理などのリスクを重点的に調べます。
また、貸借対照表に記載されていない責務を指す薄外責務や、今後起こりうる偶発責務の洗い出しや予測も財務デューデリジェンスで調査できます。
税務デューデリジェンス
税務デューデリジェンスは、デューデリジェンスの中でとても重要な項目です。
譲渡前に、適切な納税や申告が行われているかを確認する調査です。
申告や納税に漏れがあった場合、譲渡企業がペナルティーを課せられることもあるため、M&A取引前の納税申告を細かく調査します。
調査は、税理士や会計士に依頼するのが一般的です。
法務デューデリジェンス
法務デューデリジェンスは、債券債務などの法律上で問題がないかを調査する項目です。
債券債務は、おもに賃金の支払いや不動産の売買などを指します。
債券債務に問題があると、訴訟が起こるリスクがあり、企業への風評被害などから経営悪化に陥る可能性もあります。
実際に訴訟が起きてしまった場合には、膨大な時間と費用を消費することになるため、リスク回避の面で重要な調査です。
調査は、おもに弁護士や司法書士が担当します。
人事デューデリジェンス
人事デューデリジェンスは、売り手企業の組織・人事制度や構成・マネジメントに関する調査です。
おもに、売り手企業が買い手企業の人事制度を円滑に統合するために行います。
M&A後の人事は、2社の統合において非常に重要です。
特に、統合後に売り手企業の従業員のモチベーションを保つことは難しく、優秀な人材が流出してしまうと、大きな損害になるため、しっかりと事前準備をする必要があります。
従業員の数・人件費・人事システムなどを調査し、統合後、人事制度融合の役に立ちます。
売り手側企業にとっては、これまで育てた従業員が新しい環境でストレスなく働くための準備と言えます。
ITデューデリジェンス
ITデューデリジェンスは、売り手企業が営業や会計管理で採用してる情報処理システムについて調査します。
取り扱い方を調査するほか、分析することで買い手企業のシステムとどのように融合させるか検討します。
融合により、作業が複雑になってしまう・効率が下がるリスクを回避する役割があります。
現代においてITは非常に重要です。
ITデューデリジェンスを専門としている業者に依頼して、調査や統合作業を行いましょう。
知的財産デューデリジェンス
知的財産デューデリジェンスは、売り手企業が特別な著作権や特許権を所持している場合に行う調査です。
知的財産は形がない価値であるため、細かく分析して、価値を正確に把握する必要があります。
M&Aのデューデリジェンスの4つの手順とは?

この項では、M&Aのデューデリジェンスの実際の手順を解説します。
手順1.資料開示・精査
買い手企業が、売り手企業に資料開示請求を行います。
これに伴い、売り手企業は予め調査したM&Aに関わる全ての資料を開示します。
買い手企業は、開示された資料をもとに売り手企業について様々な面から分析していきます。
手順2.デューデリジェンスの方針検討
買い手側は、開示された資料とその分析結果をもとに、統合後にどのようなシナジー効果があるか・考えられるリスクは何かを検討します。
この時点で、以下の大まかな方向性が決まります。
- デューデリジェンスの方針
- 譲渡価格
- M&Aの契約内容
手順3.マネジメントインタビュー・現地調査
マネジメントインタビューや現地調査は買い手企業が売り手企業に対して行います。
インタビューの対象となるのは、おもに売り手企業の経営者やマネジメント層です。
開示された資料では判断しにくい内容や、経営理念や方針などをインタビューし、統合後の方針を具体化します。
売り手企業は、インタビューや現地調査に備えて準備することで、スムーズな取引に繋がります。
手順4.報告書作成、結果の検討
買い手企業は、開示された資料やインタビュー・現地調査の結果をもとに報告書を作成します。
報告書をもとに、譲渡価格の決定、契約内容の考案に入ります。
専門業者に依頼ている場合は、これらの全ての手順を専門業者の指導のもと行います。
デューデリジェンスの費用について
デューデリジェンスにかかる費用は以下の要素で変動します。
- 対象企業の規模や調査内容、協力する専門家の数
- デューデリジェンスの種類
①について、中小企業と大企業に分けると費用は次の通りです。
| 中小企業の場合 | 数十万円〜数百万円 |
| 大企業の場合(海外企業含む) | 数百万円〜数千万円 |
②について、一般的な1時間あたりの費用と総額の目安です。
| 事業デューデリジェンス | 約2万~約10万円/時(総額約30~約300万円) |
| 財務デューデリジェンス | 約2万~約5万円/時(総額約100~約500万円) |
| 法務デューデリジェンス | 約2万~約5万円/時(総額約70~約200万円) |
| 税務デューデリジェンス | 約2万~約5万円/時(総額約35~約200万円) |
| 人事デューデリジェンス | 約2万~約5万円/時(総額約44万円~) |
| ITデューデリジェンス | 総額約15万〜約200万円 |
表で挙げたデューデリジェンス以外にも、知的財産や環境、不動産などの調査を行う場合があります。
M&Aを実施する際には、自社と調査依頼先で調査項目と費用を決めましょう。
M&Aのデューデリジェンス、売り手側が注意することとは?

デューデリジェンスは、おもに買い手企業が主体となり、売り手企業を調査します。
調査では、買い手企業に不信感を与えないよう、積極的に協力する姿勢がM&A成立のポイントです。
では、売り手の注意すべき点とは、具体的に何があるのか見ていきましょう。
デューデリジェンスを実施するタイミング
売り手企業が最も注意するべきことは、デューデリジェンスを実施するタイミングです。
一般的にデューデリジェンスは、基本合意契約の締結後と最終条件交渉の間に行われます。
デューデリジェンスが行われると、大体の譲渡価格も決定します。
そのため、決められた期日までに適切な準備をすることが大切です。
デューデリジェンスは、種類別にチェック項目があり、それを基本に調査を行います。
事前にチェック項目を確認し調査に備えることで、成功に繋がりやすくなります。
また、セルサイドデューデリジェンスと呼ばれる、売り手企業が行うデューデリジェンスもあります。
セルサイドデューデリジェンスは、売却価格をより高くするため、買い手企業が行うデューデリジェンスの対策のために行います。
利害関係のないM&A専門家にデューデリジェンスを依頼
デューデリジェンスは、手順が複雑で多岐に渡る専門知識を必要とします。
そのため、専門家や専門業者に依頼するのが一般的です。
利害関係がない、第三者の専門業者に依頼することで、M&A取引成功に繋がります。
情報漏えいを防止する
M&Aにおけるデューデリジェンスでは、買い手企業が対象企業の財務や契約、人事、知的財産などあらゆる情報を精査します。
売り手企業は多くの内部情報を開示する必要がありますが、警戒すべきなのが情報漏えいのリスクです。
取引が成立する前に顧客情報や技術ノウハウ、経営戦略など機密情報が外部に漏れると、競争上の不利益や信用の失墜や取引先の離反など重大な影響を及ぼす可能性があります。
情報漏えいを防ぐためには、買い手側と秘密保持契約(NDA)を締結し、開示範囲や利用目的を明確に定めましょう。
情報は必要最小限の範囲に限定し、段階的に開示するステップ開示も有効です。
情報管理を一元化するデータルーム(VDR)の活用や、アクセス制限・ログ管理などのセキュリティ対策を講じることで、外部流出のリスクを抑えられます。
社内でも、M&Aに関する情報にアクセスできる従業員を限定し、秘密保持に関する教育を徹底することも大切です。
売り手企業は、情報提供の準備段階から守るべき情報と提供すべき情報を見極め、慎重な対応が求められます。
デューデリジェンスは実績があり信頼できるM&A専門家に依頼しよう

M&Aのデューデリジェンスについて解説しました。
的確なデューデリジェンスを行うことで、M&A成立の大きな足がかりになります。
デューデリジェンスには7つの種類があり、それぞれ専門の知識を必要とします。
デューデリジェンスを実施する上で、売り手側が注意することは以下2つです。
- デューデリジェンスを実施するタイミングに注意する
- 利害関係のないM&A専門家に依頼する
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。