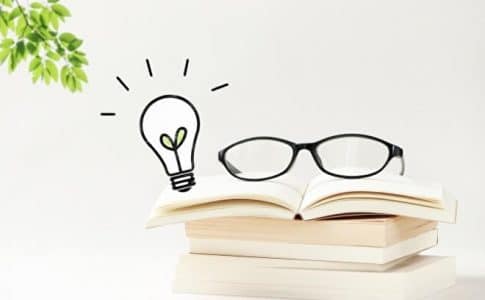会社売却は、企業の経営権を他社へ譲り渡す行為です。
売却元は売り手企業、売却先の企業は買い手企業となり、会社売却の手続きを進めていきます。売り手企業とその経営者は、買い手企業へ自社の株式を売却して売却益を取得します。
会社売却は、会社の倒産や廃業を回避し、従業員の雇用を維持できる点が最大のメリットです。
今回の記事では、企業買収の基本的な知識からメリット・デメリットと会社売却の手順、経営者や従業員が会社売却後に受ける影響を解説します。
目次
- 1 会社売却とは?
- 2 会社売却と事業売却における相場の違い
- 3 会社売却の相場
- 4 事業売却の相場
- 5 会社の売却価格や相場の算定方法
- 6 コストアプローチ
- 7 インカムアプローチ
- 8 マーケットアプローチ
- 9 会社売却のメリット
- 10 売却益の取得
- 11 企業倒産の回避
- 12 従業員の失業を回避
- 13 連帯保証からの解放
- 14 会社売却のデメリット
- 15 一定期間のビジネスができなくなる
- 16 売却後も一定期間の拘束がある
- 17 精神的な寂しさがある
- 18 人材流出の恐れ
- 19 会社を売却するタイミング
- 20 業界
- 21 会社
- 22 会社売却の流れ
- 23 売却先のソーシング・交渉
- 24 基本合意契約の締結
- 25 デューディリジェンスの実施
- 26 各契約の締結
- 27 クロージング
- 28 統合の工程
- 29 会社売却を成功させるポイント
- 30 売却価格の算定する
- 31 アドバイザーを適切に選ぶ
- 32 財務状況を明らかにする
- 33 従業員に説明する
- 34 買い手企業と交渉する
- 35 会社売却後の経営者や従業員について
- 36 経営者
- 37 従業員
- 38 会社売却は廃業や倒産を回避する最善策
会社売却とは?

第三者に会社を売却する行為を会社売却と呼びます。対して、会社のすべてではなく、事業の一部を売却する場合は、事業売却・事業譲渡と呼びます。
会社売却の場合、多くは株式譲渡と呼ばれる売り手企業の株式の移転によって対価が支払われます。
近年、少子化や後継者不足により会社売却を選択する経営者が増えているのが現状です。仮に、これらの理由で会社売却ではなく、会社を廃業させた場合、従業員は職を失い、従業員とその家族が露頭に迷います。
多くの経営者が会社売却を選ぶ主な目的は、従業員の雇用を守ることです。その他、会社の安定化や売却利益の獲得を目的として、会社売却を選択する経営者もいます。
会社売却と事業売却における相場の違い

会社売却はその名のとおり、会社そのものを売却する行為です。対して事業売却は会社の一部の事業を売却し、会社自体は残ります。そのため、2つの相場を比べた場合、会社売却の方が大きくなるのが基本です。会社売却、事業売却の相場について見てみましょう。
会社売却の相場
会社売却は、会社を丸ごと売却する行為です。会社売却はほとんどの場合、株式譲渡で実行されます。買い手企業にすべての資産と負債が移動するので、事業売却よりも相場は大きくなる傾向があります。
会社売却の相場を算出するために使われる方法は以下のとおりです。
| マーケットアプローチ | 市場取引を基準に企業価値を算出。類似する他社取引を参考にする。 類似会社比準法(マルチプル法)、類似取引比準法、市場株価法がある。 |
| インカムアプローチ | 将来得られるとされるキャッシュフローや利益を基準に会社の価値を算出。 DCF法、配当還元法がある。 |
| コストアプローチ | 貸借対照表の純資産をベースに会社の価値を算出。 簿価純資産価額法、時価純資産価額法、清算価値法がある。 |
これらの方法で相場を算出し、さらに期待できるシナジー効果や負債などを加味して決定していきます。これらの算出方法は次の章で詳しく解説しています。
事業売却の相場
事業売却はすでに存在している会社の一部の事業を売却する行為です。そのため、会社売却よりも必然的に相場は低くなるのが特徴です。しかし、売却したい事業と会社に残したい事業を選別して売却したい事業だけを手放せる点がメリットです。
事業売却の相場を算出する上で最も客観性があるのは、株式市場で用いられるPER(株価収益率)を活用して算出する方法です。PERを算出するために計算式は以下のとおりです。
- PER = 時価総額 ÷ 当期純利益
そのため、買収対象の事業の純資産がわかれば、事業売却の相場がわかります。
さらに簡易的に相場を算出する際には、年買法を用いることもあります。年買法は以下の計算式で求められます。
- 修正純資産 + 営業利益 × 3~5年
会社の売却価格や相場の算定方法

では、会社売却の際、売却価格はどのように算出するのでしょうか。
基本的に売却価格の相場は、売り手企業の企業価値で決定します。企業価値の算出方法にはさまざまな方法があり、大きく分けるとコストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチの3種類です。
コストアプローチ
コストアプローチは、中小企業の企業価値を算出する際によく用いられる手法です。純資産の時価総額を用いて簡易的な企業価値を算出できます。
コストアプローチには、さまざまな方法があります。
代表的なものでは、企業の負債や資産の帳簿から企業価値を算出する簿価純資産価額法、資産や負債を時価に置き換えて企業価値を算出する時価純資産法です。時価純資産法の欠点を補うために営業権を加算して評価する年倍法や超過収益還元法などもあります。
コストアプローチは、算出が簡単で客観性が高い方法です。しかし、収益性や将来性を加味しておらず、市場の状況も考慮されていないので、買い手企業にとってはややリスクがある方法ともいえます。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、売り手企業の将来の利益を予測して、その数値をもとに企業価値を算出します。その中でも代表的な方法はDCF法です。DCF法は、売り手企業の将来のキャシュフロー(FCF)を予測して算出します。
インカムアプローチは、将来性を加味した企業価値を算出するため、実態に近い価値を出しやすい点がメリットです。しかし、実際の数値で算出する価値ではないので、算出する人や立場により偏りが出てしまうデメリットもあります。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、対象の売り手企業と類似する企業を調査して企業価値を算出する手法です。
類似企業の中でも、上場している企業のKPI(重要業績評価指標)を使用して算出する方法をマルチプル法(類似会社比較法)と言い、マーケットアプローチの代表的な方法として多く採用されます。
マーケットアプローチは、類似企業のデータを元に算出するため、客観的な企業価値を算出できますが、類似企業のデータを揃える手間がかかる点や、選んだ類似企業により結果が左右されるデメリットがあります。
会社売却のメリット

会社売却をしたことによるメリットは以下のとおりです。
- 売却益の取得
- 企業倒産の回避
- 従業員の失業を回避
- 連帯保証からの解放
今回紹介するのは以上の4点です。詳しく見ていきましょう。
売却益の取得
会社売却を選択すると、経営者は売却益を受け取れます。退職金の代わりとしてリタイア後の生活費に当てることも可能です。その売却金を元手に新たなビジネスを始める選択肢も考えられます。
企業倒産の回避
企業の倒産や廃業した場合、従業員やその家族だけでなく取引先や顧客にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。
会社売却なら、負債を引き取ってもらえる上、倒産や廃業を回避できます。企業の倒産や廃業は経営者自身だけでなく、周りの人の人生をも変えてしまう恐れがあります。こうしたリスクを回避する方法としての会社売却は、最良の選択です。
従業員の失業を回避
前述のとおり、会社売却により倒産や廃業を防ぐと、従業員の失業を回避できます。仮に会社を廃業させる場合従業員は職を失ってしまいます。残る従業員のための会社売却の選択はとても勇敢な選択と言えます。
連帯保証からの解放
会社売却をして、経営から退いた場合、経営者ガイドラインにより決められた条件下において、連帯保証や個人保証を解除できます。
長年の重責から解放されて、肩の荷が降りたと感じる経営者も少なくありません。
出典:経営者保証ガイドライン(中小企業庁が平成26年2月施行)
会社売却のデメリット

会社売却には上述のとおり、多くのメリットがありますが、デメリットがあることも把握しておきましょう。
- 一定期間のビジネスができなくなる
- 売却後も一定期間の拘束がある
- 精神的な寂しさがある
- 人材流出の恐れ
デメリットは以上の4点です。
一定期間のビジネスができなくなる
会社売却の後、一定期間は同業種のビジネスができない取り決めがあります。
会社法21条の競業避止義務に基づくもので、その期間は20年間です。会社売却の売却益を元手に新たなビジネスを検討している場合には注意しましょう。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』|会社法21条競業避止義務
売却後も一定期間の拘束がある
会社売却後も経営者は、業務の引き継ぎなどで一定期の間、拘束されます。
具体的には、従業員の雇用先が変わったことのよる再契約や取引先や顧客などにも申し入れや再契約が必要になる場合もあります。これらの調整は創業者・経営者の協力が必要不可欠です。
業務に関わる手続きや契約が多いほど拘束期間が長期化します。
精神的な寂しさがある
会社売却後、経営者は引退するのが一般的です。
長年の重責から解放され、自由な時間も多くなり、引退後の自由な時間を楽しめますが、一気に仕事をしなくなると精神的な寂しさや虚無感に襲われる経営者も少なくありません。
社長と呼ばれなくなり、領収書も会社名で発行できなくなるなど、日常生活も大きく変化するため、気持ちが追いつかず寂しい気持ちになるのが自然です。
この気持ちを防ぐには、引退後にやることなどをあらかじめ考えておきましょう。
人材流出の恐れ
会社売却後に売り手企業と買い手企業の統合作業を実施しますが、この段階で売り手企業の人材が流出してしまう可能性もあります。
理由はさまざまなことが挙げられますが、統合後の業務内容や待遇の変化に納得がいかなかったり、買い手企業の雰囲気に馴染めなかったり、人間関係がうまくいかなかったりする点が挙げられます。
人材の流出は、統合時に従業員の聞き取りを入念に実施すると解決できることもありますが、ある程度発生してしまうことも視野にいれておくことで大きな問題にならずに済みます。
会社を売却するタイミング

中小企業オーナーが会社を売却する際は、大きく「業界の状況」と「会社の状態」といった2つの観点から判断しましょう。
業界
業界全体が成長期にあるときは、買い手の需要が高まり競争も活発化するため、高値での売却が期待できます。他社が積極的にM&Aを進めている時期に合わせて売却すると、より有利な条件を引き出せる可能性があります。
一方で、規制変更や競争激化などの影響が見込まれる場合も、リスク回避のため戦略的に売却するケースがあります。反対に、業界が衰退傾向に入ると買い手の関心は薄れ、評価額が下がる恐れがあるため注意が必要です。
会社
安定的に利益を確保している、成長が見込める、財務が健全といった状況は、買い手から高評価を得やすく売却の好機です。新規事業や市場拡大のための資金確保を目的に売却を選ぶこともあります。
反対に、業績悪化や競争力低下が見えてきた場合は、企業価値が下がる前に早めの売却を検討すべきです。
最適な売却時期を判断するには、業界トレンドと自社の経営状況を総合的に分析し、どちらを優先するかのバランスを見極めることが欠かせません。
会社売却の流れ

次に、会社売却の流れについて解説します。今回解説するのは、売り手企業の経営者が自社を売却する意思が固まった後の流れです。
- 売却先のソーシング・交渉
- 基本合意契約の締結
- デューディリジェンスの実施
- 各契約の締結
- クロージング
- 統合の工程
売却先のソーシング・交渉
会社売却の意思決定を固めたら、売却先の候補を探します。方法として、M&Aの仲介所や事業引き継ぎ支援センターへ問い合わせるのが一般的です。また、税理士や会計士などの専門知識を持つ人と契約している場合には、相談に乗ってもらいましょう。
会社売却の相手が決定した後、交渉に入りますが、交渉前に秘密保持契約(NDA)を締結します。
基本合意契約の締結
買い手企業と売り手企業、お互いに秘密保持の義務を負った後で、売り手企業は、交渉先に案件概要書(IM)を提示します。案件概要書は、公開されている情報よりも、さらに詳しい企業情報です。
買い手先の候補企業は、この情報を元に基本条件や想定価格を提示します。
その後、トップ面談により、経営者同士の意思確認をし、お互いの企業理念や文化についての考え方を共有します。双方の合意が取れれば、基本保持契約を結びます。
デューディリジェンスの実施
基本合意契約を締結した後に、買い手企業はデューデリジェンスを実施します。売り手企業が開示・提供した事業情報から会計、法務、税務など、あらゆる側面から売り手企業を精査し、売却価格を算出します。
算出した売却価格を元に条件交渉を進めますが、デューデリジェンスで万が一、開示されていない問題やリスクが判明すれば売却価格が下がったり、交渉されたりする場合もあります。
各契約の締結
交渉が成立して取締役会で決定した後、事業譲渡契約や株式譲渡契約など、決められた会社売却の方法に基づいた各種契約を締結します。この契約は基本合意契約とは異なり、法的なものです。
社内向けには、報告書として一連の内容を記載して提出します。合わせて、公正取引委員会への報告書も準備します。
クロージング
契約を締結した後は、双方ともに、クロージングに向けて準備をしていきます。クロージングとは、株式譲渡の実行を意味します。
株主への通知・公告、株式総会で説明、株式譲渡の実行など、条件がすべて完了すれば売り手企業に譲渡代が支払われます。
統合の工程
契約や支払いなどのすべての手続きが完了したら、監督省庁で許認可と各種手続きを実施します。
その後、実際の統合作業に移っていきます。まずは、3〜6カ月以内に取り組む短期プランとして組織や人事の再編を実行します。次に、現状の課題や改善点を洗い出し、半年〜数年間で中期プランを実行します。
これらに問題がなければ実際の統合作業の実行に移していきます。
会社売却を成功させるポイント

会社を有利な条件で売却するには、入念な準備と戦略的な進め方が欠かせません。特に、以下の5つは成功の鍵となる要素です。
売却価格の算定する
売却額の設定は最初の大きなハードルです。価格が低すぎれば損失を招き、高すぎれば買い手が見つからない恐れがあります。市場で受け入れられる妥当な価格を見極めることが、交渉を有利に進める前提です。
会社価値の評価には、以下の代表的な3つの手法があります。
- インカムアプローチ:将来の利益やキャッシュフローを基に価値を算定
- マーケットアプローチ:類似企業の取引事例や株価を参考に評価
- アセットアプローチ:保有資産と負債を基に価値を計算
これらを単独で用いるのではなく、複数組み合わせることで精度を高められます。また、市場環境や自社の状況により価値は変動するため、M&A専門家の助言を受けながら柔軟に見直す姿勢が重要です。
アドバイザーを適切に選ぶ
会社売却は高度な知識と複雑な手続きを伴うため、専門家の支援が不可欠です。経験豊富で信頼できるアドバイザーを選ぶことで、取引を円滑かつ有利に進められます。主なアドバイザーは以下のとおりです。
| M&A仲介会社 | 買い手探しから条件交渉、契約締結まで一貫して支援。豊富な取引実績と専門知識を活用し、最適な条件での売却をサポートします。 |
| 金融機関 | 銀行や証券会社が、M&A仲介同様の業務に加え、資金調達面での提案力を発揮します。 |
| 弁護士・会計士 | 弁護士は契約書作成や法務助言、会計士は企業価値評価や財務デューデリジェンスを担当し、法務・会計の両面から取引を下支えします。 |
アドバイザー選びでは、過去の実績、専門領域、価格などを比較し、自社に最適なパートナーを見極めることが重要です。
財務状況を明らかにする
買い手は取引前に詳細な財務調査(デューデリジェンス)を行います。この際、財務内容が不明確だと信頼を損ね、交渉が停滞しかねません。事前準備として以下を徹底します。
- 正確な財務諸表作成:最新基準に沿って作成し、過去分も必要に応じて修正します。
- 契約書の整理:取引先契約や雇用契約など、重要書類を整備・保管します。契約条件が売却条件に影響する場合もあります。
- リスク・機会の開示:訴訟や規制リスク、将来の成長余地などを適切に説明します。
財務の透明性を高めることで、買い手からの信頼を獲得し、予期せぬトラブルを回避できます。
従業員に説明する
会社売却は従業員の雇用や待遇に直接影響する重大な出来事です。不安や混乱を最小限に抑えるためには、決定の背景や今後の方針を正確かつ誠意を持って伝える必要があります。
| 説明のタイミング | 噂や憶測が広がる前に、可能な限り早期に公式な情報を共有します。遅れるほど不安や不信感を招きます。 |
| 従業員目線での説明 | 雇用形態、待遇、業務内容など具体的な影響をわかりやすい言葉で説明します。抽象的な表現は避け、事実に基づいた情報提供を行います。 |
| 意見交換の場を設ける | 説明会や個別面談を通じて、従業員が質問や意見を自由に述べられる環境を整えます。誠実な対応は信頼関係の維持につながります。 |
従業員は会社の重要な資産であり、売却成功には彼らの理解と協力が不可欠です。
買い手企業と交渉する
売却プロセスでは、買い手との交渉が成否を左右します。価格だけでなく、雇用維持や事業継続など重要条件を守るため、計画的な戦略が必要です。
| 交渉条件の優先順位を明確化 | 譲れない条件(価格、雇用維持、ブランド存続など)を事前に整理します。 |
| 買い手の意図を把握 | 買収目的や期待するシナジーを理解した上で提案を行うことで交渉を優位に進められます。 |
| 複数候補との交渉 | 競争環境を作ることで有利な条件を引き出せますが、情報漏洩防止のため守秘義務契約の締結は必須です。 |
交渉では冷静さと論理性を保ち、必要に応じて信頼できるアドバイザーの助言を受けながら、最良の条件で合意を目指します。
会社売却後の経営者や従業員について

実際に会社売却した場合、経営者や従業員はどうなるのか、売却後の影響について考えてみます。
経営者
経営者は、会社売却と同時期に引退を選択する人が多くいます。理由は、経営者がその企業の株主である場合が多いためです。しかし、会社売却と引退が必ずしも同時期に起こるではありません。
会社や事業内容によっては、売り手企業の経営者が役員として残った方がスムーズに業務の引き継ぎができる場合があります。そのため、会社売却後も一定期間は役員として残ることもあります。
従業員
会社売却をしても、従業員の雇用契約は継続します。雇用契約は、会社と従業員個人が結ぶものなので、会社が存続している以上は、雇用契約もそのまま存在します。
従業員は会社売却の際に退職を希望する権利もあります。経営者と長年、働いてきた従業員の中には、経営者と一緒に引退を願い出ることもあります。
また、雇用契約はすでに交わされているため、雇用条件は会社売却後にも引き継がれます。ただ、売却先によっては業務内容や役職の変更になることもあるので、従業員の流出を防ぐためにも、各従業員に聞き取りをして統合作業を進めていく必要があります。
会社売却は廃業や倒産を回避する最善策

今回の記事では、会社売却の基本的な知識やメリット、会社売却の際の流れについて解説しました。
会社売却は、工程が多く、労力が必要ですが、その分のメリットが大きいのも事実です。特に、従業員の雇用を守れる点は従業員だけでなく、その家族にとってもメリットです。さらに、経営者自身も売却益を受け取れるなどのメリットがあります。
会社売却の買い手企業探しや一連の手続きには、専門的な知識を持つ第三者の介入が必要です。会社売却の意思を固めたら、まずは力になってもらえる専門家を探すことから始めてみましょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。