「情報セキュリティリスクとは何か」「企業はどんな対策を取るべきか」など疑問を持つIT担当者や経営層の方も多いのではないでしょうか。
近年、サイバー攻撃や内部不正、ヒューマンエラーなど企業を取り巻く情報セキュリティリスクは巧妙かつ深刻化しています。
本記事では、情報セキュリティリスクの基本や具体的なセキュリティ対策を解説します。
大切な情報資産を守り、ビジネスを安定的に運営するための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
目次
- 1 情報セキュリティリスクとは?
- 2 情報セキュリティにおける3つのリスク要素
- 3 情報資産
- 4 脅威
- 5 脆弱性
- 6 情報セキュリティリスクの種類
- 7 機密性リスク:不正アクセス
- 8 機密性リスク:内部脅威
- 9 完全性リスク:データの改ざん
- 10 完全性リスク:サイバー攻撃
- 11 可用性リスク:サービス停止
- 12 可用性リスク:ヒューマンエラー
- 13 物理的リスク:自然災害
- 14 物理的リスク:盗難・窃盗
- 15 情報セキュリティリスク対策の必要性
- 16 経済的損失の回避
- 17 顧客信頼の維持
- 18 事業の継続性の確保
- 19 法的リスクの軽減
- 20 情報セキュリティリスクに対する具体的な施策
- 21 ウィルス対策ソフトの導入
- 22 多要素認証の導入
- 23 ファイアウォールの設置
- 24 定期的な脆弱性診断
- 25 バックアップ体制の整備
- 26 従業員への情報セキュリティ教育
- 27 情報セキュリティリスクを理解し、組織を守ろう
情報セキュリティリスクとは?
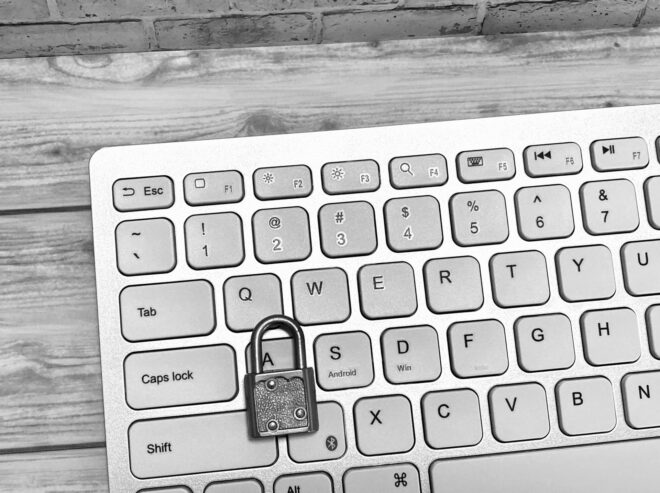
情報セキュリティリスクとは、企業が保有する情報資産が、外部からの攻撃やシステム障害などにより漏洩・改ざん・消失・不正利用される危険性のことです。
リスクは外部脅威と内部要因に大きく分けられます。
- 外部脅威:サイバー攻撃、マルウェア、不正アクセスなど
- 内部要因:操作ミス、情報管理の不備、退職者による情報持ち出しなど
情報の流出や破損は、経済的損失だけでなく、企業の信用低下や法的責任にもつながります。
情報セキュリティにおける3つのリスク要素

情報セキュリティリスクを理解するために欠かせない、情報資産・脅威・脆弱性という3つの要素を解説します。
情報資産
情報資産とは、企業や組織が業務を遂行するうえで価値を持つ情報と、保持・活用する媒体のことです。
顧客データや従業員情報、契約書、知的財産、業務システム、サーバーなどが該当します。
脅威
脅威とは、情報資産に損害を与える可能性のある外部・内部の要因を指します。
サイバー攻撃や地震のような自然災害、従業員が情報を外部に持ち出す内部不正などがあります。
脆弱性
脆弱性とは、情報資産を守る仕組みや運用体制に存在する弱点のことです。
OSやソフトウェアの未更新、パスワード管理の甘さ、セキュリティ教育不足、不要な権限設定などがあります。
情報セキュリティリスクの種類

情報セキュリティリスクは、「機密性・完全性・可用性・物理的環境」の4つの視点で分類できます。
どれか一つでも対策が不十分であれば、情報漏洩や業務停止といった重大な被害に直結します。
それぞれのリスクの具体例と影響について解説します。
機密性リスク:不正アクセス
機密性リスクの一つが、不正アクセスによる情報漏洩です。
不正アクセスとは、権限のない第三者が企業のシステムやネットワークに侵入し、重要な情報資産にアクセスする行為を指します。
顧客情報や取引先データ、知的財産などが狙われるケースが多く、漏洩した場合の影響は計り知れません。
攻撃者はIDやパスワードの漏洩、システムの脆弱性、セキュリティ設定の不備を突いて侵入することがあり、企業は常にリスクに晒されています。
機密性リスク:内部脅威
情報漏洩の原因は外部攻撃だけでなく、内部からの脅威も無視できません。
従業員や元社員、業務委託先など正規の権限を持つ人物による情報の不正利用や漏洩は「内部脅威」と呼ばれ、対策が難しいとされています。
悪意のある行動だけでなく、不注意や知識不足による情報の誤送信、紛失も内部リスクに該当します。
完全性リスク:データの改ざん
業務データや会計情報が第三者によって書き換えられた場合、業績や意思決定に誤りが生じ、重大な経営リスクになります。
データベースに保存された記録が意図せず変更されることで、トラブルが発生することもあります。
完全性リスク:サイバー攻撃
サイバー攻撃によるリスクも企業にとって深刻です。
攻撃者は、マルウェアやランサムウェアなどを使って企業のシステムに侵入し、データを改ざんしたり破壊したりします。
サイバー攻撃によるデータの改ざんは、一見すると気付きにくく、長期にわたり損失を発生させる恐れがあります。
可用性リスク:サービス停止
可用性リスクとは、必要な際に情報やシステムが利用できない状況のことを指します。
サービスが一時的または長期的に停止することは、顧客対応や業務継続に大きな支障をきたします。
可用性リスク:ヒューマンエラー
ヒューマンエラーによるシステム停止や情報損失も、可用性リスクの一つです。
重要なデータの誤削除や設定ミス、誤操作などが原因で、業務の中断や重大なトラブルにつながるケースがあります。
クラウド環境やリモート作業の増加により、個人の操作ミスが大きな影響を及ぼすリスクも高まっています。
物理的リスク:自然災害
情報セキュリティリスクには、サイバー脅威だけでなく自然災害による物理的リスクも含まれます。
地震や台風、洪水などの災害が発生した際、データセンターやサーバーが被害を受け、重要な情報資産が失われる可能性が高いです。
通信インフラが損傷を受けると、業務の継続が困難になる恐れもあります。
物理的リスク:盗難・窃盗
オフィス内のパソコンやサーバーが盗難・窃盗されることも、情報セキュリティにおける物理的リスクの一つです。
ノートパソコンやUSBメモリなど、持ち運び可能な機器はリスクが高く、万が一盗難された場合には、内部の情報が漏洩する可能性があります。
顧客情報や営業データなどが外部に流出すれば、企業の信用問題にも発展しかねません。
情報セキュリティリスク対策の必要性
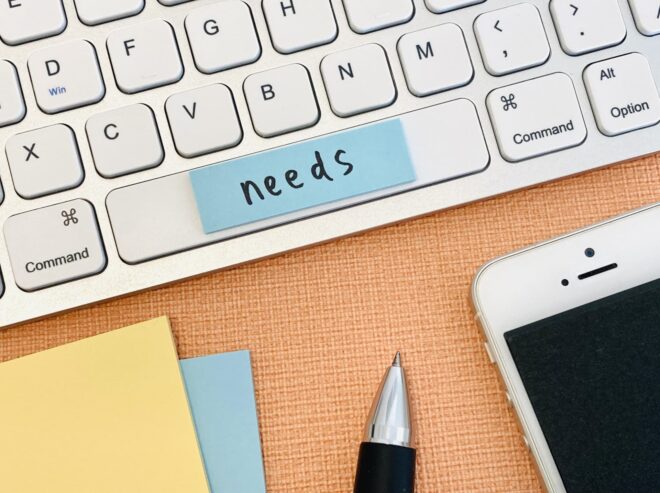
情報セキュリティリスクに適切に対処することは、企業活動の安定と成長に不可欠です。
経済的損失や顧客離れ、法的トラブルを未然に防ぐために欠かせない情報セキュリティ対策の必要性を解説します。
経済的損失の回避
情報セキュリティ対策を怠ると、サイバー攻撃や情報漏洩などによって多額の経済的損失を被る可能性が高いです。
顧客情報の流出が発覚した場合、被害者への補償金や訴訟費用、事故調査のための外部委託費用などが発生します。
取引先や顧客の信頼を失い、売上が減少することで、さらなる損害を被る恐れもあります。
顧客信頼の維持
企業が保有する個人情報や取引情報が漏洩した場合、大きなダメージを受けるのは顧客との信頼関係です。
一度失った信頼を取り戻すのは容易ではなく、SNSや口コミで悪評が拡散すれば、企業のブランド価値にも深刻な影響を与えるでしょう。
顧客情報の安全を守る取り組みは、単なる内部対策ではなく、対外的な評価にもつながる要素です。
事業の継続性の確保
情報セキュリティリスクに対して適切な対策を講じることは、企業が緊急時にも事業を止めずに継続するために欠かせません。
サイバー攻撃や自然災害、インフラ障害などが発生した際、システムのダウンやデータ損失が業務全体に影響を及ぼす可能性があります。
事前にBCP(事業継続計画)を策定し、障害時の復旧手順やバックアップ体制を整えておくことで、被害の最小化と早期回復が可能です。
クラウドサービスの活用や異なる拠点でのデータ保管といった分散管理は、災害対策としても有効です。
企業はもしもの事態に備えた体制を構築することで、継続的かつ安定的な業務運営を実現できます。
法的リスクの軽減
個人情報保護法やサイバーセキュリティ基本法、GDPRなど企業が順守すべき情報セキュリティ関連の法令は年々厳格化しています。
法規制に違反した場合、行政指導や業務停止命令、さらには高額な罰金が科されることもあり、経営に大きな打撃を与える可能性が高いです。
また、事故発生後に対応が不十分だった場合、損害賠償請求や社会的信用の低下という二次被害も招きかねません。
企業は法律の動向を常に把握し、自社のセキュリティ対策が法的要件を満たしているかを定期的に確認しましょう。
情報セキュリティリスクに対する具体的な施策

情報セキュリティリスクを防ぐためには、実践的かつ継続的な対策が大切です。
情報セキュリティリスクに対する具体的な施策について紹介します。
ウィルス対策ソフトの導入
ウィルス対策ソフトは、情報セキュリティ対策の基本的な施策の一つです。
コンピュータウィルスやマルウェアは、メールの添付ファイルやWebサイトの閲覧など日常的な業務の中でも容易に侵入してきます。
対策ソフトを導入することで、ウィルスの脅威を自動的に検出・駆除し、被害を未然に防ぐことが可能です。
多要素認証の導入
多要素認証(MFA)は、ユーザーがログインする際に複数の認証要素を組み合わせて本人確認を行うセキュリティ対策です。
一般的なIDとパスワードに加え、認証コードや指紋認証、顔認証などを組み合わせることで、不正ログインのリスクを減らせます。
パスワードが漏洩しても、追加の認証がなければアクセスを阻止できるため、情報漏洩リスクを最小限に抑えることが可能です。
ファイアウォールの設置
ファイアウォールは、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐための防壁となるセキュリティ機器です。
インターネットと社内ネットワークの間に設置することで、不審な通信を検出・遮断し、社内ネットワークを安全に保つ役割を果たします。
パケットの内容や送信元、送信先などに基づいて通信を制御することで、意図しない情報の流出や侵入を防ぐことに効果的です。
定期的な脆弱性診断
脆弱性診断は、システムやネットワークに存在するセキュリティ上の弱点を洗い出すための調査です。
ソフトウェアの設定ミスや古いバージョンの使用、パッチ未適用などが原因で、攻撃者に狙われやすくなります。
定期的に脆弱性診断を実施することで、問題点を早期に発見・修正し、被害の予防につなげることに有効です。
バックアップ体制の整備
情報セキュリティリスクに備えるうえで、バックアップ体制の整備は欠かせません。
サイバー攻撃や自然災害、人的ミスによって重要なデータが消失した場合でも、バックアップがあれば復旧が可能です。
バックアップは「どこに保存するか」「どれくらいの頻度で実施するか」がポイントになります。
クラウドストレージを活用した自動バックアップや、物理的に離れた拠点へのバックアップ保管が効果的です。
バックアップデータ自体も暗号化やアクセス制限をかけるなど、二次被害を防ぐ工夫が求められます。
従業員への情報セキュリティ教育
どれだけ技術的な対策を講じても、従業員の意識が低ければセキュリティは機能しないかもしれません。
情報漏洩やウィルス感染の多くは、人為的なミスや不注意によって引き起こされています。
パスワードの適切な管理方法や怪しいメールへの対応、機密情報の取り扱い方などを学び、全社員のセキュリティ意識を高めましょう。
情報セキュリティリスクを理解し、組織を守ろう

情報セキュリティリスクを正しく理解し、適切に管理することは、企業の存続と成長に直結する課題です。
近年、サイバー攻撃や内部不正、人的ミスなど情報セキュリティに関わる脅威は多様化・高度化しています。
一方で、対策が不十分なまま情報が漏洩すれば、企業は顧客からの信頼を失い、法的責任や多額の損失を負うリスクが高いです。
組織全体で情報セキュリティ意識を高め、堅牢なセキュリティ体制を築いていきましょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。




























