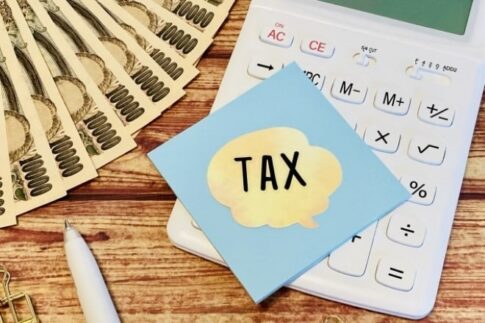M&A(合併・買収)を検討する企業にとって、「自社の価値は一体いくらなのか?」という問いは、避けては通れない最も重要なテーマの一つです。金融機関やM&A仲介会社に相談する前に、まずは自社のおおよその価値を把握したいと考えるでしょう。
しかし、専門用語が並ぶ難解な解説が多く、どこから手をつければ良いか分からないと感じる方も少なくありません。
この記事では、M&Aの専門知識がない方でも理解できるよう、企業価値の計算方法をわかりやすく具体的に解説します。アプローチ別・中小企業M&Aでよく使われる計算方法や計算できる専門家なども紹介します。
この記事を読めば、自社の企業価値を測るための具体的な計算方法・ステップが分かり、自社の正当な価値を把握できるでしょう。
目次
- 1 M&Aにおける企業価値(バリュエーション)とは?
- 2 「企業価値」「事業価値」「株式価値」3つの価値の違い
- 3 経営者が企業価値を把握すべき3つの理由
- 4 自社の現在地を正確に把握できる
- 5 経営改善の方向性が明確になる
- 6 M&A・事業承継の交渉で有利になる
- 7 【アプローチ別】企業価値の計算方法
- 8 コストアプローチ
- 9 マーケットアプローチ
- 10 インカムアプローチ
- 11 中小企業M&Aでよく使われる企業価値の計算方法3ステップ
- 12 ステップ1:会社の財産を棚卸しする「時価純資産法」
- 13 ステップ2:会社の稼ぐ力を上乗せする「年買法(年倍法)」
- 14 ステップ3:相場観を掴む「類似会社比較法(マルチプル法)」
- 15 【応用編】より理論的な計算方法「DCF法」
- 16 企業価値を高めるための3つの施策
- 17 社長がいなくても回る仕組みをつくる
- 18 不採算事業を見直し収益性の高い事業に力を入れる
- 19 借金やムダな支出を減らしてお金の流れを安定させる
- 20 M&Aの企業価値(バリュエーション)を計算できる専門家3選
- 21 金融機関
- 22 公認会計士・税理士
- 23 M&A仲介会社
- 24 企業価値の計算を依頼する際の注意点
- 25 依頼先の専門性と実績を確認する
- 26 目的に合った評価手法を提案してもらう
- 27 費用・報酬体系を事前に明確にしておく
- 28 M&Aの最終価格を決める3つのポイント
- 29 企業価値(バリュエーション)を把握し改善する
- 30 シナジー効果を買い手に具体的に示す
- 31 業績・市況・買い手の動向を見ながら交渉する
- 32 まとめ:まずは自社の企業価値(バリュエーション)を計算してみよう!
M&Aにおける企業価値(バリュエーション)とは?

M&Aにおける企業価値(バリュエーション)とは、対象企業の経済的価値を金額で算定するプロセスのことです。算出された評価額は、M&A取引の出発点となる「価格交渉の基準」であり、買い手・売り手双方にとって重要な指標となります。
- 買い手:過剰な支出を防ぎ適正な価格で投資判断を行うための判断材料
- 売り手:長年積み上げてきた事業の価値を正当に評価してもらうための根拠
企業価値の算定は、M&Aの成功を左右する最も重要なステップのひとつといえるでしょう。
「企業価値」「事業価値」「株式価値」3つの価値の違い
企業価値を理解する上で、まず押さえておきたいのが「企業価値」「事業価値」「株式価値」という3つの言葉の違いです。3つの価値は似ていますが、それぞれ意味が以下の表のように異なります。
| 用語 | 概要 | 計算イメージ |
|---|---|---|
| 事業価値 | 会社が本業によって将来生み出すキャッシュフローの価値 | 営業利益などから算出される「稼ぐ力」の価値 |
| 企業価値 | 会社全体の価値。事業価値に非事業用資産を加えたもの | 事業価値 + 預金や遊休不動産など |
| 株式価値 | 株主に帰属する価値。企業価値から負債を差し引いたもの | 企業価値 – 借入金など |
M&Aで会社を売却する際、最終的にオーナー経営者が手にする金額は、「株式価値」がベースとなります。
会社の本業の「稼ぐ力」を示す事業価値を算出し、事業とは直接関係のない資産(余剰な現預金や投資有価証券など)を加えたものが、会社全体の価値である企業価値です。企業価値から銀行からの借入金などの負債(有利子負債)を差し引いた残りが、株主の取り分である株式価値となります。
経営者が企業価値を把握すべき3つの理由

複雑な計算を専門家に任せる前に、経営者自身が企業価値の計算方法を理解しておくべきです。ここからは、経営者が企業価値を把握すべき3つの理由を解説します。
自社の現在地を正確に把握できる
企業価値を算出することで、自社の現在地を正確に把握できます。企業価値を計算する過程で財務状況や収益性、資産内容などを数値化して分析するため、経営の実態を客観的に確認できるからです。例えば、普段の経営では気づかない利益率の低い部門や、眠っている資産なども可視化されるため、強みと弱みが明確になります。
企業価値を計算することで、感覚的な判断に頼らず根拠ある経営戦略を立てられます。
経営改善の方向性が明確になる
経営者が企業価値を把握することで、経営改善の方向性が明確になります。企業価値を構成する要素を分析することで、「どの部分の評価を高め、どの部分の評価を下げていいのか」具体的な方向性が見えてくるからです。例えば、収益性は高いものの過剰な借入金が株式価値を圧迫している場合、改善が優先課題であると判断できます。
経営者が企業価値を把握し課題を明確にすることで、どの分野に注力すべきかが見えてくるため、効果的な経営戦略を立てられます。
M&A・事業承継の交渉で有利になる
経営者が企業価値を正しく把握しておくことは、M&Aや事業承継の交渉を有利に進めるうえで大きな武器になります。自社の価値を理解していれば、提示された買収価格や評価額の妥当性を自ら判断できるからです。具体的には、専門家や買い手側の提示額に対して、収益性や成長性、保有資産などの根拠をもとに自社の価値を説明できれば、価格交渉で主導権を握れます。
逆に企業価値を理解していないと、相手の提示をそのまま受け入れてしまうリスクが発生します。自社の価値を正確に把握し論理的に主張できることが、より有利な条件でM&A・事業承継の成功につながるでしょう。
【アプローチ別】企業価値の計算方法

企業価値の計算方法には、大きく分けて3つのアプローチがあります。それぞれ異なる視点から企業の価値を評価するため、M&Aの実務では複数の方法を組み合わせて多角的に分析するのが一般的です。ここでは、アプローチ別の企業価値の計算方法を3つ解説します。
コストアプローチ
コストアプローチは、企業の貸借対照表(B/S)に記載された純資産を基準に企業価値を算出する方法です。会社のすべての資産を時価で評価し、負債を差し引いた「残り(純資産)」を企業価値とみなします。会社を清算した際に、株主へどれだけの資産が残るかという視点で評価する手法です。
客観的なデータを用いるため信頼性が高く、資産を多く保有する企業や赤字企業の評価に適しています。しかし、将来の収益力やブランド価値、人材などの無形資産を反映できないため、実際の企業価値を過小評価してしまう場合があります。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、評価対象となる企業と事業内容や規模が近い上場企業の株価や、過去のM&A取引事例をもとに企業価値を算出する方法です。株式市場という客観的な「市場のモノサシ」を活用することで、投資家や買い手に対して説得力のある評価が可能になります。
実際には、同業他社の株価指標(PERやEBITDA倍率など)を基準に、自社の数値を掛け合わせて企業価値を推定します。ただし、中小企業の場合は、同等の事業規模・業種を持つ上場企業を見つけにくく、完全一致する比較対象が得られません。マーケットアプローチは、相場感を掴む補助的な評価方法として用いられることが多いです。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、企業が将来生み出すと見込まれる利益や、キャッシュフローをもとに企業価値を算出する方法です。過去の業績だけでなく、成長性や収益性といった「将来の稼ぐ力」を評価に反映できるため、理論的で実践的な手法として広く用いられています。
将来のキャッシュフローを現在価値に割り引く手法が、「DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)」です。ただし、将来予測には評価者の主観が入りやすく、前提条件の違いで結果が大きく変動するリスクがあります。インカムアプローチは、精度の高い分析と専門的な知識が求められる評価手法と言えるでしょう。
中小企業M&Aでよく使われる企業価値の計算方法3ステップ

アプローチ別の計算方法の他に、中小企業M&Aでよく使われる計算方法があります。専門家でなくても比較的簡単に企業価値を計算できます。まずはこの方法で、自社の価値を大まかに掴んでみましょう。
ステップ1:会社の財産を棚卸しする「時価純資産法」
最初のステップは、コストアプローチの代表格である「時価純資産法」です。会社の資産と負債を現在の価値(時価)に置き換えて、純資産を計算する方法です。
- 計算式:時価純資産 = 時価総資産 – 時価総負債
決算書に記載されている金額(簿価)は、取得した時点の価格であることが多く、現在の価値と乖離している場合があります。より実態に近い価値を算出するために、主要な資産・負債を時価に評価し直す作業が必要です。
| 勘定科目 | 簿価(決算書上の金額) | 時価評価のポイント |
|---|---|---|
| 土地 | 取得時の価格 | 近隣の取引事例や路線価などを参考に評価 |
| 建物 | 減価償却後の価格 | 固定資産税評価額などを参考に評価 |
| 有価証券 | 取得時の価格 | 上場株式は期末の株価、非上場株式は別途評価 |
| 在庫 | 取得時の価格 | 販売が困難な不良在庫は価値をゼロとして評価 |
| 退職給付引当金 | 計上額 | 全従業員が自己都合で退職した場合の要支給額で再計算 |
ステップ2:会社の稼ぐ力を上乗せする「年買法(年倍法)」
ステップ1で計算した時価純資産は、いわば会社の「解散価値」です。しかし、会社は事業を継続することで利益を生み出します。将来の「稼ぐ力」を価値に上乗せするのが「年買法(年倍法)」です。
計算式:企業価値 ≒ 時価純資産 + 営業利益 × 2〜5年分
「営業利益 × 2~5年分」の部分は、「のれん(営業権)」と呼ばれます。のれんとは、ブランド力や技術力、顧客基盤といった決算書には表れない無形の価値のことです。何年分の営業利益を加算するかは、業界の慣行や会社の安定性、成長性によって変動します。一般的には2年〜5年分が目安とされています。
ステップ3:相場観を掴む「類似会社比較法(マルチプル法)」
最後のステップは、マーケットアプローチの代表格である「類似会社比較法(マルチプル法)」を使って、業界の相場観を確認することです。
計算式:企業価値 ≒ EBITDA × EV/EBITDA倍率
| EBITDA | 税金や金利、減価償却費を差し引く前の利益(本業での現金創出力) |
| EV/EBITDA倍率(マルチプル) | 類似する上場企業の企業価値がEBITDAの何倍になっているかを示す数値 |
自社のEBITDAにEV/EBITDA倍率(マルチプル)倍率を掛けることで、市場の評価に基づいた企業価値を簡易的に算出できます。ただし、中小企業の場合はあくまで参考値として捉え、ステップ2の年買法と合わせて総合的に判断することが重要です。
【応用編】より理論的な計算方法「DCF法」

前述した計算方法より精密に企業価値を評価したい場合には、インカムアプローチの代表的な手法である「DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)」が用いられます。DCF法は、会社が将来生み出すと予測されるフリー・キャッシュフローを、将来のリスクを考慮した割引率で現在価値に換算・合計し企業価値を算出する方法です。
将来の事業計画を詳細に評価に反映できるため、最も理論的な手法とされています。しかし、計算プロセスが複雑で、事業計画の精度や割引率の設定に専門的な判断が求められます。DCF法による評価は、M&Aの専門家に依頼するのが一般的です。
企業価値を高めるための3つの施策

企業価値を高めるためには、単に売上を伸ばすだけでなく、会社の「中身」を整えることが大切です。M&Aを視野に入れる場合、買い手が安心して引き継げる経営体制や、安定した収益構造を持つことが高い評価につながります。
ここでは、どんな会社でもすぐに取り組める、企業価値を上げるための3つの具体的な施策を紹介します。
社長がいなくても回る仕組みをつくる
企業価値を高めるうえで重要なのが、社長がいなくても会社が回る仕組みをつくることです。特に中小企業では社長の経験や勘に頼った経営が多く、社長が抜けると業務が止まってしまうケースも少なくありません。しかし、M&Aの買い手は、経営者が退いた後も事業が安定して続けられるかを重視します。
業務マニュアルの作成や権限委譲を進めることで、社員が自律的に動ける体制を整えることが大切です。社長不在でも利益を生み出せる「仕組み化された会社」は将来性が高いと評価されるため、結果的に企業価値の向上につながります。
不採算事業を見直し収益性の高い事業に力を入れる
企業価値を上げるためには、まず儲かっていない事業を見直し、利益を生み出している事業に経営資源を集中させることが重要です。不採算事業をそのまま抱えていると、人材や資金が分散し全体の収益性が下がってしまいます。一方で、収益性の高い事業に力を入れることで、利益率の向上やキャッシュフローの改善が見込めます。
具体的には、赤字が続く部門の撤退や統合、新規顧客を獲得しやすい分野へのシフトなどが効果的です。選択と集中を進めることで、会社の経営基盤が強化され、将来的な成長性やM&Aでの評価額アップにもつながります。
借金やムダな支出を減らしてお金の流れを安定させる
企業価値を高めるには、健全な財務体質を築き、お金の流れを安定させることが欠かせません。借入金が多すぎたりムダな支出が多かったりする状態では、利益が出てもキャッシュが残らず、買い手から「リスクの高い企業」と判断されてしまいます。
まずは不要な資産や使われていない保険、過剰在庫などを整理することで、借入金の返済計画を立てることが重要です。固定費の見直しやコスト削減を行うことで、キャッシュフローも改善できます。資金繰りが安定した企業は、経営の継続性が高くM&Aの際にも安心して評価される傾向があります。
M&Aの企業価値(バリュエーション)を計算できる専門家3選

より正確な評価やM&Aの実行を検討する際には、専門家に頼る選択肢もあります。しかし、誰に頼ってもいいわけではありません。正確にM&Aにおける企業価値を計算できる専門家を選ぶ必要があります。ここでは、企業価値の計算を依頼できる主な専門家を紹介します。
金融機関
金融機関は、M&Aに関する相談先として有力な選択肢の一つです。取引のある銀行や証券会社では、専用のM&A相談窓口を設けているケースが多く、企業価値(バリュエーション)の算定や買収・売却に関する初期相談に対応してくれます。
ただし、すべての担当者が中小企業のM&A実務や企業評価に精通しているとは限りません。担当者の経験や専門性をしっかり確認し、必要に応じてM&A専門会社やアドバイザーと併用することが望ましいでしょう。
公認会計士・税理士
公認会計士や税理士は、企業価値の計算を依頼するうえで信頼性の高い専門家です。日頃から自社の財務状況を把握している顧問税理士や、M&Aに精通した公認会計士であれば、財務・税務の観点から客観的かつ正確な企業価値(バリュエーション)が算出できるからです。
数値の裏付けをもとに、過大・過小評価のない現実的な企業価値の把握が可能です。ただし、会計士や税理士の専門領域はあくまで価値評価や税務処理であり、M&Aの買い手探しや交渉の仲介は通常行いません。実際の取引を進める場合は、M&A仲介会社との併用が有効です。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、M&Aの全プロセスを専門的にサポートするプロフェッショナルです。企業価値(バリュエーション)の算出はもちろん、買い手・売り手双方のマッチングから条件交渉、契約締結まで一貫して支援してくれます。豊富な実績と独自のネットワークを活かし、経営者に代わって最適な相手企業を見つけることが可能です。
当社パラダイムシフトのようにIT業界など特定分野に強みを持つ仲介会社では、業界特有の知見を活かした戦略的な提案ができます。M&Aに関する総合的なサポートを求める経営者にとって、最も心強いパートナーになれます。
企業価値の計算を依頼する際の注意点

企業価値の計算は、専門的な知識と経験が求められるため、信頼できる専門家に依頼することが大切です。依頼先を間違えると、評価が偏ったり不要な費用が発生したりするリスクがあります。ここからは、企業価値の計算を専門家に依頼する際、失敗しないために押さえておくべき3つのポイントを紹介します。
依頼先の専門性と実績を確認する
企業価値の計算を依頼する際は、依頼先の専門性と実績を必ず確認してください。企業価値の算定には財務分析だけでなく、業界の動向やM&Aの知識、評価手法に関する深い理解が求められます。例えば、同じ業種でも市場特性や利益構造によって適切な評価手法は異なるため、経験の浅い担当者では正確な算定が難しい場合があります。
これまでのM&A支援実績や、特定業界に強みを持つ専門家であるかを事前に確認しましょう。専門性の高い依頼先を選ぶことで、信頼性の高い企業価値の算定を受けられ、交渉や意思決定にも自信を持って臨めます。
目的に合った評価手法を提案してもらう
企業価値の計算を依頼する際は、依頼目的に合った評価手法を提案してもらいましょう。M&Aの目的によって、重視すべきポイントが異なるからです。事業承継などで会社の現状価値を知りたい場合は、資産を基準に評価する「コストアプローチ」が適しています。
一方、成長性を踏まえた将来の価値を知りたい場合は、「インカムアプローチ」「DCF法」が有効です。目的と手法が合っていないと、実際の価値よりも過大・過小評価になるリスクがあります。依頼先には自社の目的を明確に伝え、最適な評価手法を選定してもらうことが正確な算定につながります。
費用・報酬体系を事前に明確にしておく
企業価値の計算を専門家に依頼する際は、費用や報酬体系を事前に明確にしておくことが重要です。料金体系には通常、以下の2通りあります。
- あらかじめ金額が決まっている「固定報酬型」
- 成果に応じて支払う「成功報酬型」
なかには初回相談料や資料作成費、追加分析費などが別途発生するケースもあるため、見積もり段階で細かく確認しておくことが大切です。
費用の仕組みを理解せずに依頼してしまうと、想定以上のコストがかかる場合があります。契約前に報酬の内訳や支払い条件、追加費用の有無をしっかり確認することで、トラブルを防ぎ安心してM&Aを進められるでしょう。
M&Aの最終価格を決める3つのポイント

これまで解説してきた企業価値の計算方法は、あくまでM&Aの価格交渉における出発点を決めるためのものです。最終的な売却価格は、算出された企業価値をベースに以下の3つのポイントを考慮した当事者間の交渉によって決まります。ここからは、M&Aの最終価格を決める3つのポイントをわかりやすく解説します。
企業価値(バリュエーション)を把握し改善する
M&Aで適正かつ有利な価格を得るためには、まず自社の企業価値(バリュエーション)を客観的に把握することが欠かせません。財務データや収益性、資産状況を基に現状を正確に把握し、評価額を高めるための経営改善を行うことが重要です。具体的には、不採算事業の整理や収益性の高い分野への経営資源の集中などが有効です。
事前に企業価値を高めておくことで、交渉を有利に進めることができるほか、将来的な企業成長の基盤づくりにもつながります。企業価値の把握は、M&Aだけでなく継続的な経営改善のための有効な指標となります。
シナジー効果を買い手に具体的に示す
M&Aにおいて買い手企業が重視するのは、対象企業を単体で見た価値だけでなく統合後に生まれる「シナジー効果」です。シナジー効果とは、販路拡大や技術共有による新製品開発、コスト削減など、両社の強みを組み合わせることで1+1が2以上になる相乗効果を指します。
売り手は、自社と買い手が組むことでどのような成長が見込めるのか、具体的なデータや事例を交えて提示することが重要です。シナジー効果を買い手に明確に示すことで、企業価値向上につながる可能性を訴求でき、結果的に評価額以上の価格で売却できる可能性も高まります。
業績・市況・買い手の動向を見ながら交渉する
M&Aの最終価格を高めるには、自社の業績や市場環境、買い手の動向を見極めながら交渉のタイミングを計ることが重要です。一般的に自社の業績が好調で市場全体が活発な時期に交渉を進めると、高値での売却が実現しやすくなります。複数の買い手候補がいれば、競争原理が働きより有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
業界の景気動向や買い手企業の戦略、資金状況などを総合的に分析しましょう。短期的な要因だけでなく、中長期的な市場トレンドを踏まえた戦略的判断が求められます。
まとめ:まずは自社の企業価値(バリュエーション)を計算してみよう!
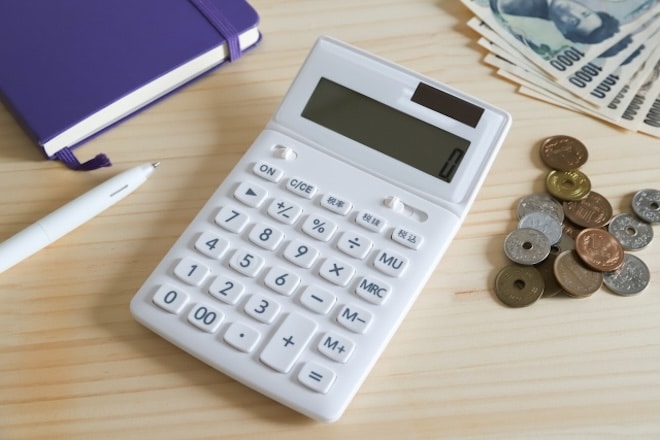
M&Aにおける企業価値は、一見すると複雑で専門的に思えるかもしれません。しかし、基本的な考え方やアプローチ別、中小企業の実務で使われる計算方法を理解することは、M&Aを検討する経営者にとって重要です。まずはこの記事で紹介した「時価純資産法」と「年買法」を使い、自社の価値を大まかに計算してみてください。
おおまかに計算した数字でも、M&Aの検討はもちろん、今後の経営戦略を見直す上での貴重な羅針盤となります。自社の価値を客観的に把握することは、会社の未来を切り拓くための力強い第一歩となるでしょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。