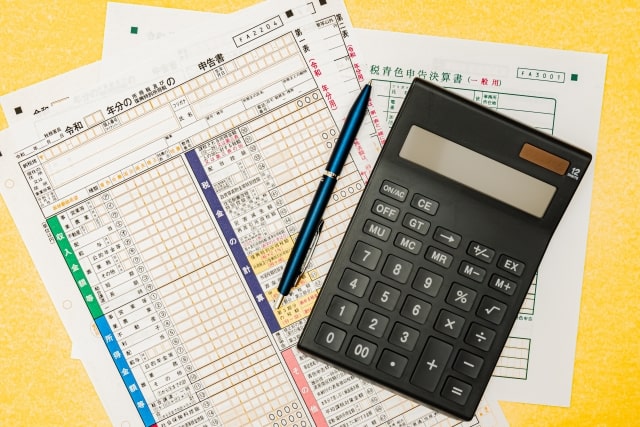「所得税ってなんだか複雑…」「総合課税と分離課税の違いがよくわからない」「確定申告、どう書けばいいの?」毎年やってくる確定申告の時期、このような疑問や不安を感じている担当者は多いのではないでしょうか。
所得の種類が複数ある企業にとって、総合課税の仕組みを正しく理解することは、適切な納税と賢い節税のために不可欠です。
この記事では、所得税の基本である総合課税について、定義や仕組み、対象となる所得の種類といった基礎知識から、具体的な税額の計算ステップ、所得控除や損益通算を活用した節税のポイントまで、わかりやすく解説します。
総合課税のメリット・デメリットを整理し、具体的なケース別に総合課税と分離課税のどちらが有利になるのかについても詳しく見ていきます。
この記事を読めば、複雑に思えた総合課税の全体像が掴め、ご自身が勤めている企業の状況に合わせた適切な確定申告や、効果的な税金対策を行うための知識が身につきます。
ぜひ最後までお読みいただき、総合課税への理解を深め、賢く税金と向き合いましょう。
目次
- 1 総合課税の基本知識
- 2 総合課税の定義
- 3 総合課税の仕組み
- 4 総合課税と分離課税の違い
- 5 総合課税の対象となる所得5つ
- 6 利子所得
- 7 配当所得
- 8 不動産所得
- 9 事業所得
- 10 給与所得
- 11 総合課税の税率計算ステップ
- 12 所得金額を計算する
- 13 所得税率を確認する
- 14 税額を計算する
- 15 復興特別所得税を計算する
- 16 総合課税の確定申告の書き方
- 17 総合課税のメリット
- 18 所得控除による節税効果
- 19 損益通算による節税効果
- 20 総合課税のデメリット
- 21 税率が高くなる可能性がある
- 22 確定申告の手間がかかる
- 23 【ケース別】総合課税と分離課税どちらが得
- 24 不動産所得がある場合
- 25 高額な一時所得が発生した場合
- 26 株式投資の譲渡益が発生した場合
- 27 まとめ:総合課税を理解して賢く税金対策を!
総合課税の基本知識
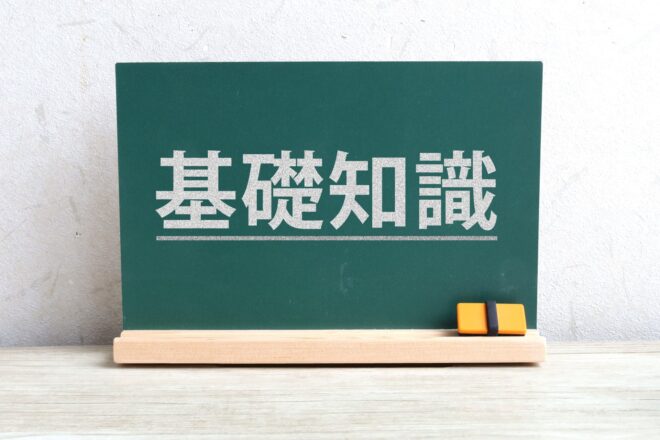
税制の仕組みを正しく理解することは、個人の財務管理や節税対策において非常に重要です。なかでも「総合課税」は、所得税や住民税の計算に深く関わる重要な概念です。
ここでは、総合課税の定義や仕組み、分離課税との違いについてわかりやすく解説します。
総合課税の定義
総合課税とは、個人が1年間に得た所得を合算し、その合計額に基づいて課税される制度です。
日本の所得税法では、所得を10種類(給与所得、事業所得、不動産所得など)に分類していますが、そのうち多くの所得が総合課税の対象となります。
総合課税の仕組み
総合課税では、以下の流れで税額が決まります。
- 各種所得(例:給与、事業、不動産など)を合算して「総所得金額」を求める
- 所得控除(基礎控除、扶養控除など)を差し引き、「課税所得」を計算する
- 課税所得に応じた「累進税率」を適用して所得税額を算出する
累進税率とは、所得が増える程高い税率が適用される仕組みで、所得の大きさに応じて税負担が変わるのが特徴です。
この仕組みにより、所得に応じた負担が求められ、バランスの取れた課税制度となっています。
総合課税と分離課税の違い
総合課税とよく比較される制度に、「分離課税」があります。両者の大きな違いは、適用される税率と、所得を合算するかどうかという点です。
総合課税では、給与や事業、不動産など複数の所得を合算し、累進税率により課税されます。分離課税では、株式や不動産の譲渡益、一部の利子所得などを他の所得と分けて計算し、一律の税率で課税されます。
例えば、高額な株式売却益があっても分離課税であれば、給与と合算されず一定の税率で課税されるため、全体としての税負担が抑えられる可能性があります。
反対に、総合課税では所得が多いほど税率が上がるため、負担が大きくなる傾向にあります。
総合課税の対象となる所得5つ

総合課税の対象となる所得の中から、代表的な5つの所得(利子・配当・不動産・事業・給与)を取り上げ、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
利子所得
利子所得とは、預貯金や債券などから得られる利息のことです。通常、国内の金融機関から発生する利子は分離課税の対象で、税金があらかじめ差し引かれているため、確定申告は不要です。
ただし、海外の銀行預金の利子や、親族が経営する会社が発行した社債の利子など、一部の利子所得は、総合課税の対象となるため、確定申告が必要です。
配当所得
配当所得とは、株式会社の配当金や投資信託の分配金などから得られる所得です。
課税方法には「総合課税」「申告分離課税」「申告不要制度」の3つがあり、いずれかを選択することができます。
総合課税を選んだ場合は、配当控除の適用によって税負担を軽減できます。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などを貸し出すことで得られる賃貸収入から、必要経費(修繕費や固定資産税など)を差し引いた金額です。
アパート経営や駐車場の貸付けによる収入などが該当し、すべて総合課税の対象となります。
経費を適切に計上すれば、課税所得を抑えて節税につなげることも可能です。
事業所得
事業所得とは、個人事業主が事業活動(飲食業、フリーランス、販売業など)を通じて得た収入から、必要経費を差し引いた金額です。
自営業や副業などで得る収入がこれにあたり、総合課税の対象となります。
一方、株式の譲渡や不動産の貸付による所得は、事業所得ではなく、それぞれ別の区分で課税されます。
給与所得
給与所得とは、会社や団体などから受け取る給料・賞与などの報酬を指します。もっとも多くの人が該当する代表的な所得であり、総合課税の対象です。
給与所得には「給与所得控除」が適用され、一定の金額までは課税対象から差し引かれます。通常は勤務先で源泉徴収されますが、副収入がある場合や医療費控除を受ける場合などは、確定申告が必要になることがあります。
総合課税の税率計算ステップ

総合課税では、さまざまな種類の所得を合算して課税されるため、正確な税額を求めるには段階的な計算が必要です。
ここからは、所得金額の算出から復興特別所得税まで、税率計算の基本的な流れをわかりやすく解説します。
所得金額を計算する
まずは、1年間に得た所得を各分類ごとに集計し、それぞれの「収入金額」を把握します。
これには、給与所得や事業所得、不動産所得などが含まれます。
そこから必要経費や各種控除を差し引いた後の金額が「所得金額」となります。
所得税率を確認する
次に、算出した所得金額に応じて適用される所得税率を確認します。日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率も段階的に高くなります。
税率は5%から始まり、最高で45%までの7段階に区分されています。税率と計算に使える「速算表」は、国税庁HPから参照可能です。
税額を計算する
所得金額と適用税率が決まったら、実際の税額を計算します。ただし、所得税は累進課税制度のため、「所得全体に一律の税率をかける」わけではありません。
そのため、課税所得がどの税率区分に該当するかを確認し、次の計算式を用いて税額を算出します。
課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税額
例えば、課税所得が700万円の場合、適用される税率は23%、控除額は63万6,000円なので、
7,000,000円 × 0.23 − 636,000円 = 974,000円
となります。なお、最終的な税額は、ここから「税額控除」や「配当控除」などを差し引いて調整されることもあります。
復興特別所得税を計算する
最後に、東日本大震災からの復興財源を確保するために導入された「復興特別所得税」を加算します。この税は、算出された所得税額の2.1%に相当し、2037年までの期間限定で課税されています。
例えば、所得税額が974,000円の場合、
974,000円 × 0.021 = 20,454円
が復興特別所得税として加算されます。最終的な納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額です。なお、税制は年々変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが大切です。
総合課税の確定申告の書き方

総合課税の対象となる所得がある場合は、原則として確定申告が必要です。
申告には、国税庁が提供する 「e-Tax(電子申告)」を利用する方法、用紙を印刷して郵送または税務署に持参する方法の2通りがあります。e-Taxを使えば、自宅からオンラインで申告・送信でき、非常に便利です。
申告にあたっては、まず1年間の所得と各種控除額を整理し、「確定申告書」を作成します。作成した申告書は、e-Taxで提出するか、印刷して郵送または税務署に持参することで提出が完了します。
総合課税のメリット

総合課税には、所得控除や損益通算など、節税につながる様々なメリットがあります。
ここでは、代表的な2つのメリットについて分かりやすく解説します。
所得控除による節税効果
総合課税では、基礎控除・扶養控除・医療費控除など、さまざまな所得控除を適用することができます。これにより課税対象となる所得が減り、結果として支払う税額を抑えることが可能です。
特に、扶養家族がいる場合や、医療費の支出が多い年には、こうした控除の恩恵を受けやすくなります。
損益通算による節税効果
不動産所得や事業所得などで損失が出た場合、総合課税では他の所得と損益通算することが可能です。これにより、全体の課税所得が減少し、税負担を抑えることが可能です。
例えば、不動産所得が赤字だった場合、事業所得と損益通算することで、最終的な税額を軽減できます。
総合課税のデメリット
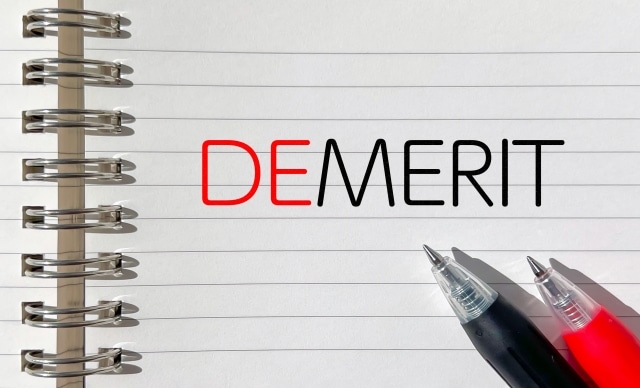
総合課税には注意すべきデメリットもあります。
ここでは、総合課税の2つのデメリットについて解説します。
税率が高くなる可能性がある
総合課税は、所得の合計額に応じて税率が段階的に上がる「累進課税制度」が適用されます。
例えば、不動産所得や事業所得など、複数の所得がある場合、それらが合算されることで、より高い税率が適用される可能性があります。
結果として、想定以上に税負担が増えるケースもあるため、注意が必要です。
確定申告の手間がかかる
総合課税の対象となる所得がある場合、確定申告が必要になることがあります。特に、給与所得以外に不動産所得や事業所得がある方、医療費控除や寄附金控除を受けたい方は、自身で申告する必要があります。
その際は、1年間の所得や控除額を整理し、必要書類を揃えて提出するなど、一定の手間や時間がかかる点がデメリットです。
【ケース別】総合課税と分離課税どちらが得

課税方法は、所得の種類によって法律で定められており、自由に選べるわけではありません。
ここからは、代表的な所得のケースごとにどの課税方式が適用されるのか、そしてその際に注意したいポイントを分かりやすく紹介します。
不動産所得がある場合
不動産所得は総合課税の対象です。必要経費を適切に計上したり、青色申告を活用することで、課税所得を減らすことが可能です。また、不動産所得が赤字となった場合には、事業所得など他の総合課税の対象所得と損益通算を行うことで、全体の税額を抑えることができます。
一方で、不動産所得が黒字になると、他の所得と合算されるため、累進税率が適用され、税負担が増える可能性もあります。所得全体のバランスを見ながら、適切な節税対策を検討することが重要です。
高額な一時所得が発生した場合
懸賞金や保険の満期金などによって一時所得が発生した場合の所得は、総合課税の対象となります。一時所得の課税対象額は、次の計算式で求められます。
(収入金額 − 必要経費 − 特別控除額※) × 1/2 = 課税対象額
※特別控除額は最高50万円まで適用されます。
このように、一時所得は他の所得に比べて優遇された計算方法が用いられていますが、金額が大きくなると、他の所得と合算され、累進税率の影響を受けて税負担が増える可能性があります。特に他に高額な所得がある年は、所得全体の構成を考慮し、事前の準備や対策が重要です。
株式投資の譲渡益が発生した場合
株式の売却による譲渡益は、分離課税の対象です。分離課税では、一律約20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税含む)の税率が適用され、他の所得とは分けて計算されます。そのため、総合課税のように所得が増えても税率が上がることはありません。
また、同一年内に株式の損失が出ている場合は、利益と損失を損益通算することで、課税所得を減らすことが可能です。
まとめ:総合課税を理解して賢く税金対策を!

総合課税は、所得の合計額に応じて課税率が決まる仕組みです。所得控除や損益通算などの制度を上手に活用すれば、税負担を抑えることが可能です。
配当所得など一部の所得では、課税方式を選択できる場合もあります。自分の収入状況や控除内容に応じて、どちらの課税方法が有利かを見極めることが大切です。
総合課税のしくみを正しく理解し、自分に合った方法で確定申告や節税対策を進めていきましょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。