M&Aとは、譲渡企業にとって成長戦略として活用することができる、最近話題を集めている手法です。
しかし、M&Aは売り手よりも買い手の立場が強いため、M&Aを成功させるハードルが高くなっています。
M&Aを実施する際には金融機関や専門家に丸投げするのではなく、具体的な目標を明確にし、目的に沿った戦略を実施することが重要です。
戦略をしっかり構築することによって、M&Aの成功の可能性を高められます。
この記事では、M&Aの戦略とは何か、ポイントをおさえて解説します。
目次
- 1 M&A戦略とは
- 2 M&A戦略策定の目的
- 3 M&A戦略の目的1.経営の安定化
- 4 M&A戦略の目的2.事業拡大
- 5 M&A戦略の目的3.雇用の維持
- 6 M&A戦略の目的4.後継者問題の解決
- 7 M&A戦略策定の方法
- 8 M&A戦略の方法1.SWOT分析(自社の分析)を行う
- 9 M&A戦略の方法2.目的を決める
- 10 M&A戦略の方法3.市場調査を行う
- 11 M&A戦略の方法4.アプローチ方法を決める
- 12 M&A戦略の方法5.戦略オプションを検討する
- 13 【ケース別】M&A戦略を立案する際のポイント
- 14 事業を整理する場合
- 15 事業承継する場合
- 16 事業拡大を図る場合
- 17 イグジットする場合
- 18 新規事業を立ち上げる場合
- 19 M&A戦略を策定する際の注意点
- 20 目的忘れずに交渉する
- 21 M&Aが最善の方法かを検討する
- 22 見通しを精査する
- 23 M&A戦略の知識をつけて、信頼できる専門家に相談しよう
M&A戦略とは

M&Aというと、中小企業の経営者の方は「大企業の合併だから中小企業は関係ない」「ドラマで観たように設備や不動産を根こそぎ持っていかれる」とネガティブな印象を持たれているかもしれません。
しかし、中小企業が買い手もしくは売り手のM&Aは増加しており、譲渡企業にとってもM&Aは事業の拡大など成長戦略につながるものです。M&Aを実施する際には目標を明確にして、目標に向かって行動計画を策定する必要があります。
これがM&A戦略と呼ばれるものです。M&Aの成功の是非は目標に沿った戦略立案にあると言っても過言ではありません。
M&A戦略策定の目的

M&A戦略策定のためには、目的を明確にすることが重要です。M&Aにはメリットとデメリットがあるため、自社の分析に基づいて目的を明確にしておくことが必要です。
経営者や株主、取引先、金融機関、従業員など様々な利害関係者の視点で影響を分析し、会社の成長のために目的を立てましょう。M&Aを実施する背景には様々な目的があるため、目的によって戦略や戦略に基づく行動計画が変わります。
M&A戦略の目的1.経営の安定化
M&Aによる経営安定化には、主に以下の2つの方法があります。
- 事業の選択と集中
- 事業の多角化
事業の選択と集中では、売り手企業が利益率の低い事業を売却し、経営資源を収益性の高い分野に集めることで体力強化が可能です。人口減少や少子高齢化により収益確保が難しくなる日本市場では、不採算事業の切り離しが大きな効果をもたらします。
一方、事業の多角化は買い手側の戦略で、実績ある企業を買収することで新しい収益源を確保し、市場変化へのリスク分散を図る方法です。売り手・買い手双方が経営基盤を安定させられます。
M&A戦略の目的2.事業拡大
買い手側にとっては、M&Aによって新しいビジネスチャンスを獲得できます。自社で一から新規事業を立ち上げようとすると、事業の立ち上げに時間がかかり、既に市場に算入している競合他社に大きさな差をつけられてしまいます。
新規事業を開始する際には、競合他社に先んじて事業に参入し、投資した資本をすぐに回収できることが理想です。M&Aによって市場で実績のある企業を買収することで、譲渡企業の持つ技術力やブランド力を活かして参入障壁を突破し、短期で軌道に乗せられます。
M&A戦略の目的3.雇用の維持
中小企業が悩まされている問題が、後継者問題です。素晴らしい技術やブランドを保有しているにもかかわらず、後継者がいないために廃業してしまう企業も少なくありません。ただし、M&Aを実施した場合は従業員の雇用が維持されるのが一般的です。
M&Aによって経営者が引退した後も事業が継続されるならば、従業員は現在の職場で働き続けられます。M&A後は、規模が大きく安定した基盤を持つ企業の傘下に入るため、従業員の活躍の場も広がります。給与等の待遇面を改善される可能性も高いです。
M&A戦略の目的4.後継者問題の解決
多くの中小企業では、経営者の高齢化や後継者が見つからない問題が深刻になっています。2020年版の中小企業白書によれば、経営者の平均年齢は毎年上昇傾向にあり、経営者の50%以上が60代以上と経営者の高齢化が進んでいます。
2025年時点で引退年齢を迎え中小企業経営者245万人のうち、約半数の127万社で後継者が決まっておらず、事業承継の体制が整っていません。親族や従業員に後継者がいない場合や経営の能力がない場合には、M&Aによる事業承継が有効な手段です。
M&A戦略策定の方法

M&A戦略の目的化の明確化の重要性について説明してきましたが、ここからはM&A戦略策定の方法を解説します。自社や業界の分析を行い、経営戦略を立てるまでの流れを掴みましょう。
M&A戦略の方法1.SWOT分析(自社の分析)を行う
M&Aの戦略策定では目的を明確することが重要であることは解説したとおりですが、目的を明確にするためには自社の分析を行います。経営者が自社の事業や組織の現状を俯瞰して、自己分析する手法としてSWOT分析があります。SWOTは以下の略称です。
- Strength(強み)
- Weakness(弱み)
- Opportunity(機会)
- Threat(脅威)
Strengthは自社の内部環境の強い部分、Weaknessは弱い部分です。例えば、営業部門が強いやバックオフィス業務が非効率などがあります。
一方で、OpportunityとThreatは外部の市場の機会と脅威であり、業界の規模や成長性、トレンド、競合の動向や法律の改正などです。SWOT分析を行うことで自社の経営環境を理解し、M&Aの目的や目標を設定します。
M&A戦略の方法2.目的を決める
SWOT分析完了したら、M&Aの目的を明確にします。目的は企業によって異なりますが、売り手側と買い手側の視点から一般的な目的についてご紹介します。M&Aの目的な今後の事業戦略の中核となるものです。売り手側の目的としてまず考えられるのが、事業承継です。
経営者の高齢化や親族や従業員に後継者がいない場合、非上場の中小企業ではM&Aによって社外の第三者へ事業承継をするケースがあります。経営の効率化も目的の一つです。
M&A戦略の方法3.市場調査を行う
M&Aの目的が決まったら、詳細な市場調査を行います。目的の達成のために、どのような形でM&Aをすべきか、どのような企業とM&Aを成約するかなどを検討しますが、M&Aの目的によって市場調査の対象は異なります。
既存事業の拡大や事業の承継を目的とする場合には、自社が精通している市場調査が主になります。一方で、異業種企業との統合によって新規参入を目的にM&Aを行う場合には、買収相手の分野について市場調査を実施する必要があります。M&Aアドバイザーや金融機関に相談するケースがほとんどです。
M&A戦略の方法4.アプローチ方法を決める
市場調査後は、買収先や譲渡先へ具体的にアプローチします。方法は大きく次の2つです。
- 直接アプローチ
- 仲介会社を通じたアプローチ
直接アプローチは、取引先や経営者同士のつながりがある場合に有効で、交渉がスムーズに進みやすく機密保持もしやすい点が強みです。ただし、対象企業が限られるため、選択肢が狭まるというデメリットもあります。
一方で、仲介会社を通じたアプローチは、専門的な知識を持つM&A仲介会社や金融機関を活用できます。幅広い候補の中から最適な相手を見つけやすく、自社分析や市場調査の支援も受けられます。状況に応じた選択がM&A成功への近道です。
M&A戦略の方法5.戦略オプションを検討する
アプローチ方法を決めた後は、M&Aの戦略オプションを検討します。M&Aの目的を達成するためには、M&A成約後の事業展開、つまりどのような経営戦略をとるか計画しておくことが重要です。M&Aが成約する前に、どの戦略オプションが効果を発揮するのか事前検証しましょう。
M&Aは単なる企業の合併・吸収だけではなく、企業文化の統合なども伴うため、複数の戦略オプションを準備して成立後にスムーズに経営体制が整うようにしておきましょう。
【ケース別】M&A戦略を立案する際のポイント
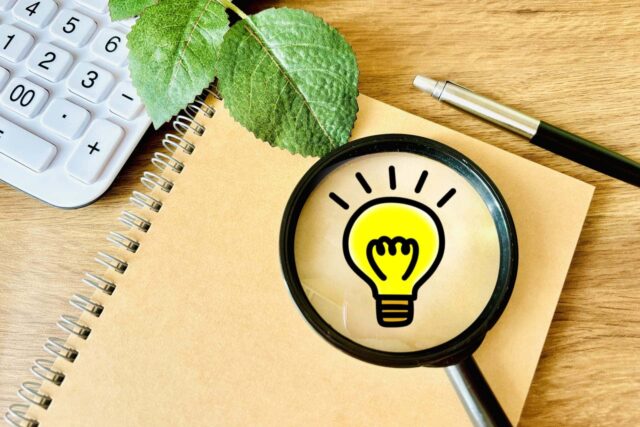
M&Aは企業ごとに目的や状況が異なるため、戦略の立て方もケースごとに変わります。ここでは、5つのケース別に戦略立案の重要な視点を解説します。
事業を整理する場合
事業整理を目的にM&A戦略を立てる際は、自社の事業を「コア事業」と「ノンコア事業」に明確にわけることが重要です。どの事業を将来の成長エンジンとして残すかを見極め、必要な選択と集中を実行しましょう。過去にかかったコストにとらわれず、将来の収益性や成長可能性に着目し、切り離す事業を合理的に判断することが大切です。
整理後の事務手続きや資産処理についても、戦略としてしっかり段取りを整えておくことが求められます。事業を整理する視点を持つことで、M&Aを通じて本当に自社にとって価値ある改革を進めていきましょう。
事業承継する場合
M&A戦略で事業承継する場合、カギとなるのは「スキームの選択」です。雇用を維持するのか、取引先や経営方針を引き継ぐのか、それとも大きく変えるのかによって適した方式が異なります。価格設定では簿外債務なども考慮に入れ、事前に調整方法を決めておくことが必要です。
M&A後に従業員の離職やキーパーソンの退職などの、リスクに備えた対応策もあわせて計画しましょう。事業の継続性と安定性を確保するうえで不可欠です。
事業拡大を図る場合
M&A戦略として事業拡大を図る場合、まず「何を拡大するのか」を明確にすることが重要です。事業規模の拡大、販路やエリアの拡大、取扱商品の多様化など、対象に応じた戦略を描きましょう。拡大によって得られるメリットを具体化することも欠かせません。
拡大する事業を明確にすることで、スケールメリットによるコスト低減や競争力の強化などが期待できます。事業拡大の目的とメリットをはっきりさせることで、よりターゲットを絞ったM&A戦略が立案でき成果につながりやすくなります。
イグジットする場合
M&A戦略でイグジットを目的とする際は、まず出口(EXIT)方法の選択が重要です。M&AによるバイアウトかIPOか、あるいは両者を組み合わせた二段階イグジットかを検討すべきです。M&Aは比較的短期間で創業者利益をキャッシュ化できる一方、IPOは資金調達や知名度向上に優れています。
しかし、準備コストや審査ハードルも高いため、自社の状況に応じた最適な選択が必要です。TOB(公開買い付け)を活用して上場後に大企業に売却する戦略もあり、長期的な出口戦略として考慮しましょう。
新規事業を立ち上げる場合
新しい事業を始めるとき、最初からすべてを自社でつくるのは時間も資金もかかります。M&Aを使えばすでに軌道に乗っている企業を買収できるので、営業や技術の土台が整った状態でスタートできます。M&Aでの新規事業立ち上げは、時間やコストを大幅に短縮できるのが大きなメリットです。
一方で、どんな会社を買うか慎重に選ばないと、期待した成果が得られないリスクもあります。目的や必要な能力がはっきりしていること、リスクへの備えがあることが、M&Aを活用した新規事業成功につながります。
M&A戦略を策定する際の注意点

M&Aは企業の成長や事業承継の有力な手段ですが、大きなリスクも伴います。戦略を立てる際には、目の前の条件や短期的な利益だけにとらわれず、交渉の目的を明確に保つことが欠かせません。ここからは、M&A戦略を策定する際の注意点3つを詳しく解説します。
目的忘れずに交渉する
M&Aの交渉は長期戦になり複雑な条件が次々出てくるため、本来の目的を見失いやすいリスクがあります。たとえ交渉相手に魅力を感じても、「なぜこのM&Aを行うのか」という根本理由を見直すことが重要です。
目的を忘れて交渉を進めると、買収そのものが目的化し、リスクや欠点に気づかず進んでしまうこともあります。交渉途中で壁にぶつかったときこそ初心に立ち返り、「このM&Aで達成したいこと」を再確認しながら、粘り強く交渉を続けることが大切です。
M&Aが最善の方法かを検討する
M&Aは目的ではなくあくまで「手段」に過ぎません。安易に進めると、自社に不要な資産や負債を抱えたり手続きが複雑になったり、コストが膨らむリスクがあります。まずはM&A以外の方法(提携や新規事業など)がないかを冷静に検討し、M&Aが本当に目的達成に必要な手段か明確にしましょう。
目的に沿った最適なアプローチを選ぶことで、資源の無駄遣いや統合失敗を避けて企業価値を守れます。
見通しを精査する
M&A戦略では、自社の見通しが現実的であるかどうかを冷静に精査する必要があります。ターゲット企業の価値評価や統合後に見込まれるシナジー効果などがあまりに楽観的だと、資金超過や計画失敗を招くリスクがあります。
市場環境や競合状況などを踏まえて、複数のシナリオ(楽観・現実・悲観)を用意しリスク管理も兼ねた計画を立てましょう。慎重な姿勢がM&A成功の確率を高めます。
M&A戦略の知識をつけて、信頼できる専門家に相談しよう

M&Aを成功させるためには、戦略の知識をつけて臨むことが重要です。
経営で忙しい経営者が単独でM&Aを成立させるのは難しいため、信頼できるアドバイザーに相談するのが一番効率的です。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。






























