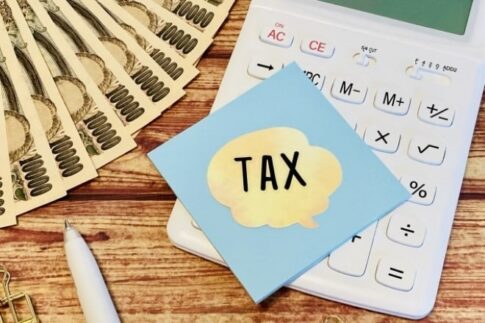本記事では、M&Aで実施されるDD(デューデリジェンス)について解説します。
M&Aを実施する上で避けては通れないものなので、必ず詳細を把握しておくようにしておきましょう。
目次
- 1 DDとはなにか
- 2 何のためにDDをするのか
- 3 DDの種類
- 4 財務DD
- 5 法務DD
- 6 人事DD
- 7 技術DD
- 8 税務DD
- 9 ITDD
- 10 環境DD
- 11 DDの進め方
- 12 誰がDDをするのか
- 13 手順
- 14 NDA(秘密保持契約)
- 15 DDで必要な書類
- 16 M&AにおけるDDに必要な費用
- 17 必要とされる費用
- 18 会計処理の方法
- 19 M&AにおけるDDの注意点
- 20 事前に計画を立ててポイントを絞る
- 21 適切なタイミングで実施する
- 22 外部アドバイザーにも相談する
- 23 ビジネスデューデリジェンスに役立つ4つのフレームワーク
- 24 PEST分析
- 25 5フォース分析
- 26 VRIO分析
- 27 バリューチェーン分析
- 28 適切にDDを実施してM&Aを成功させよう
DDとはなにか

まず、DDとは何かから説明します。
DDとは、デュー・ディリジェンスDue Diligenceの訳語で、「適切な注意」といった意味です。M&Aの場面でDDと言った場合、対象となる事業を精査し、どのようなリスクがあるかを把握し、その大きさやそのリスクが現実化する可能性を評価する作業を指します。
何のためにDDをするのか

では、なぜDDが必要なのでしょうか。
M&Aの場面では、会社分割にせよ、事業譲渡にせよ、株式譲渡にせよ、買い手は対象となる事業の将来的な収益を評価して対価を払うわけですが、同時に、リスクをも引き受けることになります。
あまりに大きなリスクが存在している場合、買い手はM&A自体を避けようと思うかもしれません。もちろん、リスクとして想定される事態には大小があり、それが顕在化する可能性にも大小があるため、リスクは必ずしもM&Aをするかどうかの判断に影響するわけではありません。
しかし、その場合でも、適切な対価を決定したり、一定の保証を付けるなどの条件を交渉したりするためには、どのようなリスクがあるかを把握し、その大きさや顕在化の可能性を評価することが、やはり不可欠です。
DDは、買い手企業の経営者から見た場合、対価に見合わないリスクを抱え込むことで買い手企業自体の企業価値を損なうことがないようにするという、株主に対する義務でもあります。
DDの種類

ここからはDDの種類について解説します。一口にDDと言ってもさまざまな種類のものがあります。一つ一つ解説していくので必ず把握しておいてください。
財務DD
財務DDは、売り手企業の経営実態を把握するために、財務関わるリスク情報を得るための調査です。売り手企業が企業価値を高く見積もるために、事実確認や隠している点がないかをチェックします。
法務DD
法務DDでは、法律上の債権債務や訴訟状況などの法律上のリスクを調査します。現在の経営状態は良くても、法律違反等で経営が危ぶまれている場合、買収してしまうとリスクを背負うことになってしまいます。
人事DD
人事DDとは、人事制度や労働協約などの人事・労務面の調査を行うものです。具体的には、残業代の未払いや保険加入の有無、優秀な人材を今後も継続的に確保できるかなどを確認します。
M&Aにおいて人材の流出は大きな痛手です。仮に問題があったとして、それを対策することで対処できるのかをじっくりと検討しましょう。
技術DD
M&Aにおける技術DDでは、商品やサービスなどの技術面の調査を実施します。基本的には買収先企業の専門の技術者へのインタビューや、専門家によって判断が下されます。
技術面は多種多様な商品やサービスが複雑に絡み合っているケースも多く、時間を要するケースが非常に多く見られます。競合との比較も行いながら適切な技術DDを行いましょう。
税務DD
税務DDは、過去の税金の納付や申告に関するリスクを調査するものです。これらの調査によって売り手企業の財務リスクを把握したうえで、対策を行うのか、買収をとりやめるのかを検討します。
また、税務DDは買収価格に反映されることや幅広い税金の知識が必要となることから、アドバイザーに任せるのが一般的とされています。
ITDD
ITDDとは、情報システムに関わる調査を実施することです。どんなにそれぞれのシステムが優れていても統合できなければ、十分なシナジー効果を発揮することはできません。
特に、個人情報の漏洩に関わるような問題は慎重に進める必要があります。もし不安点があるのであれば、早めにプロに相談するといいでしょう。
環境DD
環境DDとは、環境汚染のリスクなどの調査をするものです。近年、SDGsへの注目も高まっていることもあり、環境汚染に関わるリスクに問題がある場合は、買収を再検討する必要があるケースもあります。
適切な環境DDを行い、事前に取り除けるリスクは徹底的に排除しておきましょう。
DDの進め方

ここまでDDの種類について解説してきました。しかし、種類だけを知っていてもDDを実施することはできません。ここからはDDの進め方について解説していきます。
自社で行わずにアドバイザーに任せる場合でも、手順を知っておいた方がスムーズにDDを実施できるので、必ず確認しておいてください。
誰がDDをするのか
DDの対象は、事業全体にわたり、しかも、それを評価する観点もさまざまなものがあります。代表的なのが、法務、財務、ビジネス、税務のDDです。
これらのDDは、法律事務所、監査法人、コンサルタント企業、税理士法人などの専門的知識を持つプロフェッショナルに依頼して行うのが一般的です。
手順
DDは、一般的には、次のようなステップを踏みます。
まず、資料の開示を請求します。法務DDであれば、定款、株主名簿、株主総会や取締役会の議事録、監査報告書、社内規定や就業規則などの社内ルール、取引先、金融機関、業務提携先、従業員などとの契約書、不動産や知的財産などの資産を保有している場合にはそれに関する契約書や登記・登録関係文書、不動産の賃貸借、リース、ライセンスなどがある場合にはそれに関する契約書、許認可が必要な事業や、その他行政機関の監督を受けている場合にはそれに関する文書などが開示されます。
ここで開示された文書を、専門家、法務DDであれば法律事務所の担当弁護士が読み込み、問題となりうる点を洗い出します。
次に、売り手企業の経営者や幹部従業員と個別に直接会って、ヒアリングを行いますマネジメント・インタビュー(Management Interview. 経営者との面談)。
文書でのDDは、詳細を把握するのには適していますが、必ずしもそこから経営者の認識や考えが十分に読み取れるわけではありません。マネジメントインタビューを行なうことによって経営者に直接語ってもらい、文書のみからでは汲み取れない情報を補うことができます。
NDA(秘密保持契約)
なお、DDでは、売り手企業に関するさまざまな情報が、買い手企業や、そのアドバイザーとなる法律事務所・監査法人・コンサルタント企業・税理士法人などに開示されます。
そこで開示される情報は、一般に入手可能なものよりも、はるかに豊富かつ詳細にわたるものであり、売り手企業としてはできる限り秘匿しておきたいものです。そこで、この情報を第三者に渡さないという契約が、NDA(秘密保持契約)です。一般に、DDに先立って合意されます。
DDで必要な書類
また、DDではプロセスや相手によって必要な書類が複数存在します。プロセスごとに必要な書類を下記にまとめているので、スピーディーな取引ができるように、概要を把握しておきましょう。
M&Aアドバイザーとのやり取りで必要となる書類・契約書
・アドバイザリー契約書
・秘密保持契約書
・ロングリスト/ショートリスト
M&Aの候補先への打診で必要となる書類・契約書
・企業概要書
・ノンネームシート
M&Aの具体的な交渉で必要となる書類・契約書
・意向表明書
・DDにおける書類
・基本合意書
M&Aの最終段階で必要となる契約書
・最終契約書
M&AにおけるDDに必要な費用

ここまでの内容でDDに関する基本的な知識は理解していただけましたか?ここからはM&AにおけるDDに必要な費用について解説していきます。予算を考慮しつつ、ぜひ最後までご覧ください。
必要とされる費用
M&AにおけるDDに必要な費用は、案件の規模やどのDDを依頼するのかによって異なりますが、対中小企業であれば数十万円~数百万円くらいかかります。そして、規模の大きな案件になるとDDだけで約数千万円になることもあります。
会計処理の方法
DDで発生した費用は、個別財務諸表と連結財務諸表によって会計処理されます。基本的には両者とも一括費用処理ですが、個別財務諸表は直接取得に利用した費用は取得原価に含める点に注意してください。
M&AにおけるDDの注意点

ここまでM&AにおけるDDの具体的な手順や必要費用について解説してきました。しかし手順通りに行えば適切なDDが実施できるわけではありません。
なぜなら、M&AにおけるDDには必ず注意すべきポイントがあるからです。適切なDDを実施するためにも、必ず注意すべきポイントを把握しておく必要があります。
事前に計画を立ててポイントを絞る
事前に計画を立ててポイントを絞る必要があります。計画ゼロでDDを進めても、時間や費用を浪費するだけで、必要な情報が得られません。
DDが行える時間や情報は限られています。短期間で適切な情報を集めるためにも、事前調査を行い計画を立てておくことをおすすめします。
適切なタイミングで実施する
M&AにおけるDDは適切なタイミングで実施するように注意しましょう。DDを早く実施しすぎると従業員や取引先に余計な心配を与えてしまう可能性があります。
一般的には、基本合意契約の締結後、最終条件交渉前に行われます。遅すぎると他の企業に買収される危険性があるため、適切なタイミングの見極めが重要になるのです。
外部アドバイザーにも相談する
M&AにおけるDDでは外部アドバイザーに積極的に相談することをおすすめします。前述した通り、DDにはさまざまな手順があります。そのため、自社に専門家がいない場合、適切なDDを行い買収の有無を見極めるのは非常に困難です。
迅速かつ適切なM&Aを行うためにも外部アドバイザーに積極的に相談しましょう。
ビジネスデューデリジェンスに役立つ4つのフレームワーク

ビジネスデューデリジェンスにおいて大切なのは、外部環境と内部環境に分けた調査です。
本章では、ビジネスデューデリジェンスの調査に有用な4つのフレームワークを解説します。
PEST分析
PEST分析とは、企業の外部環境要因を分析する手法です。
PEST分析によって、企業を取り巻く環境の変化を把握でき、事業戦略やマーケティング戦略を立案する際に活用できます。
分析に用いる要因は下記の通りです。
| Politics(政治的要因) | 政策・法律・規制・外交問題など、政治の変化による影響 |
| Economics(経済的要因) | 景気動向・金利・物価・為替レート・失業率など、経済の変動による影響 |
| Social(社会的要因) | 人口動向・ライフスタイル・価値観・文化・教育制度など、社会の変動による影響 |
| Technology(技術的要因) | 新技術の開発や普及・技術革新など、技術の変動による影響 |
PEST分析は、将来の事業環境を予測して、有効な戦略を考えるために重要です。
5フォース分析
5フォース(ファイブフォース)分析とは、企業を取り巻く5つの脅威を分析し、業界の現状や収益性を把握できるフレームワークです。
分析に用いる脅威は下記の5つです。
| 業界内の競争(Rivalry) | 競合他社から受ける影響を把握する。既存の競合他社の数や資金力・技術力・営業力・ブランド力・シェア率、差別化の状況などの項目について分析する。 |
| 新規参入者の脅威(Entry) | 今後、新規参入する企業から受ける影響を把握する。市場規模・市場成長率や、既存の競合他社の経営状況・差別化の状況・資金力、新規参入企業のビジネスモデル・資金力・技術力などを分析する。 |
| 代替品の脅威(Substitutes) | 同じニーズを満たせる製品や方法に受ける影響を把握する。価格・コストパフォーマンス・独自の製品価値や、代替品業界の利益率・市場成長率などを分析する。 |
| 買い手の交渉力(Buyers) | 買い手の交渉力の影響による収益性低下の可能性を把握する。買い手の数・価格競争の有無・製品の独自性や、製品の価格帯・購買条件などを分析する。 |
| 売り手の交渉力(Suppliers) | 製品を作るための原材料の供給者から受ける影響を把握する。原材料の仕入価格・価格交渉の可否やサプライヤーを変更する際のコスト、市場全体の売り手の数・力関係などを分析する。 |
5フォース分析の結果、脅威の影響力が強いほど収益性を高めるのは難しく、脅威の影響力が低いほど収益性を高めやすいと判断するのが一般的です。
VRIO分析
VRIO分析とは、企業の経営資源が競争優位性を生み出せるかを分析できるフレームワークです。
VRIO分析で用いる要素は下記の4つです。
| Value(経済的価値) | 消費者・顧客などが求める価値を提供できているかを確認する。売上・社会への影響や継続購入の可能性の高さ、新たなビジネスチャンスにつながるかなどを確認する。経済的な視点から経営資源を評価し、競争劣位の状態を把握する。 |
| Rarity(希少性) | 独自性の有無や経営資源が競争均衡状態になっているかなどを確認し、競合他社と比較する。経営資源とは、具体的に資金力・従業員の所持スキル・設備・システムなどを指す。 |
| Imitability(模倣可能性) | 他社が自社の経営資源を模倣しやすいかや、模倣した際にコスト的な不利を受けるかなどを確認する。模倣が困難なほど希少性が高く、市場優位性が高まる。 |
| Organization(組織) | 経営資源を持続的に活用できるかを評価する。経営資源の持続的な保有が可能か、活用するための体制が整っているかなどを確認する。 |
VRIO分析は内部環境的な要因にフォーカスしているため、企業の強みと弱みを把握して、外部環境的な要因への対策を検討できるのがメリットです。
PEST分析や5フォース分析と併用することで、より高い効果を得られるでしょう。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析とは、原材料の調達から製造・営業までの一連の流れをプロセスごとに分解し、各工程で生み出されている付加価値を分析するフレームワークです。
バリューチェーン分析においては、以下のように「主活動」と「支援活動」に分類して分析します。
| 主活動 | 製品の製造・マーケティング・販売・サービス提供など、顧客に対して直接的に価値を提供する活動。 |
| 支援活動 | 人事・労務管理や技術開発・調達・全般管理など、主活動をサポートする活動。 |
サプライチェーンはバリューチェーンと混同しがちですが、フォーカスする要素が異なるため注意が必要です。
サプライチェーンはモノの流れにフォーカスしているのに対して、バリューチェーンは各工程で創出される価値にフォーカスしています。
なお、バリューチェーン分析は先述したVRIO分析と併用する方法も有効です。
適切にDDを実施してM&Aを成功させよう

以上に見てきたように、法務DDでは、さまざまな事項が、法的リスクという観点から調査されます。どのようなリスクが、どれほどの確実さをもって存在するのかは、M&Aを行うかどうかや、その対価を決めるに当たって、重要な判断材料です。
パラダイムシフトは2011年の設立以来、豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。