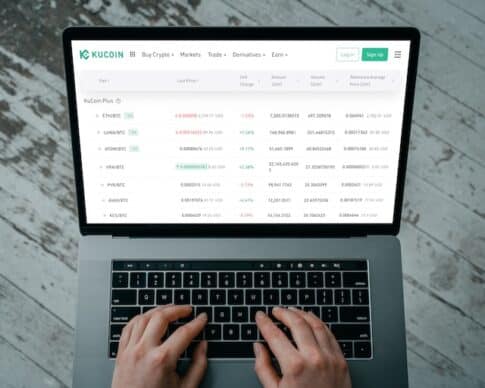非上場株式の譲渡にかかる税金について、具体的にどのような税金が、いくら発生し、どう対応すべきか、お悩みではありませんか?
M&Aによる事業承継や組織再編において、非上場株式の譲渡は中心的な手続きとなります。
非上場株式の譲渡で避けて通れないのが、譲渡時にかかる税金の問題です。特に非上場株式の場合、株主(オーナー経営者など)の手取額に直接影響するだけでなく、取引価額の妥当性や評価方法自体が税務上の論点となりやすいです。
税務への理解が不十分なままM&Aや条件交渉などを進めると、思わぬトラブルや追加負担が生じるリスクも否定できません。
この記事では、M&A実務で必須となる非上場株式の譲渡に関する税金の基礎知識や税率、具体的な計算方法から確定申告の手順までわかりやすく解説します。
目次
- 1 非上場株式の譲渡における税金の基礎知識
- 2 非上場株式の譲渡とは
- 3 譲渡益にかかる税金の種類
- 4 非上場株式の譲渡における税率
- 5 譲渡所得の計算方法
- 6 【ケース別】譲渡形態による税金の違い
- 7 法人間での譲渡
- 8 親族への無償譲渡
- 9 個人間での譲渡
- 10 非上場株式の売却方法
- 11 親族・知人への譲渡
- 12 従業員持株会への譲渡
- 13 M&A仲介会社への依頼
- 14 非上場株式譲渡の確定申告ガイド
- 15 確定申告が必要なケースと不要なケース
- 16 確定申告の期間と提出先
- 17 確定申告の必要書類と準備
- 18 法人が非上場株式を譲渡する場合の税金対策
- 19 赤字年度に譲渡して利益と相殺する
- 20 時価評価と譲渡価格の整合性を取る
- 21 売却と同時に別の投資・支出と組み合わせる
- 22 まとめ:非上場株式の譲渡は専門家に相談しよう!
非上場株式の譲渡における税金の基礎知識
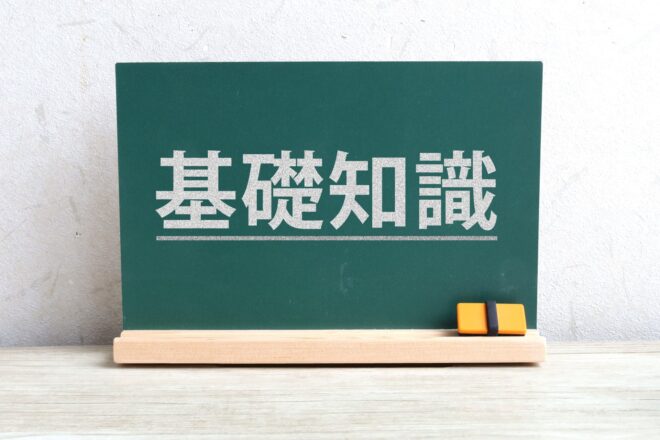
非上場株式の譲渡に伴う税金を正確に把握するためには、まず基本的なルールを理解することが不可欠です。具体的にどのような行為が「譲渡」にあたるのか、譲渡によって利益(譲渡益)が生じた場合に、所得税や住民税といったどの税金がどれくらいの税率で課されるのか。
ここでは、税額計算の基礎となる譲渡所得の計算方法など、非上場株式の譲渡における税金の基礎知識を解説します。
非上場株式の譲渡とは
非上場株式の譲渡とは、証券取引所に上場されていない株式会社の株式について、所有権を他の個人または法人へ移転する行為を指します。一般的なケースは、株式を対価(主に金銭)と引き換えに売却する取引であり、M&Aにおける株式売買も同じ対象です。税務上重要なのは有償での譲渡です。
株式を売却で取得価額を上回る対価を得た場合には、差額が譲渡所得とされ、所得税および住民税の課税対象となります。一方で、無償譲渡や死亡に伴う株式の移転(相続)の場合は、原則として所得税の対象とはならず、それぞれ贈与税または相続税の課税関係が適用される点に注意が必要です。
譲渡益にかかる税金の種類
個人が非上場株式を譲渡して譲渡益(売却益)を得た場合、利益は「株式等に係る譲渡所得等」として、給与所得など他の所得とは分けて税額を計算する「申告分離課税」の対象となります。譲渡益に対して課される税金は、以下の3種類です。
- 所得税(国税)
- 復興特別所得税(国税):所得税額に対して2.1%
- 住民税(地方税):都道府県民税および市区町村民税
一方、法人が非上場株式を譲渡して譲渡益を得た場合は、利益は法人全体の他の損益と合算され、法人税(国税)の課税対象となります。法人住民税(地方税)や法人事業税(地方税)なども課されます。
非上場株式の譲渡における税率
個人が非上場株式を譲渡して得た譲渡所得(譲渡益)に対する税率は、原則として合計 20.315%です。所得の種類に関わらず分離して課税される「申告分離課税」の税率となります。「20.315%」の内訳は以下のとおりです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315% (所得税額 × 2.1%)
- 住民税:5%
上記の税率は、上場株式等を譲渡した場合と同じです。一方、法人が譲渡益を得た場合は、利益は他の事業活動から生じる所得と合算されます。個人のような一律の税率ではなく、法人の全体の所得金額や資本金の額などに応じて変動する通常の法人税や法人住民税、法人事業税等の税率(実効税率)が適用されます。
譲渡所得の計算方法
非上場株式の譲渡所得(課税対象となる譲渡益)の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 – (取得費 + 譲渡費用)
- 譲渡収入金額:株式を売却して得た収入の総額
- 取得費:売却した株式を過去に取得した際にかかった費用
- 譲渡費用:株式を売却するために直接かかった費用
非上場株式の場合、取得時期が古いなどの理由で取得費が不明なケースもあります。上記の計算式で算出された譲渡所得の金額に対して、前述の税率(個人なら合計20.315%)が課せられます。
【ケース別】譲渡形態による税金の違い

非上場株式の譲渡に関する税金は、基本的な計算方法は同じでも、誰から誰へ、どのような形で株式が移転するかによって、適用される税金の種類や注意点が異なります。特にM&Aや事業承継の場面ではさまざまな譲渡形態が考えられます。
ここからは、代表的なケースとして「法人間」「親族への無償譲渡」「個人間」での譲渡を取り上げ、それぞれの税務上の違いについて解説します。
法人間での譲渡
法人が保有する非上場株式を他の法人に有償で譲渡した場合、譲渡法人(売り手)に発生した譲渡益または譲渡損は、原則として通常の損益と合算され、法人全体の所得として扱われます。個人が非上場株式を譲渡する場合の「申告分離課税」(税率20.315%)とは異なり、特定の税率が適用されるものではありません。
注意すべきなのは、グループ企業間などの関係者間取引において、譲渡価額が時価から大きなズレがある場合です。寄付金課税や受贈益課税といった課税リスクが生じる可能性があるため、価格設定は慎重に検討する必要があります。
親族への無償譲渡
非上場株式を親族などへ対価なしで譲渡する、いわゆる「贈与」の場合、税金の扱いが有償譲渡(売却)とは大きく異なります。株式を無償で譲渡した側(贈与者)には売却収入がないため、原則として譲渡所得は発生せず、所得税・住民税は課税されません。株式を無償で受け取った側(受贈者)に「贈与税」が課税されます。
贈与税の計算は、株式の適正な評価額(時価、相続税評価額などが基準)をもとに行われます。暦年課税の場合は、年間110万円の基礎控除額を超えた部分に累進税率で税金が課せられます。非上場株式の評価は複雑なため注意が必要です。
個人間での譲渡
個人が保有する非上場株式を、親族関係にない第三者を含む他の個人に対して有償で譲渡する場合、売り手となる個人の税務処理は原則として通常のルールに従います。譲渡により得た利益は、「所得税15.315%」および「住民税5%」を合計した20.315%の税率です。売却者は、原則として確定申告により納税を行う必要があります。
一方、買い手には通常、所得税の課税は発生しません。ただし、個人間取引において譲渡価額が時価より著しく低い場合には、差額が贈与とみなされ、買い手側に贈与税が課される可能性があります。
非上場株式の売却方法
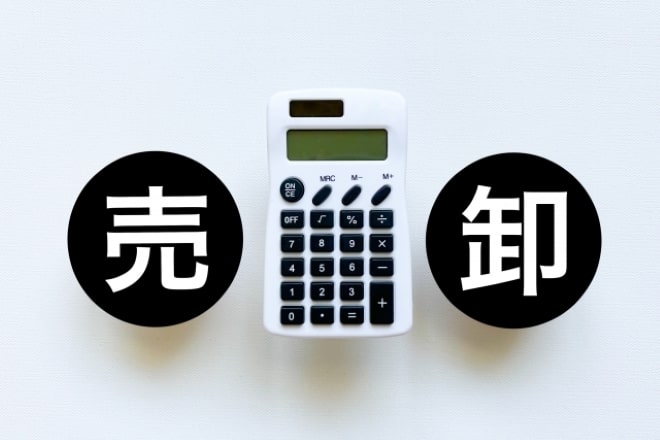
非上場株式は、上場株式のように証券取引所で自由に売買できるわけではありません。株式を売却(現金化)したいと考えた場合、買い手を見つけるための具体的な手段を検討する必要があります。
ここでは、代表的な非上場株式の売却方法として、主な選択肢を解説します。
親族・知人への譲渡
非上場株式の売却方法の一つとして、経営者の親族や会社の役員・従業員、知人など、身近な相手に直接交渉して株式を譲渡するケースがあります。事業承継や経営の引き継ぎを意識した場合に検討されやすい方法です。信頼関係に基づくため、交渉が比較的スムーズに進む可能性があるのがメリットです。
注意すべき点は「譲渡価格の妥当性」です。当事者間で合意したとしても、実際の取引価格が客観的な時価から大きくズレている場合は、買い手に贈与税が課されるおそれがあります。リスクを回避するためにも、専門家に株価評価を行なってもらい、評価に基づいて適正な価格で契約書を作成することが不可欠です。
従業員持株会への譲渡
従業員の財産形成支援や経営参画意識の向上を目的として設立される「従業員持株会」は、非上場株式の有力な売却先の一つです。オーナー経営者などが保有する株式を持株会に譲渡することで、オーナーは株式の現金化が可能となり、従業員は間接的に自社株式を保有できます。
持株会の仕組みにより、従業員のモチベーション向上や安定株主の確保、将来的な事業承継の土台作りなど、さまざまな効果が期待されます。一方で、活用するためには従業員持株会の設立が必要です。譲渡価格は適正な時価を基準として設定する必要があり、税務上のリスクを避けるためにも、株価の客観的な評価が不可欠です。
M&A仲介会社への依頼
親族や社内関係者ではなく、第三者へ非上場株式を譲渡したい場合や、会社全体の売却を検討している場合には、M&A仲介会社への依頼が有力な選択肢です。M&Aの専門業者は、自社で保有するネットワークや専用データベースを活用し、買収意欲のある企業を効率的に見つけ出すことが可能です。
企業価値の算定や条件交渉、契約書の作成・締結まで、複雑なM&Aプロセス全体を通じて専門的な支援を受けられます。適切な買い手とマッチングできれば、条件面でも有利な売却が期待できます。ただし、成功報酬型の仲介手数料など、一定のコストが発生することは考慮しないといけません。
非上場株式譲渡の確定申告ガイド
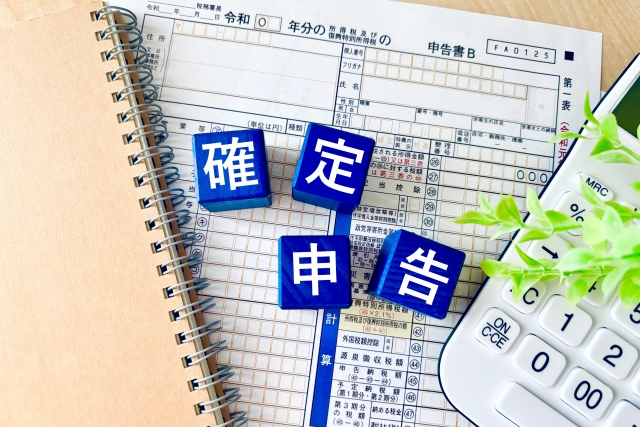
非上場株式を譲渡して利益を得た個人の方は、原則として確定申告の手続きが必要です。申告漏れはペナルティの対象にもなりかねません。
ここでは、非上場株式の譲渡に関する確定申告について具体的に解説します。
確定申告が必要なケースと不要なケース
個人が非上場株式を有償で譲渡した場合、確定申告が必要か否かは「譲渡所得が発生したかどうか」で判断します。
| 確定申告が必要なケース | 譲渡収入金額が取得費と譲渡費用を上回り、譲渡所得が生じた場合は、原則として金額の大小にかかわらず確定申告が必要 |
| 確定申告が原則不要なケース | 譲渡所得がゼロまたはマイナス(譲渡損失)になった場合 |
ただし、給与所得以外の所得があり、元々確定申告が必要な場合は損失であっても申告に含めることがあります。なお、一般的な非上場株式の譲渡損失は、他の所得との損益通算や翌年以降への繰越は通常できません。
確定申告の期間と提出先
非上場株式の譲渡によって所得が発生した場合、その年分の確定申告は原則として翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。たとえば、2024年中に譲渡益が発生した場合は、2025年3月15日が申告期限となります(※期限日が土日祝日の場合は、翌平日が締切です)。
申告書の提出先は、申告時点での納税者の住所地(住民票のある場所)を所轄する税務署です。どの税務署が該当するかは、国税庁のウェブサイトで確認できます。提出方法は、税務署への持参のほか、郵送やe-Tax(電子申告)による手続きも可能です。
確定申告の必要書類と準備
非上場株式の譲渡所得を申告する際に、必要な書類や資料は以下のとおりです。
| 提出書類 |
|
| 証拠資料 |
|
| その他必要書類・情報 |
|
提出前に税務署や税理士に内容確認を行うと安心です。スムーズに手続きが進められるよう事前に準備しておきましょう。
法人が非上場株式を譲渡する場合の税金対策

法人が保有する非上場株式を譲渡する場合、譲渡益は個人のように分離課税ではなく、法人全体の所得に合算されます。法人の特性を理解し、計画的に譲渡を行うことで、法人税等の負担を抑えるための対策を講じることが可能です。
ここからは、法人が非上場株式を譲渡する際に検討できる、代表的な税金対策について解説します。
赤字年度に譲渡して利益と相殺する
法人が非上場株式を譲渡して利益が発生した場合、他の事業活動から生じた損失(赤字)と相殺が可能です。たとえば、本業の業績悪化などにより、事業年度全体で赤字が見込まれるタイミングで含み益のある非上場株式を売却すれば、譲渡益は赤字によって吸収されます。
赤字の吸収で課税所得が圧縮されるため、法人税や住民税、事業税などの納税額を抑えられる可能性があります。法人にとって有効な節税対策の一つとして、財務状況とあわせて慎重に検討することが重要です。
時価評価と譲渡価格の整合性を取る
法人が非上場株式を譲渡する際、グループ会社などの関連当事者間取引では、譲渡価格が適正な時価であることが税務上求められます。時価より著しく低い場合、差額が「寄付金」とされ、売り手に法人税が課される可能性があるからです。逆に高すぎる価格は、買い手に「受贈益」として課税されることもあります。
税務上のリスクを回避するには、専門家による株価評価を行い、根拠を記録・保存しておくことが重要です。
売却と同時に別の投資・支出と組み合わせる
法人の株式譲渡益は、法人全体の所得と合算されるため、同一年度内の損金と相殺されます。多額の譲渡益が見込まれる年に、修繕費や研究開発費、税制優遇がある設備投資などを計画的に実施することで、課税所得を圧縮することが可能です。譲渡益発生年度の法人税等の負担軽減を図れます。
ただし、あくまで事業に必要な投資・支出であることが前提です。
まとめ:非上場株式の譲渡は専門家に相談しよう!

非上場株式の譲渡には、市場価格がないことによる株価評価の難しさや、譲渡形態に応じた適用税目・税務処理の違いといった、専門的で複雑な論点が多く含まれます。非上場株式の譲渡を正しく理解せずに進めると、適正価格とのズレによる思わぬ課税や、申告・手続きの誤りといった税務リスクを負いかねません。
後悔しないためにも、自己判断は避け、計画段階から税理士やM&A専門家などのプロフェッショナルに必ず相談しましょう。株価評価や契約、税務申告まで、適切なアドバイスのもと慎重に進められます。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。