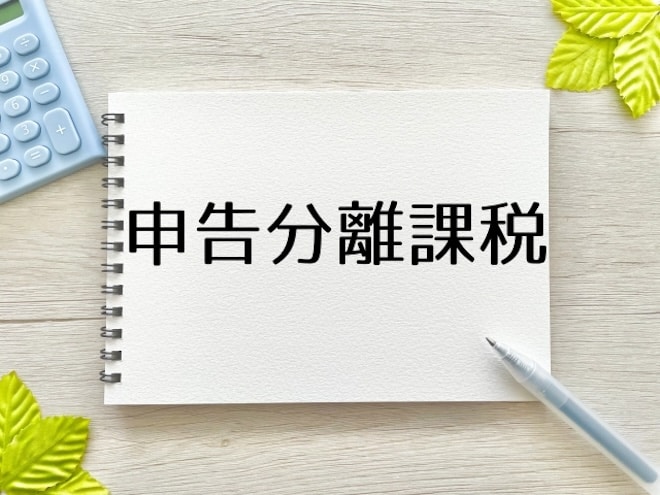申告分離課税制度は、一時的な所得が生じた際に所得税とは別で税金を計算して税金を決める制度です。
この記事では分離課税の概要や申告分離課税制度について、対象となる所得やこれらの計算方法について解説します。
申告分離課税制度について基本的な内容を知りたい方はぜひご覧ください。
目次
申告分離課税とは

申告分離課税とは株式譲渡など一時的な譲渡所得が生じた際に、通常の所得税とは別で確定申告により申告するものです。このとき、通常の所得と分離して税金が計算されます。
譲渡所得として申告する対象となるものは、株式などの他に土地や建物があります。また、譲渡所得以外にも退職金などの一時所得や利子所得も対象となります。
申告分離課税は、分離課税に属しており、申告分離課税と並んであるのが源泉分離課税です。2つは、それぞれ申告の仕方が異なります。
総合課税との違い
総合課税とは、分割して税金を計算する申告分離課税と異なり、対象となる全ての所得を合算し、その合計に対し課税する方式です。個人所得の中で譲渡所得などを除く全ての所得を計算して確定申告により税金を納付します。
源泉分離課税との違い
源泉分離課税は、支払う側が先に所得税を控除するため、確定申告が不要です。しかし、分離課税は所得を得た人が自分で所得を計算して確定申告をします。
したがって、両者の違いは確定申告が必要か、そうでないかにあるということになります。
株式等を譲渡したときの課税、申告分離課税の解釈

次に、国税庁のホームページに記載された申告分離課税について解説します。国税庁のホームページには、申告分離課税の対象税目について、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分して記載されています。
対象税目の区分
上記で説明した対象税目の区分は具体的に以下の通りです。
株式等
株式や法人の出資者の持分、協同組織金融機関の優先出資、投資信託の受益権などを指します。
上場株式等
金融取引所に上場している金融商品や登録銘柄、日本銀行出資証券などが挙げられます。また、国債や地方債もここに含まれます。
一般株式等
一般株式等は株式等と上場株式等以外のものということになります。
出典:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度の解釈

ここでは、国税庁のホームページに記載された申告分離課税について解説します。
申告分離課税制度とは、所得税である総合課税と合わせて選択するものです。
申告分離課税の税率は20.315%で、この内訳は所得税と復興特別所得税を合わせて15.315%、地方税が5%となります。
上場株式等の配当等に関する課税関係は以下の通りです。
| 確定申告あり | 確定申告なし | ||
| 総合分離課税 | 申告分離課税 | ||
| 利子の控除 | あり | あり | なし |
| 税率 | 累進課税 | 所得税 15.315% 地方税 5% | |
| 配当控除 | あり | なし | なし |
| 譲渡損失との損益通算 | なし | あり | なし |
| 扶養控除等 | 所得金額に含まれる | 所得金額に含まれる | 所得金額に含まれない |
出典:No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁
分離課税の所得対象になるものとその計算方法

この章では分離課税の所得対象となるものとその計算方法について1章ごとに解説します。解説するのは以下の項目です。
- 譲渡所得
- 山林所得
- 退職所得
- 利子所得
- 一時所得
- 雑所得
譲渡所得
譲渡所得とは、資産を譲渡された際の所得です。土地や建物、株式などを親類から譲り受けるなどしたときに発生します。譲渡所得でもそれ以外のものは分離所得ではなく総合課税となります。
また、山林所得や伐採による所得は譲渡所得に含まず、次の項で解説しています。
株式
株式の譲渡所得は以下の通りに計算します。
- 【上場株式等(特定公社債等を含む)譲渡所得】×【所得税15.315%】+【住民税5%】
- 【非上場株式等(一般株式等)譲渡所得】×【所得税15.315%】+【住民税5%】
例えば、上場株式で100万円の所得がある場合には以下の計算式になります。
所得税=1,000万円×15.315%=1,531,500円
住民税=1,000万円×5%=500,000円
土地・建物
土地、建物の譲渡所得は不動産所得として以下の通りに計算します。
【不動産所得(譲渡所得)】=【収入金額】-【(所得費+譲渡費用)-特別控除】
土地や建物の不動産所得は短期収入か長期収入で税額が異なります。短期と長期の境目は譲渡日を含む年の1月1日を基準として所有期間が5年間以上か以下かという基準です。
- 【長期譲渡所得】×【所得税15.315%】+【住民税5%】
- 【短期譲渡所得】×【所得税20.63%】+【住民税9%】
さらに、マイホームの軽減税率を適用する場合には、譲渡所得が6,000万円を基準として税額が異なります。
- 譲渡所得が6,000万円まで:【長期譲渡所得】×【10.21%】+【住民税4%】
- 譲渡所得が6,000万円を超えた分:【長期譲渡所得】×【所得税15.315%】+【住民税5%】
という計算式です。
例えば、マイホームの譲渡所得がマイホームの譲渡所得が8,500万円、所有期間10年(長期)のときは以下の計算式になります。
所得税=6,000万円×10.21%+(8,500万円-6,000万円)×15,315%=9,954750円
住民税=6,000万円×4%+(8,500万円-6,000万円)×5%=365万円
山林所得
山林所得は、以下のような所得を指します。
- 山林を伐採し、その樹木を譲渡したときに得た所得
- 山林は伐採せずにその山ごと譲渡した際に得た所得で樹木の部分。(樹木以外の土地部分は上記の譲渡所得に含まれます。)
山林所得は、取得してから5年以内に譲渡した場合は雑所得になるので注意しましょう。
山林所得の計算式は以下の通りです。
【山林所得】=【総収入金額】-【必要経費】-【特別控除額(最高50万円)】× 1/2
特別控除は、総収入から必要経費を差し引いた額で、最大50万円まで、50万円以下の場合はその額が適用されます。
【所得税額】=【課税山林所得金額 ×1/5× 税率】× 5
税率は以下の通りに決められています。
| 所得 | 控除額 | 税率 |
| 195万円以下 | 0円 | 5% |
| 195万円〜330万円以下 | 97,500円 | 10% |
| 330万円〜695万円以下 | 427,500円 | 20% |
例えば、山林所得が200万円だった場合は以下の計算式になります。
200万円×1/5=40万円で税率は5%、山林所得の税額は200万円×1/5×5%×5=10万円
ということになります。
退職所得
退職所得は会社を退職したときに受け取るお金で、長年会社に貢献した意味で支給されるものです。
退職金を総合課税で計算してしまうと課税率が高くなり、老後の生活資金が足りなくなる可能性があるため、老後の資金確保のために分離課税として計算されます。
計算式は以下の通りです。
【退職所得】 = 【収入金額】 - 【退職所得控除額】
特定役員退職手当等以外はここに【× 1/2】を追加します。
さらに控除額は勤続年数により以下のように計算します。
勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(※ただし、80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年以上の場合:70万円 ×( 勤続年数 - 20年 )+ 800万円
税率は山林所得と同じく以下の通りです。
| 所得 | 控除額 | 税率 |
| 195万円以下 | 0円 | 5% |
| 195万円〜330万円以下 | 97,500円 | 10% |
| 330万円〜695万円以下 | 427,500円 | 20% |
例えば、退職所得3,000万円、勤続年数30年、特定役員以外の場合は以下の計算になります。
退職所得控除額=(30年-20年)×70万円+800万円=1,500万円
退職所得=(3,000万円-1,500万円)×1/2=750万円
所得税額=750万円×5%=375,000円
利子所得
利子所得は公社債や預貯金の利子のことを指します。公社債投資信託や合同運用信託などの分配もここに含まれます。この中で、預貯金の利子は分離課税の中でも源泉分離課税に含まれるため、確定申告は必要ありません。
利子所得の計算方法は以下の通りです。
【その年に支払う借入金の利子】×【借入金で取得した株式などの保有した月数÷12】
一時所得
一時所得の中でも一部のものは分離課税に含まれるものがあります。
具体的には、懸賞や賞金・景品、事業による利益、生命保険の解約金などが挙げられます。保険金に関しては、通常、総合課税に含まれますが、保険期間が5年以下のものなどは源泉分離課税になります。
雑所得
雑所得は、公的年金による所得や講演料・原稿料などは総合課税となりますが、FXの取引(外国為替証拠金取引)や先物取引の所得は分離課税になります。
申告分離課税の確定申告方法

最後に、申告分離課税の申告方法について解説します。
確定申告の際に基本的に必要な書類は確定申告書B第一表と第二表です。そして、分離課税を申告するときにはこれに加えて申告書第三表(分離課税用)が必要になります。
申告書第三表(分離課税用)は、申告書B第一表の⑫の総合所得から申告書B第一表の㉙の所得から差し引かれる金額を差し引いてそれぞれの対応分に記載する方式になっています。
最終的な税額は確定申告書Bで決定します。申告書第三表(分離課税用)で記載した税金の合計額を確定申告書Bに転機して総合課税と同様に計算します。
分離課税は確定申告が必要、意味を理解して正しい申告を

今回の記事では、分離課税や申告分離課税制度について詳しく解説しました。申告分離課税制度は総合課税と並ぶ税金の計算方法で、確定申告を必要とします。
申告の際にはこの記事で紹介した方法を参考に正しく申告をしましょう。
パラダイムシフトは2011年の設立以来、豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。M&Aに精通している仲介会社を利用すると、安心して行うことが出来ますので、是非ご検討ください。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。