- 組織再編って、具体的にどんな種類があるの?
- 合併と統合はどう違う?
- 自社に最適な手法は?
めまぐるしく変化する現代のビジネス環境において、企業の成長戦略や経営効率化のために「組織再編」は不可欠な選択肢となっています。
M&A(合併・買収)のニュースを見聞きする機会も増えましたが、具体的な手法や進め方については、複雑で分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな疑問にお答えすべく、この記事では組織再編の基本的な意味や定義から、さまざまな手法、具体的な手続き、そして再編を成功に導くための重要なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、組織再編を進める上での注意点や、従業員への配慮の重要性にも触れていきます。
この記事を読めば、組織再編の全体像を体系的に理解し、自社の状況や目的に合わせた戦略的な意思決定を行うための知識が身につくでしょう。
変化に対応し、持続的な成長を遂げるための組織づくりに向けて、ぜひ最後までお読みください。
目次
- 1 再編の基本知識
- 2 再編の意味と定義
- 3 【ビジネス例文】「再編」の使い方
- 4 再編と統合の違い
- 5 組織再編の種類
- 6 合併
- 7 会社分割
- 8 株式交換
- 9 株式移転
- 10 事業譲渡
- 11 組織再編の手続き7ステップ
- 12 再編の戦略を決める
- 13 再編する企業を選定する
- 14 再編する企業と交渉する
- 15 条件交渉・各種契約を締結する
- 16 デューデリジェンスを実施する
- 17 最終合意前に再度条件を交渉する
- 18 最終契約書を締結する
- 19 再編を成功させるための3つのポイント
- 20 明確な目的を共有する
- 21 綿密な計画とリスク管理をする
- 22 従業員への丁寧な説明とケアを徹底する
- 23 組織再編をする上での注意点
- 24 多額のコストがかかる
- 25 従業員にストレスがかかる
- 26 企業文化のミスマッチが起こり得る
- 27 まとめ:再編を理解して変化に対応できる組織へ
再編の基本知識
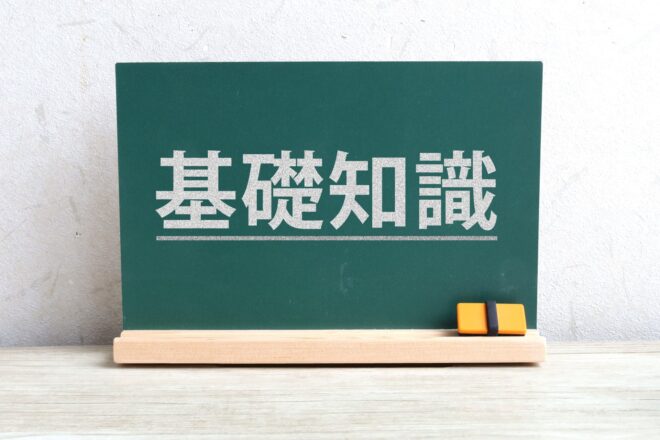
ビジネス環境がめまぐるしく変化する中で、企業が成長をするためには状況に応じて組織や事業の構造を見直す必要があります。そこで重要となるのが、「再編」です。
ここでは、再編の定義、ビジネスシーンでの使い方、よく混同されがちな「統合」との違いについてわかりやすく解説していきます。
再編の意味と定義
「再編」とは、既存の構成や仕組みを見直し、新たに編成し直すことを意味します。
一般的には、構成や体制を見直して再構築すること全般を指し、企業では競争力の維持や成長に向けた重要な取り組みの一つとして活用されます。
【ビジネス例文】「再編」の使い方
ビジネスの現場での「再編」は、企業の変革や構造改革を表す際によく使われます。
特に、組織や事業の方向性を大きく見直す場面で用いられ、単なる部署の変更や担当の入れ替えとは異なり、戦略的な経営判断を示す意味合いがあります。以下に、実際のビジネスシーンでの使用例を紹介します。
- グループ全体の経営効率を高めるため、事業部門の再編を進めています。
- グローバル市場への対応力を強化するため、海外拠点の再編を実施しました。
- 新規事業に経営資源を集中させるため、既存事業の一部を再編することにしました。
- 経営統合後、重複する機能を整理し、組織再編に取り組んでいます。
「再編」は経営変化に柔軟に対応しながら、企業の競争力を高めるための重要なアクションとして位置づけられています。
再編と統合の違い
「再編」と「統合」は、いずれも企業の組織や事業の見直しを意味する言葉として使われますが、内容や範囲に明確な違いがあります。
再編とは、企業の組織体制や事業構造を見直し、より効率的かつ戦略的な体制へと再構築することを指します。合併や会社分割、株式交換など、さまざまな手法を用いて、会社全体の方向性を再設計する取り組みです。
一方で統合は、複数の企業や事業体をひとつにまとめ、経営資源を集約することを目的とした方法です。「意思決定の一元化」や「経営効率の向上」を図るために行われ、再編の一手法として位置づけられています。
組織再編の種類

組織再編には、目的や状況に応じてさまざまな種類があります。企業は成長戦略の一環として、経営の効率化やグループ再編の必要性から、それぞれの手法を選択します。
ここでは、代表的な5つの組織再編である「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」について、それぞれの概要をわかりやすく解説します。
合併
合併とは、2つ以上の会社が1つの会社になることを指します。合併には以下の2種類があります。
- 吸収合併:既存の会社が他社を吸収し、相手の会社は消滅する
- 新設合併:すべての会社が消滅し、新会社を設立する
合併は、事業規模の拡大や経営資源の統合を目的に行われ、特にグループ企業間や競合他社との連携で用いられることが多いです。
会社分割
会社分割は、会社の事業の一部または全部を他の会社に承継させる方法です。会社分割には以下の2種類があります。
- 吸収分割:既存の他社に事業を移す
- 新設分割:新たに会社を設立し、そこに事業を移す
グループ内の事業整理や、不採算事業の切り離し、事業の専門化などを目的として活用されます。
株式交換
株式交換とは、ある会社が他の会社のすべての株式を取得し、完全子会社化する方法です。自社の株式を対価として、相手会社の株主に交付します。
グループ経営の強化や、資本関係の整理などを目的に用いられます。
株式移転
株式移転は、複数の会社が共同で新たに持株会社(親会社)を設立し、その会社の完全子会社となる手法です。
企業グループの再編や、経営の一元化や管理体制の強化を図る際に利用されます。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社が特定の事業や資産を、他の会社に売却する方法です。会社全体ではなく、「事業単位」での売買である点が特徴です。
特定の事業からの撤退や、新規事業への資金調達を目的として行われ、企業は経営資源の最適化を図り、より収益性の高い分野に注力することが可能となります。
組織再編の手続き7ステップ

組織再編は、企業の効率化や競争力強化を目的として行われる重要なプロセスです。成功には、計画的かつ慎重な進行が求められます。
ここでは、組織再編を円滑に進めるための基本的な7つのステップを解説します。
再編の戦略を決める
最初に行うべきは、再編の目的と方向性を明確にすることです。効率化や競争力の強化、財務健全化などの目標を設定し、それに基づいた具体的な戦略を策定します。
最初の段階では、再編が事業全体に与える影響を評価し、リスクとメリットのバランスを十分に検討することが重要です。
再編する企業を選定する
次に、再編の対象となる企業や事業部門を選定します。
グループ内再編であれば、子会社や関連会社の中から対象を選び、M&A(企業の合併・買収)を含む場合は、外部企業の候補をリストアップします。
企業の選定では、対象企業の市場価値やシナジー効果、将来的な貢献度を多角的に評価することが必要です。
再編する企業と交渉する
対象企業が決まったら、再編の大枠を決めるための交渉を開始します。
両社の希望条件について話し合い、再編基本方針やスケジュールについて合意を形成します。合意が取れたら、基本合意書を締結します。
条件交渉・各種契約を締結する
基本合意の後は、より詳細な契約内容の調整と正式な契約書の作成に進みます。
再編の具体的な手法(合併、分割、譲渡など)、資産や負債の移転条件、従業員の扱いなどを明記します。
契約書は法的な拘束力を持つため、専門家のチェックを受けながら慎重に作成・確認することが重要です。
デューデリジェンスを実施する
デューデリジェンスとは、対象企業の実態や潜在的なリスクを調査するプロセスです。
財務、法務、税務、労務、環境など、さまざまな側面から多角的に調査を行うことが求められます。
問題点が発見された場合は、契約条件の見直しや再交渉につながることもあります。
最終合意前に再度条件を交渉する
デューデリジェンスの結果を踏まえ、必要に応じて契約条件の再交渉を行います。
新たなリスクや課題が判明した場合には、価格や条件の見直しが必要になることもあります。
リスクと期待される効果のバランスを慎重に判断し、最終的な合意に向けて調整を進めていきます。
最終契約書を締結する
すべての条件が整ったら、最終契約書を締結します。
最終契約書にはすべての取引条件が詳細に記載されており、基本合意書とデューデリジェンス結果を踏まえて作成されます。
法的拘束力を持つ重要な文章であるため、専門家の助言を得ながら、細部まで慎重に確認することが重要です。
再編を成功させるための3つのポイント

組織再編を成功させるためには、計画的な手続きを進めるだけでなく、関係者全員が同じ目的を理解し、適切に行動することが不可欠です。
ここでは、組織再編を成功に導くために、特に重要とされる3つのポイントをご紹介します。
明確な目的を共有する
再編のプロジェクトを円滑に進めるためには、「なぜ再編を行うのか」「どのような成果を目指すのか」といった目的や期待される効果を、社内外の関係者と明確に共有することが重要です。
目的が不明確なまま再編を進めると、現場での混乱や抵抗が生じやすく、再編の効果を十分に発揮できない可能性があります。
一方で、目的が全員に浸透していれば、社員の不安を和らげるとともに、再編への前向きな姿勢を引き出すことができます。
綿密な計画とリスク管理をする
再編は、多くの法的手続きや関係者間の調整を伴う複雑なプロジェクトです。スケジュールや資金計画、人員体制、契約内容などを具体的に設計したうえで実行に移すことが重要です。
再編には以下のようなリスクが潜んでいます。
- 想定外のコスト増加
- 契約トラブルや合意不成立
- 社員の退職や士気低下
- 統合後の文化摩擦や業務混乱
リスクを最小限に抑えるには、初期段階での洗い出しと事前の対策を徹底することが必要です。特に、デューデリジェンス(詳細調査)を通じて潜在的な課題を把握しておくことは、トラブルの防止に効果的です。
従業員への丁寧な説明とケアを徹底する
再編は、従業員にとって職場環境が大きく変わる可能性のある出来事であり、精神的なストレスを伴います。新たな体制や人事配置、人事制度の変更に対して、不安を感じる従業員も多く、一人ひとりに寄り添った情報提供とサポートが欠かせません。
再編の目的やメリットを分かりやすく伝えるとともに、従業員に期待される役割を具体的に説明することで、不安が軽減し、協力体制を築くことができます。
相談窓口の設置や研修プログラムの提供といったフォロー体制を整えることも、安心して働ける環境づくりにつながります。
組織再編をする上での注意点

再編は、企業の成長や経営効率の向上に大きな効果をもたらしますが、その一方で、リスクや課題が顕在化する可能性もあります。
ここでは、組織再編を実施するうえでの3つの注意点と、それぞれの対応策について解説します。
多額のコストがかかる
再編には、専門家の知見が必要となるため、財務・法務・税務などの調査に伴う士業報酬や、コンサルティング費用など、外部専門家への支払いが多く発生します。
合併に伴うシステム統合や、株主・債権者への対応に関わる費用も必要になるほか、予期せぬ支出が発生するケースも想定されます。
コストが当初の予算を大きく上回ると、企業の財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があるため、事前に費用対効果を十分に分析し、余裕を持った予算計画を立てておくことが重要です。
外部の専門家や支援サービスを適切に活用することで、業務の一元化や効率化が図られ、結果としてコスト全体の抑制につながるでしょう。
従業員にストレスがかかる
再編に伴う組織変更や業務内容の見直しは、従業員にとって不安やストレスの要因になります。
業務の変化や将来への見通しが立たない状況では、モチベーションの低下や生産性の悪化を招く恐れがあるため、十分な配慮が必要です。
従業員のストレスを軽減するためには、早い段階での情報共有と、継続的な対話を通して従業員の安心感を高めることが重要です。
管理職による定期的な面談や声かけなど、日常的なラインケアの実施も有効な手段です。
企業文化のミスマッチが起こり得る
再編により、異なる企業文化や価値観が統合されると、従業員の間で摩擦や混乱が生じる可能性があります。
例えば、「成果主義」の企業と「年功序列」を重視する企業が統合した場合、評価基準や働き方のギャップから意思疎通が難しくなり、モチベーションの低下やチームワークの崩壊につながることもあります。
ミスマッチを放置すると、連携の不備や人間関係のトラブルを招き、業務効率にも影響を及ぼすため、事前の対策が重要です。
具体的には、両社の文化や価値観を分析し、共通点や違いを整理した上で、対話や意識調査、ワークショップなどを通じた相互理解を深めていくことが効果的です。
まとめ:再編を理解して変化に対応できる組織へ

再編は、企業が変化の激しいビジネス環境を乗り越え、持続的に成長するための有効な戦略のひとつです。一方で、多額のコストや従業員への影響といった課題も伴うため、慎重な判断と丁寧な準備が欠かせません。
だからこそ、目的を明確にし、リスクを見極めながら、関係者と丁寧に向き合う姿勢が重要です。再編を通じて、自社の強みを活かした柔軟な組織づくりに取り組み、変化に対応できるしなやかな企業体制の構築を目指しましょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。






























