近年、サイバー攻撃や情報漏洩などITセキュリティに関する脅威はますます深刻化しており、経営全体に関わるリスクとなっています。
攻撃を受ければ、顧客データの流出やシステム障害、企業イメージの失墜といった損害が発生し、回復までに膨大なコストと時間を要することも少なくありません。
本記事では、ITセキュリティの基本的な考え方や実践的な対策、押さえておきたい法的ポイントを解説します。
目次
- 1 ITセキュリティとは?
- 2 なぜITセキュリティが重要なのか?
- 3 サイバー攻撃の増加
- 4 個人データや企業機密の保護
- 5 法的・規制面での必要性
- 6 ITセキュリティにおける脅威
- 7 マルウェア
- 8 ランサムウェア
- 9 フィッシング詐欺
- 10 DDoS攻撃(分散型サービス妨害)
- 11 サプライチェーン攻撃
- 12 ゼロデイ攻撃
- 13 ITセキュリティに関する主要な法規制
- 14 個人情報保護法
- 15 サイバーセキュリティ基本法
- 16 不正アクセス禁止法
- 17 GDPR(EU一般データ保護規則)
- 18 企業がITセキュリティを強化しないと起こり得るリスク
- 19 経済的な損失
- 20 ブランドの信頼性の低下
- 21 コンプライアンス違反
- 22 企業が導入したいITセキュリティ対策
- 23 ウイルス対策ソフトの導入
- 24 多要素認証(MFA)の実施
- 25 VPN(Virtual Private Network)の使用
- 26 アクセス制御の強化
- 27 データの暗号化
- 28 ファイアウォールの設定
- 29 定期的なソフトウェアの更新
- 30 モバイルデバイスの管理
- 31 ITセキュリティの強化で経営課題を解決しよう
ITセキュリティとは?

ITセキュリティとは、企業や個人が保有するデジタル情報を不正アクセスやデータ漏洩、サイバー攻撃などのリスクから保護するための取り組み全般のことです。
近年、インターネットやクラウドサービスの普及により、ビジネスのデジタル化が進む一方で、サイバー脅威も高度化・巧妙化しています。
ITセキュリティは、機密性(Confidentiality)・完全性(Integrity)・可用性(Availability)を守ることが基本です。
情報が第三者に漏れない、改ざんされない、必要な際にアクセスできる状態を維持することが目的となります。
なぜITセキュリティが重要なのか?

ITセキュリティの重要性について解説します。
サイバー攻撃の増加
近年、ランサムウェアやフィッシング詐欺、標的型攻撃といったサイバー攻撃は、企業規模に関わらずあらゆる組織を脅かしています。
サイバー攻撃により、企業のシステムがダウンする、重要なデータが暗号化され身代金を要求される事例も後を絶ちません。
ITセキュリティを強化することで、サイバー攻撃のリスクを未然に防ぎ、被害を最小限に抑えることが可能です。
個人データや企業機密の保護
企業は顧客情報や取引先情報、従業員の個人情報など多くの個人データを取り扱っています。
また、技術資料や財務データなどの企業機密も業務の根幹を支える重要な資産です。
情報が外部に漏洩した場合、信頼の失墜や競争力の低下、損害賠償請求など深刻な事態につながる可能性があります。
法的・規制面での必要性
ITセキュリティを強化することは、法的・規制面での義務にも直結しています。
個人情報保護法では、事業者に対して適切な安全管理措置の実施が義務付けられており、違反があれば行政指導や罰則の対象になります。
GDPR(一般データ保護規則)のように、海外との取引がある企業は国際的な法令にも対応しなければなりません。
規制に対応しないまま業務を続けていると、法令違反で多額の罰金を科されたり、取引先からの信頼を失ったりするリスクが高まります。
ITセキュリティにおける脅威
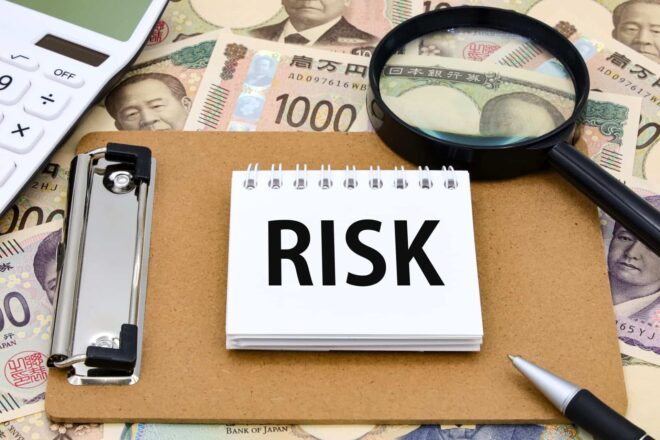
企業が警戒すべきITセキュリティにおける脅威を解説します。
マルウェア
マルウェアとは、悪意あるソフトウェア全般を指す総称で、ウイルスやスパイウェア、ワーム、トロイの木馬などです。
ユーザーの知らないうちにシステムに侵入し、情報の盗難やファイルの破壊、バックドアの設置などさまざまな被害を引き起こします。
感染経路はメールの添付ファイルや偽サイトからのダウンロード、USBメモリなどです。
ランサムウェア
ランサムウェアとは、企業や個人のコンピュータ内のデータを暗号化し、解除するために金銭を要求するマルウェアの一種です。
被害者は業務に必要なファイルやシステムにアクセスできなくなり、多くの場合、身代金を支払わなければ復旧できません。
一度感染すると被害範囲は広く、業務停止や顧客情報流出、社会的信頼の失墜につながる恐れがあります。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは企業を装ったメールや偽サイトを用いて、ユーザーからIDやパスワード、クレジットカード番号などの機密情報を騙し取る手口です。
情報が盗まれると、顧客への情報漏洩や取引先との信頼関係の損失、システムへの不正アクセスによる損害など多くのリスクが発生します。
DDoS攻撃(分散型サービス妨害)
DDoS攻撃は、複数のコンピュータから大量のデータを一斉に送信し、ターゲットのネットワークを過負荷状態にして正常なサービス提供を妨害する攻撃手法です。
Webサイトの表示が遅くなる、アクセス不能になることで、オンラインショップや予約サイトなどの売上損失や顧客離れを招く原因になります。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃とは、企業の取引先や業務委託先など外部のサプライヤーやサービスベンダーを経由して標的企業に攻撃を仕掛ける手法です。
ITセキュリティ対策が甘い中小企業やITベンダーが狙われやすく、脆弱性を足がかりに、最終的な標的である大手企業に侵入されるケースが増えています。
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃とは、ソフトウェアやOSなどの脆弱性が開発元に認知される前に悪用される攻撃のことを指します。
開発者が脆弱性に対応するセキュリティパッチを用意する「0日目」から攻撃が始まることが由来です。
対策が確立されていないため、攻撃が発見されるまで被害を受けやすい点が特徴です。
ITセキュリティに関する主要な法規制
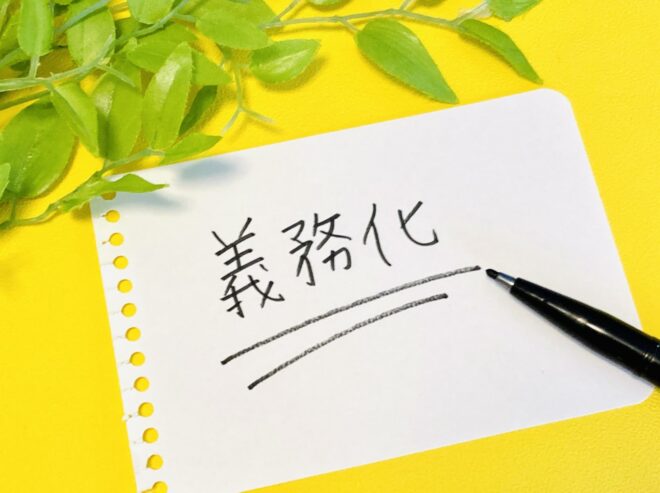
ITセキュリティに関する主要な法規制に関して解説します。
個人情報保護法
個人情報保護法は、日本国内における個人情報の取扱いルールを定めた法律です。
企業や団体が、顧客や従業員などの個人情報を適切に取得・利用・管理・提供することを義務付けています。
違反した場合は行政指導や命令、罰則の対象となるため、企業には技術面・運用面双方の対策が求められます。
サイバーセキュリティ基本法
サイバーセキュリティ基本法は、日本政府がサイバー空間の安全性を確保するために2015年に施行した法律で、国家レベルでのITセキュリティ対策の指針となるものです。
政府や地方公共団体、企業、国民全体がサイバーセキュリティ確保に取り組むことを基本理念として定めています。
不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法は、他人のIDやパスワードを無断で使用して、システムやサービスにアクセスする行為を禁止しています。
処罰の対象となるのは、第三者のログイン情報を盗用して社内システムに侵入したり、アクセス制限を回避してデータを閲覧・取得したりする行為です。
正当な管理者以外がID・パスワードを共有し、掲示板などで公開する行為も違法となります。
GDPR(EU一般データ保護規則)
GDPRは、EUが2018年に施行した個人データ保護に関する包括的な法律です。
EU域内の個人に関するデータを処理するすべての組織に適用され、EU在住者に対するサービスや取引がある場合は日本の企業も法律の対象となります。
違反した場合、最大で世界売上高の4%または2,000万ユーロのいずれか高い額が課されるため、グローバル企業にとっては重大な法的リスクです。
企業がITセキュリティを強化しないと起こり得るリスク

企業がITセキュリティ強化を怠った場合に直面し得るリスクを解説します。
経済的な損失
企業がITセキュリティ対策を怠ると、サイバー攻撃や情報漏洩によって直接的・間接的な経済的損失を被るリスクがあります。
顧客情報や業務データが流出した場合、謝罪対応や調査費用、システム再構築、法律相談などのコストが多額になる可能性が高いです。
業務停止による売上の損失や攻撃者による身代金要求に応じることで、経営の継続が困難になる事態もあり得ます。
ブランドの信頼性の低下
情報漏洩や不正アクセスが公になった場合、企業のブランドイメージに深刻なダメージを与える恐れがあります。
企業に対する不信感を抱かれやすくなり、SNSなどを通じて企業の不祥事が急速に拡散されれば、信頼を取り戻すのは容易ではありません。
売上減少や顧客離れ、新規取引先の獲得難化など経営に悪影響を及ぼします。
コンプライアンス違反
企業がITセキュリティを強化しないままでいると、コンプライアンス違反につながるリスクがあります。
個人情報保護法など法令に違反すると、行政指導や業務停止命令、罰金などの制裁が課される可能性が高いです。
違反すれば、営業許可の取消や社会的信用の低下につながる場合もあります。
企業が導入したいITセキュリティ対策

企業が導入したいITセキュリティ対策を紹介します。
ウイルス対策ソフトの導入
ウイルス対策ソフトは、マルウェアやランサムウェアなど悪意あるプログラムの侵入を検知・隔離し、企業のシステムやデータを保護するための対策ソフトです。
定期的なアップデートを怠ると新種のウイルスに対応できなくなるため、常に最新版を維持する必要があります。
多要素認証(MFA)の実施
多要素認証は、知識要素(パスワード)、所持要素(スマホやトークン)、生体認証(指紋・顔)など複数の認証要素を組み合わせて本人確認を行うセキュリティ技術です。
万が一パスワードが流出しても、追加の認証要素がなければ不正ログインはできません。
VPN(Virtual Private Network)の使用
VPNは、インターネット上に仮想の専用線を設け、通信内容を暗号化することで安全なネットワーク接続を実現します。
リモートワークや出張先から社内ネットワークにアクセスする際、VPNを介せば第三者による盗聴や改ざんのリスクを低減できます。
アクセス制御の強化
アクセス制御とは、業務システムやファイルへのアクセスをユーザーごとに制限する仕組みです。
退職者のアカウント放置や業務と関係のない部署にまで機密ファイルが共有されると、内部不正や情報漏洩の温床となる可能性があります。
定期的に権限の見直しを行い、不正アクセスや誤操作によるトラブルを防ぎましょう。
データの暗号化
データの暗号化は、万が一データが流出しても第三者に内容を解読されないようにするための施策です。
デバイス全体の暗号化やファイル単位の暗号化など通信暗号化を併用すれば、多層的なセキュリティを構築できます。
ファイアウォールの設定
ファイアウォールは、社内ネットワークと外部ネットワークとの間に配置し、特定の通信を遮断・許可することで不正アクセスや攻撃を防ぐセキュリティ機器です。
社内ネットワーク内のトラフィック監視や内部不正の検知・対応にも活用されています。
定期的なソフトウェアの更新
ソフトウェアやOSの脆弱性はサイバー攻撃の格好の標的になります。
WindowsやmacOS、各種アプリケーションを常に最新バージョンに保つことが重要です。
自動アップデート機能の活用やパッチ管理ツールの導入により、更新作業を効率的かつ漏れなく実施する仕組みを構築しましょう。
モバイルデバイスの管理
社外での業務が多い営業職やリモートワークを行う社員が利用するデバイスは、盗難や紛失リスクが高いです。
デバイス管理ツールを導入すれば、遠隔からのデータ削除や位置情報の取得、アプリ利用制限などが可能になり不正利用を防げます。
私物端末の業務利用を認める場合も、企業側が一定の管理権限を保持する体制を整えておくことが必須です。
ITセキュリティの強化で経営課題を解決しよう

ITセキュリティの強化は、情報の保護にとどまらず、企業の経営課題を多角的に解決するための重要な施策です。
サイバー攻撃による情報漏洩やシステムダウンは、直接的な損害だけでなく、顧客からの信頼失墜や事業停止といった深刻な影響を及ぼします。
ITセキュリティを強化すれば、リスクの低減に加え、BCP(事業継続計画)の実現にもつながります。
ITセキュリティは経営を守る投資と捉え、戦略的に取り組みましょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。




























