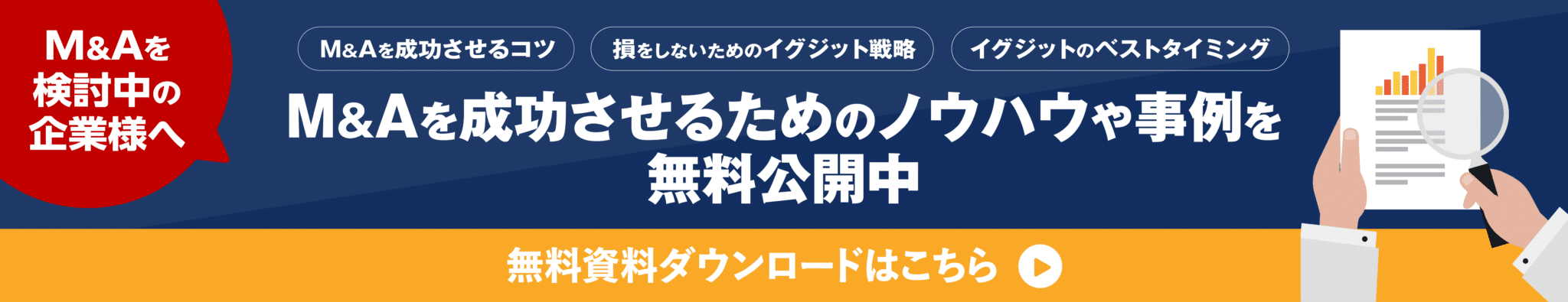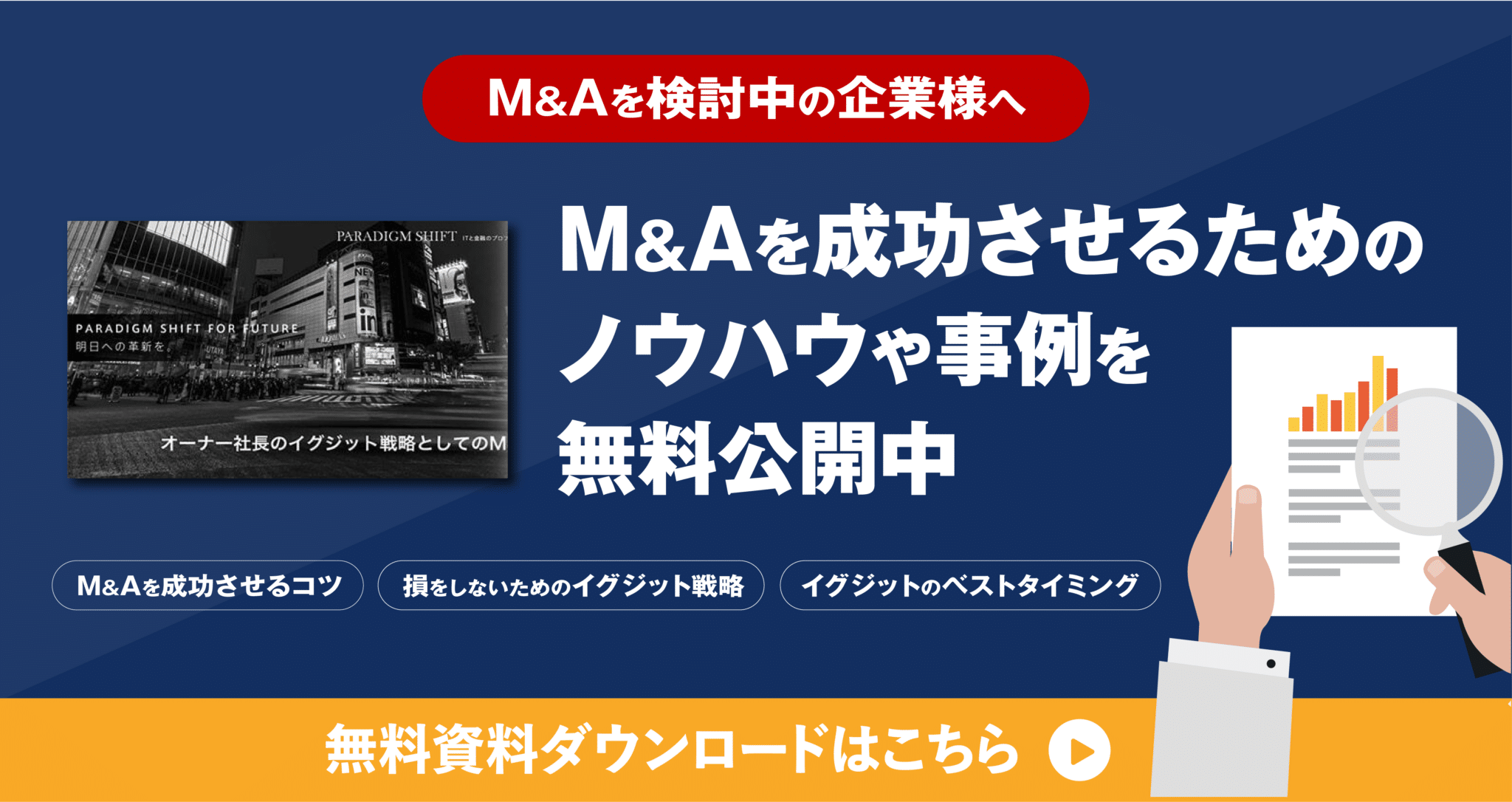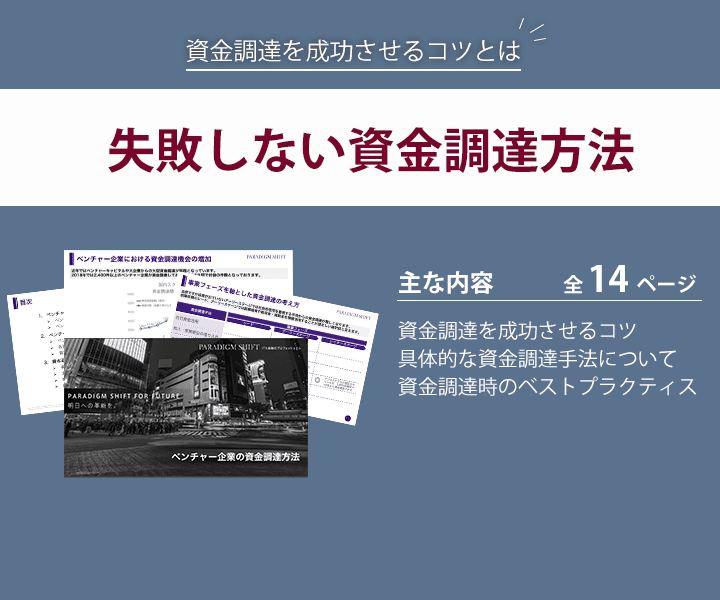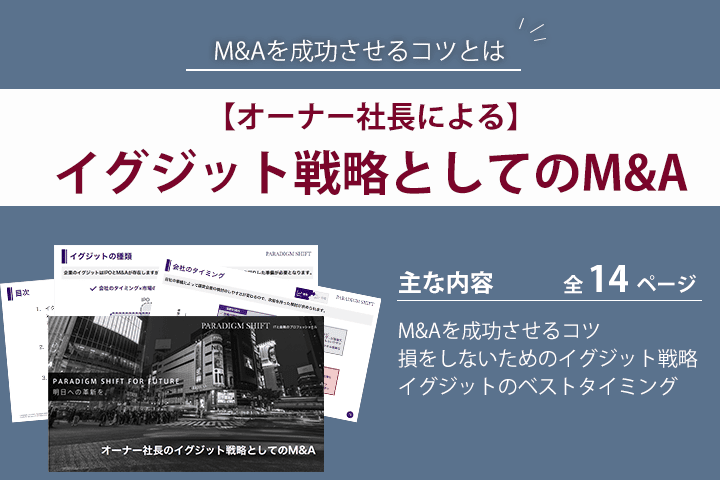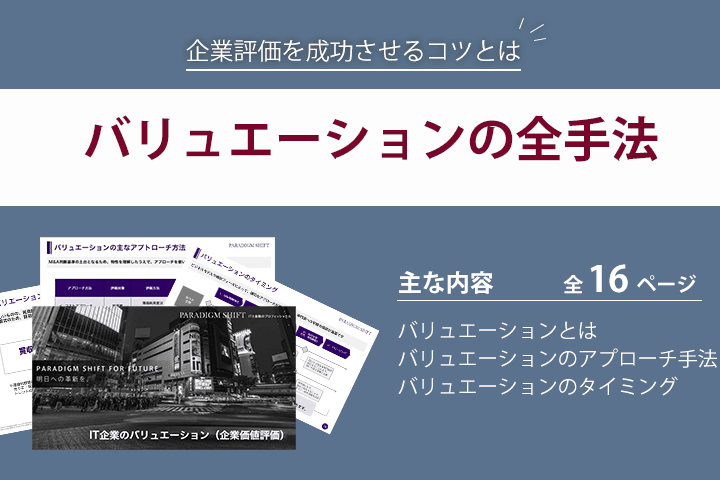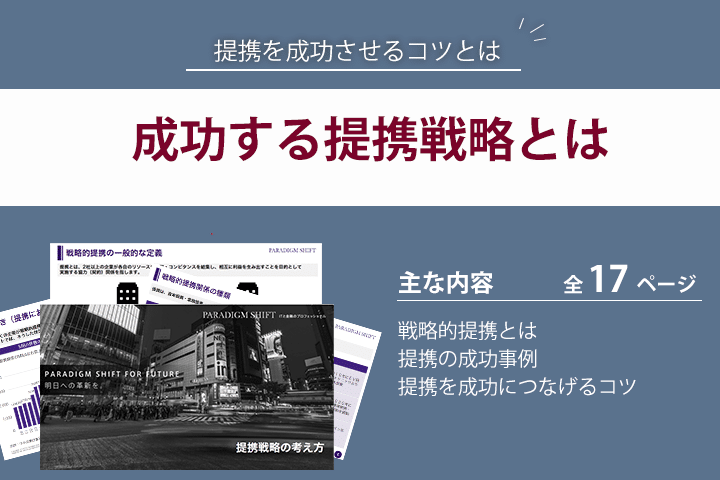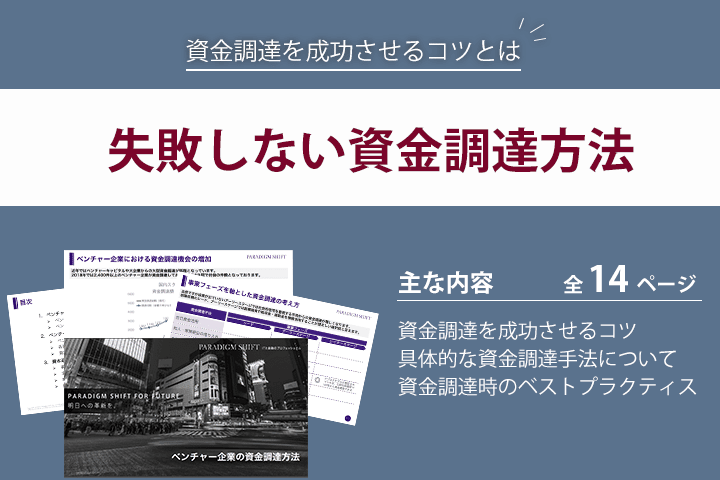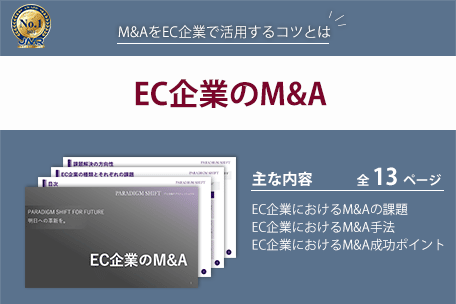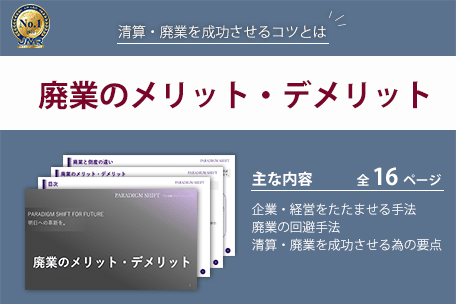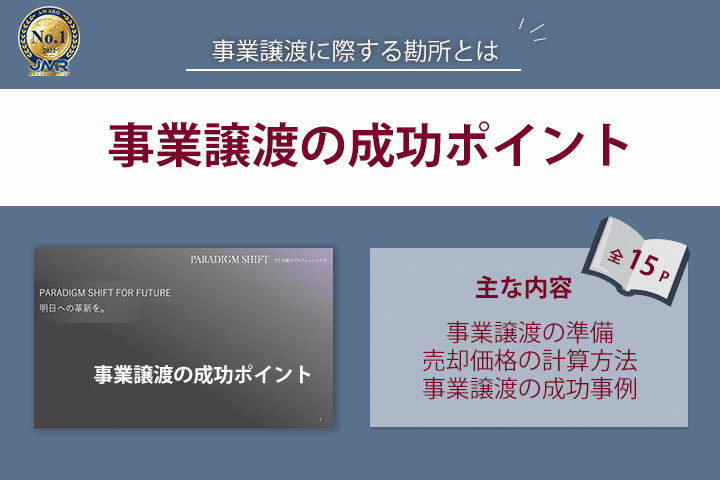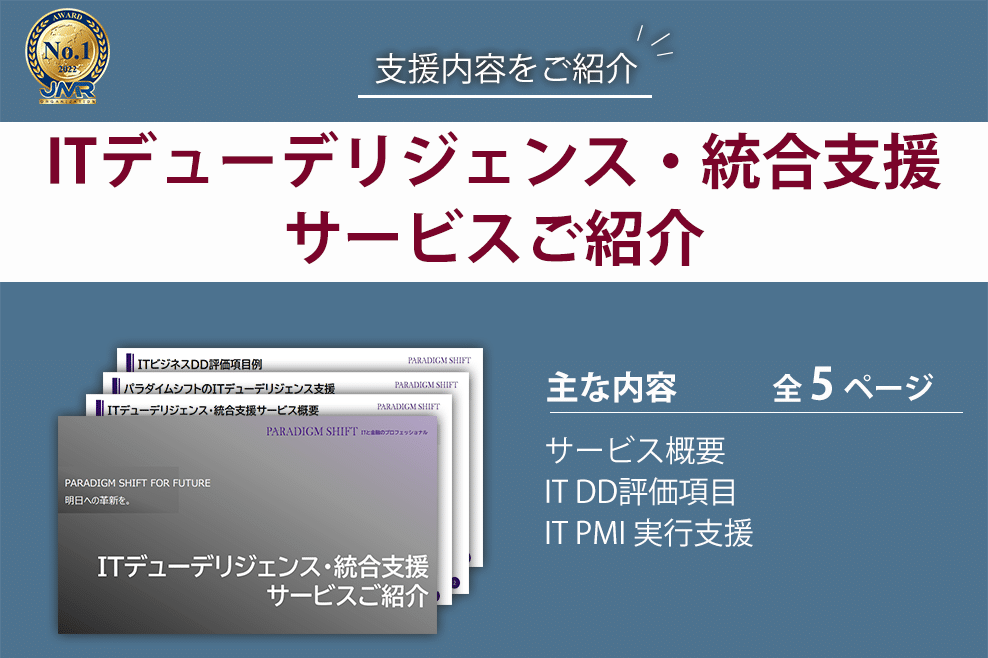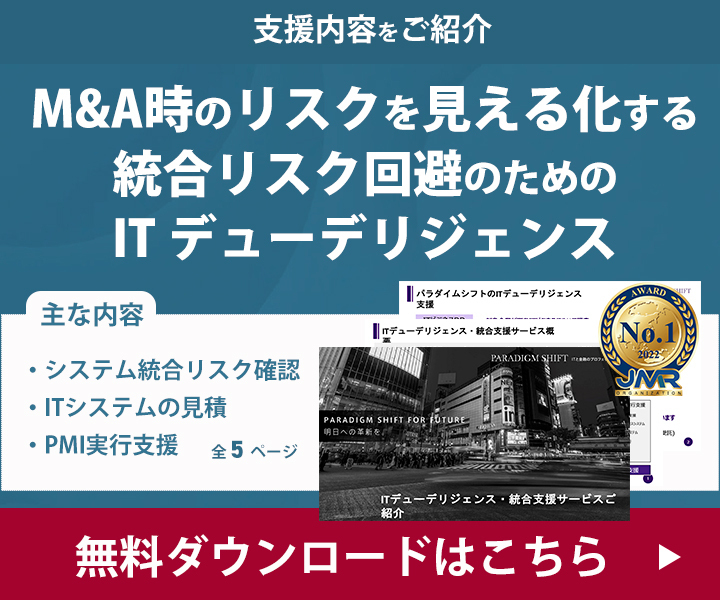法人保険の加入で節税できると一度は耳にしたことがあるかもしれません。ですが、これは事実とは言えません。
ではなぜ、法人保険は節税になると言われるのでしょうか?
それは、法人保険の商品の特徴や、国税庁の税制改正など、複雑な事情が重なっています。
今回の記事では、法人保険が節税対策になると言われるようになった理由や仕組みについて、税制改正後のルールを紹介しながら解説します。
目次
- 1 法人保険を活用した節税はできる?
- 2 法人保険を活用した節税ができない具体的な理由
- 3 これだけは知っておきたい、法人保険で使う基礎用語
- 4 損金
- 5 解約返戻金
- 6 出口戦略
- 7 法人保険の節税戦略に関する過去・今後の動向
- 8 法人が保険に加入するメリットとは?
- 9 将来法人税率が下がった時に、節税につながる可能性がある
- 10 企業を取り巻くさまざまなリスクに備えられる
- 11 経営者の手取り額を増やせる
- 12 福利厚生を充実させられる
- 13 企業が加入できる法人保険の種類
- 14 養老保険
- 15 年金保険
- 16 逓増定期保険
- 17 長期定期保険
- 18 医療保険・がん保険
- 19 法人保険に加入した際の経理処理の方法
- 20 解約返戻率のピークが50%以下の場合
- 21 解約返戻率のピークが50%超70%以下の場合
- 22 解約返戻率のピークが70%超85%以下の場合
- 23 解約返戻率のピークが85%超の場合
- 24 法人の保険は節税のためではなく、保障・福利厚生のため。
法人保険を活用した節税はできる?

法人の節税について調べてみると、「節税の目的で法人保険に入る」という話を一度は耳にしたことがあるでしょう。
全額損金タイプの法人保険に加入して、保険料を全額損金として計上します。それにより、課税対象となる所得税を少なくさせ、税金も少なくさせる方法です。
そして、保険を解約した際には、今まで支払った払込保険料が戻ってきて、節税になる仕組みです。
しかし結論から言うと、現在の税制ルールでは、法人の保険で節税するのは、難しいと言わざるを得ません。
2019年の税制改正前は、死亡保障や医療保障など、本来の保険の価値を受けながら節税するために良く使われる手段でした。しかし、改正後はこの手法では節税できなくなりました。
理由は、税制改正後、保険料を損金にするためのルールや基準金額が厳しく、複雑化したためです。
法人保険を活用した節税ができない具体的な理由

保険料を支払った際に経費として扱う保険は、法人税を減らす効果があるため、節税できると思われるかもしれません。
しかし、その保険が満期になったり被保険者が亡くなったりして、保険金が会社に支払われると、保険金は収入として扱います。
したがって、会社が受け取る保険金には多額の法人税が課税されるため、法人保険を活用した節税はできません。
たとえば、500万円の保険料を支払い、法人税を200万円分減らした場合、保険金500万円が会社に支払われると、収入として扱うため、200万円の法人税が課税される仕組みです。
節税とは、最終的に支払った税金を減らす行為を指します。
保険料を支払うときは法人税が減りますが、保険金を受け取ると、減らした分の法人税が課税されるため、結果的には節税できません。
これだけは知っておきたい、法人保険で使う基礎用語

法人の保険で節税できるか否かを議論する上で、よく出てくる用語は「損金」、「解約返戻金」、「出口戦略」です。
この項では3つの意味について詳しく紹介します。
損金
損金とは、資本や取引を除いた資産の減少となる損失で、法人の税務用語として使われています。
損金が増えると、会社の税務上の利益が減り、課税対象が少なくなるため、損金を多くしたほうが良いと考えられています。
経費として使用した項目には、損金の対象になるもの・ならないものがありますが、一部の保険では、保険料が損金の対象になります。
そのため、法人で保険の加入を考えたとき、保険料を損金にできた方が良いと考えるのは自然なことでしょう。
法人の保険には、保険料が全額損金になる商品や保険料の何%まで損金にできるなど、商品や保険の加入期間、保険料によって様々です。
解約返戻金
解約返戻金とは、保険を解約した際に戻ってくる払込保険料で、解約返戻率は、払込保険料に対する解約返戻金の割合いです。
解約返戻率が100%未満の場合、解約までに支払った金額よりも少ない金額が払い戻され、割合が多いほど、払込保険料の戻る金額が多くなります。
解約返戻金は一定期間を迎えるとピークになり、その後は低下していきます。
法人保険で節税をするときには、解約返戻率がピークのときに解約して、多くのお金が手元に戻るようにすると良いと考えられてきました。
出口戦略
出口戦略は、解約返戻金の使い道を指します。
法人保険を解約すると、解約返戻金は手元に戻りますが、戻ってきたそのお金には税金が掛かります。
そのため、解約返戻金の使い道を予め決めておきます。具体的な使い道は、従業員の退職金や事業継承のための費用が一般的です。
解約返戻率がピークになったところで解約する場合、100%の保険料は戻りませんが、多くの解約返戻金が戻ってくるため、総体的にみると、得しているという見方もあります。
法人保険の節税戦略に関する過去・今後の動向

解約返戻金がピークのときに解約すれば、100%の保険料は戻りませんが、税金を支払うよりは得をすると言われた時期もありました。
しかし、戻ってきた解約返戻金にも税金がかかるため、納税を先送りしたに過ぎず、結果的には節税効果にはなっておらず、損をしていることも多いのです。
こうした状況を受け、国税庁は2019年に保険商品を規制する新しいルールを通達しました。
全額損金タイプの保険は、解約返戻率を50%未満にするというルールです。
そのため、現在では、全額損金タイプの保険での節税効果がなくなっただけでなく、納税を先送りするのも難しくなったと言えるでしょう。
法人が保険に加入するメリットとは?

節税ができないなら、法人保険に加入する意味がないと思われる方もいるかもしれません。
しかし、法人が保険に加入すると、以下のようなメリットがあります。
- 将来法人税率が下がった時に、節税につながる可能性がある
- 企業を取り巻くさまざまなリスクに備えられる
- 経営者の手取り額を増やせる
- 福利厚生を充実させられる
それでは、各メリットを解説します。
将来法人税率が下がった時に、節税につながる可能性がある
将来、法人税率が下がると、その時までに課税した分の節税が可能です。
たとえば、500万円の保険料を支払い、法人税を200万円分減らした場合を考えてみましょう。
保険金500万円が会社に支払われる際、法人税が下がっていれば、収入として課税される分の金額が減ることになります。
とはいえ、得られる効果はほんの数%ほどです。
数%節税するために解約返戻率が7~80%ほどの保険に加入すると、節税額より元本の方が少ないため、結果的に損します。
法人保険に加入する際には、経費による節税ではなく、将来的な法人税率の減少による節税を意識しましょう。
企業を取り巻くさまざまなリスクに備えられる
企業は、常に何かしらのリスクを抱えて経営しています。
たとえば、経営者の健康面など人的リスク、経営状況の悪化や従業員への退職金といった資金リスクなどです。
そこで、法人保険に加入すれば、それらのリスクに備えることができます。
経営者が病気や事故で働けなくなった場合、法人が保険金を受け取り、事業の存続に向けて企業の損失を補ったり、遺族への生活保障に役立てたりすることが可能です。
なお、経営者が死亡した際に、死亡退職金を遺族に支払うには、退職金規定を作成しなければなりません。
また、事業が悪化し、経営不振に陥った場合や多額の投資資金が必要になった場合も、保険を解約し、解約返戻金を得れば、事業資金として利用できます。
法人保険に加入すれば、将来起こり得るさまざまな出来事に対して、リスクヘッジが可能です。
経営者の手取り額を増やせる
個人保険に加入する場合、自分の収入から保険料を支払いますが、法人保険に加入し、会社の支払いにすると税金や社会保険料が減るため、経営者の手取り額を増やせます。
さらに、確定申告の面でも法人保険の方が得られるメリットが多いといえるでしょう。
個人保険の場合、保険料控除は上限が4万円となっていますが、法人保険の場合は会社の経費として支払えるだけでなく、金額に上限がありません。
つまり、法人保険の金額が高くても、すべて保険料控除として扱うことが可能です。
福利厚生を充実させられる
法人保険を活用すれば、従業員の福利厚生を充実させることも可能です。
保険を解約し、得られるお金をもとに、退職金や医療費、遺族への生活保障に充てることで従業員の福利厚生を確保できます。
福利厚生の充実度の高さは、従業員のモチベーションアップだけでなく、優秀な人材の確保・維持にも役立つでしょう。
従業員は、保険料を会社と折半し、医療保険や労災保険、年金保険といった福利厚生を得られます。
労働者不足が深刻な日本では、離職率の低下や優秀な人材の確保など、従業員の確保・維持が重要です。
法人保険に加入し、満期を迎えた保険金や解約返戻金を原資にし、役員や従業員の福利厚生をサポートできれば、企業としてもより成長できるでしょう。
企業が加入できる法人保険の種類

税制改正により、節税効果はなく、納税を先送りする対策も難しくなりました。
そのため、法人保険の本来の意味である保障や福利厚生を充実させることを目的に、保険に加入することをおすすめします。
保障や福利厚生のために法人保険に加入し、その分の保険料が少しでも損金にできれば、一石二鳥という考えの元、法人保険に加入するのが良いでしょう。
この項では、保障・福利厚生を充実させながら、税金の支払いを少しでも少なくするための保険の種類について紹介します。
養老保険
被保険者の死亡時に死亡保険金、生存していて満期を迎えたときには満期保険金が支給されます。死亡保険金と満期保険金の支給額が同額の保険を養老保険といいます。
将来の資金を蓄えながら、万一に備えたいときにおすすめの保険です。
法人向け養老保険の場合、従業員の退職金を養老保険で準備する場合が多く、保険料の半額を損金として計上できます。法人保険の中でもよく使われます。
年金保険
予め定めた時期を迎えると、所定の従業員へ年金が支払われ、被保険者が途中で死亡した場合、死亡保険が支払われるものもあります。
従業員の福利厚生として加入していると、保険料の1/10を損金として計上できます。
逓増定期保険
逓増定期保険は、死亡保険金の金額が契約当初よりも多くなる保険。
解約返戻率が高く、ピークも早い時期にくるため、法人でも資産形成として活用されることの多い保険です。
保険料が割高ですが、契約後4〜5年で全額を損金として計上できるものが多くあります。
長期定期保険
保険期間を長期で設定する生命保険です。
解約返戻率のピークは加入後10〜30年ほどと長く、返戻率が70%〜90%と高くなります。
逓増定期保険と同様に、法人の資産形成として頻繁に使われますが、保険の商品や被保険者の年齢により保険料が異なるため、契約時によく確認しましょう。
医療保険・がん保険
医療保険・がん保険は、第三分野保険と呼ばれます。
怪我や病気の際の保障も充実しているため、従業員の福利厚生として加入するのがおすすめです。
掛け捨ての保険の場合、全額を損金として計上できるため、福利厚生を充実させながら節税できる可能性も高くなります。
法人保険に加入した際の経理処理の方法

税制改正後に法人保険に加入したときの経理処理の方法は、保険のピーク時の解約返戻率によって4つに分かれます。
- 解約返戻率のピークが50%以下
- 解約返戻率のピークが50%超70%以下の場合
- 解約返戻率のピークが70%超85%以下の場合
- 解約返戻率のピークが85%超の場合
「解約返戻率のピークが50%以下」の保険で全額損金にできても、支払った保険料の半額しか払い戻されないため、節税効果はないと言えるでしょう。
以下の項で、それぞれの損金の期間や条件について、具体的な数値と合わせて見ていきましょう。
解約返戻率のピークが50%以下の場合
解約返戻率が50%未満は、保険料の全額を損金として計上できます。
全額損金として計上できるのはこのときのみで、その他の解約返戻率の場合は、損金として計上できる期間や割合に制限があります。
解約返戻率のピークが50%超70%以下の場合
解約返戻率のピークが50%超70%以下の場合は、被保険者一人あたりの保険料により、計算方法が異なります。
1人の年間保険料が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金として計上できます。
1人の年間保険料が30万円以上の場合は、保険料により、損金にできる金額や期間が異なります。概ね、保険加入時期の保険料の40%を超すと保険料の60%前後を損金に計上できます。
解約返戻率のピークが70%超85%以下の場合
解約返戻率のピークが70%超85%以下の場合も、被保険者一人あたりの保険料により、計算方法が異なります。
1人あたりの保険料の下限はなく、保険料が保険加入時の金額の40%を超すと、保険料の40%前後を損金として計上できますが、解約返戻率のピークが50%超70%以下の場合よりも損金にできる割合が少なくなります。
解約返戻率のピークが85%超の場合
解約返戻率のピークが85%超の場合、保険加入から10年間は「年間の保険料×最高解約返戻率×0.9」を資産に計上し、残りを損金として計上します。
それ以降は、「年間の保険料×最高解約返戻率×0.7」は損金にせず、残りを損金にします。
解約返戻率の最高値を迎えたあとは、「保険料の全額」と「それまで損金に計上できなかった分の金額の合計」を損金に計上できます。
法人の保険は節税のためではなく、保障・福利厚生のため。

今回の記事では、法人の保険について、節税効果があると言われる理由について紹介しました。
結果的に、法人の保険には節税効果はなく、納税を先送りする対策も難しいと言えます。
法人の保険は本来の意味である、従業員への保障・福利厚生を充実させるために加入するべきでしょう。
節税対策は保険ではなく、その他の方法で実現できます。
保険について検討しているオーナーや経営者の方は、今回の記事を参考に、保険の種類を検討してみてください。
パラダイムシフトは2011年の設立以来、豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。