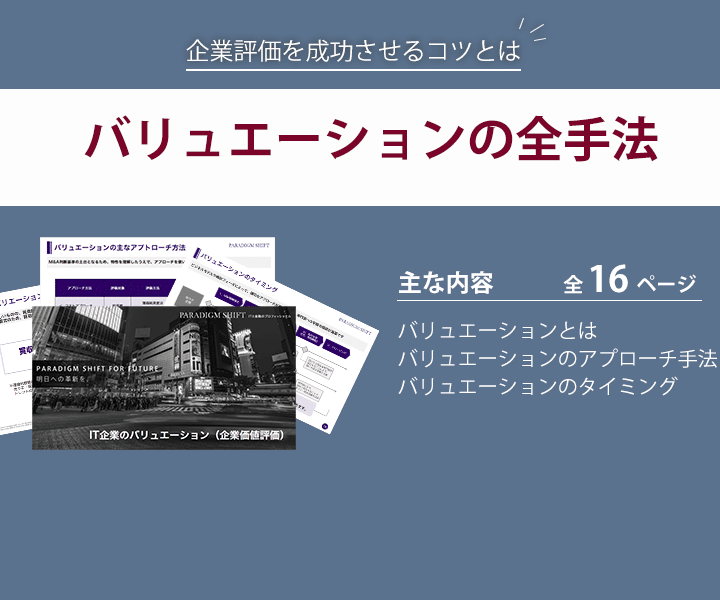M&Aなど企業活動において重要な「のれん」ですが、減損は企業価値に大きな影響を与えます。
のれん減損が発生する原因や企業価値への影響など、M&Aを実施する上で理解しておくべきポイントがたくさんあります。また、IFRSとの違いや実際にあったのれん減損の事例を確認して、より具体的なイメージを把握しておきましょう。
この記事では、のれん減損の基礎知識から発生要因・企業価値への影響を詳しく解説します。
償却方法や会計処理も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 1 のれん減損とは?
- 2 そもそも「のれん」とは
- 3 のれん償却との違い
- 4 のれん減損が発生する要因
- 5 買収価格が高すぎた
- 6 PMIを失敗した
- 7 のれん減損による影響
- 8 企業価値の低下
- 9 株主への配当金が減少
- 10 のれん減損テストとは
- 11 目的と重要性
- 12 テストを実施するプロセス
- 13 テスト結果の解釈と対応策
- 14 のれん減損の発生を抑制するためのコツ
- 15 M&A戦略とPMIの最適化
- 16 のれん減損の兆候を見極める
- 17 継続的なモニタリング体制を構築する
- 18 デューデリジェンスを実施する
- 19 のれんの償却方法
- 20 のれんの償却期間
- 21 定額法が一般的
- 22 のれんの仕訳方法
- 23 のれん減損に関するよくある質問Q&A
- 24 のれん減損を計上すると、税金はどう変わる?
- 25 投資家はどうやってのれん減損の情報を入手できる?
- 26 のれん減損の計上は企業の信頼性を損なう?
- 27 まとめ:のれん減損を避けるために企業価値を正しく見極めよう
のれん減損とは?

のれん減損とは、のれん(将来的な収益価値を持つ無形資産)の帳簿価額を下方修正することです。
貸借対照表に載せられる資産額には上限があり、M&Aで失敗すると想定していた資金を回収できなくなる可能性があります。
また、見込み額を回収できない場合、貸借対照表に資産として計上できません。
貸借対照表に載せられる資産額の上限をオーバーした状態を「減損」と呼び、上限額を切り下げなければなりません。
切り下げた金額は損失になり、のれんが減損した部分を「のれん減損」と呼びます。
のれん減損について詳しく知るためには、下記の基本情報を理解しておく必要があります。
- そもそも「のれん」とは
- のれん償却との違い
のれん減損についての基礎知識を理解した上で、発生する原因や企業価値への影響を確認しましょう。
そもそも「のれん」とは
企業が、別の企業を買収する際に、買収価格が買収対象企業の純資産額(資産から負債を引いた額)を上回った場合の差額が「のれん」です。
のれんは、買収対象企業のブランド力・顧客基盤・技術力など、会計上の資産として計上されない無形資産の価値を表しています。
言い換えれば、買収企業が将来的な収益増加やシナジー効果に期待して支払ったプレミアムがのれんです。
のれんを求める際の計算式は、以下のとおりです。
| のれん=買収価格-被買収企業の純資産額 |
具体例として、A社がB社の純資産額100億円で評価される企業を、150億円で買収した場合、50億円がのれんとして計上されます。
のれんとして計上される50億円は、B社の目に見える資産や負債には反映されない潜在的な価値を表す指標として扱われます。
のれん償却との違い
償却とは、資産の価値が時間とともに減少していくため、資産の使用に伴って価値を適正に配分し、費用として計上する会計処理です。
のれんも企業が保有する資産であり、時間とともに価値が減少していく「償却期間」にわたって減価償却することを「のれん償却」と呼びます。
なお、日本の会計基準ではのれん償却が必要ですが、国際会計基準(IFRS)では償却されません。
日本の会計基準では、のれんを20年以内の期間で償却(費用として計上)する必要があります。
一方、IFRSでは、のれんは減損テストと呼ばれるテストを行い、減損の可能性がある場合にのみ減損損失を計上し償却は行いません。
代わりに、のれんは減損テストを経て、価値が減少した場合にのみ、減損損失として計上されます。
| 項目 | 日本の会計基準 | 国際会計基準(IFRS) |
| 処理方法 | 償却(20年以内) | 減損テストによる減損処理 |
| のれんの価値観 | 時間とともに減衰 | 継続的な評価、減損時は減損処理 |
| 財務諸表への影響 | 毎期費用計上による利益減少 | 減損発生時のみ利益減少 |
のれん減損とのれん償却の違いは、次のとおりです。
| 項目 | のれん償却(旧会計基準) | のれん減損(現行会計基準) |
| 処理方法 | 一定期間にわたって、定額法または定率法で償却する | 減損テストを行い、減損が発生した場合のみ減損損失を計上する |
| 計上時期 | 毎年、計画的に計上する | 減損が認められた時のみ計上する |
| 価値減少の反映 | 時間の経過による価値減少を反映 | 市場価値や将来キャッシュフローの減少による価値減少を反映 |
| 会計上の影響 | 毎年の費用として計上されるため、利益を圧迫する | 減損が発生した年度にのみ計上されるため、利益への影響は不定期 |
のれん償却と減損では、価値減少の反映方法や会計上の影響に大きな違いがあります。
現行の会計基準では、のれんの価値減少は減損テストによって判断され、減損が発生した場合のみ減損損失として計上される点が重要です。
のれん減損が発生する要因

のれん減損は、企業買収後に発生した場合、企業に損益をもたらすため買収前にリスクを把握しておく必要があります。
のれん減損が発生する要因は、主に次のとおりです。
- 買収価格が高すぎた
- PMIを失敗した
それぞれ要因を確認して、のれん減損で損益を出さないよう注意しましょう。
買収価格が高すぎた
M&Aにおいて、買収価格が被買収企業の価値を上回ってしまうと、差額が「のれん」として計上されます。
のれんは、買収企業が被買収企業から期待する将来的な収益力やシナジー効果を反映したものです。
しかし、買収後の業績が予想を下回ったり、シナジー効果が期待通りに発揮されなかったりした場合、のれんの価値が減少し減損処理が必要となる可能性があります。
買収価格が高すぎる要因は、以下のとおりです。
| 要因 | 説明 |
| 市場の過熱感 | M&A市場が活況で、競争が激化すると、買収価格が高騰する傾向があります。 |
| 情報不足による過剰評価 | デューデリジェンスが不十分で、被買収企業の真の価値を正確に把握できていない場合、買収価格が高くなる可能性があります。 |
| シナジー効果の過剰な期待 | 買収によって期待されるシナジー効果を過大に評価し、買収価格に織り込んでしまうと、現実のシナジー効果が期待を下回った場合に減損リスクが高まります。 |
PMIを失敗した
PMIとは、M&A後に買収企業と被買収企業を統合し、シナジー効果を最大限に発揮するためのプロセスです。
PMIが失敗すると、買収によって期待された収益改善やコスト削減が実現せず、のれんの価値が減損する可能性があります。
PMI失敗の要因は、次のとおりです。
| 要因 | 説明 |
| 企業文化の衝突 | 買収企業と被買収企業の企業文化が大きく異なる場合、統合プロセスが困難になり、シナジー効果が阻害されます。 |
| 従業員のモチベーション低下 | 統合プロセスにおいて、従業員の不安や不満が解消されない場合、モチベーションが低下し、業績悪化につながります。 |
| システム統合の遅延・失敗 | システム統合が遅延したり、失敗したりすると、業務効率が悪化し、コスト削減効果が期待通りに得られないです。 |
| 経営陣の不一致 | 買収企業と被買収企業の経営陣が、統合の方向性や戦略について意見が一致しない場合、PMIが失敗する可能性があります。 |
のれん減損は買収価格とPMIの両面から発生するリスクであり、M&A戦略においては要因を綿密に検討し、リスク軽減策を講じる必要があります。
のれん減損による影響

のれん減損による影響は、次のとおりです。
- 企業価値の低下
- 株主への配当金が減少
それぞれの影響を確認して、のれん減損のデメリットを把握しましょう。
企業価値の低下
のれん減損は、企業価値の低下に直結する重大な問題です。
のれんは、買収によって生じる買収価格と被買収会社の純資産の差額を表す無形資産であり、減損したと判断されると企業の資産価値が減少します。
企業の財務諸表に直接影響を与え、投資家や金融機関の評価に悪影響を及ぼす可能性があります。
企業価値は、将来の収益力や成長性などを総合的に評価したものです。
のれん減損は将来の収益予想の低下を意味するため、企業価値の低下につながります。
| のれん減損の影響 | 具体的な影響例 |
| 財務状況の悪化 | 損益計算書上の減損損失の計上、純資産の減少 |
| 信用力低下 | 投資家からの評価低下、資金調達コストの上昇 |
| 株価下落 | 市場での企業価値の低下、株主への損失 |
| M&A戦略の見直し | 今後の買収戦略の修正、投資判断の慎重化 |
株主への配当金が減少
のれん減損は、企業の利益を減少させるため、株主への配当金にも悪影響を及ぼします。
減損損失は、当期の利益を圧迫し、剰余金の減少につながります。
剰余金は、配当金の原資となるため、剰余金が減少すると配当金の削減や最悪の場合、配当金の無配につながります。
これは、株主にとって大きな損失であり、企業への投資意欲の低下を招く可能性があります。
特に、減損額が大きい場合や減損が連続して発生する場合は、株主への影響はより深刻なものです。
配当金の減少は、株価にも悪影響を与える可能性があり、安定した配当金を期待して投資している株主を失望させる要因となり、株価が下落してしまうのです。
のれん減損テストとは

のれん減損テストとは、企業が保有するのれんが適切に評価されているか確認し、必要があれば減損処理を行うためのテストです。
「なぜのれん減損テストを行うのか?」疑問に思う方は、下記のポイントを確認しておきましょう。
- 目的と重要性
- テストを実施するプロセス
- テスト結果の解釈と対応策
それぞれのポイントを押さえて、のれん減損テストを実施する際の参考にしてください。
目的と重要性
のれん減損テストとは、企業が買収などを通じて取得したのれんの価値が減損しているかどうかを評価するためのプロセスです。
企業の財務報告の正確性と透明性を確保するために、IFRSに基づいて行われます。
具体的には、のれんの帳簿価額と回収可能価額を比較し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に減損処理を行います。
回収可能価額とは、のれんが将来にわたって創出すると予想されるキャッシュフローの現在価値です。
のれん減損テストの目的は、のれんの減損を早期に発見し適切な会計処理を行います。減損が認められた場合、企業は減損損失を計上しなければなりません。
のれん減損テストを実施しなければ、企業の利益を減少させるだけでなく、株価にも悪影響を与える可能性があります。
そのため、企業の財務状況を正確に把握し、投資家の信頼を維持するためにのれん減損テストが必要不可欠です。
のれん減損テストの目的と重要性を下記にまとめました。
| 目的 | 重要性 |
| のれんの減損の有無を客観的に判断する | 正確な財務報告、投資家への情報開示の信頼性確保 |
| 減損損失の適切な計上 | 企業の財務状況の正確な把握、将来の経営戦略への反映 |
| 早期発見による経営判断の支援 | 経営資源の最適配分、リスク管理の強化 |
テストを実施するプロセス
のれん減損テストは、一般的に以下のプロセスにしたがって実施されます。
- 減損の兆候を確認する: まず、のれんに減損の兆候がないかを確認します。
減損の兆候としては、買収対象企業の業績悪化、市場環境の変化、技術革新などがあります。 - 回収可能価額の算定: 減損の兆候が認められた場合、または毎年行う必要がある場合、のれんの回収可能価額を算定します。
のれんが将来にわたって創出すると予想されるキャッシュフローの現在価値を算出すれば、回収可能価額が求められます。
回収可能価額の算定には、将来の売上高、コスト、割引率などの予測が必要です。 - 帳簿価額との比較: 算出した回収可能価額とのれんの帳簿価額を比較します。
回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合、減損が発生していると判断されます。 - 減損損失の計上: 減損が発生した場合、差額を減損損失として計上します。
減損損失は、損益計算書に計上され、企業の利益を減少させます。
テストにおいてはのれん単体ではなく、のれんを含む「キャッシュジェネレーティングユニット(CGU)」より大きな単位で実施することが一般的です。
なぜなら、のれんの価値が他の資産とのシナジー効果によって影響を受ける可能性があるからです。
テスト結果の解釈と対応策
減損テストの結果、のれんに減損が認められた場合、企業は減損損失を計上する必要があります。
減損損失は、企業の利益を減少させ株価にも悪影響を与えるリスクがあるため、減損テストの結果を適切に解釈し、適切な対応策を講じましょう。
対応策としては、事業再編・コスト削減・新たな事業への投資など、さまざまな方法がありますが、減損の原因を分析し将来の収益性を向上させるための具体的な対策を講じることが大切です。
また、減損テストの結果は、投資家への情報開示にも用いられるため、透明性のある説明が求められます。
| テスト結果 | 解釈 | 対応策 |
| 減損あり | のれんの価値が減少している | 事業再編、コスト削減、新たな事業への投資など |
| 減損なし | のれんの価値は維持されている | 現状維持、または更なる成長戦略の推進 |
継続的なモニタリングと、必要に応じた柔軟な対応が、のれん減損リスクの軽減につながります。
のれん減損の発生を抑制するためのコツ

のれん減損は、企業にとって大きな損失となるため、発生を抑制するための対策は必要不可欠です。
のれん減損の発生を抑制するために、次のコツを押さえておきましょう。
- M&A戦略とPMIの最適化
- のれん減損の兆候を見極める
- 継続的なモニタリング体制を構築する
- デューデリジェンスを実施する
それぞれのコツを押さえて、効果的な対策を実施してください。
M&A戦略とPMIの最適化
M&A戦略の策定とPMIの最適化は、のれん減損抑制に効果的な対処法です。
買収対象企業の選定から、買収価格の設定、買収後の統合プロセスに至るまで、綿密な計画と実行が求められます。
| M&A戦略のポイント | PMIのポイント |
| シナジー効果の実現可能性を徹底的に検証する | 買収後の組織構造や人事体制を事前に明確化し、迅速な統合を実現する |
| 買収価格の妥当性を慎重に評価する | ITシステムや業務プロセスの統合をスムーズに進める |
| 買収対象企業の財務状況や経営状況を詳細に分析する | 従業員のモチベーション維持とエンゲージメント向上に努める |
| リスク管理を徹底する | 統合後の経営体制を確立し、迅速な意思決定を行う |
特に、シナジー効果の明確な見込みがない買収や、買収後の統合が遅延するケースは、のれん減損のリスクを高めます。
買収前のデューデリジェンスに加え、買収後の継続的なモニタリングと迅速な対応が重要です。
のれん減損の兆候を見極める
のれん減損は突然発生するわけではなく、多くの場合は事前に兆候が現れるため、早期に発見し適切な対応をとることが重要です。
具体的な兆候としては、以下のようなものがあります。
| 兆候 | 説明 |
| 買収対象企業の業績悪化 | 売上高や利益の減少、市場シェアの低下など |
| 競争環境の変化 | 新規参入者の増加、既存競合の強化など |
| 経営陣の交代や人事異動 | キーパーソンを失うことによる影響 |
| 買収後の統合プロセスにおける遅延やトラブル | シナジー効果が期待通りに発揮されない場合 |
兆候が見られた場合は、速やかに減損テストを実施し、必要であれば減損損失を計上するなどの対応を行うべきです。
継続的なモニタリング体制を構築する
のれん減損リスクを抑制するためには、買収後も継続的なモニタリング体制を構築することが重要です。
定期的な業績レビューや、市場動向の分析、競合状況の把握などを通じて、早期にリスクを検知する必要があります。
さらに、内部統制システムの強化や情報共有体制の構築も重要であり、経営判断の迅速化とリスクへの対応を効率的に行うことが可能です。
デューデリジェンスを実施する
M&Aにおけるデューデリジェンスは、のれん減損リスクを抑制するためのもっとも重要なステップです。
財務デューデリジェンスに加え、事業デューデリジェンス、法的デューデリジェンスなどを徹底的に実施すれば、買収対象企業の真の姿を把握し、買収価格の妥当性を検証する必要があります。
デューデリジェンスでは、買収対象企業の業績予想の妥当性、将来の成長性、潜在的なリスクなどを詳細に分析した情報をもとに買収価格を決定します。
適切なデューデリジェンスを行えば、買収価格が高騰し、のれん減損リスクを軽減できます。
のれんの償却方法
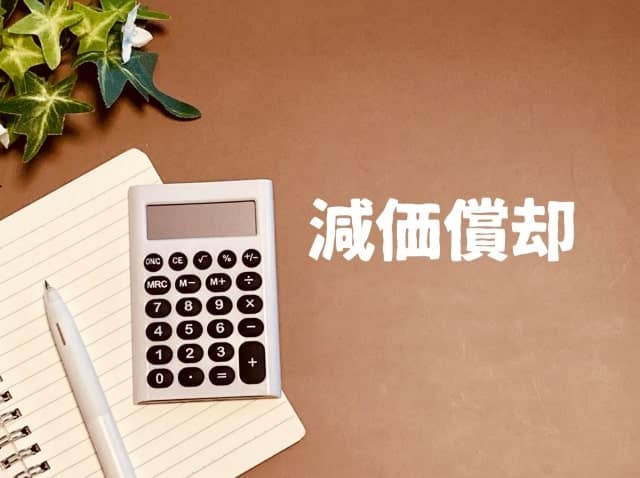
のれん償却方法を理解するためには、次のポイントを押さえておくことが重要です。
- のれんの償却期間
- 定額法が一般的
- のれんの仕訳方法
それぞれのポイントを押さえて、のれん償却の方法を把握しましょう。
のれんの償却期間
日本の会計基準では、のれんは20年以内の上限期間内に、企業が合理的な期間を設定して償却します。
実務上は、5年から10年と期間が広く採用されており、買収した企業の事業の将来性や、のれんに含まれる無形資産の有用期間などを考慮して決定されます。
より長期的な事業価値の向上が見込まれる場合は、償却期間を長く設定するケースもありますが、会計基準にのっとり20年以内であるケースが一般的です。
また、買収に費やした投資金額の回収期間を参考に設定すれば、のれん償却による資金繰り悪化のリスクを抑制する効果も期待できます。
定額法が一般的
日本の会計基準下では、のれんの償却には通常、定額法が用いられます。定額法とは、償却期間を通じて、毎年一定額を償却していく方法です。
定額法の計算式は、以下のとおりです。
| 項目 | 計算式 |
| 年間償却額 | のれん取得額 ÷ 償却期間 |
例えば、のれん取得額が1,000万円で償却期間を10年と設定した場合、年間償却額100万円が毎期末に計上されます。
のれんの仕訳方法
のれんの償却処理は、毎期末に以下の仕訳を行います。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| 減価償却費 | 年間償却額 | 200,000円 |
| のれん | 200,000円 | 年間償却額 |
仕訳により、費用である減価償却費が増加し資産であるのれんが減少する仕組みです。
のれんが時間とともに価値を失っていくことを反映した処理です。
注意すべき点として、のれんは減損リスクもあり、償却とは別にのれんの価値が減少し減損処理が必要となるケースも存在します。
減損処理は、のれんの帳簿価額を回収可能額に減額する処理です。
減損が発生した場合は、減損損失と費用を計上し、のれんの金額を減額します。
のれん減損に関するよくある質問Q&A

のれん減損に関するよくある質問は、次のとおりです。
- のれん減損を計上すると、税金はどう変わる?
- 投資家はどうやってのれん減損の情報を入手できる?
- のれん減損の計上は企業の信頼性を損なう?
それぞれの質問に対する回答を確認して、のれん減損について理解を深めましょう。
のれん減損を計上すると、税金はどう変わる?
のれん減損の計上は、税務上の影響を及ぼします。
具体的には、減損損失は損金として計上できるため、法人税の税額を減少させる効果があります。
ただし、減損損失を計上した年度の課税所得が減少し、法人税負担が軽減されるだけで、過去の税金が還付されるわけではありません。
また、減損損失の計上は、企業の税務申告書に反映されるため、税務調査の対象となる可能性も考慮する必要があります。
税金に関する具体的な影響は、各企業の状況や税制によって異なるため、税理士などの専門家に相談することが重要です。
投資家はどうやってのれん減損の情報を入手できる?
投資家は、主に以下の方法で企業ののれん減損に関する情報を入手できます。
| 情報源 | 入手方法 | メリット | デメリット |
| 有価証券報告書 | 企業が公開する決算報告書 | 公式情報であるため信頼性が高い | 専門的な知識が必要な場合がある |
| 四半期報告書 | 四半期ごとの決算報告書 | 最新の状況を把握できる | 詳細な情報が不足している場合がある |
| 決算短信 | 簡潔な決算概要 | 迅速に情報を入手できる | 詳細な情報は記載されていない |
| IR情報 | 企業のWebサイトやIR資料 | 企業の発表内容を直接確認できる | 情報が偏っている可能性がある |
| アナリストレポート | 証券アナリストによる分析レポート | 専門家の分析に基づいた情報が得られる | 有料である場合が多い |
| ニュース記事 | 経済ニュースサイトや新聞記事 | わかりやすく簡潔な情報が得られる | 正確性に欠ける場合がある |
のれん減損の計上は企業の信頼性を損なう?
のれん減損の計上自体は、必ずしも企業の信頼性を損なうとは限りません。
むしろ、会計基準に則って適切に減損処理を行うことは、企業の透明性を高め、投資家の信頼を維持する上で重要です。
しかし、のれん減損の発生は、M&A戦略や事業運営に問題があった可能性を示唆するため、投資家から懸念される可能性があります。
特に、巨額ののれん減損や繰り返し発生する減損は、企業の経営能力や将来性に対する疑念を招き、株価の下落や信用格付けの低下につながるため要注意です。
のれん減損が発生した際には、原因を明確に説明し再発防止策を講じて、投資家の信頼回復に努めましょう。
透明性のある情報開示と事業戦略の改善が、企業の信頼性を維持する上で重要です。
まとめ:のれん減損を避けるために企業価値を正しく見極めよう

のれん減損は、企業の財務状況に大きな影響を与えるため、M&A戦略の立案から実行、事後の統合プロセス(PMI)に至るまで、綿密な計画と実行が不可欠です。
重要なポイントは、買収対象企業の企業価値を正確に見極めるために、デューデリジェンスを徹底しましょう。
買収価格が高すぎる場合やPMIが失敗した場合には、のれん減損が発生するリスクが高まります。
そのため、買収価格の妥当性やPMIの成功確率を慎重に評価し、リスクを最小限に抑えるための戦略を立てることが重要です。
また、のれん減損の発生を抑制するためには、継続的なモニタリング体制の構築も必要不可欠です。
買収後も、定期的に買収対象企業の業績や市場環境をモニタリングし、のれん減損の兆候を早期に発見する体制を整えましょう。
兆候が見られた場合は、迅速に対応策を講じて、損失を最小限に抑えてください。
本記事で紹介した内容を参考に、M&A戦略の立案から実行、事後の管理まで、それぞれの段階で適切な対策を講じてのれん減損のリスクを軽減しましょう。