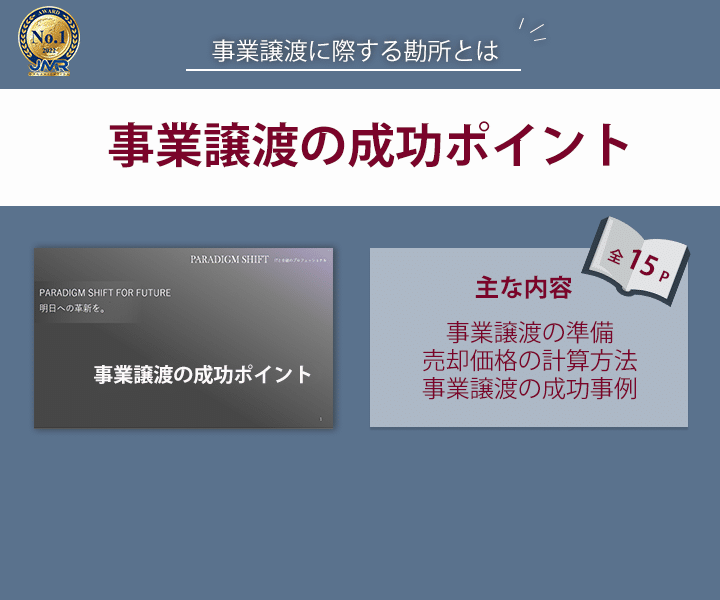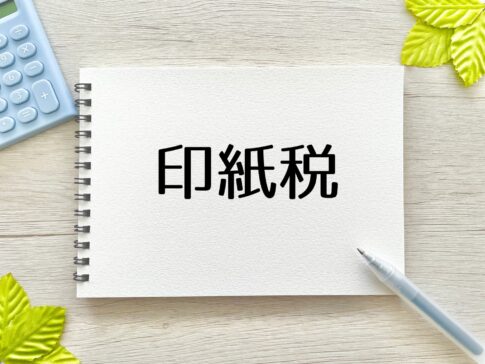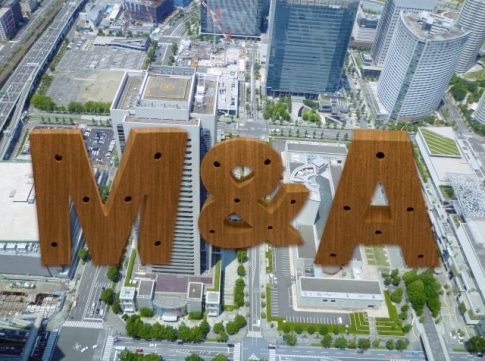事業譲渡は、会社の成長戦略として非常に有効なM&A手法の一つです。
しかし、事業譲渡の際に「何が課税対象になるのか」など消費税に関する判断を迷っていませんか。
問題を曖昧にしたままでは、予期せぬ税負担や手続き漏れのリスクが高く、円滑な手続きができないかもしれません。
本記事では、事業譲渡における消費税の基本や売り手・買い手それぞれの注意点を解説します。
目次
- 1 事業譲渡における消費税とは
- 2 事業譲渡における消費税の計算方法
- 3 事業譲渡で課税される消費税以外の税金
- 4 【売り手側】法人税
- 5 【買い手側】不動産取得税や登録免許税
- 6 事業譲渡時に課税される資産
- 7 有形固定資産(土地を除く)
- 8 無形固定資産
- 9 棚卸資産
- 10 のれん代
- 11 事業譲渡時に非課税される資産
- 12 土地
- 13 有価証券
- 14 債権
- 15 事業譲渡時の消費税に関する注意すべきポイント4つ
- 16 のれん代に追加費用が発生する
- 17 棚卸資産の変動で課税額は影響される
- 18 消費税の増税に注意する
- 19 簡易課税では消費税還付が受けられない
- 20 事業譲渡時の消費税を軽減する方法
- 21 消費税の還付を受ける
- 22 会社分割や合併を検討する
- 23 事業譲渡における消費税の取り扱いに困ったら専門家に相談しよう
事業譲渡における消費税とは

事業譲渡における消費税とは、事業の一部や全部を譲渡する際に発生する税金です。
事業譲渡が消費税の課税対象となるかどうかは、譲渡される資産の内容によって変わります。
消費税が課税されるのは、事業に関連する有形資産や無形資産の譲渡、商品や設備、商標などの移転です。
一方で土地や有価証券、債権など一部の資産は非課税とされます。
譲渡する事業が消費税を課税される取引を含む場合、売り手は消費税を納付しなければなりません。
事業譲渡における消費税は、契約書においても明記しておく必要があり、税務署に提出する書類にも反映が必要です。
事業譲渡における消費税の計算方法

消費税額は、課税対象となる資産の譲渡価額に消費税率を乗じて計算します。
事業譲渡における消費税の計算方法は、譲渡される資産が課税資産か非課税資産かによって決まります。
例えば、売却される資産が次のような金額であると仮定しましょう。
- 建物:6,000万円
- 土地:1億円
- のれん代:2,000万円
- 棚卸資産:2,000万円
- 特許権:1,000万円
- 債権:3,000万円
課税資産に該当するのは建物やのれん代、棚卸資産、特許権で、非課税資産に該当するのは土地と債権です。
次に、課税資産の合計額を計算しましょう。
建物(6,000万円)+のれん代(2,000万円)+棚卸資産(2,000万円)+特許権(1,000万円)=1億1,000万円が課税対象となります。
非課税資産である土地(1億円)と債権(3,000万円)は消費税の計算に含まれません。
消費税率が10%の場合、1億1,000万円に対して10%の消費税が課税されます。
1億1,000万円×10%=1,100万円が事業譲渡における消費税です。
非課税資産は計算に含める必要がない点は注意してください。
事業譲渡で課税される消費税以外の税金

事業譲渡には消費税のほかにも、売却金額や譲渡する資産に応じて複数の税金が発生します。
売り手側と買い手側それぞれに発生する税金を紹介します。
【売り手側】法人税
事業譲渡において、売り手企業が譲渡した事業から得た利益は、法人税の課税対象となります。
法人税は、企業が事業活動を通じて得た利益に対して課される税金です。
譲渡事業の資産から負債を差し引く計算が完了した後、得られた利益に対して法人税が課されます。
【買い手側】不動産取得税や登録免許税
不動産を譲渡資産として含む場合には、買い手側に不動産取得税と登録免許税が課されます。
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される税金です。
2027年3月31日まで、特例により取得した不動産の課税標準額に3%を掛けて算出されます。
登録免許税は、不動産の所有権を移転する際に支払う税金です。
不動産の名義変更に伴う登記申請を行う際に課税され、課税標準額に1.5%を掛けた額が税金として納められます。
事業譲渡時に課税される資産

事業譲渡においては、譲渡される資産の種類に応じて消費税が課されます。
有形固定資産や無形固定資産、棚卸資産、のれん代に関する消費税の取り扱いを紹介します。
有形固定資産(土地を除く)
有形固定資産とは、企業が長期間使用するために保有している物理的な資産を指します。
事業用に使用していた建物や店舗、工場などの構築物、生産設備、事務用機器、車両運搬具などが該当します。
ただし、土地については非課税資産となるため、土地の譲渡には消費税は課税されません。
土地以外の有形固定資産には消費税が課されるため、売却時には注意しましょう。
無形固定資産
無形固定資産とは、物理的な形を持たないが、企業にとって重要な価値を持つ資産のことです。
特許権や商標権、意匠権、著作権、漁業権、ソフトウェアなどが該当します。
形あるものではありませんが、企業の知的財産やブランド価値に関わる重要な資産で、会社の収益向上に貢献する無形資産です。
棚卸資産
棚卸資産は、企業が製品の販売を目的に保有している在庫資産です。
販売を目的とする製品や生産に使用する原材料などが該当し、事業譲渡時に消費税の計算に影響を与えます。
のれん代
のれん代とは、事業の価値が財務諸表に現れない資産、ブランド力や顧客基盤、企業の良好な評判など無形の資産に対して支払われる金額のことです。
「営業権」と呼ばれる場合もあります。
のれん代を正確に算出することは難しいため、「営業キャッシュフロー(営業CF)の3〜5年分」を基に計算されるのが一般的です。
事業譲渡時に非課税される資産

事業譲渡においては、すべての資産が消費税の対象になるわけではなく、一部の資産は非課税です。
非課税資産に関しては、消費税が発生しないため、譲渡時には税務処理が簡素化されます。
土地や有価証券、債権の消費税について解説します。
土地
土地の売却に際しては、消費税が発生しないため、譲渡額に対して消費税を計算する必要はありません。
ただし、土地の上に存する権利の譲渡は課税対象になるので注意しましょう。
有価証券
株式や債券などの有価証券も事業譲渡における非課税資産の一つです。
ただし、有価証券の譲渡が法人税や所得税の対象となる場合があり、税務上の取り扱いが異なる点には注意してください。
債権
債権も事業譲渡における非課税資産に該当します。
債権とは、ある企業が他の企業に対して有する返済請求権を指し、事業譲渡において譲渡される場合には消費税は課税されません。
ただし、債権自体が譲渡されることにより、譲渡益に対して法人税などの別の税金が発生する可能性があります。
事業譲渡時の消費税に関する注意すべきポイント4つ

事業譲渡を行う際、税金の計算において間違えやすい点がいくつかあるため、事前にしっかり理解しておくことが大切です。
事業譲渡時に消費税に関して注意すべき4つのポイントを解説します。
のれん代に追加費用が発生する
未上場の中小企業が事業譲渡を行う際、譲渡価格は「純資産+営業利益3年分」という計算式で求められます。
純資産との差額は「のれん」として扱われ、のれん代による消費税額が増加する場合があることに注意しましょう。
のれんは前述の通り「課税資産」として扱われます。
企業のノウハウやブランド力が強い場合、営業利益が増加してのれん代が膨らみ、消費税額が増加する可能性が高いです。
棚卸資産の変動で課税額は影響される
事業譲渡における消費税の計算には、棚卸資産が関係します。
事業譲渡時に棚卸資産の価格を予測していても、譲渡日に予測とは大きく異なる価格となる可能性は高いです。
棚卸資産が予想以上に高額であれば、消費税もその分多くなってしまいます。
多額の棚卸資産を有する事業を譲渡する場合、棚卸資産にかかる消費税額について事前にきちんと見積もりを取りましょう。
対象企業の棚卸資産に影響を与える季節的な要因や、棚卸資産の量をコントロールできるかどうかなど事前に対策を考えましょう。
消費税の増税に注意する
消費税は定期的に税率が見直されるため、事業譲渡が行われるタイミングで消費税率も影響を受ける点に注意しましょう。
2014年4月以降は8%でしたが、2019年10月からは軽減税率8%と標準税率10%に分かれ、事業譲渡には10%が適用されています。
税法の改正により適用される税率が変動するため、注意が必要です。
簡易課税では消費税還付が受けられない
事業譲渡を行う企業が簡易課税制度を採用している場合、消費税の還付を受けられません。
消費税の課税事業者は、「簡易課税」と「本則課税」を選ぶのが一般的です。
簡易課税は、受け取った消費税に対して事前に定められた仕入れ率を掛け算して消費税を計算する方法で、事務作業を簡単に済ませられるメリットがあります。
本則課税では、受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納付します。
受け取った消費税が支払った消費税より多いと、還付を受けることが可能です。
買い手企業が事業譲渡により不動産を受け取った場合、通常は支払った消費税が受け取った消費税を上回ることが多く、本則課税を選択していれば還付を受けられます。
ただし、買い手企業が簡易課税を選択している場合、還付を受けることはできません。
簡易課税では、みなし仕入れ率を基に計算し、消費税の納税額が発生するためです。
本則課税に切り替えたい場合は、適用を取りやめる課税期間の初日までに、税務署に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
事業譲渡時の消費税を軽減する方法

消費税の軽減には戦略的な対応が必要であり、適切な方法を選択すれば、無駄なコストを避けられます。
事業譲渡における消費税を軽減する方法を紹介します。
消費税の還付を受ける
事業譲渡に伴って消費税が発生した場合、特定の条件を満たすことで消費税の還付を受けられます。
譲渡する資産がすべて消費税の非課税取引となる場合、消費税を計算した結果、還付額が発生する場合などが該当します。
還付申請を行うためには、いくつかの条件があり、手続きには専門的な知識が欠かせません。
手続きの複雑さを考慮すると、専門家に依頼することをおすすめします。
会社分割や合併を検討する
消費税の軽減方法として、会社分割や合併を検討することも一つの選択肢です。
会社分割とは、会社がその事業の全部または一部を新たに設立する会社(新設分割)または既存の会社(吸収分割)に承継させることをいいます。
会社分割の場合、原則として消費税は課税されません。
ただし、会社分割の手法によっては、消費税が課税される場合もあるため注意が必要です。
会社分割や合併は、税金を軽減するためだけではなく、企業の将来の成長戦略にも影響を与える手段となるため慎重に検討しましょう。
事業譲渡における消費税の取り扱いに困ったら専門家に相談しよう

事業譲渡において消費税の取り扱いは、重要かつ複雑な問題です。
譲渡する資産が多岐にわたる場合、消費税の計算方法や納税義務の範囲を正確に把握することが求められます。
しかし、事業譲渡における消費税の取り扱いを完璧に理解し、対応するのは難しいかもしれません。
事業譲渡時の消費税について判断に迷うことがあれば、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
事業譲渡における消費税の適正な計算や納税手続きについてアドバイスを行い、法令に準拠した方法での対応をサポートしてくれます。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。