経営統合により従業員の給料や賞与が下がってしまったり、給料格差が生じてしまったりすることがあります。
給料格差を放置すると、従業員の関係性悪化など、さまざまな問題を引き起こします。この問題が大きくならないために、M&Aの統合プロセスであるPMIの段階でこれらを解消していきます。
今回の記事では、経営統合における社員の給料について、また給料格差について詳しく解説します。
目次
経営統合における社員の給料について

経営統合における社員の給料は、労働条件や評価制度とともに統合される2社のものを参考にして決定しますが、多くの場合、買い手企業の基準に合わせられます。
しかし、買い手企業の基準をそのまま押し付けては、売り手企業の従業員が働きづらくなってしまう可能性があります。そのため、異なる2社の労働条件において統一と調整が必要なのです。
給料の調整は、M&Aで2社が統合されたあとの融合プロセスであるPMIを経て実施します。この場合、経過的な措置として、数年に緩和期間を設けるのが一般的です。
統合する2社の給料テーブルが異なる場合には、
- どちらかの基準に合わせる
- その中間を給料基準として定める
- 基本給や退職などの項目ごとに採用する基準を決める
などの方法があります。
社員への告知の可否
従業員は会社と雇用契約を結び、定められた条件のもと働いています。給料もそのうちの一つなので、従業員の同意なしで変更することはできません。これは統合時も同様です。
したがって、統合によって労働条件や給料が変更される場合には、従業員それぞれへ告知し、変更の同意が必要となります。その際には、書面を作成して、変更部分を丁寧に伝える必要があります。
経営統合後の給料はどうなる?
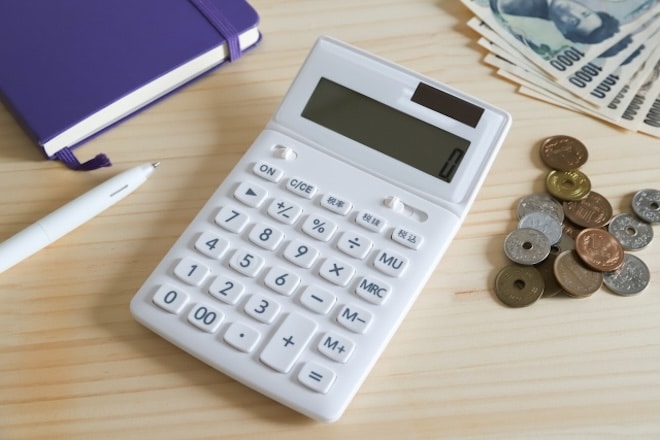
では、統合後の給料は具体的にどうなるのでしょうか。さまざまな立場から見てみましょう。
| 状況 | 買い手企業 | 売り手企業 |
| 買い手企業の給料テーブルが高い | これまでと同じ | 買い手企業の水準へ上がる可能性有り |
| 売り手企業の給料テーブルが高い | これまでと同じ | 買い手企業の水準へ下がる可能性有り |
| 統合により役職や勤務地が変更になる | 給料や手当に影響する | 下位役職になれば給料が下がる可能性有り |
| 買い手企業にあり、売り手企業にない手当てがある | これまでと同じ | 統合後は同じ手当がもらえない可能性有り |
給料が上がるケース
統合先の給料テーブルが高ければ、合併後に給料が上がります。また、合併後に就業時間が伸びたり、負担が大きくなったりする場合などは基本給があがることもあるでしょう。
給料が下がるケース
反対に、統合先の給料テーブルが低かった場合、統合後に給料が下がることもあるでしょう。会社の業績が低迷している場合にも、統合を期に給料が下がることが考えられます。
また、組織編成の変更や役職分担による負担軽減から給料が下がることもあります。しかし、統合直後から下がるのではなく何年かかけて下げていき、基準に合わせるケースが多くなります。
給料が大きく下がってしまう人が出るときには、差額分を前払いしてから給料形態を統一することもあります。
一般的に20代〜30代の給料が下がることは少なく、40代以降の管理職において減給となることが多いと言われています。
給料減額の手続きについて

この章では、実際に減給する場合、どのような手順で手続きが必要になるのか紹介します。
- 給料削減案を作成
- 従業員へ告知
給料削減案を作成
まずは、統合元の給料形態を確認しながら給料削減案を作成します。そして、統合による組織編成で生じると思われる負担軽減や事業規模の変化など減給に相当すると思われる理由を洗い出します。
その際には、その従業員の生活を守ることができるのか、同業他社の給料と大きな相違がないかなどを確認しましょう。
従業員へ告知
給料削減案が確定したら従業員にそれらを周知します。給料の削減は基本的に従業員の合意が必要です。そのため、説明会を実施したり、個人面談を実施したりして丁寧に説明しましょう。
会社の規模によっては、必要があれば専門の委員会を設置したり労働組合いと協議したりするようにします。
無事に従業員の合意が得られたら給料削減を実施する流れになります。
経営統合で生じる給料格差

給料格差は、今回のように、経営統合などで統合した2社の間で給料の格差が生じる現象です。なぜ経営統合で給料格差が生まれてしまうのでしょうか。
給料格差について、詳しく解説します。
給料格差が生じる理由
そもそも、給料格差が生じる理由は、統合後も各従業員がこれまでの労働契約を引き継ぐ点にあります。統合前の基本給がそのまま適用されるため、統合する2社の間で給料テーブルが異なると給料格差が生じることとなります。
前述の通りPMIの統合作業により2社の給料テーブルを調整していきますが、企業文化や業務体制の違いにより給料格差がなくならないこともあります。
給料格差を放置するリスク
このような給料格差を放置してしまうと様々なリスクを引き起こします。代表的な例としては以下の通りです。
- 従業員のモチベーション低下
- 従業員の関係悪化
- 従業員の訴訟
給料が低い従業員は、同じ条件下で働くことに不公平さを感じて、働く意欲が低下してしまうかもしれません。同じ部署やポジションで働く従業員の給料格差は従業員同士の関係性やチームワークを悪化させます。
さらに、給料格差を放置し続けると不公平感が高まり、最悪の場合は訴訟に至ってしまうことも考えられます。
経営統合後に給料格差を解消する方法

最後に統合後の給料格差を解消するための方法について考えてみましょう。考えられる方法は以下の5つです。
- 存続会社の給料水準に合わせる
- 両方の給料水準に合わせる
- 賞与や手当で相殺
- 受け入れ会社の入社前に相殺
買い手は会社の給料水準に合わせる
統合後も存続する買い手企業の給料テーブルに合わせる方法です。
この場合、買い手企業の従業員の給料はこのままですが、売り手企業の従業員は給料が上がる可能性が高くなります。
売り手企業は統合後に消滅するため、売り手企業の給料テーブルに合わせることはほとんどありません。
両方の給料水準に合わせる
統合する2つの会社の給料テーブルの間、もしくは、基本給やインセンティブなど、項目ごとにどちらかの水準に合わせていく方法です。
この方法は、買い手企業の給料テーブルが売り手企業の給料テーブルよりも低い場合に採用されやすい方法といえるでしょう。
賞与や手当で相殺
基本給を減らさなければならない場合、減額分を賞与や手当て相殺する方法もあります。この方法は代替措置という位置づけになるので、従業員の個別の同意が必要です。
受け入れ会社に入社前に相殺
前述でも紹介した通り、買い手企業の従業員の給料が下がってしまう場合に使われる方法です。
具体的には、統合前に差額分を支払ったり、数年間をかけて相殺していく方法があります。売り手企業の給料テーブルが買い手企業の給料テーブルよりも低い場合に使われる手法です。
給料の増減は統合前に通知することが大切
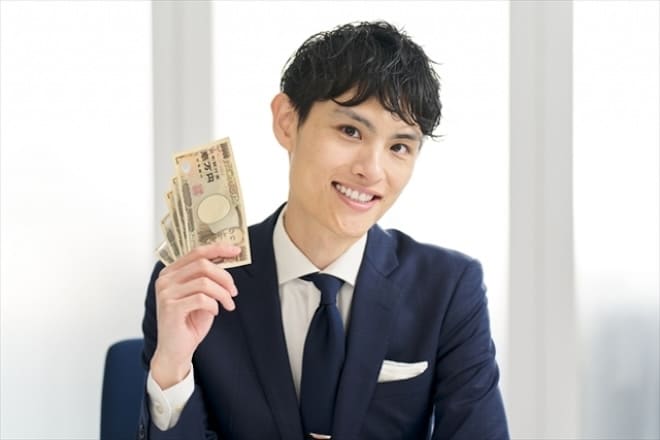
今回の記事では、経営統合による従業員の給料について解説しました。
統合する2社の給料テーブルが異なる場合、その2社の従業員の間で給料格差が生じる恐れがあります。給料格差を放置すると非常に危険で、最悪の場合訴訟に至る恐れもあります。
給料格差は2社の給料テーブルの調整や統合前の相殺で最小限に抑えられますが、結果的に従業員の給料が下がってしまう可能性もあります。やむを得ず言及する場合には個別で同意を取る必要があります。
パラダイムシフトは2011年の設立以来、豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。M&Aに精通している仲介会社を利用すると、安心して行うことが出来ますので、是非ご検討ください。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。






























