「M&Aの担当になったが、技術デューデリジェンスとは一体何だろうか」「財務や法務のDDは経験があるが、IT企業の評価はどこから手をつければ良いのかわからない」といったお悩みを持っている人は多いです。
デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代において、企業の価値は技術力と密接に結びついています。
特にIT企業やスタートアップを対象としたM&Aや投資では、その技術的な価値とリスクを正確に見極める「技術デューデリジェンス」が、取引の成否を分ける極めて重要なプロセスとなっています。
しかし、技術デューデリジェンスの具体的な内容や進め方については、まだ広く知られていないのが現状です。
本記事では、M&Aや投資の担当者で初めて技術デューデリジェンスに携わる方に向けて、基本からわかりやすく解説します。
目次
- 1 技術デューデリジェンスの基本
- 2 技術デューデリジェンス(TDD)とは
- 3 技術デューデリジェンスが重要視される理由
- 4 ITデューデリジェンスとの違い
- 5 技術デューデリジェンスの5つの目的
- 6 ①技術的な強み・弱みの正確な評価
- 7 ②知的財産(IP)の価値とリスクの査定
- 8 ③隠れた技術的リスク(技術的負債)の特定
- 9 ④M&A後のシナジー効果の検証
- 10 ⑤投資・買収価格の妥当性判断
- 11 技術デューデリジェンスの7つの主要評価項目
- 12 ①技術スタック
- 13 ②アーキテクチャ
- 14 ③コード品質
- 15 ④インフラ
- 16 ⑤セキュリティ
- 17 ⑥知的財産
- 18 ⑦開発プロセスと組織文化
- 19 技術デューデリジェンスの進め方
- 20 ステップ1:計画策定
- 21 ステップ2:データ収集
- 22 ステップ3:分析・評価
- 23 ステップ4:リスク評価
- 24 ステップ5:報告書作成
- 25 技術デューデリジェンスの費用相場と期間の目安
- 26 まとめ:技術デューデリジェンスはM&A・投資の成否を分ける羅針盤
技術デューデリジェンスの基本
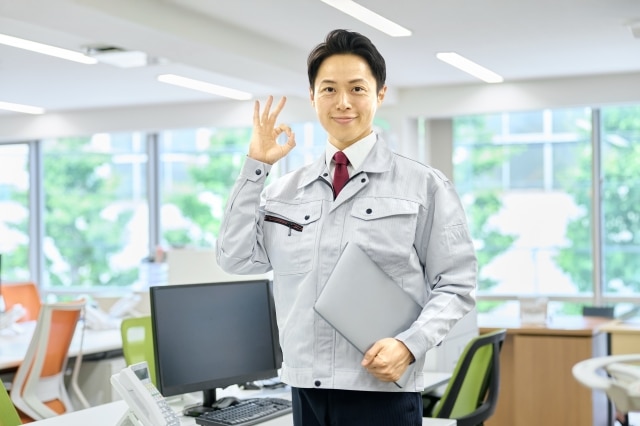
本章では、技術デューデリジェンスの定義や重要性、混同されがちな「ITデューデリジェンス」との違いについて解説します。
技術デューデリジェンス(TDD)とは
技術デューデリジェンスとは、M&Aや投資といった取引の対象となる企業の技術に関する価値やリスクを詳細に調査し、評価するプロセスです。英語では「Technical Due Diligence」と表記され、実務の現場では頭文字をとって「TDD」と呼ばれるのが一般的です。
技術デューデリジェンスでは、対象企業が保有するソフトウェアのソースコード、製品の設計、知的財産権といった技術資産を多角的に分析します。そして、技術が持つ競争力や将来性、反対に隠れた問題点や脆弱性などを洗い出します。
技術デューデリジェンスが重要視される理由
現代のビジネス環境において、技術デューデリジェンスの重要性はますます高まっています。背景には、DXの進展により、多くの企業で事業の根幹をITシステムやソフトウェアが支えるようになったことがあります。
技術は単なる業務効率化のツールではなく、製品やサービスの競争力を生み出す源泉そのものです。そのため、M&Aの意思決定において対象企業の技術力を正しく評価するプロセスは、事業価値を正確に見極めるうえで不可欠な要素です。
ITデューデリジェンスとの違い
技術デューデリジェンスとよく混同される言葉に「ITデューデリジェンス」があります。両者は対象領域が異なり、違いを理解しておくことが重要です。
技術デューデリジェンスは、主に「事業や製品の競争力の源泉となる技術」に焦点を当てます。一方、ITデューデリジェンスは、「事業運営を支える社内のIT環境全般」を評価の対象とします。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 技術デューデリジェンス(TDD) | ITデューデリジェンス(ITDD) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 製品・サービスの技術的な競争力、将来性、リスクの評価 | 事業運営基盤としてのITインフラの安定性、効率性、セキュリティの評価 |
| 評価対象の例 | – ソフトウェアのソースコード – プロダクトのアーキテクチャ – AIのアルゴリズム – 特許や著作権などの知的財産 – 開発チームの技術力や開発プロセス | – 社内ネットワーク、サーバー – 業務システム(会計、人事など) – 情報セキュリティ体制 – IT資産管理、ライセンス – IT部門の組織体制や運用プロセス |
| 評価の焦点 | 「攻めのIT」:事業成長や収益に直結する技術資産 | 「守りのIT」:事業継続を支えるIT基盤 |
技術デューデリジェンスの5つの目的

技術デューデリジェンスには、M&Aや投資の意思決定を成功に導くための明確な5つの目的が存在します。
①技術的な強み・弱みの正確な評価
第一の目的は、対象企業の技術が持つ本質的な強みと弱みの客観的な評価です。例えば、使用されている技術(技術スタック)は先進的か、システムの設計(アーキテクチャ)は将来の事業拡大に耐えうるか、といった点を詳細に分析します。
結果として技術的な優位性が一過性のものではなく、持続可能な競争力に繋がるのかを見極められます。
②知的財産(IP)の価値とリスクの査定
ソフトウェアの著作権やビジネスモデル特許など、目には見えない技術資産の価値の正しい評価も重要な目的の一つです。同時に、対象企業の技術が他社の特許を侵害していないか、といった権利関係のリスクも徹底的に調査します。
結果的に、知的財産(Intellectual Property: IP)の観点から事業の安定性や将来性を判断します。
③隠れた技術的リスク(技術的負債)の特定
買収した後に事業の成長を妨げる可能性のある、隠れたリスクを事前に特定します。
代表例が「技術的負債」です。短期的な開発スピードを優先した結果、将来的な改修や保守が困難になるような、いわば「技術の借金」です。他にも、セキュリティの脆弱性やシステムの老朽化といったリスクも洗い出します。
④M&A後のシナジー効果の検証
M&Aの大きな目的の一つに、両社の強みを掛け合わせることで生まれる「シナジー効果」があります。
技術デューデリジェンスでは、買収側の技術と対象企業の技術を組み合わせることで、本当に新たな製品開発や開発効率の向上といったシナジーが期待できるのかを技術的な観点から冷静に検証します。机上の空論で終わらせないための現実的な評価が不可欠です。
⑤投資・買収価格の妥当性判断
最終的に、前述した1から4の評価結果は、投資や買収の価格(バリュエーション)が妥当であるかを判断するための客観的な根拠として用いられます。例えば、大きな技術的負債が見つかれば、改修コストを見積もり、買収価格の減額交渉に繋がる可能性があります。
技術的な価値とリスクを金額に反映させることが、適正な取引の実現に不可欠です。
技術デューデリジェンスの7つの主要評価項目

本章では、特に重要とされる7つの主要な評価項目について解説します。以下で、各項目についてもう少し詳しく見ていきましょう。
①技術スタック
技術スタックとは、特定のソフトウェアやサービスを構築・運用するために使用されている技術の組み合わせを指します。プログラミング言語(Java, Pythonなど)、フレームワーク(Ruby on Rails, Reactなど)、データベース(MySQL, PostgreSQLなど)が含まれます。
採用されている技術がモダンで将来性があるか、特定のベンダーに依存しすぎていないか(ベンダーロックイン)、などを評価するのが一般的です。
②アーキテクチャ
アーキテクチャは、システム全体の設計図や骨格です。将来のユーザー数増加に対応できる拡張性(スケーラビリティ)があるか、機能追加や変更が容易な構造になっているか、などを評価します。
例えば、一つの巨大なシステムとして作られている(モノリシック)のか、小さなサービスの集合体として作られている(マイクロサービス)のかは、将来の保守性や開発スピードに大きく影響します。
③コード品質
ソフトウェアの本体であるソースコードの品質を評価します。コードが整理されていて読みやすいか、他の開発者が修正しやすいか(保守性)、バグを未然に防ぐためのテストが十分に行われているか(テストカバレッジ)などを、専門的なツールやレビューを通じて調査するのが一般的です。
品質の低いコードは、将来の大きな「技術的負債」とされます。
④インフラ
システムが稼働する土台となるインフラストラクチャーを評価します。自社でサーバーを保有するオンプレミス環境か、AWSやGoogle Cloudなどのクラウドサービスを利用しているか、といった構成を確認します。
また、災害時にもサービスを継続するための計画(ディザスタリカバリ計画)や、安定稼働を支える監視体制なども重要な評価ポイントです。
⑤セキュリティ
企業の信用問題に直結するセキュリティ体制を評価します。外部からのサイバー攻撃に対する防御策は十分か、顧客データなどの機密情報は適切に管理されているか、といった点を診断します。
専門家による脆弱性診断やペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施し、潜在的なセキュリティホールを洗い出すケースも多いです。
⑥知的財産
特許や商標、ソフトウェアのソースコードそのものも著作権で保護される重要な知的財産です。こうした権利が適切に管理されているか、他社の権利を侵害していないか、オープンソースソフトウェアのライセンス規約を遵守しているかなどを精査します。
知的財産に関する問題は、後に大きな訴訟リスクに発展する可能性があります。
⑦開発プロセスと組織文化
優れた技術は、優れた開発チームとプロセスから生まれます。アジャイル開発のようなモダンな手法を取り入れているか、品質を担保する仕組みは整っているか、といった開発プロセスを評価します。
さらに、エンジニアチームのスキルレベルや、M&A後に自社の文化と融合できるかといった組織文化の側面も、円滑な統合(PMI)を見据えるうえで重要な評価対象です。
技術デューデリジェンスの進め方

技術デューデリジェンスがどういった流れで進められるのか、具体的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。以下で、各ステップをもう少し詳しく見ていきましょう。
ステップ1:計画策定
M&Aの目的や対象企業の特性に応じて、調査の範囲(スコープ)と評価の重点項目を決定します。例えば、AI技術がコアとなる企業であれば、アルゴリズムの評価に重点を置く、といった具合です。
本ステップで、スケジュール、調査チームの体制、予算などを固め、対象企業との間で秘密保持契約(NDA)を締結します。
ステップ2:データ収集
計画に基づき、対象企業から評価に必要な情報を収集します。仮想データルーム(VDR)とよばれるセキュアなオンラインスペースを通じて、ソースコード、設計書、技術関連の契約書、エンジニアのリストなどの資料を提供してもらうのが一般的です。
また、資料だけではわからない定性的な情報を得るために、対象企業のCTO(最高技術責任者)や主要なエンジニアへのインタビューも実施します。
ステップ3:分析・評価
収集したデータや情報を基に、専門家が詳細な分析を行います。専用のツールを用いてソースコードの品質や脆弱性を自動解析したり、システムの設計図をレビューして構造的な問題がないかを評価したりするのが一般的です。
本フェーズの分析が技術デューデリジェンスの核となる部分であり、高度な専門知識が要求されます。
ステップ4:リスク評価
分析によって明らかになった問題点を「リスク」として整理し、深刻度を評価します。「セキュリティの脆弱性」というリスクが発見された場合、それが実際に悪用される可能性や、情報漏洩などが起きた際の事業への影響度を評価するのが一般的です。
さらに、リスクを解消するために必要な対策と概算コストも検討します。
ステップ5:報告書作成
最終的に、すべての調査・分析・評価の結果を一つの報告書にまとめます。
報告書には、対象企業の技術的な強みと弱み、特定されたリスクとその深刻度、そM&A実行の可否や条件に関する提言などを盛り込むのが一般的です。経営陣の最終的な意思決定における重要な判断材料として用いられます。
技術デューデリジェンスの費用相場と期間の目安

技術デューデリジェンスを検討するうえで、現実的な課題となるのが「費用」と「期間」です。案件の規模や複雑さによって大きく変動するため、一概には言えませんが、一般的な目安を知っておくことは重要です。
費用は調査の範囲や深さ、依頼する専門家の種類によって異なりますが、一般的には数百万円から数千万円程度が相場とされています。特にスタートアップや中小企業向けの比較的小規模な案件でも、最低で200〜300万円程度からとなる場合が多いです。
期間については、数週間から2〜3カ月程度を要するのが一般的です。案件の特性に依存し、迅速な意思決定が求められる場合は短縮される一方、大規模で複雑なシステムの評価にはさらに長い時間が必要となる場合もあります。
| 案件の規模 | 費用(目安) | 期間(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 小規模 (スタートアップなど) | 200万円〜800万円 | 2週間〜1カ月 | – 特定のプロダクトや技術に焦点を絞った調査 – 比較的シンプルなシステム構成 |
| 中規模 | 800万円〜2,000万円 | 1カ月〜2カ月 | – 複数のプロダクトや事業部門が対象 – 組織やプロセスも評価範囲に含まれる |
| 大規模 | 2,000万円〜 | 2カ月〜 | – グローバル展開している企業や複雑なシステム群が対象 – 知的財産や法務面での詳細な調査が必要 |
まとめ:技術デューデリジェンスはM&A・投資の成否を分ける羅針盤

技術デューデリジェンス(TDD)は、対象企業の技術的な価値とリスクを精査するプロセスです。技術力の評価、リスクの特定、シナジーの検証などを通じて、M&Aや投資の意思決定を支援する目的で実施されます。
評価項目は、技術スタックやアーキテクチャから、開発プロセス、組織文化まで多岐にわたります。計画策定から報告書作成まで、体系化されたステップに沿って行われるのが一般的です。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。






























