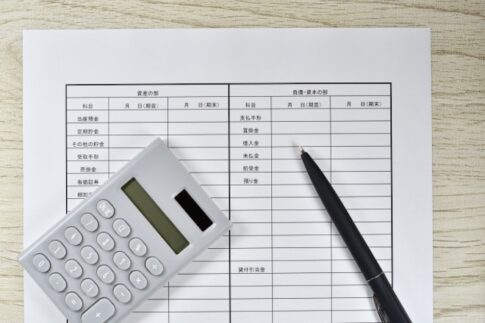ベンチャー企業の創業者は事前に出口戦略を検討しておく必要があります。
日本では、出口戦略としてIPOが主流でしたが、東証の上場基準の見直しによって、従来のIPO偏重からM&Aにシフトするのではないかという見方があります。
海外では、ベンチャー企業の出口戦略として主流となっているM&Aですが、IPOとの違いはなんでしょうか?
ベンチャー企業の視点でM&Aのメリットや「売れる企業」の特徴を解説します。
目次
- 1 イグジット
- 2 ベンチャー企業の出口戦略としてのM&A
- 3 ベンチャー企業の出口戦略としてのM&AとIPOの違い
- 4 海外ではM&Aによる出口戦略が主流
- 5 ベンチャー企業をM&Aで売却するメリット
- 6 創業者利益の獲得
- 7 事業の成長速度の加速
- 8 IPOより迅速な資金調達ができる
- 9 円滑な事業承継
- 10 ベンチャー企業をM&Aで買収するメリット
- 11 新しい事業領域の開拓
- 12 技術やノウハウの獲得
- 13 節税対策
- 14 M&A市場で人気のあるベンチャーの特徴
- 15 将来性のある業界に属している
- 16 最先端技術を持っている
- 17 業績が好調である
- 18 資金調達からEXITまでの流れ
- 19 出資者を募る
- 20 審査を受ける
- 21 資金を調達する
- 22 資金調達先から支援を受ける
- 23 イグジットする
- 24 M&Aはベンチャー企業の出口戦略として最適
イグジット

イグジットとは、投資家が出資した資金を回収し、利益を確定させるための出口戦略を指します。
イグジットが特に重視されるのは、ベンチャー企業やスタートアップが外部の投資家から資金を受けた場合です。
投資家は、企業の成長を見越して出資し、将来的に大きなリターンを得ることを目的としています。
そのため、資金提供を受けた企業は、最終的にM&A(企業売却)やIPO(株式上場)などを通じて投資家へ利益を還元する必要があります。
これは投資家との関係の「出口」にあたるため、イグジットは出口戦略と呼ばれます。
イグジットには成功への強いプレッシャーが伴います。
投資家は資金を回収するために経営支援を行い、事業の成功可能性を高めようとしますが、経営者はその期待に応える成果を出す責任を負います。
また、予定した期間内に成果が出ない場合や事業の見通しが立たないと判断された場合、投資家が株式を売却するなど、資金回収を優先するケースもあります。
イグジットは、企業にとって成長と成果を問われる重要な局面なのです。
ベンチャー企業の出口戦略としてのM&A

ベンチャー企業は、創業時に出口戦略を検討しておく必要があります。
出口戦略は、「EXIT戦略」とも呼ばれ、創業した会社の最終的な利益を確定させ、現金化する戦略です。
創業時に決めておくことで、投資家やベンチャーキャピタルを納得させ、資金調達が円滑に進みます。
出口戦略には大きく分けて「M&A」と「IPO」があります。
M&Aは、”Mergers(合併) and Acquisitions(買収)”の略称です。
一方でIPOは、”Initial(最初の)Public(公開の)Offering(売り物)”の略称で、新規に株式を発行し、証券取引所に上場することを指します。
ベンチャー企業の出口戦略としてのM&AとIPOの違い

ベンチャー企業が出口戦略を検討する時に代表的なのがM&AとIPOですが、両者は様々な点で異なります。
ベンチャー企業が上場する先はグロース市場ですが、上場には「株主数」「時価総額」「株式数」などについて、厳しい審査基準を満たす必要があります。
一方でM&Aは、買い手企業と合意できれば実施可能です。
IPOのように絶対的な基準があるわけではないので、柔軟な対応が可能です。
また、IPOでは不特定多数の投資家から資金を募ることになりますが、M&Aでは、特定の第三者に株式を売却します。
そして、単に株式の売却にとどまらず、会社の経営権そのものを譲渡することになるのです。
このように経営権の移譲が含まれている点や実施の難易度などが大きく異なります。
海外ではM&Aによる出口戦略が主流
日本では、2022年4月廃止以前の東証マザーズの上場基準が低かったことでIPOに出口戦略が偏る傾向にありました。
しかし、米国を筆頭に海外では、M&Aによる出口戦略が主流となっているようです。
一説には、米国では出口戦略としてのM&AはIPOの約10倍から15倍に上るようです。
IPOの場合、新規発行株式の目安は時価総額の10%から20%程度であり、資金調達額に限りがあります。
また、上場後はベンチャーキャピタルからの出資も期待できないため、事業で利益を出すしかありません。
反対にM&Aでは、大きな資金調達の可能性があり、実施後も増資が可能なので、海外ではM&Aが選択されています。
ベンチャー企業をM&Aで売却するメリット

米国をはじめとして海外において、ベンチャー企業がM&Aによる出口戦略を検討する背景にはM&Aに大きなメリットがあるからです。
グロース市場の誕生と審査基準の厳格化によって、日本でもM&Aが盛んになるでしょう。
ここからは、ベンチャー企業をM&Aで売却するメリットを解説します。
創業者利益の獲得
M&Aによって自社株を売却すると、株主は売却益を獲得できます。
ベンチャー企業では、創業者が株主ですので、創業者はM&Aによって多額の利益の確保が可能です。
得た資金は、借入金の返済分を差し引いて、創業者の生活資金に充当できます。
資金を使って、新しく事業を始めてもいいでしょう。
株式の売却価額は買い手企業との話し合いで決定されるので、企業価値が高く評価されれば、莫大な資金を得られます。
ちなみにM&Aと比較されるIPOでは、新規発行株式の目安は時価総額の10%から20%程度であり、市場の反応次第では、獲得できる資金が小さくなります。
事業の成長速度の加速
M&Aによって大手企業や優良企業に自社の事業を譲渡することで、事業が加速度的に発展することになります。
買い手となる企業は大きな資金力があり、広範な取引ネットワークを持っています。
大手のインフラや資金力などを活用することで、自社のさらなる発展が見込めるでしょう。
また、仕入れ先や販売先の統合を行うことで、売上の拡大や経費の削減といった効果も得られます。
出口戦略の後には、経営者ではなくなりますが、譲渡した先で自分の創業した会社が発展していくことほど創業者として嬉しいことはないでしょう。
IPOより迅速な資金調達ができる
IPOとM&Aの差が顕著に現れるのが実施に至るまでの期間です。
ベンチャー企業が上場するグロース市場では、「株主数」「株式数」「時価総額」といった基準をクリアする必要があります。
また、監査法人や主幹事証券会社の選定、事業計画・資本政策の策定といった準備に時間がかかります。
すべての準備を整えるために最低でも3年程度の期間が必要です。
一方で、M&Aでは、買い手企業との交渉次第で準備の負担を軽減すれば、3ヶ月程度で実施が可能です。
また、IPOでは、短期間で成長が期待できない事業は市場で忌避される傾向にありますが、M&Aでは長期的なポテンシャルを期待されて、買い手が見つかる場合があります。
円滑な事業承継
経済産業省によれば、2025年までに、引退年齢を超える中小企業の経営者は約245万人です。
そのうち半分の127万社で後継者が決まっておらず、迅速な事業承継が急務となっています。
ベンチャー企業を創業後に経営者が高齢化している場合、親族や従業員に事業を承継してくれる人がいるのが理想ですが、後継者が見つからないこともあります。
廃業には費用がかかるので、簡単なことではありません。
また、廃業すれば、従業員の雇用は失われ、取引先は販売先や仕入れ先を失うことになります。
出口戦略としてM&Aを活用することで、同時に事業承継の問題も解決することができます。
ベンチャー企業をM&Aで買収するメリット

ベンチャー企業のM&Aは、ベンチャー企業側から見た出口戦略の文脈で議論されることが多いですが、買い手企業にとってもメリットがあります。
海外、特に米国では誰もが知る大手企業もベンチャー企業の買収に積極的です。
買い手企業が、ベンチャー企業をM&Aで買収するメリットはなんでしょうか?
新しい事業領域の開拓
新しい事業を始めたい時に一からスタートすると資材や従業員の手配、必要な技術の獲得に途方も無い時間とお金がかかります。
それでも成功するとは限らず、一説では、新規事業の成功率は10%程度と言われているのです。
しかし、M&Aは、既に事業展開に成功している企業を買収するため、計画から事業を軌道に乗せるまでの時間を大幅に短縮することができます。
国内外問わず、IT企業がM&Aによって、異業種へ参入し、独自の経済圏を構築している例も多数あります。
ベンチャー企業は、創業まもなく売却価額が高価になりにくいので、M&Aによってお手頃な価格で優れた企業の獲得が可能です。
技術やノウハウの獲得
ベンチャー企業を含めて、規模の小さい企業の中には誰でも真似できない独自の優れた技術を持つ企業が多数あります。
M&Aによって、これらの企業を買収すると、雇用されている従業員やそれに付随するノウハウ・技術、そして特許などをまとめて承継することができます。
通常、新しい技術の開発・獲得には莫大な時間とお金がかかりますが、それであっても成功するとは限りません。
優良なベンチャー企業を買収すれば、時間とお金を短縮しつつ、優れた技術を取り込むことができます。
節税対策
法人税の高い国に本社を持つ外資系企業が日本のベンチャー企業を買収することで、租税地が変換され、節税ができる場合があります。
タックスヘイブンが話題になり、規制が強められていますが、今でも実施される合法的な節税対策です。
また、M&Aが思いがけず節税対策になることもあります。
買収後に売り手の繰越欠損金が明らかになると、欠損金は7年間繰越しができるので、黒字と相殺し、法人税の課税対象額を引き下げることができるのです。
M&A市場で人気のあるベンチャーの特徴

ベンチャー企業の出口戦略としてM&Aは有力な選択肢となります。
しかし、ベンチャー企業であれば必ずM&Aによって売却できるわけではありません。
買い手から欲しがられる人気のあるベンチャー企業には特徴があります。
将来性のある業界に属している
異業種の企業が新規参入する業界は将来性のある業界です。
したがって、将来性のある業界に属していると業界内シェアを獲得したい同業他社や新しく参入したい異業種の企業が積極的にM&Aを行うので、売却しやすくなります。
例えば、IT業界は成長産業の筆頭ですが、人材不足が深刻なため、人材獲得のためのM&Aも実施されており、日本M&Aセンターによれば、コロナ禍にもかかわらず2021年にM&A件数が過去最多を記録しているのです。
また、AI関連産業や医療、介護、再生エネルギー関連の業界も長期的に成長が見込まれています。
これらの業界では、M&Aが盛んに行われています。
最先端技術を持っている
他社にはない独自の技術を持っていれば、将来性に期待が持てるため、売れやすくなります。
企業規模が小さくても、誰もが真似できない希少な技術やノウハウを持った企業がたくさんあります。
M&Aの目的が技術・ノウハウの獲得であることも珍しくありませんので、最先端技術の有無は重要な要素です。
実際にニッチな分野で高いシェアを誇る製造業のベンチャー企業などが高い評価を受けています。
業績が好調である
最近の業績が好調な企業は今後の成長性も期待されますので、売れやすくなります。
業績の目安として以下が挙げられます。
- 過去5年間に売上高が増加している
- 利益率(粗利率や最終利益率)が高い
- 資産超過
- 借入金が適正な水準
- 自己資本比率が高い
売上や利益があればよいわけではなく、安定性も重要です。
一時的な利益ではなく、継続して安定した利益が出ていることが必要になります。
自己資本や借入金の水準を見ることで、過去の売上や利益の推移をある程度予想できます。
資金調達からEXITまでの流れ

ここでは、ベンチャー企業が資金を調達してからイグジットに至るまでの基本的なプロセスを整理してみましょう。
一般的に、ベンチャー企業がベンチャーキャピタルなどの投資家から出資を受け、イグジットに到達するまでには次のような5つの段階を踏みます。
- 出資者を募る
- 審査を受ける
- 資金を調達する
- 資金調達先から支援を受ける
- イグジットする
この一連の流れをしっかり理解しておくことで、戦略的な資金調達と成長計画の設計が可能になります。以下で各ステップを詳しく見ていきましょう。
出資者を募る
まず、ベンチャー企業がイグジットを見据えるうえで最初に行うのが、投資家へのアプローチです。
多くの企業は、ベンチャーキャピタルが参加するピッチイベントやビジネスマッチングイベントに参加し、出資のきっかけをつくります。
近年ではオンライン上で投資家と企業をつなぐマッチングプラットフォームも普及しており、登録しておくだけで投資家側から連絡を受けられる可能性もあります。
こうした資金調達活動を理解するには、まずベンチャー企業が利用できる資金調達手段を押さえることが重要です。
創業間もない企業は信用力が十分でないため、銀行融資を受けるのは容易ではありません。そのため、主な選択肢となるのがベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの「出資」です。
このほかにも、融資制度を活用する方法として 日本政策金融公庫 の新創業融資を利用するケースや、国・自治体による補助金・助成金、クラウドファンディングなどの手段もあります。
どの方法を選ぶかは、企業の成長段階や必要な資金規模によって最適解が異なります。
資金調達を検討する際は、経営コンサルタントや 中小企業診断協会所属の専門家など、外部のプロフェッショナルに相談するのも有効な手段です。
審査を受ける
資金調達先へのアプローチが完了すると、次のステップは投資の可否を判断するための審査です。
この審査には数か月かかることが多く、通常は3か月前後を目安とします。
期間中、経営者と投資家との間で複数回の面談やヒアリングが行われ、事業内容やビジョン、成長戦略などが細かく確認されます。
審査では、ビジネスモデルの収益性や競争優位性、経営者のリーダーシップや判断力といった定性的な部分も重視されます。
そのため、事業計画を的確に伝えるプレゼンテーション能力が出資可否を左右する大きな要素となります。
資金を調達する
審査を経て投資先として適格と判断されれば、投資契約の締結に進み、実際の出資が行われます。
契約書には、資金の使途や経営目標、達成すべきマイルストーンなどが明記され、双方の合意のもとで資金調達が実行されます。
出資後は、資金が計画通り活用されているか、事業が成長戦略に沿って進んでいるかについて、定期的なモニタリングが行われます。
これにより、投資家と企業双方が目標達成に向けた連携を強化していくのです。
資金調達先から支援を受ける
出資が完了すると、投資家は単なる資金提供者としてではなく、経営のパートナーとして企業をサポートするケースが多くあります。
支援の内容は幅広く、経営戦略や財務戦略の立案、人事・組織体制の構築支援、コーポレートガバナンスの整備、さらには事業拡大につながる企業やパートナーの紹介といった実践的な内容が含まれます。
特に創業間もない企業では、経営者の経験不足から判断を誤り、成長が滞ることも少なくありません。投資家は多くのベンチャー企業を支援してきた知見をもとに、事業の方向性や意思決定をサポートし、失敗のリスクを抑えながら企業価値の最大化を図ります。
イグジットする
事業が計画通りに成長し、目標とする成果を上げられた段階で、投資家はイグジットへと進みます。
主なイグジットは株式上場(IPO)またはM&Aによる企業売却です。IPOでは上場後に保有株式を売却し、M&Aでは買収時の売却益によって投資家は利益を確定させます。
このイグジットによって投資家は資金を回収し、新たなスタートアップ支援へと資金を再投資する流れが生まれます。
イグジットは投資家と企業双方にとって、一つの大きな節目となる重要なプロセスです。
M&Aはベンチャー企業の出口戦略として最適

本記事では、ベンチャー企業の出口戦略としてのM&AとIPOの違いや買い手、売り手双方のM&Aのメリットなどを解説しました。
M&Aは、実現のハードルや資金調達額といった様々な点でIPOより優れており、米国をはじめとする海外ではベンチャー企業の主流な出口戦略です。
日本では、IPO偏重の傾向がありましたが、東証の再編によって、上場のハードルが上がったことでIPOからM&Aによる出口戦略に移行するのではないかという意見もあります。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。