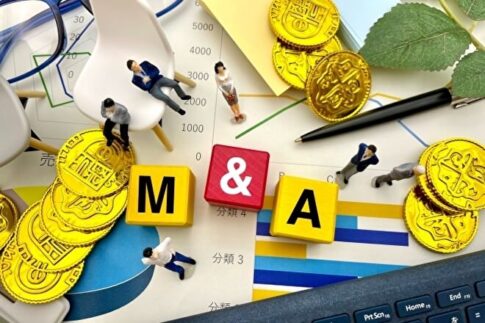企業の成長や変化に伴い社内に複数のシステムが乱立し、業務効率の低下やデータの分散といった課題に直面していませんか。これらの課題を解決する有効な手段の一つが「システム統合」です。
しかし、システム統合と聞いても、具体的な進め方やメリット・デメリットがわからない方も多くいます。
今回は、システム統合の基本的な知識から具体的な進め方、成功させるためのポイントまで専門外の読者にもわかりやすく解説します。本記事を読んでシステム統合の全体像を理解し、自社の課題解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。
目次
- 1 システム統合とは?
- 2 システム統合の定義と必要性
- 3 システム統合の種類
- 4 システム統合のメリット・デメリット
- 5 メリット
- 6 デメリット
- 7 システム統合の具体的なステップ
- 8 ステップ1:現状分析と課題の明確化
- 9 ステップ2:目標設定とスコープ定義
- 10 ステップ3:システム選定とベンダー選定
- 11 ステップ4:詳細設計と開発
- 12 ステップ5:テストと移行
- 13 ステップ6:運用と保守
- 14 システム統合を成功させるための4つのポイント
- 15 ポイント1:明確な目標設定と計画
- 16 ポイント2:関係者との密なコミュニケーション
- 17 ポイント3:適切なベンダー選定
- 18 ポイント4:継続的な改善
- 19 まとめ:システム統合でビジネスを加速させよう
システム統合とは?

システム統合は、現代のビジネス環境において重要なテーマの一つです。本章では、基本的な定義と、必要とされる背景を中心に解説します。
システム統合の定義と必要性
システム統合とは、企業や組織内で利用されている複数の情報システムを、機能的あるいは物理的に一つにまとめ上げることです。データの連携をスムーズにし、業務プロセスの効率化を図ることを目指します。
以下に、各用語の意味をまとめました。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| システム統合 | 複数の独立した情報システムを連携させ、一つのシステムとして機能させる行為。 |
| データ連携 | 異なるシステム間でデータを共有し、活用できるようにする行為。 |
| 業務プロセス | 仕事を進める上での一連の手順や流れのこと。 |
近年、企業活動の複雑化やM&A(企業の合併・買収)の増加に伴い、システム統合の必要性が高まっています。古いシステム(レガシーシステム)の維持コスト増大や、部門ごとに最適化されたシステムの乱立による非効率も、統合を後押しする要因です。
課題を解決し、企業全体の競争力を高める上で、システム統合は不可欠な取り組みです。
システム統合の種類
システム統合には、目的や対象に応じていくつかの種類が存在します。以下に、代表的なシステム統合の種類をまとめました。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| データ統合 | 複数のシステムに散在するデータを一カ所に集約し、一元的に管理・活用できるようにする統合。顧客データや商品データなど、企業活動の根幹となるデータの整合性を保ち、分析などに役立てる。 |
| アプリケーション統合 | 異なる業務アプリケーション間でデータを連携させたり、機能を連携させたりする統合。例えば、販売管理システムと会計システムを連携させると、売上データを自動的に会計処理に反映できる。 |
| プロセス統合 | 複数のシステムにまたがる業務プロセス全体を最適化し、自動化する統合。ワークフローシステムなどを活用し、手作業による処理を減らし、業務の迅速化と標準化を目指す。 |
| プラットフォーム統合 | サーバーやOS、データベースといったシステムの基盤(プラットフォーム)を共通化する統合。運用管理の効率化やコスト削減が期待できる。 |
各種システム統合は独立しているわけではなく、プロジェクトの目的によって複合的に実施される場合もあります。
システム統合のメリット・デメリット

システム統合は多くの利点をもたらす反面、注意すべき点や潜在的なリスクも存在します。
本章では、システム統合がもたらす主なメリットと考慮すべきデメリットを整理します。双方を事前に理解しておくと、より現実的で効果的な統合計画の策定が可能です。
メリット
システム統合を実施すると、企業は多岐にわたる恩恵を受けられます。主なメリットを以下に示しました。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 業務効率の大幅な向上 | データ入力の重複排除や手作業の削減、部門間連携の強化により、業務プロセスが円滑化する。 |
| コスト削減 | ハードウェアやソフトウェアライセンス、運用保守に関わる費用を削減できる。 |
| データの一元管理と活用 | 正確なデータに基づいた迅速な意思決定が可能になり、データドリブン経営を推進できる。 |
| 意思決定の迅速化 | 経営層が必要な情報をリアルタイムで把握でき、的確な判断をスピーディーに下せる。 |
| セキュリティレベルの向上 | 最新のセキュリティ対策を施した統合システムにより、情報漏洩リスクを低減できる。 |
| コンプライアンス強化 | データのトレーサビリティ向上やアクセス管理の徹底により、法令遵守の体制を強化できる。 |
| 拡張性と柔軟性の向上 | 将来のビジネス環境の変化や新しい技術の導入に対応しやすくなる。 |
メリットを最大限に引き出すには、事前の計画と適切な実行が不可欠です。
デメリット
システム統合は大きな変革を伴うため、いくつかのデメリットやリスクも考慮する必要があります。デメリットやリスクを認識し、対策を講じることが成功の鍵です。
主なデメリットを以下に示しました。
| デメリット | 詳細と対策の方向性 |
|---|---|
| 初期コストの発生 | 新しいシステムの導入費用や開発費用、コンサルティング費用など、初期投資が大きくなる場合がある。費用対効果を慎重に評価し、段階的な投資も検討する。 |
| 業務プロセスの変更に伴う混乱 | 新しいシステムに合わせて業務フローの変更が必要となり、一時的に現場の混乱や生産性の低下を招く可能性がある。十分な教育研修と丁寧なコミュニケーションが重要。 |
| データ移行のリスク | 既存システムからのデータ移行時に、データの欠損や不整合が発生するリスクがある。綿密な移行計画とテスト、データクレンジングの徹底が重要。 |
| システム障害時の影響範囲の拡大 | システムが統合されると、障害が発生した際の影響が広範囲に及ぶ可能性がある。冗長性の確保やバックアップ体制の強化など、リスク管理策を講じる。 |
| ベンダーロックインの可能性 | 特定のベンダー製品に依存すると、将来的な選択肢が狭まる可能性がある。オープンな技術標準の採用やマルチベンダー戦略の検討が不可欠。 |
| プロジェクトの長期化・複雑化 | 大規模なシステム統合は計画から実行、安定稼働までに長期間を要し、プロジェクト管理が複雑になる場合がある。現実的なスケジュール設定と強力なプロジェクトマネジメント体制が必要。 |
デメリットを最小限に抑えるには、専門家からサポートを受けるのも有効な手段です。
システム統合の具体的なステップ

システム統合プロジェクトは、複数の段階を経て進められるのが一般的です。各ステップで何をすべきかを明確にすると、プロジェクトをスムーズに、成功に導けます。
本章では、システム統合を進める上での代表的なステップを紹介します。
ステップ1:現状分析と課題の明確化
システム統合の最初のステップは、現在のシステム環境と業務プロセスの詳細な分析です。「As-Is(現状)」モデルを明らかにし、問題がある場所や、解決したい課題を具体的に特定します。
具体的な作業内容は、以下のとおりです。
- 既存システムの機能、構成、問題点の洗い出し
- 業務フローの可視化と非効率な点の特定
- ユーザー部門へのヒアリングによるニーズの収集
正確な現状把握が、後のステップの基礎として機能します。
ステップ2:目標設定とスコープ定義
現状分析と課題が明確になったら、システム統合によって達成したい目標を設定します。目標は、具体的で測定可能、達成可能、関連性があり、期限付き(SMART)であることが望ましいです。
また、統合対象となるシステムや業務の範囲(スコープ)を定義します。
具体的な作業内容は、以下のとおりです。
- 統合後の「To-Be(あるべき姿)」モデルの策定
- 定量的・定性的な目標値の設定(例:コスト削減〇〇%、業務時間〇〇%短縮など)
- 対象システム、機能、部門の明確化
明確な目標とスコープはプロジェクトの方向性を定め、関係者の認識を統一する上で非常に重要です。
ステップ3:システム選定とベンダー選定
設定した目標とスコープに基づき、最適なシステムや統合方法を選定します。既存システムを活用するのか、新しいパッケージ製品を導入するのか、あるいは独自開発するのかなどを検討します。
同時に、プロジェクトを支援してくれるITベンダーの選定も重要です。システムとベンダー選定のポイントを、以下にまとめました。
| システム選定のポイント | ベンダー選定のポイント |
|---|---|
|
|
情報収集依頼書(RFI)や提案依頼書(RFP)を活用し、複数の候補を比較検討しましょう。
ステップ4:詳細設計と開発
選定したシステムとベンダーに基づき、新しいシステムの詳細な設計を行います。業務プロセスやデータフロー、画面インターフェースなどを具体的に定義し、設計書に落とし込みましょう。
設計が完了したら、実際の開発作業に入ります。具体的な作業内容は、以下のとおりです。
- 要件定義書に基づいた機能設計、データベース設計、インフラ設計
- プロトタイプ作成によるユーザーレビュー
- 開発標準や品質管理基準の策定
本ステップは、ユーザー部門との連携を密にし、認識の齟齬がないように進めましょう。
ステップ5:テストと移行
開発されたシステムが要件どおりに動作するかを確認するため、さまざまなテストを実施します。具体的には、以下のようなテストを実施しましょう。
- 単体テスト: 個々のプログラムが正しく動作するかを確認する
- 結合テスト: 複数のプログラムを連携させた場合の動作を確認する
- 総合テスト: システム全体が業務シナリオ通りに機能するかを確認する
- 受入テスト: ユーザーが実際にシステムを操作し、要求を満たしているかを確認する
テストで問題がないことが確認されたら、既存システムから新システムへの移行作業を行います。慎重なテストと計画的な移行が、トラブルを未然に防ぎます。
ステップ6:運用と保守
新システムが本稼働を開始したら、安定的に運用するための体制を整えます。日常的な監視、トラブル発生時の対応、ユーザーからの問い合わせ対応などを行います。
また、稼働後に明らかになった改善点やビジネス環境の変化に合わせて、システムを継続的に保守・改善していきましょう。システム統合は導入して終わりではなく、その価値を維持・向上させていくための継続的な努力が必要です。
システム統合を成功させるための4つのポイント

システム統合プロジェクトは大規模で複雑になることが多く、残念ながら失敗に終わるケースも少なくありません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえておくと、成功の確率を大幅に高められます。
本章では、システム統合を成功に導くための4つのポイントを解説します。
ポイント1:明確な目標設定と計画
システム統合プロジェクトを始める前には、明確な目標の設定が最も重要です。目標が曖昧なままでは、プロジェクトの方向性が定まらず、関係者の足並みも揃いません。
以下に、具体的に意識すべきポイントをまとめました。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 具体的な目標 | 「コストを20%削減する」「顧客対応時間を15%短縮する」など、測定可能な目標を設定する。 |
| 優先順位付け | 複数の目標がある場合は優先順位を明確にし、リソースを効果的に配分する。 |
| 現実的な計画 | 達成可能なスケジュールと予算に基づいた、詳細なプロジェクト計画を策定する。 |
初期段階での目標や計画の明確化が、プロジェクト成功の鍵を握ります。
ポイント2:関係者との密なコミュニケーション
システム統合は、一部の情報システム部門だけの問題ではなく、経営層から現場のユーザーまで、企業全体の多くの関係者が関わります。関係者全員とプロジェクトの目的、進捗状況、課題などを常に共有し、密なコミュニケーションを取りましょう。
具体的な施策は以下のとおりです。
- 定期的な進捗報告会の開催
- 各部門の代表者を含めたワーキンググループの設置
- 懸念事項や意見を自由に発言できる雰囲気づくり
良好なコミュニケーションは、誤解を防いで協力を促進し、プロジェクトを円滑に進めます。
ポイント3:適切なベンダー選定
システム統合プロジェクトの多くは、専門的な知識や技術力を持つ外部のITベンダーの協力を得て進められます。自社の状況や目標に最も適したベンダーの選定が、プロジェクトの成否を左右する重要な要素の一つです。
以下のポイントを参考に、明確な基準で選定しましょう。
- 同業種・同規模のシステム統合実績
- 提案内容の実現性や技術力
- プロジェクト管理能力とコミュニケーション能力
- 費用とサポート体制のバランス
複数のベンダーからの提案を比較検討し、長期的なパートナーとして信頼できる相手を選びましょう。
ポイント4:継続的な改善
システム統合は、新しいシステムが稼働を開始したら終わりではありません。実際に運用を開始すると、計画段階では見えなかった課題や、さらなる改善点が見つかる場合があります。
稼働後の効果測定と評価を定期的に実施しましょう。具体的には、ユーザーからのフィードバックを収集し改善に生かします。
ビジネス環境の変化や技術の進展に合わせて、システムを柔軟に進化させていく姿勢が重要です。PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回し続けると、システム統合の効果を最大限に高めて維持できます。
まとめ:システム統合でビジネスを加速させよう

システム統合は、企業が抱えるさまざまな課題を解決し、業務効率の向上、コスト削減、競争力の強化を実現するための強力な手段です。
システム統合は決して簡単なプロジェクトではありませんが、効果は非常に大きいです。本記事が、皆様のシステム統合への理解を深め、ビジネスをさらに加速させるための一助となれば幸いです。具体的な計画や実行でお困りのことがあれば、専門家への相談もご検討ください。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。