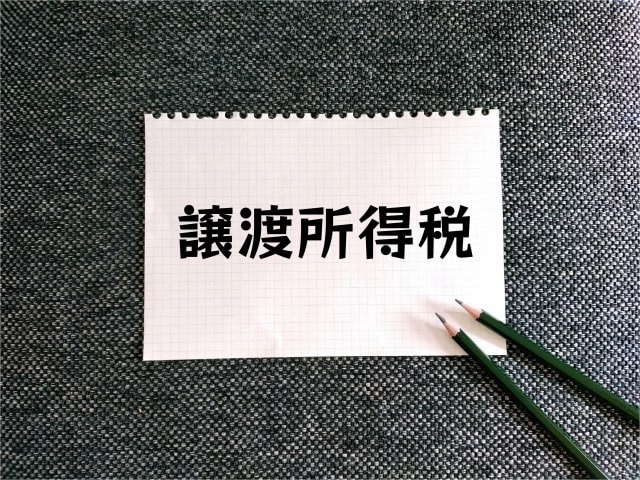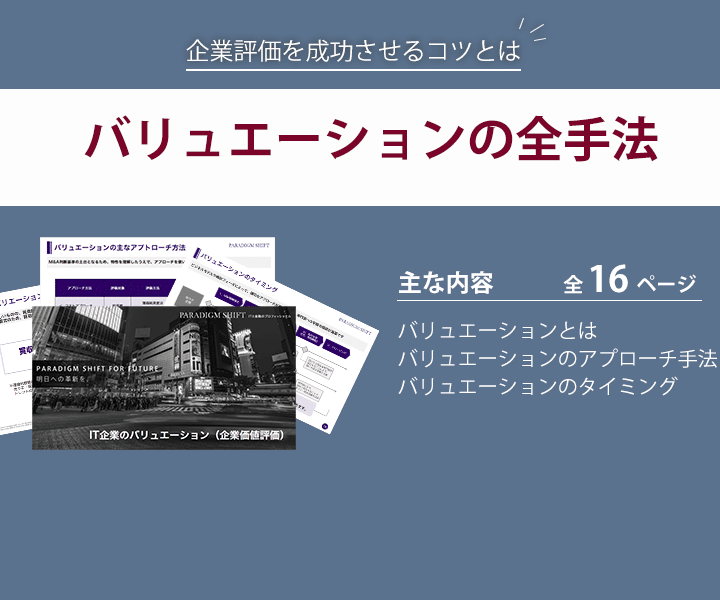株式の譲渡益が出た場合、適切な申告と納税が必要となるため、適切な計算方法を理解して追徴課税を避けることが大切です。
また、税制を理解しておけば節税対策を講じられます。
この記事では、株式譲渡所得税の計算方法から、確定申告の方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
上場株式・非上場株式の違いや税金を節税できる控除・特例制度についても解説するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 1 株式譲渡にかかる税金の種類
- 2 株式譲渡の所得税を計算する方法
- 3 譲渡所得の計算式
- 4 取得費の計算方法
- 5 取得費の調べ方
- 6 譲渡損失の繰越控除
- 7 株式譲渡で所得税が課税される対象
- 8 譲渡益
- 9 配当金・分配金
- 10 株式譲渡所得税の税率早見表
- 11 上場株式の税率(特定口座・一般口座)
- 12 非上場株式の税率
- 13 株式譲渡の税金を節税できる控除・特例制度
- 14 株式譲渡損失の繰越控除
- 15 事業承継税制
- 16 取得費加算の特例
- 17 少額投資非課税制度(NISA)の活用
- 18 特定口座源泉徴収ありのメリット・デメリット
- 19 メリット
- 20 デメリット
- 21 株式譲渡所得を得た際の確定申告書
- 22 確定申告が必要なケースと不要なケース
- 23 確定申告書の記入例
- 24 e-Taxでの申告方法
- 25 郵送・持参での提出方法
- 26 特定ケースにおける株式譲渡所得税
- 27 非上場株式の譲渡所得税の注意点
- 28 同族会社株式の譲渡所得税の特例
- 29 相続した株式を売却した場合の税金
- 30 よくある質問Q&A【株式譲渡所得税の疑問を解決】
- 31 Q. 譲渡損が出た場合はどうなりますか?
- 32 Q. 特定口座と一般口座、どちらがお得ですか?
- 33 Q. 確定申告の期限はいつですか?
- 34 Q. 海外の株式を売却した場合の税金はどうなりますか?
- 35 まとめ:M&Aを実施する際は株式譲渡所得への理解が重要
株式譲渡にかかる税金の種類
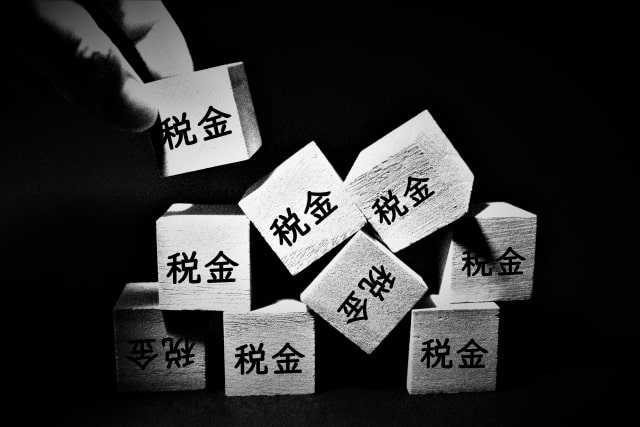
株式譲渡によって生じる利益(譲渡益)に対しては、さまざまな税金が課税されます。株式譲渡にかかる主な税金の種類は、以下のとおりです。
| 税金の種類 | 概要 | 税率 | 課税対象 |
| 所得税 | 譲渡益に対する国税。譲渡所得は分離課税の対象となるため、所得税率は一律です。 復興特別所得税も合わせて課税されます。 | 15% | 譲渡益 |
| 住民税 | 譲渡益に対する地方税。所得税と同様に分離課税の対象です。 | 5% | 譲渡益 |
| 復興特別所得税 | 東日本大震災の復興財源確保のため、所得税と住民税に上乗せして課税される時限税。2037年まで課税されます。 | 2.1% | 譲渡益(所得税額に連動) |
| 法人税等 | 譲渡益が法人から得られた場合に課税される税金。法人税、法人事業税、法人住民税などが含まれます。 | 23.2% | 譲渡益(法人課税対象の場合) |
| 相続税・贈与税 | 相続または贈与によって取得した株式を譲渡した場合、譲渡益に加えて、相続税または贈与税の課税対象となる可能性があります。 | 10%~ | 相続または贈与によって取得した株式の譲渡益、および株式の評価額 |
| 外国株式の譲渡所得税 | 外国株式の譲渡益に対しても、日本の税法に基づいて課税される場合があります。課税の有無や税率は、条約の有無や居住地の状況などによって異なります。 | 15% | 外国株式の譲渡益 |
上記以外にも、個々のケースに応じて、他の税金が適用される可能性があります。
複雑な税制のため、株式譲渡を検討する際は、税理士などの専門家へ相談しましょう。
特に、高額な株式の譲渡や非上場株式、相続した株式の譲渡など特殊なケースでは、専門家のアドバイスが必要不可欠です。
株式譲渡の所得税を計算する方法

株式譲渡によって得た利益(譲渡所得)には、所得税が課税されます。正確な税額を計算するには、譲渡所得の算出が必要です。
株式譲渡の所得税を計算するために、以下の方法を確認しておきましょう。
- 譲渡所得の計算式
- 取得費の計算方法
- 取得費の調べ方
- 譲渡損失の繰越控除
所得税の計算方法を4ステップに分けて解説するので、M&Aの参考にしてください。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
| 譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 |
- 譲渡価額: 株式を売却した金額。複数回にわたって売却した場合、それぞれの売却金額を合計する
- 取得費: 株式を取得した際に支払った費用
- 譲渡費用: 株式の売却に際して発生した費用。証券会社への手数料、税金(源泉徴収された税金を除く)などが含まれる
譲渡所得がマイナスになった場合は、譲渡損失の対象です。
取得費の計算方法
取得費は、株式の取得に要した費用を指します。
具体的には以下の費用が含まれます。
| 費用項目 | 説明 |
| 購入代金 | 株式を購入した際の金額 |
| 手数料 | 証券会社などに支払った手数料 |
| 名義書換料 | 株式の名義変更にかかった費用 |
| 印紙税 | 株式の売買契約書などに貼付した印紙税 |
| その他費用 | 取得に関連するその他の費用(弁護士費用など) |
同一銘柄の株式を複数回にわたって購入している場合、取得費の計算は総平均法が用いられることが一般的です。
購入日や数量にかかわらず、すべての購入金額を合計し、総購入数量で割ることで、1株当たりの平均取得費を算出します。
| 取得費の計算例 | |
| 条件 | A社の株式を100株×1,000円=10万円で購入し、その後50株×1,200円=6万円で購入した場合 |
| 平均取得費 | (10万円+6万円) ÷ (100株+50株) =1,066.67円/株 |
取得費の調べ方
取得費を正確に計算するには、株式の購入記録を保管しておくことが重要です。
証券会社から送られてくる取引明細書や、購入時の領収書などを大切に保管しましょう。
過去に遡って取得費を調べる必要がある場合は、証券会社に問い合わせれば、過去の取引履歴を確認できます。
ただし、古い取引履歴については、手数料がかかる場合もあります。
また、相続や贈与で株式を取得した場合、取得者は被相続人や贈与者の取得費を引き継がなければなりません。
取得費を確認するために、相続税・贈与税の申告書や被相続人・贈与者の購入記録をチェックしましょう。
譲渡損失の繰越控除
譲渡損失の繰越控除とは、譲渡所得がマイナスとなり、譲渡損失が発生した場合、損失を翌年以降の譲渡益から控除できる制度です。
繰越控除によって税負担を軽減できますが、適用できる期間や金額には制限があるので、税務署の規定を確認する必要があります。
譲渡損失の繰越控除を活用するためには、確定申告で譲渡損失を適用させる旨を申告しなければなりません。
株式譲渡で所得税が課税される対象

株式譲渡で所得税が課税される対象は、次のとおりです。
- 譲渡益
- 配当金・分配金
所得税を計算するために、課税対象を理解しておきましょう。
譲渡益
譲渡益とは、株式の売却によって得られる利益のことです。具体的には、株式の売却価格から取得費用を差し引いた金額を指します。
譲渡益の計算式は次の通りです。
| 譲渡益=売却価格-(取得価額+必要経費) |
取得価額とは、株式を購入した際の価格です。
必要経費には、株式の購入手数料、売買手数料などが含まれます。
譲渡益が発生した場合、金額に応じて所得税が課税されますが、株式の種類(上場株式か非上場株式か)や特定口座の利用状況によって税率が異なります。
| 項目 | 説明 | 例 |
| 売却価格 | 株式を売却した際の価格 | 1,000,000円 |
| 取得価額 | 株式を購入した際の価格 | 500,000円 |
| 必要経費 | 購入手数料、売買手数料など | 10,000円 |
| 譲渡益 | 売却価格 - (取得価額 + 必要経費) | 490,000円 |
配当金・分配金
株式を保有することで受け取る配当金や分配金も、所得税の課税対象です。
ただし、譲渡益とは異なり、配当金や分配金は株式の売却とは関係なく、定期的に受け取れます。
配当金や分配金の課税は、所得税法上の「配当所得」として扱われます。
配当所得の税率は、所得税と住民税を合わせて20.315%です。
ただし、特定口座を利用している場合は、源泉徴収されるため、確定申告は不要なケースが多いです。
譲渡益と配当金・分配金は、それぞれ異なる課税対象であり、計算方法も異なります。
譲渡益は分離課税、配当金・分配金は総合課税の対象となる場合が多いため、それぞれの税額を正確に計算することが大切です。
なお、譲渡益と配当金・分配金の両方を得た場合、それぞれの所得に対して個別に税金を計算しなければなりません。
株式譲渡所得税の税率早見表

株式譲渡所得税を計算するために、税率を確認しておきましょう。
上場・非上場株式それぞれの税率を早見表で紹介します。
上場株式の税率(特定口座・一般口座)
上場株式の譲渡益にかかる税率は、特定口座と一般口座で手続きが異なります。どちらも税率自体は同じですが、申告方法や納税方法に違いがあります。
| 口座の種類 | 税率 | 申告 | 納税 | 備考 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 20%(所得税15%、住民税5%) ※復興特別所得税0.315%は含む | 不要(源泉徴収済み) | 源泉徴収により自動的に納付 | 譲渡益が少額の場合、確定申告不要。ただし、損失の繰越控除や他の所得との損益通算を希望する場合は確定申告が必要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 | 確定申告により納付 | 譲渡益の額にかかわらず確定申告が必要 | |
| 一般口座 |
上記の税率は、2025年現在の税率であり、将来的に変更される可能性があります。最新の情報は国税庁のWebサイトをご確認ください。
参照元:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
非上場株式の税率
非上場株式の譲渡益にかかる税率も、上場株式と同様に20%(所得税15%、住民税5%)です。
ただし、上場株式と異なり特定口座制度の適用がないため、確定申告が必須です。
| 株式の種類 | 税率 | 申告 | 納税 |
| 非上場株式 | 20%(所得税15%、住民税5%) ※復興特別所得税0.315%は含む | 必要 | 確定申告により納付 |
非上場株式の譲渡所得税の計算においては、取得費の算定が複雑になるため、専門家のアドバイスを受けましょう。
また、譲渡損失の繰越控除や、同族会社株式の譲渡に関する特例など、非上場株式特有の注意点に気を付けてください。
株式譲渡の税金を節税できる控除・特例制度

株式譲渡の税金を節税できる控除・特例制度は、次のとおりです。
- 株式譲渡損失の繰越控除
- 事業承継税制
- 取得費加算の特例
- 少額投資非課税制度(NISA)の活用
それぞれの概要を確認して、節税対策してください。
株式譲渡損失の繰越控除
株式の売却で損失が発生した場合、損失を翌年以降の譲渡益から差し引ける「株式譲渡損失の繰越控除」制度があります。
最大3年間繰越せるため、損失が出た年度は税金がゼロでも、将来の節税につなげられます。
ただし、上場株式と非上場株式では、繰越できる損失の範囲や条件が異なるため注意が必要です。
具体的には、上場株式の損失は、他の譲渡所得と損益通算できますが、非上場株式は譲渡所得同士での損益通算に限られます。
| 項目 | 上場株式 | 非上場株式 |
| 繰越期間 | 3年間 | 3年間 |
| 損益通算の範囲 | 他の譲渡所得と可 | 譲渡所得同士のみ |
繰越控除を活用するには、損失の発生した年度に確定申告を行う必要があります。なお、損失の金額や適用条件など、詳細については税務署や税理士にご相談ください。
事業承継税制
事業承継税制は、中小企業のオーナーが事業を承継する際に、相続税や贈与税の負担を軽減する制度です。
株式譲渡においても、事業承継税制の適用条件を満たせば、税負担を大幅に減らせます。
具体的には、株式の譲渡価額を評価額より低く評価できる場合があり、税金計算における譲渡益が減少し、節税効果が期待できます。
なお、事業承継税制の適用には、一定の要件を満たさなければなりません。
例えば、承継される事業が継続性を持つこと、承継者が一定期間事業を継続することなどが挙げられます。
取得費加算の特例
相続によって株式を取得した場合、取得費の計算方法に特例があります。
通常、取得費は株式の購入価格などを指しますが、相続の場合は被相続人が株式を取得した際の価額が計算対象です。
しかし、取得費が不明な場合、譲渡価額の5%を概算取得費として計上できる特例が認められています。
取得費加算の特例を利用すれば、取得費を正確に算出できない場合でも、税金の計算が可能です。
ただし、特例はあくまで概算であり、実際の取得費よりも低い可能性があるため、できる限り正確な取得費を把握することが重要です。
少額投資非課税制度(NISA)の活用
NISAは、投資で得た利益に税金がかからない制度です。
株式投資においては、NISA口座で売買した株式の譲渡益は非課税として扱われます。
ただし、NISAには年間投資額の上限や非課税期間などの制限があるため、利用にあたっては制度のルールを理解しなければなりません。
NISAを活用すれば、税金対策と合わせて資産形成を効率的に進められます。NISAの口座開設や運用方法については、証券会社などの専門機関にご相談ください。
特定口座源泉徴収ありのメリット・デメリット

特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
どちらを選択するべきか悩んでいる方は、源泉徴収ありを選択した場合のメリット・デメリットを確認しておきましょう。
メリット
特定口座を源泉徴収ありに選択した場合のメリットは、次のとおりです。
| メリット | 詳細 |
| 確定申告が不要 | 年間の給与所得が2,000万円以下、特定口座の年間運用益が20万円以下の場合、確定申告が不要。確定申告の手間や時間を大幅に削減できる |
| 税金の支払いが自動化 | 売却時に税金が自動的に源泉徴収されるため、納税忘れの心配がない。確定申告の手続きが不要な分、税金の支払いを意識する必要がなくなる |
| 税金計算の手間が不要 | 証券会社が税金の計算を代行してくれるため、複雑な計算が不要。税金計算に不慣れな方でも安心して利用できる |
デメリット
特定口座を源泉徴収ありに選択した場合のデメリットは、次のとおりです。
| デメリット | 詳細 |
| 税金が売却時に差し引かれる | 利益確定するたびに約20%の税金が差し引かれるため、手元に残る金額が少なくなる。短期売買を繰り返す投資家にとっては、大きな負担となる可能性がある |
| 損失の繰越控除ができない場合がある | 源泉徴収ありの特定口座では、損失を翌年に繰り越して税金控除できない場合がある。損失が出た場合、その損失分を翌年の利益から差し引けないため、税負担が増える可能性がある |
| 税金計算の確認ができない | 証券会社が税金計算を代行するため、計算内容を詳細に確認しにくい。計算ミスがあった場合に気づきにくい |
| 年間所得が2,000万円を超える場合、確定申告が必要 | 年間の給与所得が2,000万円を超える場合、たとえ特定口座の年間運用益が20万円以下であっても、確定申告が必要 |
特定口座「源泉徴収あり」は、確定申告の手間を省けるという大きなメリットがありますが、税金が売却時に差し引かれる点や、損失の繰越控除ができない可能性があります。
自身の投資スタイルや年間所得を考慮し、メリット・デメリットを比較検討して自分に合った選択をしましょう。
株式譲渡所得を得た際の確定申告書
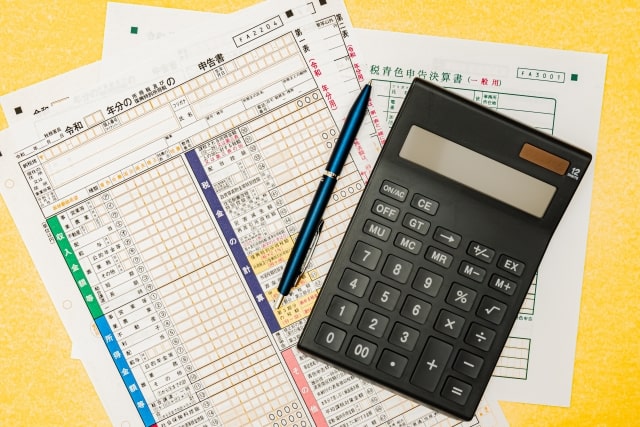
株式譲渡所得を得た際には、確定申告が必要なケースがあります。
確定申告書の書き方や申請方法を知らない方は、下記のポイントを確認しておきましょう。
- 確定申告が必要なケースと不要なケース
- 確定申告書の記入例
- e-Taxでの申告方法
- 郵送・持参での提出方法
それぞれのポイントを押さえて、確定申告が必要な際の参考にしてください。
確定申告が必要なケースと不要なケース
株式譲渡によって生じた所得に対しては、原則として確定申告が必要です。
ただし、いくつかの例外ケースも存在するため、確定申告が必要なケースと不要なケースを把握しておきましょう。
| ケース | 確定申告の必要性 | 備考 |
| 特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を売却し、年間の譲渡益が50万円以下 | 不要 | 税金は売却時に源泉徴収されます。 |
| 特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を売却し、年間の譲渡益が50万円を超える | 必要 | 源泉徴収された税金が不足している可能性があります。 |
| 特定口座(源泉徴収なし)で株式を売却 | 必要 | 自ら税金を計算し、納付する必要があります。 |
| 一般口座で株式を売却 | 必要 | 自ら税金を計算し、納付する必要があります。 |
| NISA口座で株式を売却 | 不要 | 売却益は非課税です。 |
| 譲渡損失が発生した場合 | 必要(損失の繰越控除を受ける場合) | 損失を翌年以降に繰り越して、将来の譲渡益から控除できます。 |
確定申告書の記入例
確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。記入方法は複雑ですが、必要事項を正確に記入することが重要です。
以下に、記入例の一部を紹介します。
※ これはあくまで例であり、実際の記入内容は個々の状況によって異なります。正確な記入方法については、国税庁のホームページや税理士などの専門家に相談してください。
| 項目 | 記入例 |
| 氏名 | 山田 太郎 |
| 住所 | 東京都○○区○○町1-1-1 |
| 所得の種類 | 株式譲渡所得 |
| 譲渡所得金額 | 1,000,000円 |
| 取得費 | 500,000円 |
| 譲渡益 | 500,000円 |
| 税額 | 100,000円 |
e-Taxでの申告方法
e-Taxは、インターネットを通じて確定申告を行うシステムです。
マイナンバーカードがあれば、e-Taxで確定申告をオンライン申請できます。
e-Taxでの確定申告方法は、次のとおりです。
- e-Taxのサイトにアクセスし、マイナンバーカードでログインします。
- 確定申告書を作成。必要事項を入力し、添付書類をアップロードします。
- 送信ボタンをクリックして、確定申告完了です。
郵送・持参での提出方法
e-Taxを利用できない場合は、確定申告書を郵送または税務署へ持参して提出しましょう。
提出期限までに届くように、余裕を持って手続きを行う必要があります。
- 確定申告書を印刷し、必要事項を記入します。
- 必要書類を添付します。
- 税務署の窓口に持参するか、郵送で提出します。
郵送の場合は、簡易書留やレターパックなど利用し、送付状況を確認することをおすすめします。また、提出期限に間に合うように、余裕を持って手続きを進めましょう。
特定ケースにおける株式譲渡所得税

株式譲渡で所得税を得る際に、さまざまな例外ケースが存在します。下記の特定ケースごとの注意点や特例を確認して、株式譲渡の所得税を適切に納税しましょう。
- 非上場株式の譲渡所得税の注意点
- 同族会社株式の譲渡所得税の特例
- 相続した株式を売却した場合の税金
非上場株式の譲渡所得税の注意点
非上場株式の譲渡は、上場株式とは異なるいくつかの注意点がありますが、最大のポイントは時価の算定が難しい点です。
上場株式であれば、市場価格が時価として明確に示されますが、非上場株式には市場がないため、時価を正確に算定することが困難です。
そのため、税務調査において、税務署から時価の算定方法について厳しく問われる可能性があります。
時価の算定方法は、主に以下のとおりです。
| 算定方法 | 説明 | 適用事例 |
| 相続税法上の時価 | 相続税の評価方法を準用し、純資産価額法や類似会社比較法などを用いて算定します。 | 個人間での譲渡、個人から法人への譲渡 |
| 所得税法上の時価 | 所得税法に基づく評価方法を準用し、純資産価額法などを用いて算定します。 | 法人から個人への譲渡、法人間での譲渡 |
| 取引価格 | 実際に取引された価格を時価とします。第三者間での公平な取引であれば、この価格が認められることが多いです。 | 第三者間での譲渡 |
上記の方法によって算出された時価に大きな差が生じる可能性があり、税務リスクを伴います。
同族会社株式や低額譲渡の場合は、税務署から厳しく精査される可能性が高いため、注意が必要です。
同族会社株式の譲渡所得税の特例
同族会社株式の譲渡には、税制上の取り扱いに特例があります。
同族会社とは、特定の株主(同族)が議決権の過半数を保有する会社であり、譲渡所得の取り扱いが一般の非上場株式とは違うのです。
具体的には、時価評価が厳格に適用される傾向があり、譲渡益が過少申告されるリスクが高まります。
しかし、事業承継税制を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。また、譲渡価額が低い場合、税務上のリスクが高まるため、専門家に相談しましょう。
相続した株式を売却した場合の税金
相続により取得した株式を売却する場合、取得費の計算が重要です。
相続税の申告時に評価された時価は、株式の取得費として計上できます。さらに、相続税の一部を取得費に加算できる特例もあります。
また、相続開始後3年10カ月以内に発行会社に譲渡する場合は、みなし配当課税の特例を適用可能です。
具体的には、相続税の申告期限から3年以内の譲渡で、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を譲渡前に発行会社へ提出することで、譲渡対価の全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額として扱えます。
みなし配当課税の特例を利用すれば、みなし配当として課税されることを回避し、税負担を軽減できます。
よくある質問Q&A【株式譲渡所得税の疑問を解決】

株式譲渡所得税に関するよくある質問は、次のとおりです。
- Q. 譲渡損が出た場合はどうなりますか?
- Q. 特定口座と一般口座、どちらがお得ですか?
- Q. 確定申告の期限はいつですか?
- Q. 海外の株式を売却した場合の税金はどうなりますか?
それぞれ質問に対する回答を確認して、株式譲渡所得税の疑問を解消しましょう。
Q. 譲渡損が出た場合はどうなりますか?
株式の売却で譲渡損が生じた場合、その損失は他の譲渡益と損益通算できます。
具体的には、同じ年の他の株式譲渡益から差し引かれ、譲渡益が譲渡損を下回ると税金はかかりません。
ただし、譲渡損は翌年以降に繰り越すことも可能です(譲渡損失の繰越控除)。繰り越しできる期間は3年間なので、期間中に確定申告して譲渡損を処理しましょう。
Q. 特定口座と一般口座、どちらがお得ですか?
特定口座と一般口座、どちらがお得かは、個々の状況によって異なります。
| 項目 | 特定口座(源泉徴収あり) | 一般口座 |
| 申告 | 多くの場合不要(ただし、譲渡損がある場合や損益通算が必要な場合は確定申告が必要) | 必ず確定申告が必要 |
| 税金の支払い | 売却時に源泉徴収される | 確定申告時に一括納付 |
| 手続きの簡便さ | 比較的簡単 | 確定申告が必要なため、手続きが複雑 |
| 損益通算 | 損益通算が可能だが、手続きが必要な場合がある | 損益通算が可能 |
譲渡益が少なく、損益通算の必要がない場合は、特定口座の方が手続きが簡便で税金の支払いを売却時に済ませられるため便利です。
一方、譲渡損がある場合や、他の所得と損益通算したい場合は、一般口座で確定申告を行う方が有利な可能性があります。
また、特定口座では源泉徴収されるため、実際の税額と異なる可能性があり、精度の高い計算が必要な場合は一般口座が適しています。
Q. 確定申告の期限はいつですか?
株式譲渡所得の確定申告期限は、原則として翌年の3月15日です。ただし、e-Taxで申告する場合は、3月15日23時59分までが期限です。
期限を過ぎた場合は、延滞税が課せられる可能性があるので注意してください。
Q. 海外の株式を売却した場合の税金はどうなりますか?
海外株式の売却益にも、日本の所得税が課税されます。
計算方法は国内株式とほぼ同様ですが、為替レートの変動を考慮しなければなりません。
また、二重課税を防ぐための租税条約が締結されている国もあるので、条約の内容を確認しておきましょう。
まとめ:M&Aを実施する際は株式譲渡所得への理解が重要

株式譲渡は、高額な税金が発生する可能性があるため、事前にしっかりと理解しておくことが非常に重要です。
特にM&Aなど、まとまった数の株式を譲渡する際には、税金対策を綿密に計画する必要があります。
上場株式と非上場株式では税率や手続きが異なり、特定口座と一般口座のメリット・デメリット、譲渡損失の繰越控除、事業承継税制など、さまざまな制度や注意点が存在します。
株式譲渡所得税に関する知識をしっかりと把握し、税理士などの専門家と相談しながら、最適な税務戦略を立てて、節税対策しましょう。
本記事でご紹介した情報を参考に、株式譲渡に関するリスクと機会を正しく理解し、賢く税金対策を行ってください。