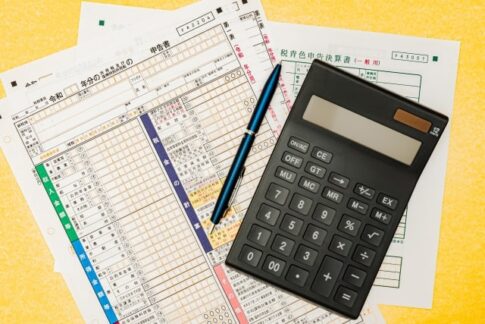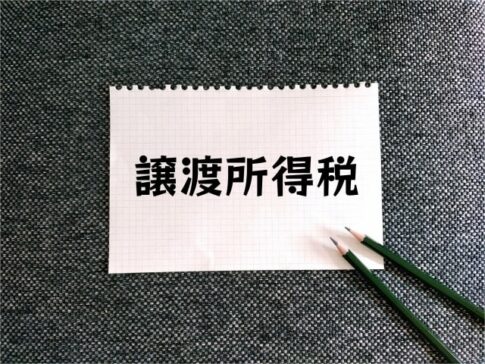景気の悪化や少子高齢化が進む現在、資金調達や後継者不足にお困りの経営者も少なくないでしょう。
株式譲渡は、中小企業でよく用いられるM&A手法です。
自社株式を売却する対価として現金を得たり、株式を譲渡することによって後継者問題を解決できたりと便利な手続きです。
本記事では、株式譲渡するメリット・デメリットや手続き方法、株式譲渡のあと、従業員や社長の待遇について解説します。
目次
- 1 株式譲渡とその他のM&A手法との違い
- 2 事業譲渡との違い:事業の一部譲渡ができるかどうか
- 3 合併との違い:会社が消滅するかどうか
- 4 会社分割との違い:組織再編行為に該当するか否か
- 5 株式交換との違い:買収資金を必要とするかどうか
- 6 M&Aで活用される株式譲渡の方法3つ
- 7 相対取引
- 8 市場買付け
- 9 公開買付け(TOB)
- 10 M&Aにおける株式譲渡のメリット3つ(売り手企業)
- 11 税金が抑えられる
- 12 手続きが簡単
- 13 創業者利益の獲得
- 14 M&Aにおける株式譲渡のデメリット2つ(売り手企業)
- 15 支配権を失う
- 16 買い手が見つからない
- 17 株式譲渡でM&Aを実施する際の手続きの流れ
- 18 株式譲渡の承認請求
- 19 取締役会(株主総会)で譲渡承認
- 20 決定内容の通知
- 21 株式譲渡契約の締結
- 22 代金決済
- 23 株主名簿の書き換え
- 24 株主名簿の交付
- 25 株式譲渡でM&Aを実施する際の企業価値算定方法
- 26 インカム・アプローチ
- 27 マーケット・アプローチ
- 28 コスト・アプローチ
- 29 株式譲渡でM&Aを実施したあとはどうなる?
- 30 社員の処遇について
- 31 役員の退職金について
- 32 税金について
- 33 株式譲渡によるM&Aの成功事例
- 34 エンジャパンによるアウルスの買収
- 35 COMBOによるテクノモバイルへの株式譲渡
- 36 コウイクスによるSDアドバイザーズへの株式譲渡
- 37 株式譲渡を利用してM&Aを成功させよう
株式譲渡とその他のM&A手法との違い

株式譲渡とは、売り手の保有する株式を買い手に譲渡して資金を得るM&A手法の1つです。
株式譲渡は他のM&A手法と比べて簡単に取引ができるため、中小企業のM&Aでは最も使われます。
M&Aにはさまざまな手法がありますが、財務内容が健全で経営者が株式の大半を保有している場合は株式譲渡が効果的です。
M&Aで使用する用語には、株式譲渡のほかに事業譲渡や合併、分割、株式交換などがあります。
言葉自体は聞いたことがあっても、違いをうまく説明できない方もいるのではないでしょうか。
M&Aを行うなら、違いをしっかりと理解する必要があります。
ここからは、株式譲渡と「事業譲渡」「合併」「分割」「株式交換」には、どのような違いがあるのか解説します。
事業譲渡との違い:事業の一部譲渡ができるかどうか
事業譲渡とは、譲渡企業が保有する事業の一部もしくはすべてを譲渡できるM&A手法を指します。
株式譲渡と事業譲渡の違いは、譲渡する範囲です。
株式譲渡は経営権を譲渡しますが、事業譲渡は事業の一部だけ譲渡できます。
つまり、事業譲渡では不要な事業のみを切り離すことが可能です。
契約に関しては、株式譲渡では株式譲渡契約を結び、事業譲渡では事業譲渡契約を結びます。
合併との違い:会社が消滅するかどうか
合併とは、複数の会社が1つに合体する組織再編行為を指します。
株式譲渡と合併の違いは、消滅する会社があるかどうかです。
株式譲渡では消滅する会社はありませんが、合併では必ず消滅する会社が存在します。
組織再編行為は取引額が多額になる場合が多く、課税関係やスキームを慎重に検討し、適切に処理することが重要です。
株式譲渡と合併のどちらを利用するか迷っている方は、専門家へ相談しましょう。
会社分割との違い:組織再編行為に該当するか否か
会社分割とは、会社が保有する事業の権利義務の一部またはすべてを第三者の会社へ承継するM&A手法を指します。
株式譲渡と会社譲渡の違いは、組織再編行為に該当するか否かです。
株式譲渡は、対象企業の株式を売買する単純な売買契約のため、会社法における組織再編行為に該当しません。
一方、会社分割は対価を自社株式で支払うため、組織再編行為に該当します。
株式交換との違い:買収資金を必要とするかどうか
株式交換とは、譲渡企業が持つすべての株式と譲受企業の株式を交換し、完全な親会社・子会社の関係を作るM&A手法を指します。
株式譲渡と株式交換の違いは、買収資金を必要とするかどうかです。
株式譲渡と異なり、株式交換では買収資金を必要としません。
株式譲渡では、譲渡企業が保有する株式を譲受企業に渡し、対価として現金を受け取ります。
一方で株式交換は譲渡企業が保有する株式を譲渡し、譲受企業は対価として自社株式の一部を提供する手続きです。
M&Aで活用される株式譲渡の方法3つ

株式譲渡には、3つの方法があります。
- 相対取引
- 市場買付け
- 公開買付け(TOB)
上場企業と非上場企業では、取引方法が異なります。
非上場企業の場合は、相対取引のみです。
では、それぞれの取引方法について詳しく見てみましょう。
相対取引
1つ目の方法が、相対取引です。
相対取引とは、買い手が売り手である株主と個別で交渉して、株式譲渡する取引方法。
非上場企業の株式譲渡の方法は相対取引のみです。
株主が分散している場合は、買い手はいかに株式を買い集めるかが問題となります。
譲渡価格は、株主ごとで付ける価格が異なる場合があるため、株主間で不満が生じ買い手との交渉に時間がかかる場合があります。
買い手はそれぞれの株主と実務上、同じ価格で取引することが一般的です。
市場買付け
2つ目の方法が、市場取引です。
市場取引とは、対象会社が上場している場合に株式市場から直接買い集める取引方法。
上場企業の場合は、非上場企業と異なり株式市場から株式を買い集めることが可能です。
また市場取引では、株価が安いときに多くの株式を取得することで投資コストを削減できます。
しかし、発行済株式総数および潜在株式総数の合計が5%を超えて取得した場合は、取得日から5営秒日以内に「大量保有報告書」を税務局へ提出することが必要です。
大量保有報告書とは、発行済株式数の5%以上を保有した株主が公表しないといけない書類で「5%ルール」ともいわれています。
また、その後に1%を超える保有割合の変化があった場合は変更報告書の提出が必要です。
大量保有報告書は、公表されれば買付け動向が明らかになり、株価が暴騰してしまう可能性が高まります。
取得する株式が過半数を目的とする場合には、市場買付けを選択されることはほとんどありません。
公開買付け(TOB)
3つ目の取引が公開買付け(TOB)です。
TOBとは、個別株主を含む多数の株主から、公告によって買付けの申し込みを勧誘し、市場外で株式を買い集める取引方法。
TOBは、上場企業など(有価証券報告書提出企業)の発行する株式を大量に買付けすることが目的です。
市場外で5%を超える買付けを実施する場合は、TOBよる取引方法が強制されています。
TOBを実施する場合は、現在の株価からプレミアムを乗せた高い株価で申し込みを勧誘することが一般的です。
プレミアムとは、元も株価に上乗せする形で株式を買い取ることを指します。
プレミアムを上乗せするのは、現在の株価より低い価格でTOBを行っても株主が応じないためです。
市場で売却した方が利益を得られるので、TOBによる経済的なメリットがなくなってしまいます。
M&Aにおける株式譲渡のメリット3つ(売り手企業)

株式譲渡における売り手側のメリットは、以下の3つです。
- 税金が抑えられる
- 手続きが簡単
- 創業者利益の獲得
株式譲渡に関するそれぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
税金が抑えられる
1つ目のメリットは、税金が抑えられる点です。
事業譲渡とくらべて株式譲渡の方が利益にかかる税率が低くなります。
事業譲渡の場合は、法人税(29.97%)に加えて消費税(10%)もかかるため、合計で約40%前後の税率となります。
株式譲渡の場合は、譲渡所得にかかる税率の20.315%だけなので事業譲渡と比べて税金を低く抑えることが可能です。
事業譲渡では、「のれん」が含まれるため、のれんが多くなるほど支払う税金額が大きくなります。
のれんとは、企業のブランドや技術などを総称する無形固定資産。
のれん価値が大きい場合は、株式譲渡によるM&Aが有利です。
手続きが簡単
2つ目のメリットは、手続きが簡単である点です。
株式譲渡では、売り手が取引先や従業員、債権者などから個別に同意を得るといった手続きが必要ありません。
株式譲渡は、取締役会や株式総会で承認を得て、株主名簿を書き換えることで手続きは完了です。
そのため、スムーズに株式譲渡の手続きを済ませられます。
創業者利益の獲得
3つ目のメリットは、創業者利益の獲得ができる点です。
株式の譲渡側は、株式の対価として現金を受け取ります。
株式譲渡を実施することが多い中小企業の経営者は、自社の株式をほとんど保有している状態が多いでしょう。
そのため、株式を売却すれば第三者に会社を渡せるだけではなく、創業者利益を獲得できます。
後継者がいない場合や現役から引退したい場合には、株式譲渡はとても有効なM&A手法です。
また、のれんの価値が大きいほど株式譲渡した際に受け取る金額も大きくなります。
創業者利益を獲得すると、新規事業の資本にしたり現役から引退し優雅な暮らしをしたりとさまざまな選択ができます。
M&Aにおける株式譲渡のデメリット2つ(売り手企業)

次に、売り手側のデメリットについて解説します。
株式譲渡における売り手側のデメリットは、以下の2つです。
- 支配権を失う
- 買い手が見つからない
では、2つのデメリットについて見ていきましょう。
支配権を失う
1つ目のデメリットは、支配権を失う点です。
株式の過半数(50%以上)を譲渡した場合、単独で取締役の選任などの重要な議決ができなくなり、支配権を失います。
事業譲渡では、法人格を売り手側の手元に残すことができますが、株式譲渡で100%の株式を売却した場合には自分の手元に法人を残すことができません。
買い手が見つからない
2つ目のデメリットは、買い手が見つからない点です。
株式譲渡は負債も財産の一部として買い手に譲渡されます。
そのため、売り手の負債が大きすぎると買い手が見つからない場合があるでしょう。
売り手が見つからない場合は、事業の一部を事業譲渡することで、買い手が現金化しやすい事業のみを売却してお金を得られます。
判断が難しい場合は、M&A専門家に相談しましょう。
株式譲渡でM&Aを実施する際の手続きの流れ

次に、株式譲渡の手続き方法を解説します。
手順は以下のとおりです。
- 株式譲渡の承認請求
- 取締役会で譲渡承認
- 決定内容の通知
- 株式譲渡契約の締結
- 代金決済
- 株主名簿の書き換え
- 株主名簿の交付
株式譲渡の手続きは、他のM&A手法とくらべて短時間で実施可能です。
では、手続き方法について順を追って解説します。
株式譲渡の承認請求
始めに、株式譲渡の承認請求をします。
株式譲渡の承認請求は、譲渡に制限が設けられている場合に必要です。
譲渡する株式の種類や数、譲渡先の相手などを記載した株式譲渡承認請求書を作成し、会社に提出します。
取締役会(株主総会)で譲渡承認
次に、意思決定機関にて譲渡の認否を決定します。
取締役会を設置している企業は取締役会で、取締役会を設置していない企業は株主総会で譲渡承認の手続きをしましょう。
決定内容の通知
会社法139条2項により、決議の結果を譲渡承認請求した株主に通知しなければなりません。
通知は書面や電子メールなどの方法で行うのが一般的ですが、法的には内容と意思表示が明確であることが大切です。
会社法では通知の期限が明確に定められており、譲渡承認請求があった日から2週間以内に承認・不承認の結果を通知しなければなりません。
ただし、期限は定款で短縮可能です。
会社法145条1項によると、期間内に会社から通知がない場合、たとえ不承認の決議が行われていたとしても、自動的に株式譲渡は承認されたものとみなされます。
通知の遅れや不備があると、予期せぬトラブルにつながるため、慎重に対応しましょう。
株式譲渡契約の締結
売買価格や従業員の取扱など様々な条件を売り手と買い手で決めることが株式譲渡では必要です。
すべての条件にお互いが合意したら、正式に株式譲渡契約書を締結します。
代金決済
契約書を締結したその場で代金の授受を行う場合もありますが、実務上は契約後に一定の前提条件を満たしたうえで決済する形が多く採用されています。
取引の安全性を確保し、買い手が安心して代金を支払えるようにするためです。
決済時には、売り手から買い手に対してさまざまな書類や物品が引き渡されます。
株式譲渡承認請求や承認結果の通知書、承認を記録した議事録、株主名簿、そして売り手が押印した株主名簿書換請求書などが含まれます。
経営体制に変更が生じる場合には、役員の辞任届なども必要書類として用意されるのが一般的です。
株券発行会社であれば、売り手は株券そのものを買い手に交付する義務があります。
代金決済は、単なる支払いの場面ではなく、株式譲渡を実行するための手続きが集中する重要なプロセスです。
株主名簿の書き換え
最後に、株式名簿の書き換えをします。
株式名簿とは、企業の株式を保有している株主リストです。
売り手から買い手に株主が変わるため、正式に名義を変更する必要があります。
株主名簿の交付
株主名簿とは、会社の株主の氏名や住所、保有株式数などを記載した公式の帳簿であり、株主としての地位を証明する極めて重要な資料です。
譲渡契約が成立し、代金の支払いと必要書類の引き渡しが完了すると、会社は株主名簿の書換手続きを行います。
買い手が新たな株主として正式に登録され、法的にも権利義務を有する立場になります。
もし不備があれば、将来の株主総会での議決権行使や配当請求に支障をきたす可能性があるため、慎重なチェックが欠かせません。
株式譲渡でM&Aを実施する際の企業価値算定方法

株式譲渡によるM&Aを進める際には、適正な企業価値の算定が欠かせません。
正しい評価ができなければ、売り手にとっては安売りのリスクが、買い手にとっては過大投資のリスクが生じてしまいます。
代表的な算定方法は、以下のとおりです。
- インカム・アプローチ
- マーケット・アプローチ
- コスト・アプローチ
それぞれの特徴を解説します。
インカム・アプローチ
インカム・アプローチは、企業が将来生み出す収益力に着目して価値を算定する方法です。
過去の実績よりもこれから得られるキャッシュフローを重視するため、将来の成長性や事業の持続可能性を反映できる点が大きな特徴です。
株式譲渡を伴うM&Aにおいて、買い手が投資回収の見通しを立てるうえで重要な指標となります。
代表的な手法として用いられるのが「DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法」です。
DCF法では、譲渡企業が今後一定期間に生み出すと見込まれるキャッシュフローを予測し、リスクや資本コストを考慮した割引率を適用して現在価値に換算します。
結果で得られる数値が、その企業の理論的な価値とされます。
ただし、正確な事業計画や収益予測が前提となるため、計画が十分に整っていない中小企業では活用が難しい場合が少なくありません。
予測値に過度な不確実性が含まれると、算定結果が変動してしまうリスクもあります。
実務ではインカム・アプローチ単独で評価を行うのではなく、マーケット・アプローチやコスト・アプローチと併用し、総合的に企業価値を判断することが一般的です。
マーケット・アプローチ
マーケット・アプローチは、株式市場での取引価格を基準にして企業価値を算定する手法です。
対象企業と同業種や規模の近い上場企業の株価や財務指標を参照し、その水準をもとに評価を行います。
市場という第三者の視点を反映させるため、客観性や透明性が高く、公正な評価方法として位置付けられています。
代表例が「類似会社比較法」と呼ばれるものです。
PER(株価収益率)やEV/EBITDA倍率などの指標を活用し、同業の上場企業と比較することで対象企業の理論的な価値を推定します。
市場参加者の評価をダイレクトに取り込める点がメリットであり、買い手と売り手双方の納得感を得やすいのも特徴です。
ただし、マーケット・アプローチは万能ではありません。
特に非上場企業や中小企業では、上場企業のように豊富な公開データが存在しないため、適切な比較対象を見つけにくいという課題があります。
また、事業規模や収益構造が異なると、単純に倍率を当てはめても実態を正しく反映できない恐れがあります。
さらに、市場全体の景気や投資家心理によって株価水準が変動するため、タイミングによって評価額が左右される点にも注意が必要です。
中堅・中小企業のM&Aにおいては、マーケット・アプローチ単独での採用は少ない傾向にあります。
コスト・アプローチ
コスト・アプローチは、企業が保有する資産と負債の差額、すなわち純資産に着目して企業価値を評価する方法です。
対象企業の収益力ではなく、財務諸表に表れる資産価値を基準に算定するため、特に不動産や設備など有形資産を多く持つ企業の評価に適しています。
手法の1つは簿価純資産法で、貸借対照表に記載された帳簿上の純資産額をそのまま評価額とします。
会計上の数値をもとにするため、計算が容易で客観性が高いです。
しかし、資産や負債の簿価が実際の時価と乖離している場合、実態を正しく反映できないというデメリットがあります。
もう1つの方法が、時価純資産法です。
資産と負債を市場価値に修正したうえで評価を行うため、より現実的な企業価値を算出できます。
ただし、将来の利益や成長可能性は加味されないため、収益性の高い企業では過小評価につながる恐れがあります。
中小企業のM&Aにおいて、時価純資産に営業権(のれん)を上乗せして評価するケースが多いです。
営業権とは、取引先との関係やブランド力、人的ネットワークなど将来の収益力を数値化したものです。
資産価値と収益力の両面をバランスよく反映でき、より実態に近い価値評価が可能となります。
株式譲渡でM&Aを実施したあとはどうなる?

株式譲渡が完了すると、手続きは一区切りつきますが、それで終わりではありません。
株主構成の変更に伴い、会社の運営体制や各種の事務手続きが必要になります。
- 社員の処遇について
- 役員の退職金について
- 税金について
M&A成立後のさまざまな事柄について紹介します。
社員の処遇について
株式譲渡の後、社員の処遇がどのようになるかが一番気になる点ではないでしょうか。
社員が解雇されてしまったら、その社員と家族は露頭に迷ってしまいます。
解雇だけではなく、これまでよりも雇用条件や労働環境が悪くなってしまうことは避けたいところです。
株式譲渡ではこれまでの契約雇用が引き継がれるため、実行後に従業員が解雇されることはありません。
しかし、給与や退職金などの雇用条件は変更になる可能性もあります。
また、労働環境においても、これまでと変わらない場合も考えられますが、部署異動や組織変更で大きく変わることも考えられます。
そのため、従業員には株式譲渡の前に丁寧に伝えることが必要です。
役員の退職金について
株式譲渡をした場合、社長や役員は会社を退職する場合と残る場合の両方が考えられます。
株式譲渡が事業継承の目的であるなら、社長や役員は時期を見て退職しますが、役員の退職金はどうなるのでしょうか。
会社を譲受した企業は退職する役員に対して退職金を支払います。
支払い額において法律上、決められた金額や倍率はありませんが多くの場合、以下の計算式で算出されます。
退職金 = 退職時の月額報酬 × 役員勤続年数 × 功績倍率
※功績倍率は2倍〜3倍が一般的です。
ここから退職所得控除が差し引かれ、さらに1/2がその年の課税対象となります。
税金について
社長(オーナー)が株式譲渡で会社を譲渡した場合、譲渡益を受け取ることになります。
その場合の税金はどうなるのでしょうか。
まず、株式の譲渡益は以下の計算式で求められます。
株式の譲渡益 = 譲渡金額 - 取得費・譲渡費用
譲渡益は分離課税として、その他の個人の収入とは分けて課税されます。
課税の種類は他の税金と同様で以下のとおりです。
所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 個人住民税5% = 税率は20.315%
(2021年6月時点)
株主が役員である場合は、譲渡益と退職金を組み合わせることで課税額を少なくできます。
株式譲渡によるM&Aの成功事例

次は、株式譲渡によるM&Aで成功した事例を紹介します。
実際の成功事例を知り、自社で株式譲渡を行うべきか検討してみましょう。
エンジャパンによるアウルスの買収
譲受企業のエンジャパンは求人サービス事業を展開している東証一部上場企業で、譲渡企業のアウルスはコンサルティング業務やデザイン開発受託を行う企業です。
エンジャパンとアウルスが実施したM&A手法は、株式譲渡と株式交換の2段階となっています。
人材領域を得意とするエンジャパンは新規ビジネスの展開を目的に、アウルスを連結子会社化しました。
M&Aにより、アウルスが持つUI/UXデザインの技術やノウハウを活かし、幅広い企業の課題解決につながるサービスを提供しています。
COMBOによるテクノモバイルへの株式譲渡
譲受企業のテクノモバイルはWebシステムとモバイルアプリの開発事業を展開している企業で、譲渡企業のCOMBOはVRやAR開発を得意とする企業です。
売り手であるCOMBOは、新型感染症の景況による経営への不安を解消するために株式譲渡による会社売却を実施しました。
買い手のテクノモバイルは、地方への事業拡大と優秀なエンジニア獲得を目的としてM&Aを実施。
COMBOはテクノモバイルに自社株式の90%を譲渡し、双方のシステム開発業務における連携体制を確立しました。
コウイクスによるSDアドバイザーズへの株式譲渡
譲受企業のSDアドバイザーズは金融業に特化したシステム開発や支援を行う企業で、譲渡企業のコウイクスはシステム開発やインフラの構築サービスを提供している企業です。
コウイクスは、社外への事業承継を目的としてSDアドバイザーズへ株式譲渡を行いました。
元々は社内で事業を引き継ぐ予定だったコウイクスですが、諸事情により社内承継が難しくなったため、M&Aを実施。
買い手のSDアドバイザーズは、非金融システムの分野へ参入するためにコウイクスを買収しました。
株式譲渡によってSDアドバイザーズの傘下企業になったコウイクスは、経理業務のデジタル化や社員の主体性向上に成功した企業です。
株式譲渡を利用してM&Aを成功させよう

この記事では、株式譲渡とは何か、メリット・デメリットについて解説しました。
株式譲渡とは、中小企業で最も使われるM&A手法で、株式と引き換えに現金を受け取る取引です。
株式譲渡をするメリットは、以下の3つです。
- 税金が抑えられる
- 手続きが簡単
- 創業者利益の獲得
株式譲渡は、他のM&Aの手続きよりも比較的簡単に実施できます。
しかし、企業の状況によっては買い手が見つからない場合があるので、M&A専門家に相談することをおすすめします。
パラダイムシフトは2011年の設立以来、豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、以下よりダウンロードしてご利用ください。