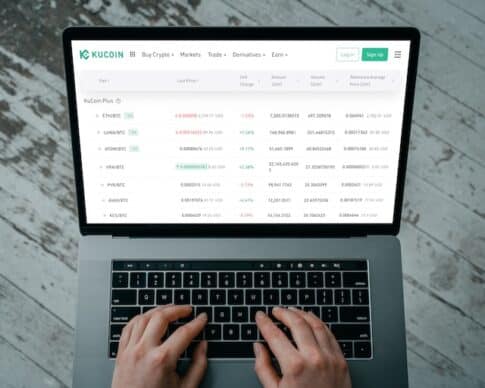経営環境の変化が激しさを増す中で、企業が持続的な成長を遂げるための戦略として事業統合が注目されています。
しかし、事業統合とは具体的に何を指し、どういったメリットやデメリットがあるのかわからない方も多くいます。また、事業統合と類似する経営統合や合併との違いについてもあまり知られていません。
今回は、事業統合の基本的な知識から具体的な手続き、成功のためのポイントまで、専門外の方にもわかりやすく解説します。本記事を読んで、事業統合に関する理解を深め、自社の成長戦略をご検討いただければ幸いです。
目次
- 1 事業統合とは?
- 2 事業統合の定義と目的
- 3 事業統合の種類
- 4 事業統合と経営統合、合併の違いを比較
- 5 事業統合と経営統合の違い
- 6 事業統合と合併の違い
- 7 各統合手法の選択基準
- 8 事業統合のメリット・デメリット
- 9 事業統合のメリット
- 10 シナジー効果による競争力強化
- 11 経営資源の効率化
- 12 新規市場への参入
- 13 事業統合のデメリット
- 14 統合プロセスの複雑さ
- 15 従業員の不安と抵抗
- 16 想定外のコスト発生
- 17 事業統合の手続きと注意点
- 18 事業統合の準備段階
- 19 デューデリジェンスの実施
- 20 統合計画の策定
- 21 事業統合の実行段階
- 22 契約締結
- 23 法的手続き
- 24 事業統合後のフォローアップ
- 25 PMI(Post Merger Integration)の重要性
- 26 事業統合後に従業員の不安を解消するポイント
- 27 組織文化の融合
- 28 人事制度の統合
- 29 コミュニケーション戦略
- 30 まとめ|事業統合で企業の成長を加速させよう
事業統合とは?

まずは、事業統合の基本的な定義や目的、どのような種類があるのかを見ていきましょう。
事業統合の定義と目的
事業統合とは、複数の企業が各々の事業の一部または全部を統合し、新たな組織体制のもとで事業運営を行うことです。
主な目的は、経営資源の集中、事業規模の拡大、競争力の強化など多岐にわたります。市場での優位性を確立し、持続的な成長を目指します。
事業統合は、単なる組織再編にとどまらず、企業の将来を左右する重要な経営判断です。
事業統合の種類
事業統合には、いくつかの種類があります。代表的なものとしては、以下の3つが挙げられます。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 吸収分割 | ある企業が営む事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の企業に承継させる手法。 |
| 新設分割 | ある企業が営む事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する企業に承継させる手法。 |
| 共同新設分割 | 複数の企業が、各々の事業を共同で新たに設立する企業に承継させる手法。 |
上記の手法は、統合の目的や当事者企業の状況に応じて選択されます。
事業統合と経営統合、合併の違いを比較

事業統合と経営統合、合併はいずれも企業再編の手法ですが、意味が異なります。本章では各用語の定義と特徴を比較し、明確に区別できるように解説します。
事業統合と経営統合の違い
事業統合と経営統合はしばしば混同されがちですが、統合範囲に違いがあります。事業統合は、特定の事業部門に焦点を当てて統合を行う一方、経営統合は企業全体の経営権を統合する包括的なアプローチです。
以下に両者の違いをまとめました。
| 比較項目 | 事業統合 | 経営統合 |
|---|---|---|
| 統合の対象 | 特定の事業部門 | 企業全体の経営権 |
| 組織構造 | 既存の法人格が残る場合も、消滅する場合もある | 多くの場合、持株企業の体制へ移行 |
| 意思決定 | 比較的、各社の独立性が保たれやすい | 持株企業によるグループ全体の戦略的意思決定が中心となる |
| 目的の焦点 | 事業レベルのシナジー追求、効率化 | グループ全体の最適化、企業価値の向上 |
事業統合と合併の違い
事業統合と合併は、法的な手続きや組織のあり方に大きな違いがあります。合併は、複数の企業が法的に一つの企業になることを指し、吸収合併と新設合併の2種類があります。
吸収合併では一方の企業が存続し、もう一方の企業は消滅するのが特徴です。新設合併では、すべての企業が消滅し、新たに設立された企業が権利義務を承継します。
これに対し、事業統合は必ずしも法人格の消滅を伴いません。特定の事業だけを切り出しての統合が可能です。
各統合手法の選択基準
統合手法の検討は、企業の目的や状況によって異なります。以下は、手法を選択する際に考慮すべき一般的なポイントです。
- 統合の範囲:特定事業のみか、企業全体か
- 統合のスピード:迅速な統合を目指すか、段階的な統合を目指すか
- 法人格の維持:既存の法人格を維持したいか
- 従業員への影響:従業員の処遇や企業文化の維持をどの程度重視するか
- 許認可の承継:事業に必要な許認可をスムーズに引き継げるか
上記の要素を総合的に勘案し、最適な手法を選択しましょう。
事業統合のメリット・デメリット

事業統合は多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、デメリットやリスクも存在します。事前の十分な検討と準備が、事業統合を成功に導く鍵です。
本章では、事業統合の主なメリットとデメリットを具体的に見ていきます。
事業統合のメリット
事業統合がもたらすメリットは多岐にわたります。主なメリットを3つ紹介します。
シナジー効果による競争力強化
事業統合の最大のメリットの一つは、シナジー効果の発揮です。シナジー効果には、主に以下の種類があります。
| シナジーの種類 | 期待される効果 |
|---|---|
| 販売シナジー | 販路の共有やブランド力の向上により、売上増加が期待できる。 |
| 生産シナジー | 生産拠点の集約や技術の共有により、コスト削減や品質向上が見込める。 |
| 開発シナジー | 研究開発力の統合により、新製品開発のスピードアップやイノベーション創出が期待できる。 |
シナジー効果により、市場における競争優位性を確立できます。
経営資源の効率化
経営資源を効率的に活用できる点も大きなメリットです。重複する管理部門の統合や遊休資産の有効活用により、コスト削減が図れます。
また、人材の再配置や育成を通じた組織全体の生産性向上も期待可能です。限られた経営資源を成長分野へ集中的に投下できます。
新規市場への参入
自社単独では参入が難しかった新規市場へのアクセスが可能になる点も、事業統合の魅力です。統合相手の企業が持つ販路や顧客基盤、技術力を活用すると、市場参入のリスクやコストを低減できます。
特に海外市場への展開や異業種への進出において有効な手段です。新たな収益源を確保し、事業ポートフォリオの多角化を図れます。
事業統合のデメリット
事業統合には、慎重に検討すべきデメリットも存在します。リスクを事前に認識し、対策を講じましょう。
代表的な3つのデメリットを紹介します。
統合プロセスの複雑さ
事業統合のプロセスは非常に複雑であり、多大な時間と労力を要します。法務、財務、人事など、多岐にわたる分野での調整が必要です。
特に、異なる企業文化を持つ組織同士をスムーズに融合させるのは容易ではありません。計画段階での綿密な準備と、実行段階での柔軟な対応が求められます。
従業員の不安と抵抗
事業統合は、従業員にとって大きな変化をもたらします。雇用の安定性や処遇、職場環境の変化に対する不安から、モチベーションを低下したり、離職を検討する人が出たりする可能性があります。
また、旧組織への愛着や新しい方針への抵抗感が生まれるケースも少なくありません。丁寧なコミュニケーションと、従業員の不安を軽減するための配慮が重要です。
想定外のコスト発生
事業統合には、想定以上のコストが発生するリスクがあります。例えば、システムの統合費用、コンサルティング費用、リストラクチャリング費用などが代表的なコストです。
また、統合後のシナジー効果が期待どおりに発揮されず、収益性が悪化する可能性も考慮しなければなりません。事前のデューデリジェンスを徹底し、現実的なコスト試算とリスク評価を行いましょう。
事業統合の手続きと注意点

事業統合を成功させるには、適切な手続きを踏み、注意すべき点を押さえておくことが重要です。準備段階から実行段階、統合後のフォローアップまで、各フェーズで慎重な対応が求められます。
本章では、事業統合の一般的なプロセスと、特に注意すべきポイントを解説します。
事業統合の準備段階
事業統合の成否は、準備段階の質に大きく左右されます。慎重かつ徹底した準備が、スムーズな統合と期待される効果の実現につながります。
デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスは、統合対象となる企業の価値やリスクを詳細に調査・分析するプロセスです。財務状況、法務関連、事業内容、人事労務など、多角的な視点から評価を行います。
調査を通じて、買収費用の妥当性や、統合後の潜在的な問題点を把握します。不十分なデューデリジェンスは、後に大きなトラブルを引き起こす可能性があるため、専門家の協力も得ながら慎重に進めましょう。
統合計画の策定
デューデリジェンスの結果を踏まえ、具体的な統合計画を策定します。計画には、以下の要素を含めるのが一般的です。
- 統合の目的と目標
- 統合後の事業戦略、組織体制
- シナジー効果の具体的な内容と創出方法
- 統合スケジュール
- コミュニケーションプラン
- リスク管理計画
明確で実行可能な計画は関係者全員の意思統一を図り、統合プロセスを円滑に進める上で重要な役割を果たします。
事業統合の実行段階
準備段階で策定した計画に基づき、実際に事業統合を実行していきます。法的な手続きを遵守し、関係者との連携を密に取りましょう。
契約締結
当事者間で統合条件について合意に至れば、事業統合の契約を締結します。契約書には、承継する資産や負債の範囲、従業員の処遇、対価の支払い方法などが詳細に規定されます。
契約内容に曖昧な点や不備がないか、法務の専門家を交えて慎重に確認しましょう。本契約が、後の統合プロセスの法的根拠としての役割を持ちます。
法的手続き
事業統合は、企業法などの関連法規に則って進める必要があります。具体的には、以下のような手続きが求められる場合があります。
- 株主総会での承認決議
- 債権者保護手続き(官報公告、個別催告など)
- 公正取引委員会への届出(一定規模以上の場合)
- 登記申請
手続きを怠ると、統合が無効になる可能性もあるため、漏れなく実施しましょう。
事業統合後のフォローアップ
事業統合は、契約締結や法的手続きが完了すれば終わりではありません。統合後の効果を最大限に引き出すための、継続的なフォローアップが極めて重要です。
PMI(Post Merger Integration)の重要性
PMIとは、経営統合の作業を指します。統合計画で描いたシナジー効果を早期に実現し、企業価値を最大化するのが主な目的です。
具体的には、経営戦略の再構築、業務プロセスの統合、組織文化の融合、人事制度の整備など、多岐にわたる活動が含まれます。PMIの成否が、事業統合全体の成果を左右すると言っても過言ではありません。
PMIを成功させるためには、以下の点が重要です。
- 経営層が統合を推進する強力なリーダーシップを発揮する
- 従業員を巻き込み、当事者意識を持たせる
- 問題発生時には迅速に対応し、遅滞なくプロセスを進める
- 定期的に進捗状況を確認し、計画との差異を評価・改善する
事業統合後に従業員の不安を解消するポイント

事業統合は従業員にとって大きな環境変化を伴うため、不安や混乱が生じやすくなります。従業員のモチベーションを維持し、円滑な統合を実現するためには、彼らの不安を解消する取り組みが不可欠です。
本章では、事業統合後に従業員の不安を解消するポイントを4つ紹介します。
組織文化の融合
異なる背景を持つ企業同士が統合する場合、組織文化の違いが摩擦を生むことがあります。新しい企業文化を創造するためには、双方の文化を尊重しつつ、共通の価値観や目標を育む努力が必要です。
具体的に意識すべきポイントは、以下のとおりです。
- ワークショップや交流イベントなどを通じて、従業員間の相互理解を深める
- 経営層から新しい企業理念や経営方針を明確に伝え、共感を醸成する
- 統合後に達成された小さな成功を共有し、一体感を高める
時間をかけて丁寧に組織文化の融合に取り組むことが、長期的な成功につながります。
人事制度の統合
人事制度(評価、処遇、キャリアパスなど)の統合は、従業員の関心が高い事項の一つです。公平性・透明性の高い制度設計と、丁寧な説明が求められます。
以下に、人事制度の統合に関する主な課題と対応策をまとめました。
| 課題 | 対応策 |
|---|---|
| 評価基準の不統一 | 新しい評価基準を明確に設定し、全従業員に周知徹底する。 |
| 処遇格差への不満 | 統合後の役割や貢献度に応じた、納得感のある処遇体系を構築する。 |
| キャリアパスの不透明感 | 新しい組織でのキャリア展望を示し、成長機会を提供する旨を明言する。 |
| コミュニケーション不足による誤解 | 制度変更の背景や目的、内容について、説明会や個別面談を通じて丁寧に説明する。 |
従業員が安心して働ける環境の整備が、人材の定着と組織の活性化に不可欠です。
コミュニケーション戦略
事業統合のプロセス全体を通じて、従業員との積極的なコミュニケーションが極めて重要です。以下のポイントを踏まえて情報開示の透明性を高め、不安や疑問に迅速に対応すると、信頼関係の構築につながります。
- 統合の進捗状況や今後の見通しについて、定期的に情報発信を行う
- 質疑応答の機会や意見交換の場を設け、従業員の声を吸い上げる
- 社内報やイントラネット、説明会など、さまざまな手段で情報伝達を行う
経営層からのメッセージを一貫して発信し続けると、従業員の安心感を醸成できます。
まとめ|事業統合で企業の成長を加速させよう

適切な事業統合は、企業の競争力を高めて持続的な成長を実現するための強力な手段です。
しかし、プロセスは複雑であり、多くの課題を伴うのも事実です。以下に、事業統合を成功させるための重要なポイントを再掲します。
- 何のために事業統合を行うのか、明確な方針を持つ
- 徹底したデューデリジェンスでリスクを事前に把握し、適切な判断を下す
- 綿密な統合計画で、リスクへの対応策を準備する
- 効果的なPMIで、統合後のシナジー効果を最大化する
事業統合は、企業にとって大きな決断です。専門家のアドバイスも活用しながら、自社に最適な成長戦略を描いていきましょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。