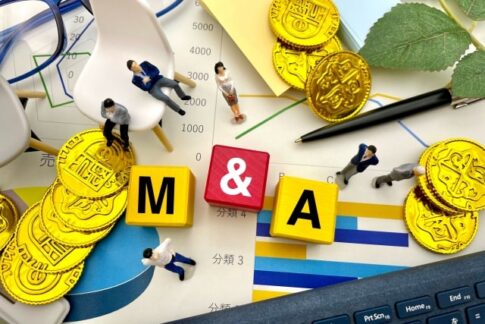経営者の高齢化と後継者不足などによって、会社の売却を決断する経営者が増えてきました。
会社売却・事業売却の手段として、最も多く活用されているのがM&Aです。
M&Aとは「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略称であり、企業や事業の合併・買収のことです。
中小企業庁によれば、国内のM&A件数は右肩上がりで増加しており、高水準を維持しています。
この記事では、M&Aによる会社売却の定義や最終合意までのプロセスや事業売却との違い、事業売却のメリット・デメリットを解説します。
M&Aにおける会社売却・事業売却の基本がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 1 M&Aによる会社売却とは?
- 2 売却と合併との違いは?
- 3 M&Aによる会社売却のプロセス
- 4 M&Aの準備
- 5 トップ会談
- 6 基本合意の締結
- 7 デューデリジェンス
- 8 最終合意の締結
- 9 M&Aによる会社売却のメリット
- 10 会社や事業を存続させられる
- 11 経営者がキャッシュを獲得できる
- 12 従業員の雇用を維持できる
- 13 M&Aによる会社売却のデメリット
- 14 顧客や取引先から反発される
- 15 買い手が見つからないことがある
- 16 M&Aによる事業売却とは?
- 17 会社売却との違いは?
- 18 M&Aによる事業売却のメリット
- 19 会社の商号を売却後も使用できる
- 20 主力事業に注力できる
- 21 事業の売却益を得られる
- 22 M&Aによる事業売却のデメリット
- 23 事業ごとに財務諸表の作成が必要になる
- 24 売却事業と同じ事業をできなくなる
- 25 事業を売却した後の会計処理
- 26 買い手側
- 27 売り手側
- 28 事業売却を検討する際の相談先
- 29 M&A仲介会社
- 30 FA(ファイナンシャル・アドバイザー)
- 31 M&Aによる会社売却には入念な準備が必要
M&Aによる会社売却とは?

M&Aとは企業の合併買収を指し、M&Aによる会社売却とはM&Aによって第三者に会社を売却することです。
具体的には、売り手企業が非上場企業の中小企業の場合、売り手企業の経営者が保有する自社株を買い手企業である第三者にすべて売却します。
買い手企業は株式を取得することで、売り手企業の経営権など会社に関連するさまざまな権利や義務を承継することが一般的です。
権利や義務を引き継ぐことを株式譲渡といい、M&Aによる会社売却は株式譲渡によって実行されます。
売り手企業の経営者は自社株の売却の対価として、買い手企業から現金を受け取ります。
売却と合併との違いは?
会社を売却する方法には、売却と合併の2種類です。
株式譲渡による会社売却では、売り手企業が買い手企業に株式を譲渡し、会社の経営権を引き継ぎます。
この場合、M&Aが実行された後も、売り手と買い手の両方の会社は存続し続けます。
一方で合併とは、複数の会社が一つになることです。
合併される会社(消滅会社)は、合併する会社(存続会社)に事業や資産、社員のすべてを統合され、M&Aの実行とともに法人格を失います。
M&Aの前後で、元の会社が存続するか消滅するかどうかが売却と合併の大きな違いです。
M&Aによる会社売却のプロセス

事業承継対策などでM&Aによる会社売却を検討する経営者の方も多いでしょう。
確実に会社売却を成功させるためには双方が合意しながら、手続きを一つ一つ丁寧に進めることが大切です。
法的拘束力のある手続きもあるので、事前にしっかり確認しましょう。
ここからは、M&Aによる会社売却の流れについて解説します。
M&Aの準備
M&Aの相手企業と会談する前に事前に準備が必要です。
まずはM&Aの目的や条件を検討しましょう。
特に条件については、売却価格や売却のスキーム、売却の時期などを明確にしておきます。
次にM&A仲介会社を選定しましょう。
円滑な交渉のためにM&A仲介会社が必要になります。
事前に決めた目的や条件を伝えて、理解してくれる仲介会社がいいでしょう。
M&A仲介会社は売り手企業の名前を伏せたまま会社概要を記載したリストを公開します。
興味のある買い手企業が仲介会社に接触してくるので、条件に合致した買い手企業のなかから交渉に進みたい企業を選定しましょう。
トップ会談
条件に合致する買い手企業が見つかったら、経営者同士のトップ会談に進みます。
トップ会談はお見合いのようなもので、双方の企業のビジョンや運営方針、経営方針などを共有し、お互いの理解を深めます。
会談は何度か実施して双方の意思が固まったら、交渉に進みましょう。
条件面についても詰めていきますが、最もタフな交渉になるのが売却価額です。
少しでも高く売りたい売り手と、安く買いたい買い手が双方の妥協点を探りながら、適切な価額を決定します。
売却価額はさまざまな評価方法がありますが、M&A仲介会社の双方が納得のいく方法で算定することが一般的です。
基本合意の締結
トップ会談後に双方の経営者がM&A実施に合意したら、基本合意の締結に進みます。
交渉の段階で双方が合意した事項について基本合意書に記載し、経営者が押印します。
- 売却価額
- 売却スキーム
- 今後のスケジュール
- デューデリジェンス
- 独占交渉権の付与
- 秘密保持義務
- 保証債務
- 一般条項
- その他の合意事項
ちなみに、基本合意書には法的拘束力を持たせないのが一般的です。
合意によって双方を縛るというよりは、合意した内容を文書に残すという意味合いが強いです。
法的拘束力はないが、基本合意が締結されれば、成約に向けて双方が動き出します。
デューデリジェンス
M&Aにおけるデューデリジェンスとは、売り手企業やその事業に関する情報を収集、分析及び検討する手続きです。
弁護士や公認会計士などに依頼して、売り手企業の財務や法務、財務、人事、ITシステムなどについて精査し、問題点やリスクなどを洗い出します。
デューデリジェンスは売り手企業が開示した情報が実態と乖離していないかを確認する作業でもあり、新しく問題点が見つかった場合には信用に関わります。
デューデリジェンスが始まる前の段階で、最大限の情報開示を行いましょう。
問題点やリスクが発見されれば、既に合意した売却価額の引き下げや条件の変更、最悪の場合にはM&Aの中止となります。
最終合意の締結
デューデリジェンスが完了し、双方の経営者がM&A実施について意思が確定したら、最終合意を締結します。
正確には「最終合意書」という名称ではなく、売却スキームが株式譲渡であれば「株式譲渡契約書」という名称となります。
最終合意書に記載する事項は、以下のとおりです。
- 売却価額とその根拠
- 表明保証
- 補償条項
- 誓約事項
- 前提条件
- 解除条件
- 債務不履行と損害賠償責任
- 秘密保持条項
- 競業避止義務
最終合意は弁護士による内容確認の後に双方が合意するものであり、法的拘束力が発生します。
なお、最終合意には債務不履行と損害賠償に関する規定があるので、解約の申し出をする場合には相手に損害賠償をする義務が生じます。
最終合意締結前には、M&A実行の可否について十分な検討が必要です。
M&Aによる会社売却のメリット

中小企業庁が公表した「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」によれば、M&A自体の件数は伸び、事業承継型のM&Aも増加傾向にあります。
このように多くの中小企業がM&Aによる会社売却を決断している背景には何があるのでしょうか。
ここからは、M&Aによる会社売却のメリットを解説します。
会社や事業を存続させられる
売上が上がっていても後継者が不在のまま経営者が引退すると、会社は廃業となります。
廃業すれば、会社を支えてきた社員は職を失い、取引先は取引相手を失います。
また、廃業に際しては現金や在庫、設備、土地などすべての保有資産を換金して、負債を返済しなければなりません。
資産の多くは簿価以下で換金されるので、負債を返済するために十分な現金を準備できないことも多いです。
廃業は簡単に実施できるものではなく、ハードルが高いといえます。
しかし、M&Aによって会社を売却すれば、雇用は守られ、取引関係も維持し、負債の即時返済の必要もありません。
経営者がキャッシュを獲得できる
M&Aによる会社売却は、株式譲渡によって実施されます。
株式譲渡では、売り手企業の株主が買い手企業に保有株式を譲渡する方法です。
中小企業の場合、経営者が自社株式のほとんどを保有していることが多いでしょう。
経営者は自社の株式を売却して現金を得られ、引退後の生活資金や老後の資金を確保できます。
また、経営者が会社の債務の連帯保証人である場合、買い手企業が債務を承継するので、経営者が債務から解放されます。
こうして得た現金を元手に、新しい事業を始めたり、引退後の人生を自由に楽しんだりすることが一般的です。
従業員の雇用を維持できる
中小企業庁によれば、8割以上のケースでM&A後に従業員の雇用が完全に維持されています。
後継者不足で会社が廃業した場合、従業員は解雇となり、仕事を失います。
これまで事業を支えてきた従業員を解雇することは経営者として厳しい決断です。
景気状況によっては従業員が次の仕事を見つけられず、生活に窮することもあるでしょう。
M&Aによって会社売却に成功すると、買い手企業によって従業員の雇用が継続されます。
事業を支えてきた高度なスキルや技術を持つ従業員の雇用が継続されれば、新しい雇用主の元で事業がさらに発展するでしょう。
M&Aによる会社売却のデメリット

事業承継の解決手段として幅広く活用されているM&Aによる会社売却ですが、M&A特有の問題点もあります。
M&Aは取引先や株主、顧客などのステークホルダーに多大な影響を与えるため、メリットだけではなく、デメリットも考慮して実施の可否を検討しましょう。
ここからは、M&Aによる会社売却のデメリットについて解説します。
顧客や取引先から反発される
M&A実施によって取引先から反発を受けて、契約条件の変更、最悪の場合には取引を停止されることがあります。
また、BtoB企業の場合には顧客企業から仕入れを中止されることがあるかもしれません。
M&Aによって、取引先や顧客との契約内容を修正せざるを得なかったり、取引先の競合他社を利するような結果となったりした場合に発生することが多いです。
中小企業の場合、売上のほとんどを特定の企業に依存している場合があります。
このような場合に取引が打ち切りとなることは、致命的な打撃となるでしょう。
買い手が見つからないことがある
M&Aを検討した企業多くが、交渉に至る前にM&Aを断念しています。
断念した理由の一つに、「相手先が見つからなかった」を挙げている企業も少なくありません。
中小企業にとってM&Aは会社の廃業を防ぐ有効的な方法です。
しかし、多くの中小企業が経営者の高齢化と事業承継という問題に直面する中で「会社を売りたい」と考える企業が増えています。
M&Aは買い手市場となっており、業績が悪い企業や売却希望企業の多い業種では、相手先を見つけることができずに断念せざるを得ない場合があります。
M&Aによる事業売却とは?

M&Aによる事業売却は、経営戦略の一環として特定の事業を第三者に売却するプロセスを指します
これに対して、会社売却は企業自体の株式を完全に第三者に譲渡する取引です。
ここからは、2つの売却の違いについて詳しく説明します。
会社売却との違いは?
M&Aによる事業売却と会社売却の違いは、売却の対象や売却対価、消費税の課税対象などで異なります。
事業売却では一部もしくは全部の事業を売却しますが、会社全体の経営権は変わりません。
一方、会社売却は会社そのものの経営権を譲渡します。
| 会社売却との違い | 概要 |
| 売却の対象 |
|
| 売却対価の受領者 |
|
| 消費税の課税対象の有無 | 事業売却では、一部の資産に消費税が課税される場合がありますが、会社売却は株式の売買であるため、消費税の課税対象外になる |
事業売却と会社売却は、異なる取引方法と税制上の影響を持ちます。
適切な売却戦略は、売却対象や目的に応じて選択しましょう。
M&Aによる事業売却のメリット

M&Aによる事業売却は、売り手側企業に多くのメリットをもたらします。
ここからは、事業売却によって得られる売り手側のメリット3つについて解説します。
会社の商号を売却後も使用できる
売却側のメリットで注目すべきなのは、「会社の商号を売却後も使用できる」という点です。
事業売却ではなく会社売却を選択した場合、買い手が会社の商号を保持し続ける権利を持つので、売り手は商号を失います。
しかし、事業売却を選択した場合は、商号を保持し続けることができるため、歴史やブランド価値があると大きな価値になります。
愛着のある商号を維持することで、過去の成功や信頼を引き継ぎ、将来のビジネス展開にも活用できる点が有利です。
主力事業に注力できる
M&Aによる売り手側の事業売却には、主力事業への注力がもたらすメリットがあります。
主力事業や黒字事業に注力することで、以下のような効果をもたらします。
- 経営の安定化
- 赤字リスク軽減
- 人材や設備の集中
事業売却から受け取った資金を主力事業に注入することで、黒字分野の拡大や安定化を推進することができ、企業価値を上げていくことに繋がります。
事業の売却益を得られる
M&Aによる事業売却の最大のメリットは、事業売却の売却益です。
事業売却から得た資金は、以下のような用途に活用できます。
- 企業運営に安定性をもたらすための運転資金
- 返済に充てることで財務健全性が高まる
- 新規事業に投資して企業を成長させる
事業売却は企業にとって、資金調達や経営の最適化に役立つ手段となるのです。
M&Aによる事業売却のデメリット
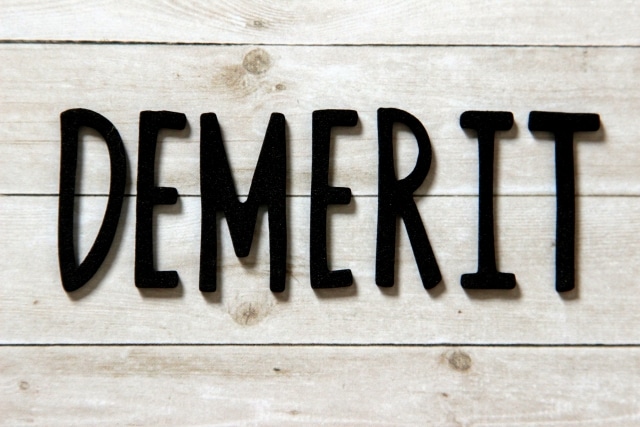
M&Aによる事業売却には、さまざまなメリットが売り手側にありますが、同時にデメリットも存在します。
ここからは、2つの事業売却の売り手側のデメリットに焦点を当てて対策も解説します。
事業ごとに財務諸表の作成が必要になる
M&Aにおける売り手側の事業売却デメリットの一つは、事業ごとに財務諸表を作成する必要があることです。
財務諸表の作成は煩雑で時間を要しますが、売却予定の事業ごとに売却価格や売却益(あるいは売却損)を正確に算定するためには欠かせません。
時間の浪費をしかねない財務諸表作成を軽減する対策には、以下のようなものが考えられます。
- 売却を検討する前から財務データを整理して整合性を持たせる
- M&Aアドバイザリーなどを活用して財務諸表の作成や評価をサポートしてもらう
- 財務データの自動化ツールやソフトウェアを導入する
- 財務諸表作成時間をあらかじめ売却プロセスのスケジュールに組み込んでおく
事前に対策を考えておき、財務諸表の作成などの事業売却におけるデメリットを軽減しましょう。
売却事業と同じ事業をできなくなる
事業売却による売り手側のデメリットには、競業避止義務による「同じ事業を一定の期間・地域で行えなくなる」という点があります。
事業売却をした売り手側企業が売却後も同じ事業をしてしまうと、買い手側企業が事業買収で計画していた事業の目的が達成できなくなる可能性があるからです。
売り手側のデメリットに対処するためには、以下の方法が考えられます。
- 売買契約書の競業避止義務において、売り手側と買い手側の双方が納得できる条件を設ける
- 売却前に、売却対象の事業とは異なる新たな事業領域への投資や展開を検討する
- ブランドやノウハウを他の地域や新たな事業に活用する方法を模索する
- 弁護士や法律専門家のアドバイスを受けて戦略を立てておく
競業避止義務は事業売却において一般的な規定ですが、適切に対処すれば売り手側が将来の事業展開に制約を受けることを最小限に抑えられます。
事業を売却した後の会計処理
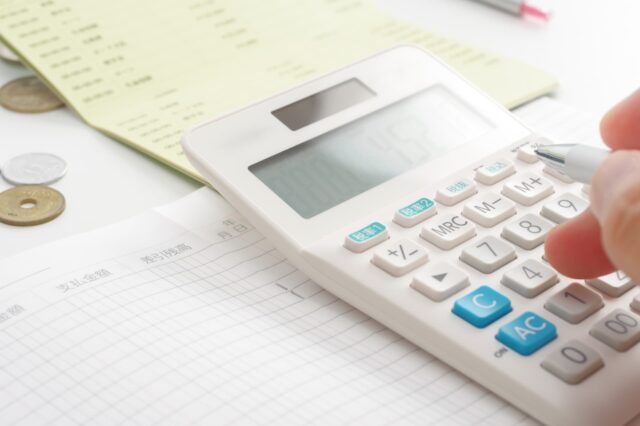
M&Aや事業譲渡の手続きが完了しても、経理や財務の業務は終わりではありません。
売却益の計上方法や固定資産、のれんの処理、税務上の取り扱いなど正確な会計処理が求められます。
特に中小企業や個人事業主にとっては、専門的な知識が必要となる場面も多く、誤った処理をしてしまうと後にトラブルに発展する可能性が高いです。
事業売却後の会計処理を買い手側と売り手側に分けて解説します。
買い手側
買い手企業が事業を取得すると、取得対象資産の時価評価と会計処理が必要になります。
固定資産や棚卸資産など譲渡された資産や負債を個別に時価評価し、取得価格を按分して仕訳計上することが一般的です。
たとえば、A事業の諸資産8,000万円・諸負債3,000万円を6,000万円で取得した場合、借方に諸資産8,000万円・のれん1,000万円、貸方に現預金6,000万円・諸負債3,000万円と仕訳します。
有形固定資産や棚卸資産、従業員退職引当金などは取得日現在の時価で引き継ぎ、取得原価との差額はのれん(超過収益力)として計上します。
のれんは将来的な収益力として償却や減損処理の対象となるため、財務諸表上で注意深く管理しなければなりません。
また、買収費用は支払時に費用計上します。
のれん以外にも契約書作成費やデューデリジェンス費用などの関連費用は取得時の費用として計上されることがほとんどです。
買い手企業は、税務面でも譲渡対象の資産区分やのれんの償却方法を確認し、専門家の助言を受けたうえで適切に処理しましょう。
売り手側
売り手企業は、譲渡した事業に関連する資産や負債を帳簿から除き、譲渡代金との差額を「事業譲渡益」または「事業譲渡損」として処理します。
例としてA事業(諸資産5,000万円・諸負債3,000万円)を4,000万円で売却した場合、貸方に諸資産5,000万円・事業売却益2,000万円、借方に諸負債3,000万円・現預金4,000万円と仕訳します。
帳簿価額より高い価額で売却すれば差額が譲渡益、低い価額で売却すれば譲渡損です。
また、仲介手数料や弁護士費用など譲渡に直接かかった費用は売却価額から差し引いて損益を計算できます。
譲渡益が発生した場合は、法人税等の課税対象です。
譲渡に伴う仲介手数料や弁護士費用、その他の関連費用は譲渡損益の計算上、譲渡価額から控除することが認められています。
従業員の移籍がある場合は退職給付引当金の調整も必要となり、譲渡後の給与負担が減少するため引当金の戻入れ益が出る場合もあります。
さらに、売却事業に関連する債務保証や訴訟リスクが残る場合は偶発債務として注記が求められることもあり、契約内容を踏まえた慎重な会計処理が必要です。
事業売却を検討する際の相談先

事業売却を成功させるには、適切なパートナー選びが重要です。
専門知識が求められるM&A分野では、各相談先の役割や強みを理解することで、手続きや交渉、デューデリジェンスなど複雑なプロセスを円滑に進められます。
代表的な相談先であるM&A仲介会社とFAの2つを紹介します。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、売り手企業と買い手企業の橋渡し役を担い、取引を円滑に進める専門組織です。
中立的な立場で双方のニーズを調整し、交渉条件のすり合わせや秘密保持体制の構築、基本合意書の策定支援まで幅広く関与します。
相手先の発掘から交渉、クロージングまで一貫してサポートするため、特に中小企業のM&Aでは仲介会社の活用が一般的です。
収益モデルは売り手と買い手企業双方からの成功報酬が中心であり、成約額に応じた手数料が設定されています。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)
FAは、売り手または買い手のいずれかと専属契約を結び、M&A取引で最適な成果を引き出すことを目的に助言や交渉を担います。
大規模案件での利用が主流で、証券会社や銀行、M&A専門のコンサルティングファームなどがサービスを提供しています。
売却価格の算定支援や資金調達戦略の立案、税務面の最適化提案など、複雑な財務・会計課題に対応可能です。
また、交渉局面では相手との条件調整をリードし、取引構造の設計からデューデリジェンス対応まで一貫したサポートを行う点が特徴です。
M&Aによる会社売却には入念な準備が必要

この記事では、M&Aによる会社売却の特徴や具体的な手続き、事業売却との違い、事業売却のメリット・デメリットを解説しました。
M&Aによる会社売却・事業売却は、戦略的なプロセスを必要とする過程で多くの要因を検討する必要があります。
事業承継問題の解決や経営者の創業者利益の獲得、主力事業へ注力など、M&Aはさまざまなメリットがあり、多くの中小企業がM&Aによる会社売却・事業売却を検討・決断しています。
しかし、M&Aの準備から最終合意に至るまで専門的な手続きを踏む必要があり、実際にM&Aを実施するためには入念な準備と知識が必要です。
M&Aを検討している場合には、潜在的なリスクとリワードのバランスを取ることができる専門家に相談しましょう。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。