M&A戦略や事業承継、資本政策の見直しにおいて、自己株式の取得を検討されるケースは少なくありません。自己株式取得の際に注意すべき重要な税務上の論点が、「みなし配当」です。自己株式の取得価額が、株式に対応する資本等の金額を超える場合、超過額は配当とみなされ、株主側で配当所得として課税される可能性があります。
みなし配当は意図せず発生し、株主への課税に影響を与えるだけでなく、M&Aのスキームや条件交渉にも関わります。特に非公開株式の取引は評価や税務処理が複雑です。
この記事では、自己株式のみなし配当について基礎知識から具体的な計算方法、手続き、注意点まで網羅的に解説します。この記事を読むことで、みなし配当への理解を深め、適切な税務対応やスキーム検討を進めるための助けとなるでしょう。
目次
- 1 自己株式のみなし配当の基礎知識
- 2 みなし配当の定義と自己株式取得における意義
- 3 みなし配当課税の対象となる自己株式取得
- 4 みなし配当の税務上の取り扱い
- 5 【個人・法人別】自己株式のみなし配当手続きと必要書類
- 6 法人の場合
- 7 個人の場合
- 8 【ケース別】自己株式のみなし配当の計算方法
- 9 株主への対価が資本剰余金を超える場合
- 10 株主への対価が利益剰余金を超える場合
- 11 株主への対価が資本剰余金と利益剰余金の合計を超える場合
- 12 【計算例】自己株式のみなし配当額
- 13 自己株式のみなし配当で押さえておくべきポイント
- 14 みなし配当課税を回避する
- 15 種類株式を活用する
- 16 税務専門家との連携をスムーズにする
- 17 みなし配当が発生しない自己株式取得の条件
- 18 取得価額が資本等の金額以下である場合
- 19 完全子会社による親会社からの取得
- 20 会社法上の組織再編に基づく取得
- 21 まとめ:自己株式のみなし配当を正しく理解し、適切に対応しよう!
自己株式のみなし配当の基礎知識
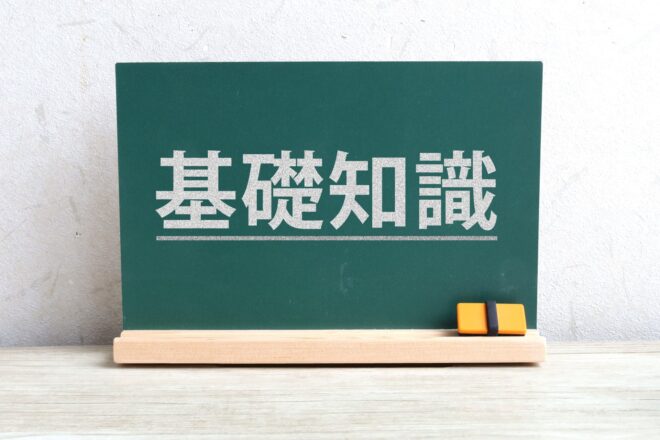
自己株式の取得を検討する上で押さえておきたいのが、みなし配当の基本的な考え方です。みなし配当とは、会社が自己株式を取得する際に、株主への支払額の一部が税務上「配当」とみなされる制度を指します。
ここでは、みなし配当とは具体的に何を指すのか、どのような自己株式取得が課税対象となるのか、基礎から解説していきます。
みなし配当の定義と自己株式取得における意義
みなし配当とは、通常の剰余金配当とは異なり税法上の特有な概念です。会社が自己株式を有償で取得する際に、株主へ支払う対価のうち株式に対応する「資本金等の額」(株主の出資に相当)を超える部分を指します。超過額は、会社に蓄積された利益剰余金が株主に払い戻されたものとみなされます。
自己株式の取得という形式上は資本取引であるものの、実質的には利益の分配であると見なすことで、適正な課税を実現するための制度です。
みなし配当課税の対象となる自己株式取得
みなし配当課税の対象となるのは、原則として会社が「有償」で自己株式を取得するすべてのケースです。株主に支払う取得価額が、対応する株式lの「資本金等の額」を上回る場合、超過額に対して課税が生じます。市場での買付けや公開買付け(TOB)に加え、特定の株主から直接買い取る相対取引も対象です。
M&A準備や事業承継などの取得の目的、取得資金の出所にかかわらず、上記の条件を満たす場合は、みなし配当が発生する可能性があると理解しておくことが重要です。
みなし配当の税務上の取り扱い
みなし配当された金額は、株式を譲渡(売却)した株主において、通常の株式譲渡益(キャピタルゲイン)とは区別され、「配当所得」として課税されます。個人株主の場合、みなし配当された配当所得は、原則として総合課税の対象となります。ただし、上場株式等に該当する場合には、申告不要制度や申告分離課税を選択することも可能です。
一方で、法人株主が受け取るみなし配当については、一定の要件を満たすことで「受取配当等の益金不算入制度」が適用され、課税を免れる場合があります。自己株式を取得し対価を支払う会社側には、みなし配当部分に対して所得税の源泉徴収義務が発生する点にも注意が必要です。
【個人・法人別】自己株式のみなし配当手続きと必要書類

自己株式の取得でみなし配当が発生した場合の税務処理に関して、支払う会社側と受け取る株主側の双方で所定の手続きが必要となります。特に、株主側での確定申告などの手続きや必要書類は、株主が法人であるか個人であるかによって異なります。
ここでは、それぞれの立場別に、みなし配当発生時における主な手続きの流れと、関連する書類について解説します。
法人の場合
自己株式を譲渡し、みなし配当を受け取る株主が法人である場合、法人は法人税の確定申告において、受け取った金額を益金(収益)として計上します。ただし、一定の要件を満たせば、「受取配当等の益金不算入制度」が適用され、みなし配当の全額または一部が課税所得から除外されます。
制度の適用を受けるには、所定の計算を行い、関連する別表に正しく記載することが必要です。一方、みなし配当を支払う会社は、支払先が内国法人である限り、原則として所得税の源泉徴収は不要です。ただし、「配当等とみなす金額に関する支払調書」を作成し、税務署へ提出しなければなりません。
個人の場合
個人株主が自己株式の譲渡によってみなし配当を受け取った場合、金額は原則として「配当所得」として取り扱われます。配当所得は、給与所得など他の所得と合算して総所得金額を算出し、累進税率が適用される「総合課税」の対象です。一定の要件を満たすことで、配当控除の適用を受けることも可能です。
一方、みなし配当を支払う会社側には、個人株主に対して支払う際、所定の税率に基づいて所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、国へ納付する義務があります。「配当等とみなす金額に関する支払調書」を税務署に提出し、通常は株主本人にも源泉徴収税額などを記載した支払調書の写し等を交付します。
【ケース別】自己株式のみなし配当の計算方法

みなし配当の基本的な考え方を理解したところで、具体的な金額の計算方法を見ていきましょう。みなし配当の額は、株主への支払対価から対応する株式の「1株当たり資本金等の額」を差し引いて算出します。ただし、会社の資本構成、特に資本剰余金や利益剰余金の残高との関係で、計算結果の解釈や影響が異なる場合があります。
ここからは、いくつかのケース別に自己株式のみなし配当の計算方法を解説します。
株主への対価が資本剰余金を超える場合
みなし配当の金額は、原則として次の計算式により算出されます。
みなし配当額 = 取得対価 −(1株当たり資本金等の額 × 取得株式数)
資本金等の額には、資本金に加え、資本準備金やその他資本剰余金なども含まれます。算出された金額は、利益剰余金を原資とする配当とみなされ、税務上の処理が必要となります。支払対価が資本剰余金の残高を超えるかどうかは、課税関係とは別に、会社の資本構成や財務戦略に関わる事項として検討しましょう。
株主への対価が利益剰余金を超える場合
みなし配当額の計算には、次の基本的な式が用いられます。
みなし配当額 = 取得対価 −(1株当たり資本金等の額 × 取得株式数)
上記の計算式は、株主に支払われる対価が会社の利益剰余金の残高を超える場合でも、原則として適用されます。
「支払対価が利益剰余金を超える」という状況は、会社法上、分配可能額の範囲や支払い後の剰余金の構成に影響する重要な論点です。ただし、みなし配当額の計算式そのものが変更されることはありません。算出された金額は、株主において配当所得として課税対象となります。
株主への対価が資本剰余金と利益剰余金の合計を超える場合
みなし配当額の計算に用いる基本式は、以下の通りです。
みなし配当額 = 取得対価 −(1株当たり資本金等の額 × 取得株式数)
上記の計算式は、株主への支払対価が会社の「資本剰余金と利益剰余金の合計額」を超える場合でも、税務上のみなし配当額を算出する際には原則として適用されます。
支払対価が剰余金の合計を上回るという状況は、株主への支払いが利益の蓄積(利益剰余金)、および過去の資本取引による剰余金(資本剰余金)だけでは賄えていない可能性を示唆します。会社法上の分配可能額を超える違法配当に該当するおそれがあるため、経営上も重大な問題となり得るでしょう。
【計算例】自己株式のみなし配当額

これまでの解説をもとに、実際の数値を使ってみなし配当額を計算した例は以下のとおりです。
- 取得株式数:100株
- 1株あたりの取得対価:8,000円(総額:800,000円)
- 1株あたり資本金等の額:5,000円
みなし配当額 = 800,000円 −(5,000円 × 100株)= 300,000円
上記の計算例の場合、株主が受け取る80万円のうち、30万円が配当所得として課税対象です。残りの50万円は株式譲渡による対価として取り扱われます。
自己株式のみなし配当で押さえておくべきポイント

みなし配当の単純な税務処理だけでなく、課税をどうコントロールするか、どのような手法が有効か、といった戦略的な視点が求められます。
ここでは、自己株式のみなし配当で押さえておくべきポイントを解説します。
みなし配当課税を回避する
みなし配当課税を回避する基本的な方法は、自己株式の取得に際し、株主への支払対価を「1株当たり資本金等の額」以下に抑えることです。みなし配当額は、「取得対価 −(資本金等の額 × 株式数)」で算出されるため、対価が資本金等の額を超えなければ課税対象とはなりません。
ただし、会社の企業価値が上昇している場合、実勢価格が資本金等の額を上回るため、紹介した方法を現実的に採用するのは難しいです。
種類株式を活用する
会社法では、普通株式とは異なる権利内容を持つ「種類株式」の発行が認められています。種類株式の制度を利用することで、自己株式取得時の条件をあらかじめ設計することが可能です。例えば、特定株主の保有株式を「取得条項付株式」として発行し、将来的に会社が一定の事由に基づいて取得できるように設定します。
取得対価を「1株当たり資本金等の額」以下に定めておけば、実際の取得時にみなし配当課税を回避できる可能性があります。ただし、種類株式の設計や運用には、法務・税務両面で高度な検討が必要です。取得対価の妥当性や他の株主との公平性を含め、事前に専門家の助言を受けながら慎重に対応しましょう。
税務専門家との連携をスムーズにする
自己株式取得に関するみなし配当の税務は、資本金等の額の算定方法や株主ごとの課税関係の判定、会社法との整合性など、多くの要素が絡む高度な分野です。判断を誤ると、会社や株主にとって予期せぬ追徴課税や手続き上の不備が生じるおそれがあります。
税務上のリスクを回避するには、税理士など税務の専門家と連携しながら進めることが不可欠です。特に、自己株式取得やM&Aなどの計画段階から早期に相談を始めることで、適切なスキーム選定や課税リスクの洗い出しが可能です。
みなし配当が発生しない自己株式取得の条件

自己株式を有償で取得する場合、原則としてみなし配当課税の可能性があります。ただし、法律上、特定の条件を満たす自己株式の取得については、例外的にみなし配当が発生しないと定められています。みなし配当が発生しない条件を知っておくことは、意図しない課税を避けられ、適切な取引スキームを検討する上で重要です。
ここでは、みなし配当課税の対象外となる主なケースについて解説します。
取得価額が資本等の金額以下である場合
みなし配当が発生しないための基本的な条件は、自己株式の取得価額(株主への支払額)が、対応する株式の「資本金等の額」を超えないことです。みなし配当額の基本式「取得対価 − 資本金等の額」に基づいて導かれる考え方です。
取得対価が資本金等の額以下であれば、計算上、みなし配当額はゼロまたはマイナスとなるため、配当所得としての課税対象にはなりません。株主への支払いは、あくまで出資の払い戻しにとどまるため、会社の蓄積利益の分配とは扱われません。結果、株主が受け取った対価の全額は株式譲渡による収入とされるため、譲渡所得(キャピタルゲイン)の計算対象となり、配当所得としての課税は生じません。
完全子会社による親会社からの取得
子会社が、すべての発行済株式を保有する直接の親会社(完全親会社)から自己株式を有償で取得する場合、原則としてみなし配当は発生しません。法人税法第24条第1項第1号等により、完全支配関係(100%直接または間接保有)のある法人間での自己株式の取得は、みなし配当課税の対象外とされているからです。
100%グループ内における株式の移動が、実質的には利益の分配ではなく、グループ内の資本構成の調整とみなされるという考え方に基づいています。親会社側では配当所得課税は行われず、株式の譲渡損益として処理されます。
会社法上の組織再編に基づく取得
合併や会社分割、株式交換、株式移転など、会社法に定められた組織再編の過程で、会社が自己株式を取得する場面があります。たとえば、合併により消滅会社が保有していた株式を存続会社が引き継ぐ場合や、再編に反対した株主から株式買取請求権に基づき株式を取得する場合などが代表的です。
税法上の適格組織再編に該当する場合には、再編に伴う自己株式の取得について、原則としてみなし配当課税は適用されません。再編が非適格と判定される場合や、取引内容に特有の事情がある場合には課税関係が異なるため、事前に税務専門家へ確認することが重要です。
まとめ:自己株式のみなし配当を正しく理解し、適切に対応しよう!

自己株式取得によるみなし配当は、過去の資本取引を反映する「資本金等の額」の算定が煩雑になりがちです。株式を譲渡する株主が個人か法人か、あるいは居住者か非居住者か等によって、適用される税率などが異なります。みなし配当の複雑さが、M&Aや事業承継、資本政策における自己株式取得の検討を難しくしているのです。
十分な検討をしないで進めることで、株主には想定外の配当所得課税が、会社側には源泉徴収漏れなどのリスクが生じるため悪影響を及ぼしかねません。自己株式取得を伴う取引を検討する際は、必ず計画の初期段階で税理士などの専門家へ相談することが不可欠です。具体的な取引スキームに基づき、課税リスクを正確に評価することで、円滑な実行と将来のトラブル回避となります。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。






























