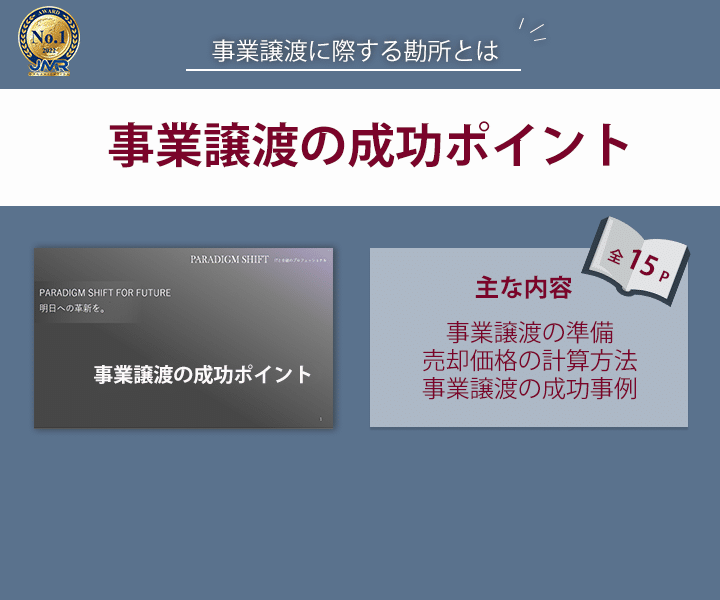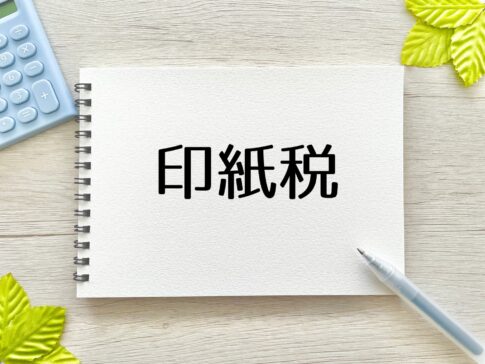会社の未来を託すM&Aの成功には、「事業譲渡」と「株式譲渡」のどちらを選ぶかに大きく左右されます。
- 一部の事業だけを売却したい
- 会社を丸ごと手放したいが、手続きは簡単に済ませたい
- 買い手として、簿外債務などの見えないリスクは絶対に避けたい
あなたが抱えるこうした悩みや希望によって、最適な手法は全く違います。簡潔に分かりやすく「事業譲渡」と「株式譲渡」を説明すると以下のとおりです。
- 事業譲渡:売買する資産や負債を自由に選べる「アラカルト方式」
- 株式譲渡:会社を丸ごと引き継ぐ「フルコース方式」
本記事では、事業譲渡と株式譲渡の根本的な違いから、手続きや税金、メリット・デメリットに至るまでを比較解説します。最後まで読むことで、あなたの会社にとって最良の選択はどちらなのか、明確な答えを見つけるためのヒントとなります。
後悔のないM&Aを決断するために、まずは2つの手法の本質を理解することから始めましょう。
目次
- 1 事業譲渡とは
- 2 株式譲渡とは
- 3 事業譲渡と株式譲渡の違い
- 4 一事業の譲渡か、会社全体の譲渡かの違い
- 5 税金の違い
- 6 簿外負債のリスク
- 7 事業譲渡のメリット・デメリット
- 8 事業譲渡のメリット
- 9 譲渡する事業を選択できる
- 10 買い手が簿外負債を引き継ぐ恐れがない
- 11 事業譲渡のデメリット
- 12 事業引継ぎにあたり、権利義務の個別同意が必要
- 13 消費税の対象となる
- 14 株式譲渡のメリット・デメリット
- 15 株式譲渡のメリット
- 16 株式を譲渡するだけで全ての権利義務が買い手に移転する
- 17 消費税がかからない
- 18 個人株主の税制優遇
- 19 株式譲渡のデメリット
- 20 買い手にとって簿外負債のリスクがある
- 21 不必要な事業まで買収してしまう
- 22 事業譲渡によるM&Aの手続き
- 23 事業譲渡の準備
- 24 取締役会による決議
- 25 買い手の選定
- 26 基本合意書を締結
- 27 買収監査
- 28 事業譲渡契約書を締結
- 29 関係各所への届け出
- 30 株主への通知
- 31 株主総会における特別決議
- 32 名義変更や許認可の手続き
- 33 契約手続きの完了
- 34 株式譲渡によるM&Aの手続き
- 35 経営陣間のM&Aへの合意
- 36 株式譲渡への承認を請求
- 37 取締役会や株主総会での承認決議
- 38 株式譲渡の承認を通知
- 39 株式譲渡契約書を締結
- 40 売買代金の決済を完了
- 41 登記申請
- 42 事業譲渡と株式譲渡の選び方
- 43 事業譲渡を選んだ方が良いケース
- 44 手続きをスムーズに進めたい場合
- 45 譲受側がリスクを抑えたい場合
- 46 株式譲渡を選ぶ場合
- 47 譲受企業が節税効果を期待している場合
- 48 譲渡企業に新たな事業を起こす予定がある場合
- 49 譲渡側が企業そのものを手放したくない場合
- 50 まとめ:事業譲渡と株式譲渡の違いを理解してM&Aを進めよう
事業譲渡とは
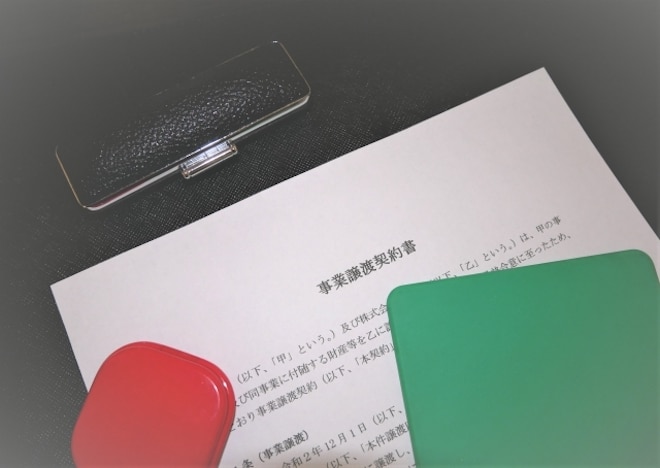
事業譲渡とは、会社の一部、または全ての事業を他社へ売買する行為です。会社の一部事業を切り離す際に良く利用されますが、全ての事業を譲渡する際も事業譲渡のスキームを利用ことがあります。
例えば、A事業とB事業を営んでいるX社が、B事業の赤字に長年苦しんでいるとしましょう。この場合、B事業だけを他社に事業譲渡することにより、経営課題が解決できる可能性があります。
株式譲渡とは
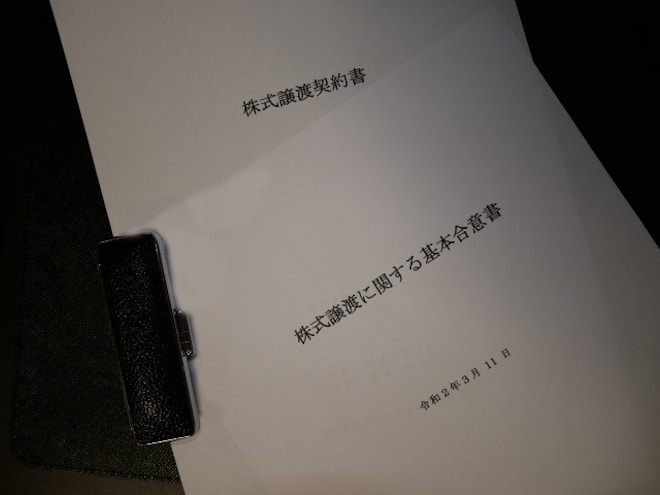
株式譲渡とは、株式を譲渡することにより会社の経営を承継させる行為です。M&Aの方法として最も広く利用されます。
例えば、先ほどと同様にX社のケースで株式譲渡の例を考えてみましょう。事業譲渡と異なり、株式譲渡によりX社の経営権そのものが売り手から買い手に承継されることとなります。結果として、買い手企業はA事業だけでなくB事業も経営することになります。
事業譲渡と株式譲渡の違い

以上のように、事業譲渡と株式譲渡の概要を解説してきました。この項では、事業譲渡と株式譲渡の違いを3つに整理します。
一事業の譲渡か、会社全体の譲渡かの違い
事業譲渡は事業そのものの譲渡、株式譲渡は会社全体の譲渡という点が大きくなります。
株式譲渡は会社の経営権そのものの譲渡です。そのため、買い手企業は売り手企業の会社の運営状況がどうなっているか、買収前に調査しなければなりません。具体的には、会社登記簿、定款、取締役会議事録や株主総会議事録、各種規程類などが挙げられます。
また、会社全体の譲渡となる株式譲渡では、特定の事業だけを買収したい場合でも不要な事業も含めて全体を買収しなければなりません。なお、事業譲渡以外に特定の事業を買収したい場合には、会社分割をすることも可能です。
税金の違い
事業譲渡において、譲渡対象資産に消費税の課税資産が含まれている場合には、消費税の対象となります。一方、株式譲渡の場合、消費税はかかりません。
また、個人が事業譲渡や株式譲渡をする際、税率が大きくなるケースがあります。事業譲渡も株式譲渡もどちらも「譲渡所得」である点は共通しています。しかし、事業譲渡は「総合課税」、株式譲渡は「分離課税」である点が大きな違いを生み出しています。
「総合課税」の場合は累進課税となっており最大税率45%、「分離課税」の場合は一律20.315%です。譲渡金額が高くなる場合には、株式譲渡の税制が有利になっていることが分かります。
簿外負債のリスク
事業譲渡では簿外負債のリスクはなく、株式譲渡ではリスクをなくすことはできません。事業譲渡は、譲渡する資産・負債を網羅的に契約書に明記することにより効力が発生するため、リストに載らない簿外負債を引き継ぐことはありません。
一方、株式譲渡ではいくら詳細にデューデリジェンスを実施したとしても、簿外負債のリスクをゼロにすることはできません。株式譲渡契約書の表明保証の中で、売り手企業に簿外負債がないことを表明してもらうのが一般的です。
事業譲渡のメリット・デメリット

次に事業譲渡のメリット・デメリットについて考えてみましょう。
事業譲渡のメリット
事業譲渡のメリットは以下の2つです。
- 譲渡する事業を選択できる
- 買い手が簿外負債を引き継ぐ恐れがない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
譲渡する事業を選択できる
売り手企業として、事業譲渡の最大のメリットは譲渡する事業を選択できる点です。不採算事業、成長事業、規模が小さな事業、ノンコア事業など、自社の成長戦略に合わせて自由に売却する事業を選べます。
反対に、買い手企業としても事業譲受する事業を自ら選択することができ、自社とシナジーが生じない不要な事業にお金を出す必要はありません。売り手企業、買い手企業ともに、譲渡すべき事業が選択できる点は大きなメリットとなるでしょう。
事業譲渡の範囲は広く、従業員や売掛金・買掛金などの流動資産、特許・技術などの無形資産も含まれます。事業譲渡において譲渡する資産・負債は、事業譲渡契約書に全て網羅的に明記することが必要です。
買い手が簿外負債を引き継ぐ恐れがない
事業譲渡の場合、譲渡される資産・負債の明細が添付されているため、明細に載っていない資産・負債は引き継ぎません。言い換えると、簿外負債を引き継ぐ恐れがないということです。
M&Aにおいて避けるべきリスクの一つとして、簿外負債が挙げられます。株式譲渡でM&Aする場合には、簿外負債に関するデューデリジェンス(DD)は必要不可欠です。
事業譲渡のデメリット
事業譲渡をすることでのメリットは以下の2つです。
- 事業引継ぎにあたり、権利義務の個別同意が必要
- 消費税の対象となる
事業引継ぎにあたり、権利義務の個別同意が必要
事業譲渡の場合、事業譲渡契約書に引き継ぐ資産・負債を明記していたとしても、権利義務の承継には個別同意が必要です。
例えば、売掛金などを譲渡する場合、債権者ごとに売り手から買い手に権利が承継されたことの同意を取っていく必要があります。従業員の引継ぎも同様に、従業員一人ずつ、買い手企業で今後勤務する旨の同意を得なければなりません。
そのため、実務上、事業譲渡契約書の譲渡実行の前提条件として、重要な個別同意を得られることを入れておくことが一般的です。事業譲渡をしたのに、事業引継ぎできなければ意味がないため、個別同意の取得を効力発生の前提とするのです。
以上のように、事業譲渡は株式譲渡と異なり、同意を得るべき取引先や人が多い場合には、手続きに時間がかかる点がデメリットです。
消費税の対象となる
事業譲渡をする場合、譲渡資産に消費税を課すべき資産が含まれているものは、消費税の対象となります。消費税の対象とならない資産は土地が代表的で、技術や特許などの無形資産は消費税の対象となります。
買い手企業の消費税のポジションによっては、事業譲渡において支払った消費税がそのまま投資コストとなります。消費税考慮後の金額を引き継いだ後の事業で回収しなければならず、投資回収期間が延びることになるのです。
株式譲渡のメリット・デメリット
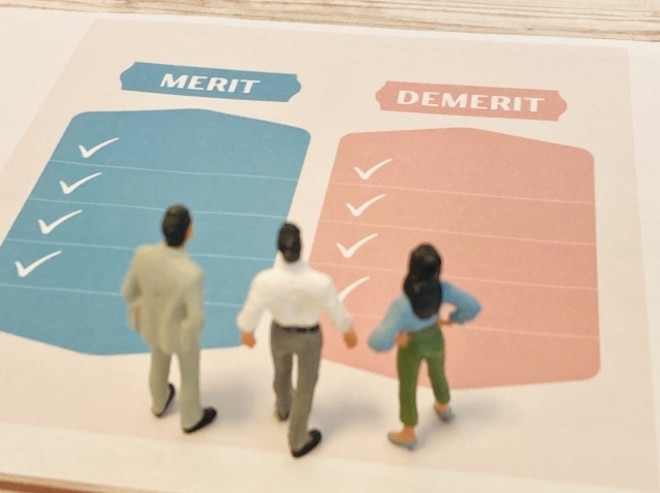
続けて、株式譲渡のメリットとデメリットも確認しておきましょう。
株式譲渡のメリット
株式譲渡のメリットは以下の3つです。
- 株式を譲渡するだけで全ての権利義務が買い手に移転する
- 消費税がかからない
- 個人株主の税制優遇
株式を譲渡するだけで全ての権利義務が買い手に移転する
事業譲渡と異なり株式譲渡は、株式を売り手企業から買い手企業に譲渡することです。基本的に全ての権利義務が移転します。そのため、取引先や従業員一人ひとりから同意を得る必要はありません。
ただし、事業に必要な許認可は、主要株主が変更になる場合、改めて取得しなければならない可能性もあります。
また、事業譲渡のように承継させる資産・負債を網羅的に列挙する必要はなく、株式の譲渡のみで一括して譲渡できます。そのため、株式譲渡は、事業譲渡と比べて簡便に短時間で完了できる場合が多くなります。
消費税がかからない
事業譲渡の場合、譲渡時に消費税が課税されますが、株式譲渡の場合は課税されません。純粋に株式の譲渡価格のみが投資コストになります。
個人株主の税制優遇
個人株主が事業譲渡をした場合、「譲渡所得」と区分され「総合課税」とされます。そのため、給与所得など他の所得と合算されてしまうという点、累進課税によって事業譲渡金額が高ければ高いほど所得税率も上がってしまうため注意が必要です。
総合課税の最大税率は45%となるため、高い金額で事業譲渡できたにもかかわらず、所得税だけで半分近く持っていかれてしまうということが起こります。
一方、個人株主が株式譲渡をした場合、「譲渡所得」である点は事業譲渡と同様ですが、「分離課税」されます。株式譲渡の税率は令和3年現在、一律で20.315%となります。どんなに高い金額で株式譲渡したとしても、20.315%の税率は変わらないため、金額が高額であればあるほど、個人株主の場合、事業譲渡よりも株式譲渡の方が望ましいと言えます。
株式譲渡のデメリット
株式譲渡におけるデメリットは以下の2つです。
- 買い手にとって簿外負債のリスクがある
- 不必要な事業まで買収してしまう
買い手にとって簿外負債のリスクがある
株式譲渡は会社全体の買収であるため、会社に簿外負債があってもそのまま引き継いでしまうことになります。簿外負債とは帳簿に載らない負債のことですが、例えば、税金や残業代の未払、訴訟による損害賠償などが挙げられます。
買収後に多額の簿外負債があることが判明した場合、買収したにもかかわらず会社が潰れかねません。このようなリスクを避けるため、買い手企業は必ず買収前にデューデリジェンス(DD)を実施しましょう。
不必要な事業まで買収してしまう
例えば、X社が黒字のA事業と赤字のB事業を営んでいるとしましょう。買い手企業はA事業の成長性とシナジー効果に期待してX社を買収したいと考えています。
X社を株式譲渡により買収した場合、買い手が望んでいたA事業は手に入るものの、赤字であるB事業も自動的についてきてしまいます。事業譲渡であればA事業のみを買収することが可能ですが、株式譲渡の場合、会社全体の買収になります。
事業譲渡によるM&Aの手続き

次に、M&Aの事業譲渡による手続きの流れを見ていきましょう。
事業譲渡の準備
まずは、売り手企業が事業譲渡を準備します。自社の現状を把握し、市場や自社の価値を分析します。
準備段階では、以下のことを決定するのが一般的です。
- どの事業を譲渡するか
- いくら位の価格で譲渡するのか
- いつまでに譲渡するのか
これらを考慮して譲渡までの計画を立てましょう。
取締役会による決議
会社法では、事業譲渡する際に取締役会で承認を得なければなりません。売り手企業は、取締役会で事業譲渡の目的や理由を丁寧に説明して過半数以上の承認を得るようにします。
買い手の選定
取締役会で承認を得られたら買い手企業の選定に入ります。このとき、一般的にはM&Aの専門業者に依頼して探してもらいます。その中から買い手企業の候補を絞り交渉を始めます。
交渉の際は、条件や譲渡金額、経営者の理念や相性、譲渡の後もコミュニケーションがとれるかなどの観点で話し合いましょう。
基本合意書を締結
売り手企業と買い手企業の両者が合意したら基本合意書を締結します。
基本合意書には、譲渡の条件や金額、今後のスケジュールなどを記載します。基本合意書の締結は、合意の確認という意味合いであり、法的な拘束力はありません。そのため、基本合意の締結後に破綻する可能性もあります。
買収監査
買収監査はM&A用語でデューデリジェンス(DD)とも呼び、買い手企業が売り手企業に対して実施する内部調査です。
財務や法務・税務・労務など各分野の専門家に調査を依頼します。この結果から、売り手企業が提示した譲渡金額が適正であるかどうか判断したり、リスクを洗い出して把握したりします。
その後、今度は買い手企業が取締役会で承認を得ます。
事業譲渡契約書を締結
その後、譲渡契約書の作成に入ります。譲渡契約書には、以下の内容などを記載しましょう。
- 譲渡日
- 譲渡の目的
- 譲渡金額・支払い方法
- 注意義務・守秘義務
- 従業員の取り扱い
- 協議事項
記載内容が定められているわけではありませんが、契約書自体には法的拘束力があります。ネット上には無料でダウンロードできる見本がたくさん見られますが、安易に使用してしまうとトラブルのもととなるため注意しましょう。
関係各所への届け出
事業譲渡する企業は公正取引委員会へ報告が必要となり、場合によっては有価証券報告書の提出を求められます。公正取引委員会へは、買い手企業が計画届出書を提出します。有価証券報告書の提出が必要なのは、以下の企業です。
- 譲渡または譲受が純資産額の30%以上増減する場合
- 譲受または譲渡により、売上が最近事業年度の実績よりも10%以上増減する場合
株主への通知
事業譲渡の決定について株主へ通知します。原則として、株主総会の特別決議で承認されなければ、事業譲渡の効力は発生しません。事業譲渡に反対する株主には、買取請求ができる旨を伝えます。
株主総会における特別決議
株主紹介の特別決議は、議決権を持つ株主が過半数以上出席して、そのうちの3分の2の賛成で可決となります。ただし、簡易事業譲渡と略式事業譲の場合は株主総会での特別決議は必要ありません。簡易事業譲渡とは、譲渡資産の帳簿額が譲渡会社(売り手企業)の総資産20%を超えない場合の事業譲渡を指します。
略式事業譲は、契約相手が特別支配会社である場合には、略式事業譲となります。特別支配会社は、議決権のある株式を90%以上保有している会社です。この場合、特別決議は間違いなく承認されるため、株主総会は必要ありません。
名義変更や許認可の手続き
売り手企業の財産や所有物を買い手企業の名義に変更する必要があります。また、許認可の手続きは引き継がれないので、管轄の監督官庁で手続きをします。業種によっては許認可が降りるまでに時間がかかることもあるので予め確認しておきましょう。
契約手続きの完了
決められた効力発生日から事業譲渡の効力が発生します。これ以降は事業の引き継ぎに入り、業務や従業員の引き継ぎなど、統合のプロセスに入ります。
株式譲渡によるM&Aの手続き
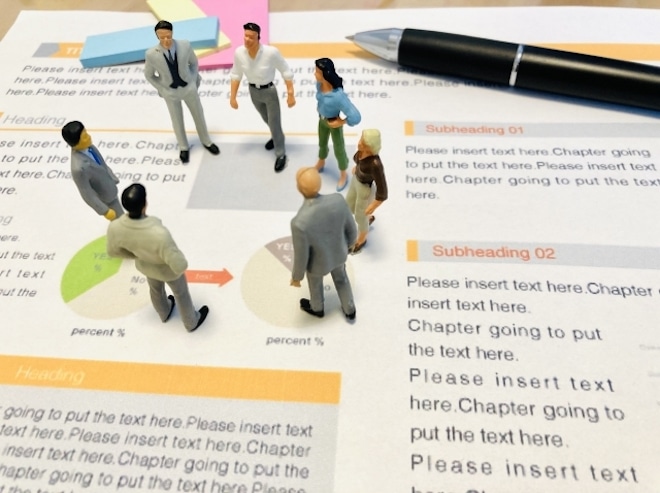
次に、株譲渡の流れについて見てみましょう。
経営陣間のM&Aへの合意
売り手企業と買い手企業の経営陣による大筋の合意が取れたら、基本合意契約書を締結します。事業譲渡の基本合意同様、ここでは、法的な効力はありません。規模や交渉状況によっては、メールなどでお互いの意思確認のみをしておく場合もあります。
株式譲渡への承認を請求
売り手企業が譲渡制限に関する規定のある譲渡制限会社の場合、株主総会で承認を得る必要があります。買い手企業へ株式譲渡承認を請求して、その承認のプロセスが開始されます。
取締役会や株主総会での承認決議
株式譲渡の承認は取締役会で承認決議がなされます。取締役会のない会社は、株式総会にて株式譲渡の承認を取ります。株主の人数が多い場合、各株主は代表の株主へ委任状を預けます。代表の株主は、一連の手続きを一括して実施します。
株式譲渡の承認を通知
取締役会か、株主総会で株式譲渡が承認されたら、各株主にその旨を通達します。譲渡請求日から2週間以内に通達しなかった場合、譲渡の承認は決定したものとされます。
株式譲渡契約書を締結
その後、株式譲渡の契約を締結します。契約書に記載する主な内容は以下の通りです。
- 譲渡価格
- 支払い方法
- クロージング
- 保証内容
- 誓約事項
売買代金の決済を完了
売り手企業は、買い手企業へ株式を引き渡します。買い手企業は株式を確認した後に、銀行の担当者へ連絡して決済を実行します。売り手企業は決められた金額が振り込まれていることを確認し、売買代金の決済が完了します。
登記申請
株式譲渡によるM&Aが終了したあと、臨時取締役会にて新たな役員を決定します。役員の専任が終わったら、役員専任の登記申請をします。
事業譲渡と株式譲渡の選び方

事業譲渡と株式譲渡は、手続きや税務、引き継ぐ資産・負債の範囲が大きく異なるため、自社の目的や状況に応じた適切な選択が必要です。ここでは、事業譲渡を選んだ方が良い具体的なケースについて詳しく解説します。
事業譲渡を選んだ方が良いケース
事業譲渡は、会社が営む事業の一部または全部を対象に売買するM&A手法です。事業譲渡の最大の特長は、譲渡する資産や負債、契約などを個別に選んで引き継げる点にあります。譲受側(買い手)は、不要な事業や簿外債務などの潜在的リスクを切り離せるため、安心して事業を譲り受けることが可能です。
株主が多数にわたる場合でも、個別に交渉する手間を省け、手続きが円滑に進むことがあります。
手続きをスムーズに進めたい場合
事業譲渡は、資産や契約を個別に引き継ぐため、手続きが煩雑になりがちです。しかし、株主が多数に分散している場合には、株式譲渡よりも手続きが円滑に進められます。株式譲渡によって会社全体の経営権を移転するには、原則として全株主の同意が必要となり、個別に交渉し株式を買い集めるには手間と時間がかかります。
一方、事業譲渡は、会社の重要事項として株主総会の特別決議で進めることが可能です。議決権の過半数を持つ株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成で可決されるものです。一部に反対する株主がいても、大多数の賛成があれば会社として迅速な意思決定ができます。
譲受側がリスクを抑えたい場合
譲受側(買い手)にとって事業譲渡の最大のメリットは、引き継ぐ資産や負債を個別に選択できる点です。譲受側は、自社の事業戦略に必要な資産のみを取得し、不要な事業や負債を切り離せます。貸借対照表に記載されない簿外債務や、将来訴訟に発展する可能性のある偶発債務といった「見えないリスク」も引き継がずに済みます。
譲渡対象をデューデリジェンス(企業調査)で精査し特定することで、予期せぬ負債を抱えるリスクの大幅な低減が可能です。事業譲渡は、譲受側にとって安全性の高いM&A手法といえます。
株式譲渡を選ぶ場合
株式譲渡は、会社の株式を売買することで経営権を包括的に移転させるM&A手法です。事業譲渡と異なり会社を丸ごと引き継ぐため、許認可や従業員の雇用、取引先との契約などをそのまま承継できるのが大きな特徴です。ここからは、株式譲渡を選ぶ場合の3つのケースについて詳しく解説します。
譲受企業が節税効果を期待している場合
株式譲渡を選択する大きなメリットの一つは、譲渡企業の「繰越欠損金」を引き継ぐ可能性がある点です。繰越欠損金とは、過去の事業年度に生じた税務上の赤字のことです。株式譲渡によって会社を丸ごと引き継ぐと繰越欠損金も承継されるため、譲受後に事業から利益(黒字)が出た際に、利益と繰越欠損金を相殺できます。
例えば、利益が200万円出たとしても、100万円の繰越欠損金があれば、課税対象所得は100万円に減ります。事業譲渡では事業に関する資産のみを引き継ぎ、法人格は別であるため、繰越欠損金を引き継ぐことはできません。ただし、節税目的のみのM&Aと判断される場合には適用が認められないこともあるため注意が必要です。
譲渡企業に新たな事業を起こす予定がある場合
株式譲渡は、会社の経営権は移転しますが会社自体は存続します。株式譲渡の大きな特徴は、株主である経営者が保有する株式を売却することで、対価となる現金を直接得られる点です。売却によって得た資金を元手にし、全く新しい会社を設立したり、別の事業を始めたりするなど、新たな事業を起こす資金として自由に活用できます。
例えば、会社経営からは引退し、株式売却で得た資金で新たなビジネスを立ち上げる「シリアルアントレプレナー(連続起業家)」のようなキャリアプランも可能です。しかし、事業譲渡の場合は売却代金は法人に入るため、株主個人が資金を得るには役員退職金や配当といった手続きが必要になります。
会社を売却した資金でスピーディーに次の事業展開を考えている経営者にとって、株式譲渡は有効な選択肢です。
譲渡側が企業そのものを手放したくない場合
株式譲渡は、必ずしも会社の全株式(100%)を売却するわけではありません。経営者が会社に愛着があり、今後も何らかの形で経営に関与し続けたいと考える場合、保有株式の一部のみを譲渡する選択肢があります。
過半数の株式を譲渡して経営権は譲受企業に移しつつも、自身は一部の株式を保有し続けることで、株主としての権利を一部保持できます。経営から完全に離れるのではなく、役員や顧問といった立場で会社に残り、事業の成長を見守り支援していくことが可能です。
一部の株式を譲渡する手法は、創業者利益を確保しながら、会社との関わりを維持したいと考える経営者の意向に合うでしょう。
まとめ:事業譲渡と株式譲渡の違いを理解してM&Aを進めよう

M&Aの手法は様々なものがありますが、事業譲渡と株式譲渡は最もよく使われる方法です。売り手企業、買い手企業とも、事業譲渡か株式譲渡かによって、税金や事業戦略やリスクなどが大きく異なってきます。
M&Aの中でもスキーム選択は、M&Aの成否にも大きく関わってくるため、どちらが望ましいか専門家を交えて事前によく検討しなければなりません。事業譲渡と株式譲渡のどちらもデメリットはあり、最適なM&A手法というものは存在しません。
デメリットを踏まえたデューデリジェンスの設計、譲渡契約書の中での手当、PMIを実施して、デメリットを最小限に抑えられるようなM&Aの実施が望まれます。
パラダイムシフトは2011年の設立以来、豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴
- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー
- IT業界の豊富な情報力
- 「納得感」と「満足感」の高いサービス
- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてご利用ください。